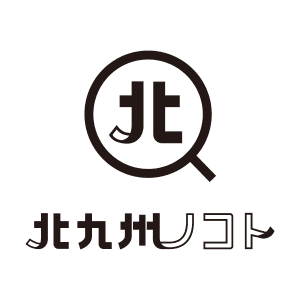(画像提供:木村洋子さん)
独学で一級建築士の資格を取得した異色の建築家。子どもの頃からインテリアデザイナーに憧れ、親の反対を振り切って上京し美術大学に進学した情熱の人でもあります。
北九州市出身・在住の木村洋子さんは、ご自身のことを家全体のデザインを考える「インテリアコーディネーター」で、都市空間をデザインする「ランドスケープデザイナー」だと紹介します。
今は雨水を利用した治水や災害防止の推進に情熱を傾けているといいます。「雨水活用施設設計技士」(雨水デザイナー)の資格も持つ木村さんにお話しを聞きました。
「インテリアデザイナー」になるのが夢だった
―木村さんはもともと建築家志望だったのですか?
「小さい時から『インテリアデザイナー』になりたかったので、そのために美術大学で勉強がしたかったのですが、昔は美術大学が東京にしかありませんでした。父が封建的な人で、地元を出ることは許されず、父の希望の通りに地元の短大を出て、銀行に就職しました。1年足らずで大病をしたことで、『どうしてもデザインの勉強をしたい』という気持ちが強くなったのです。父の反対を押し切って、家出同然で東京の叔父に頼み込んで身を寄せました」
―20歳で東京の叔父さんのところに。
「叔父は有名な画家の息子で、芸大を出て美術関係の仕事をしていました。半年間、デッサンやデザインの基礎の基礎をしっかりと教えてもらいました。叔父は大局をつかむことが得意な人で、そのやり方を見て学びましたし、この間に学んだことは今でも、建築家として仕事をする時にも生きています」
―その後美大に入学したのですか?
「女子美術大学を受験して、無事に合格できました。(半年間の勉強だけだったので)奇跡的です。父に頼み込んで入学金を支払ってもらい、奨学金をもらうためによく勉強しました。東大教授たちがくる本郷のバーでアルバイトをしたことも楽しい想い出です」
―どういったことを学びましたか。
「卒業の時には、吉祥寺の再開発についての論文をまとめました。論文を書いたのは、多分、私だけだったと思います。吉祥寺は戦後の闇市があった場所をすべて壊して作り変えてしまったのですが、井の頭公園が中心にあって、街にあった楽しさはそこに残ったのだと思います。すべてが変わってしまい、たいへんなカルチャーショックを受けました。吉祥寺は旦過市場のような場所でした」

井の頭公園での1枚(画像提供:木村洋子さん)
旦過市場の”匂い”を残したい
―吉祥寺が旦過市場に似ていたというのは初耳です。旦過市場も再開発の話が進んでいるようですね。
「その昔は闇市だった旦過市場のノスタルジックな匂い、そこにあるモノはそのまま残したいです。美味しい物、安心な物がそこにある、という場所。暮らしの安心感がある、すごく貴重な場所だと思います。お店の方は、たくさん売ろうという商売ではなくて、毎日、すべての商品を売り切ってしまう商売をしています。用事がなくとも買い物がしたくなる場所です」
―今の旦過市場の文化は残るとよいですね。
「旦過市場をもっと楽しい活気のある市場にするには、壊すのではなく、市場全体のデザインから考えて、アメリカ・シアトルのフィッシャーマンズワーフのような店舗の色合いや活気のある店づくりなどを参考にできると思います」
デザイナーから建築士へ
―どういう経緯で建築士になったのでしょうか?
「美大を卒業し、25歳で北九州に戻ってきました。スイミングクラブでプールを作る計画があって、デザイナーとして参加することになったのです。設計事務所のみなさんと打ち合わせをするようになって、オフィスの中に机をもらって仕事をするようになりました。みなさんが休み時間に建築士の勉強しているのを見て、自分でも建築のことを知りたくなりましたね。建築士2級の勉強を始めましたが、4ケ月ほど周りの方々に教えていただきながら受験して、無事に合格しました」
―数ケ月の勉強で合格とはすごいですね。
「自分でも欲が出てきて、1級建築士を受験するには4年の実務経験が必要で、4年後には受験しようという気持ちになりました。1980年に2級建築士として独立しましたが、自分ではデザイナーのつもりでいました。いざ1級の受験をしてみると、試験の内容がまったくわからず、2級とはまったく違うレベルだとわかりました。3年目にようやく学科に受かり、それからは鬼のようになって実技を勉強して、合格できました」
―1級建築士になって、建築の仕事を本格的に始めたのですか?
「建築デザインの仕事がしたかったのですが、建築士という名前が仕事を連れてきてくれました。家族に一生関わる仕事と考えていましたので、どんな仕事も1年以上かけて取り組みました。お客さんの希望を聞き、街の計画を調べた上で家の設計をしました。半年から8カ月くらいで設計し、家の完成までは1年半くらいかかりました。普通は10回で終わる打ち合わせを30回はしていました」
―通常の3倍の打ち合わせをしていたのですね。
「バブルのころはキッチンの仕上げ材の違いで100万円ほどは違っていました。そこで不要な費用を減らして、浮いたお金を奥様向けの家事コーナーやクローゼット、子どものコーナーに使うと喜んでもらえましたね。家が完成した後のメンテナンスについても相談をいただくので、関わったお宅とは長いお付き合いを続けています」
―予算の調整もされるのですね。
「予算管理は厳しくやります。施工業者の仕事の内容をしっかりチェックするので、本当に信頼ができる業者さんとしか仕事をしなくなりました。全体の予算をみて家具やカーテンも考えます。40年、この仕事をしているので、予算が足りない時にはテーブルを作る大工さんに注文したこともあります」
25年間、街づくりに関わる
―自治体関係の仕事もされたのですか?
「これまで25年間、街づくりに関わってきました。八幡東区丸山大谷地区の住環境整備計画という名称の『街づくりプロジェクト』では、急な斜面地がある土地をどう暮らしやすく改良するかを考えるものでしたが、ボランティアで住民との対話を担当し、立ち退き後にはどう住みやすくなるのかを伝えていました」
―街づくりには以前から興味があったのでしょうか。
「ずっと『ランドスケープ』(*)の勉強がしたかったのですが、日本には当時はなかったのです。2002年に京都造形芸術大学の造園学部にランドスケープ・コースができたので、すぐ入学しました。とても楽しくて、これまでで一番、一生懸命に勉強したと思います。『自然を生かしつつ、自然と人の暮らしを作る』のがランドスケープの考え方です」
*ランドスケープ=都市における広場や公園などの公共空間のデザイン。
雨水の力を実感 世界が変わった
―今は雨水の利用が一番の関心事ということですが、きっかけは。
「2009年10月から半年間、台北で開催された『世界国際花博』に友人と参加して、『五感の庭』をテーマに庭を造り、3位に入賞しました。花博が始まるまでに、土壌改良に3ケ月をかけました。水を貯めて循環する仕組みを作りましたが、水が土壌に浸透すると土壌がどんどん改良されていきます。そこにトンボなどの生物が集まって、水が命を作るすごさを実感しました。ここで『雨水を生かしていかなくてはいけない』という発想が生まれました。世界を見る目が変わったのです」
―雨水を生かしたプロジェクトは何かありますか?
「2012年に『らくらく庵』(小倉南区)という小規模な老人福祉施設で、35トンの雨水を貯水して利用する先進的なシステムを作りました。北九州市が国の支援を受けて推進した『小規模多機能の老人福祉施設(10床)』のプロジェクトです」
―貯水した雨水は何に使用するのでしょうか。
「雨水をトイレや雑洗い用に利用しています。屋根から落ちた雨水からきれいな水を集めて、いくつかの水槽に送り、少しずつ浄水してきれいにした水を施設の中に入れて使うシステムです。公共的な設備ではこうした方法があります」
―そうなんですね。雨水利用は全国で増えてきていますか?
「雨水の利用を促進する法律『雨水の利用の促進に関する法律』(2014年)ができて、東京や福岡市、その他の都市でも雨水を利用する設備が作られていますが、まだ全国的な動きにはなっていません」

台北・世界国際花博で3位受賞の庭(画像提供:木村洋子さん)
「グリーンインフラ」を増やしたい
―調べてみると、雨水タンクを設置する助成金の制度が全国の自治体にあるようですが、北九州市にはまだないようですね。
「上水と下水の管轄が違うのが難しいところです。水資源意識を高めていかなくてはいけないと思います」
―具体的には。
「『グリーンインフラ』とは自然の機能や仕組みを利用したインフラのことなのですが、グリーン化して水を循環させる仕組みを作り、雨水を利用できれば、気温が2~3度は下がると言われています。北九州にはその反対の概念の『グレーインフラ』といって、コンクリートやアスファルトでできた人口造形物が多いのです」
「若松の工業地帯は工場や駐車場をグリーン化して雨水を利用すると、トイレなどの雑用水を使う場所がたくさんありますし、上水が少なくて済めば経済効率も高まり、グリーン化で土地の安全性も高まります。雨水を吸収して保水性がある『トース土工法』という舗装は、東京マラソンのコースにも使われています。初期費用がかかりますが、長期間使えば経済メリットがあります」
―一般住宅に貯水タンクを設置することも可能でしょうか。
「一般の住宅では駐車場の下などに貯水タンクを置いて、家の水として使っていく方法があります。2011年には、福岡大学の渡辺亮一先生の個人宅ですが、実験データを取るための『雨水ハウス』に貯水タンクと空タンクを設置しました」
「最近は都市が浸水する水害が増えています。日本は土地が狭いので、雨水を大きな公共施設で貯水して利用するだけでなくて、一般の家庭でも貯水と空の容器に雨水を貯めて使うシステムが必要です」
―私たちも雨水の利用を考えないといけませんね。
「そうです。水資源を利用することが当たり前になるように、市民の意識を高めていきたいのです。災害時にも生活に使える水があるだけで、メンタルにもよい影響があります。汚れたテーブルを拭ける水があると大きく違うものです」
「街づくりを生業にしてきましたが、雨水に関してはNPOの理事としてもっと気合いを入れて本腰をいれてやらないといけないと思っています」
地元に循環システムを
木村さんが中学生のころ、汚濁した洞海湾に魚が浮かび、汚れた空に煙突からの七色の煙が出ていたのだそうです。ご家族が若いころの写真で、洞海湾の海水が足の見えるくらいきれいだったのを知って驚いたこともあったそうです。
汚れた空気を吸って育っていたので、洞海湾が目に見えて浄化されていったことは非常に大きな出来事だったといいます。その時の水に対する気持ちが、今の雨水の循環システムの仕事につながっているように思えました。
努力家で、勉強好きな木村さんのことですから、今日もどこかで水資源の勉強をしていることでしょう。そんな木村さんを応援していきたくなりました。
■木村洋子さんプロフィール
北九州市出身、北九州市在住。建築事務所アトリエPAO代表(一級建築士/ランドスケープデザイナー/園芸福祉士)。「街づくり」に25年携わる。国による雨水活用促進を支援する特定非営利活動法人「雨水まちづくりサポート」理事。関心事は「雨水の貯水・利用」による治水・災害対策。
(北九州ノコト編集部)
※3月18日に取材しました。