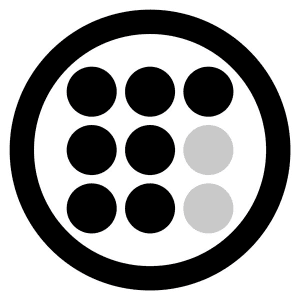元横浜高監督・平田徹氏が考える「結果と育成の両立」とは
First-Pitch編集部では「指導者」をテーマにした連載「ひきだすヒミツ」をお届けします。前横浜高の監督・平田徹さんは、名門を指揮したとあり、卓越した野球理論を持つ。前回の指導者編に続き、今回のテーマは「結果と育成の両立」。後にプロへ進む選手も育てた平田さんには、絶対にやらないと決めていた3つの指導方針があった。
◇◇◇◇◇◇◇
指導者が直面する難しい問題の1つに「結果と育成の両立」があります。私が横浜高で監督をしていた時は、ありがたいことに能力の高い選手に数多く恵まれました。一方でいい選手が多いほど、周囲は結果への期待を膨らませます。目先の結果を得ようとすることと、選手やチームの伸びしろを最大化していくことは、ときに両立が難しい課題となります。優れた素質を持った選手の伸びしろを、余すことなく大きく伸ばそうと思えば、それには時間がかかるからです。
もちろん私も「勝ちたい」「勝たねば」と思っていますが、一方で高校野球は通過点だから目先の結果は度外視してじっくりと好素材の選手を伸ばしたいという思いもあり、そこにジレンマがあったと思います。
周りからは「もっともっと貪欲に、結果を求めてシビアにやらないといけない」と言われることもありました。しかし私は、勝利を目指しながらも、伸びしろを余すことなく大きく伸ばそうとしていくことが、時間はかかっても最終的には勝利に結びつくということを信念して指導にあたってきました。
例えば、日本ハムの万波中正外野手のような選手(横浜から2018年のドラフトで入団)は目先の結果にこだわらず、5年後、10年後を見据えて大きく伸ばすことだけを考えていました。なので彼にはなかなか結果が出ない時期もありましたが、試合に起用し続けました。必要以上の技術指導をすることもありませんでした。
絶対にしない「小さくまとめる」「型にはめる」「酷使する」
私には、指導する上で絶対にやらないと決めていたことが3つありました。「小さくまとめる」、「型にはめる」、「酷使する」。例えば、バットを短く持たせてコンパクトなスイングをさせれば、能力の高い選手は一定の結果を出してくれるでしょう。ただ、それでは伸びしろを奪ってしまうことになります。ホームランが打てる能力を持った選手を、アベレージヒッターにしたくはありません。いい投手をできるだけ多く投げさせれば、勝利の確率は高くなりますが、酷使した結果、将来を奪ってしまう危険性もあります。
全国制覇を期待される中、甲子園で結果を出せずに苦しい部分はありました。2年半で選手が入れ替わるということにも難しさがあります。でも、好素材の選手ほど時間が必要です。私は時間がかかっても、最終的には結果と育成を両立できると信じてやってきました。
だからこそ、万波選手や阪神に入団した及川雅貴投手のような選手が、次のステージで活躍しているのを見るととてもうれしく感じます。私は基本的に、選手の打ち方や投げ方はよほど問題がない限りいじりません。サイドスローを勧めたりすることはありますが、それは何か創意工夫をしなければ生き残れないと判断された場合です。それも強制はせずに、選択肢の1つとして提案する形です。
育成に重点を置きすぎる分、周囲の期待に応えられないこともあったと感じています。今思えば、自分で「時間をかけて結果と育成を両立させる」という方針を打ち出していたのですから、もっともっと選手をフォローできたと思っています。結果が出ずに苦しんでいる選手に「全然、気にしなくていいぞ」、「思い切ってやれよ」、「進むべき方向性は間違っていないんだから」と言って励ましてあげることが大切だと考えます。(記事提供:First-Pitch編集部)