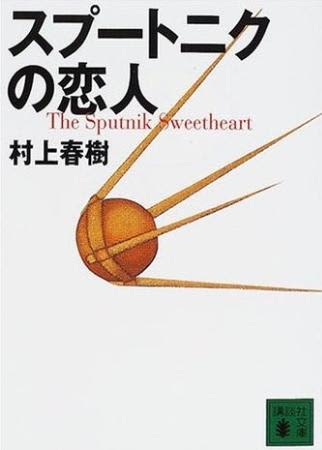
〈床屋はもう穴を掘らない〉―。村上春樹の『スプートニクの恋人』(1999年)の中に、「すみれ」という女性が書いた文章が引用される部分があります。その文章の中にはいくつかの見出しがついていて、中に〈床屋はもう穴を掘らない〉というものがあります。
『スプートニクの恋人』は、忽然として姿を消してしまった「すみれ」が、物語の最後の最後に帰ってくる長編小説です。あるいは、失踪した「すみれ」が「ぼく」のもとに戻ってきたのではないかとも読める物語です。今回のコラム「村上春樹を読む」では『スプートニクの恋人』で、途中から失踪してしまった「すみれ」が、最後の最後になぜ帰還するのかについて考えてみたいと思います。そのことについて、この〈床屋はもう穴を掘らない〉という言葉を手がかりにして、考えてみたいと思うのです。
『スプートニクの恋人』は、語り手である「ぼく」が、小説家を志望している「すみれ」と親しく、かつ彼女に恋をしているのですが、一方の「すみれ」のほうは「ミュウ」という17歳年上の在日韓国人の女性を好きになってしまいます。
「すみれ」は「ミュウ」の秘書のようになり、2人はギリシャの小さな島にわたるのです。そして、ある夜、「すみれ」は同性の「ミュウ」に関係を迫りますが、でも「ミュウ」は「すみれ」の気持ちは理解できても、受け入れることができないのです。その夜、「すみれ」は忽然と、まるで煙のように消えてしまいます。「ミュウ」からの国際電話で、「ぼく」もギリシャの島に駆けつけますが、やはり見つけることができません。
でも、物語の最後の最後、東京に戻った「ぼく」のところへ、深夜電話がかかってきて、それに「ぼく」が出ると「ねえ帰ってきたのよ」「いろいろ大変だったけど、それでもなんとか帰ってきた。ホメロスの『オデッセイ』を50字以内の短縮版にすればそうなるように」と「すみれ」が言うのです。
「今どこにいる?」と「ぼく」が問うと、「わたしが今どこにいるか? どこにいると思う?」と言った後に続けて「昔なつかしい古典的な電話ボックスの中よ」「交換可能で、あくまで記号的な電話ボックス。さて、場所はどこだろう? 今はちょっとわからない」と「すみれ」は答えます。
これは『ノルウェイの森』(1987年)のラストシーンによく似ていますね。『ノルウェイの森』では、物語の最後に「僕」が「緑」という女の子に電話ボックスから電話をするのですが、「緑」が「あなた、今どこにいるの?」と問うと、それに対して「僕は今どこにいるのだ?」と思います。さらに「僕は受話器を持ったまま顔を上げ、電話ボックスのまわりをぐるりと見まわしてみた。僕は今どこにいるのだ? でもそこがどこなのか僕にはわからなかった。見当もつかなかった。いったいここはどこなんだ」と「僕」が思うところで終わっています。
『スプートニクの恋人』『ノルウェイの森』は、ともに電話ボックスからの電話の場面で物語が終わっていますので当然、両者の関係は意識されたものでしょう。『スプートニクの恋人』の最後の「昔なつかしい古典的な電話ボックスの中よ」「交換可能で、あくまで記号的な電話ボックス」という言葉は『ノルウェイの森』の最後の「電話ボックス」のことを言っているのかなと思います。
そして『スプートニクの恋人』の「すみれ」からの電話も、『ノルウェイの森』の「僕」の電話も、冥界巡りから生の世界への帰還報告という意味でも重なっていると思いますし、「すみれ」が言う、ホメロスの『オデッセイ』もトロイ戦争のあと、冥界巡りのような長い漂流・冒険を経て故郷へ帰還する物語です。
さてさて、その「すみれ」の帰還は、なにゆえに可能だったのか。なぜあとかたもなく、忽然と消えた「すみれ」が帰ってきたのか。この問題を考えてみたいのです。
話を簡単にするために、私の考えをまず先に記してしまいましょう。
なぜ「すみれ」が帰ってきたのか。それは「ぼく」が自分の足りない部分に本当に深く気がついたからだと思います。ほんとうの深い気づきによって、「ぼく」が成長したからだと思うのです。その深い気づきと成長の力によって「ぼく」が「すみれ」を心から求め、その力によって「すみれ」は「ぼく」のところに戻ってきたのだと、私は思っています。
そのことについて、〈床屋はもう穴を掘らない〉という見出しがついた文章から考えてみたいのです。
それらの文章は「すみれ」が失踪後、ギリシャまで訪ねた「ぼく」が、「すみれ」のパソコンの中から見つけたものですが、その〈床屋はもう穴を掘らない〉という見出しが書かれた文章には、こんなことが記されています。
「わたしはひとつ重大な決心をした。わたしのそれなりに勤勉なつるはしの先はようやく強固な岩塊を叩く。こつん。わたしはミュウに、わたしが何を求めているかをはっきり示そうと思う。このような宙ぶらりんの状態をいつまでも続けていくことはできない。どこかの気弱な床屋のように裏庭にしけた穴を掘って、『わたしはミュウを愛している!』とこっそり打ち明けているわけにはいかないのだ。そんなことを続けていたら、わたしは間断なく失われていくだろう」
もちろん〈床屋はもう穴を掘らない〉の見出しは、その「どこかの気弱な床屋のように裏庭にしけた穴を掘って」という部分に関連して、付けられています。
そして、この「どこかの気弱な床屋のように裏庭にしけた穴を掘って…」というのは有名な寓話である「王様の耳はロバの耳」の話かと思います。
これはギリシャ神話のミダス王に関する話です。話自体は幾つかのパターンがあるようですが、オウィディウスの『変身物語』から紹介しますと、山の神トモロスを判定者として、アポロンの竪琴と、牧神パーンの葦笛が音楽の腕比べをして、アポロンが勝ち、トモロスもパーンに負けを認めさせます。
でもミダス王だけが、山の神トモロスの判定に賛成しません。アポロンはミダス王の鈍感な耳が人間なみの形をしていることに我慢がならないので、ミダス王の耳をロバの耳にしてしまいます。
ミダス王はこれを隠しておきたいのですが、髪を刈るおそばづきの床屋には秘密にできません。床屋はその事実を内心言いふらしたくてたまらないのですが、思い切って口外する勇気がなく、かといって黙っているのにも我慢がならなかったので、そこで館をぬけ出すと、地面に穴を掘り、自分が見たままの主人の耳の様子を、小声で話し、掘った穴のなかにささやきかけます。
それから、土をもとに戻し穴を埋めて、口をぬぐって、床屋は立ち去りましたが、でもその場所一面にたくさんの葦が生え、その葦が風に揺り動かされると、秘密にされた言葉を葦たちが、そよそよと話し、その王の耳の話がばれてしまったという話です。
ですから〈床屋はもう穴を掘らない〉というのは、もう、内心のことを隠して生きたりしないで、勇気をもって、本当の気持ちを相手にしっかり伝えて生きるということでしょう。本当の自分の気持ちを、言わずに、こっそり自分だけで〈本当は、こういう気持ちなんだけれど…〉と思いながら生きていたら「そんなことを続けていたら、わたしは間断なく失われていくだろう」という意味です。そしてギリシャ神話の「ミダス王」の話が、ここに記されているのは、「すみれ」の文章が残された場所がギリシャの小島であることと関係しているのかもしれませんね。
ともかく「すみれ」は、そんな勇気をもって、ちゃんと生きようとする人間です。それに対して、「ぼく」のほうはどんな人間でしょうか。
物語の語り手として、「ぼく」が登場する時には、こんな人間として描かれています。
「ぼくが人生になにを求めているのか、それは自分にだってよくわからなかった」「小説を読むのが並外れて好きだったけれど、あえて小説家を志すほどの文章の才能があるとは思えなかったし、かといって編集者や批評家になるには好みが激しすぎた」というふうに記されています。
これに対して、「すみれ」のほうは「そのころ職業的作家になるために文字どおり悪戦苦闘していた。この世界に人生の選択肢がどれほど数多く存在しようとも、小説家になる以外に自分の進むべき道はない。その決意は千歳の岩のように堅く、妥協の余地のないものだった」と記されています。
〈床屋はもう穴を掘らない〉のところで紹介した「わたしのそれなりに勤勉なつるはしの先はようやく強固な岩塊を叩く。こつん」という文章は、この「小説家になる以外に自分の進むべき道はない。その決意は千歳の岩のように堅く、妥協の余地のないものだった」という「すみれ」の気持ちと対応したものかもしれません。
そして、「ぼく」は大学では文学ではなく、歴史学を専攻するのですが、そこでも「とりたてて歴史に関心があるわけではなかったのだが、実際にとりくんでみるとそれがなかなか興味深い学問であることがわかった。しかしだからといってそのまま大学院に進み(実はそうすることを指導教授に勧められたのだが)歴史学に身を捧げようという気持ちにはなれなかった。僕はたしかに本を読んでものを考えるのは好きだったが、結局のところ学者向きの人間ではなかった」というタイプの人間なのです。
この『スプートニクの恋人』の「ぼく」と「すみれ」は、文学好き、本好きの人間であることは共通していますが、でも、その方向性はかなり異なった2人ですね。
そんな「ぼく」が、自分の心の弱点に気がついていく物語が『スプートニクの恋人』です。
「すみれ」は「ミュウに髪を触られた瞬間、ほとんど反射的と言ってもいいくらい素速く、すみれは恋に落ちた」そうです。「小説家になりたいという望みをべつにすれば、わたしは人生に対してこれまでになにかを強く求めたことがなかった」「でも今、このたった今、わたしはミュウがほしいの。とても強く。わたしは彼女を手に入れたい。自分のものにしたい」と思ったのです。
「ぼく」は人生になにを求めているのか、よくわかっていない人間です。小説好きですが、大学では歴史を学びます。でも歴史学に身を捧げようという気持ちにはなれない人間です。それに対して、「すみれ」は小説家になる以外に自分の進むべき道はないと決意している人間です。とても強く、ミュウをほしいと思う人間です。『スプートニクの恋人』では、この「ぼく」と「すみれ」の違いをまず理解しておくことが大切かと思います。
そんな「ぼく」に大きな変化がやってくるのです。それはこんな場面です。
彼は「ミュウ」からの国際電話でギリシャの小島に駆けつけて、そこで「すみれ」の残した文章を読みます。
〈すみれの夢〉という見出しがついた文章がありますが、それは三人称で書かれていて「すみれはずっと昔に死んだ母親に会うために長いらせん階段を上っていた」と始まっています。「すみれ」の母親は彼女が3歳の時に亡くなっているのですが、「階段のいちばん上では母親が待っているはずだった。母親はすみれに伝えたいことがあるのだ。これから生きていくためにすみれがどうしても知っておかなくてはならない重大な事実を」と思って、「すみれ」は、らせん階段を上っていきます。そして、階段の終わりに母親が横になっているのですが、「お母さん」とすみれが叫ぶと、母親も口を開いて、何かを叫びます。でもその言葉は周囲の風音のせいで「すみれ」の耳には届きません。さらに母親は暗い穴の中に消えてしまい、振り向くと、階段も消えています。
彼女は高い塔のてっぺんにいます。下を見ると高さに目がくらんで、空には小さな飛行機のようなものがたくさん飛んでいます。一人乗りの飛行機です。自分をここから助け出してくれるように頼んでも、飛行士たちは彼女の方に顔を向けようとしません。「すみれ」は着ている服を脱ぎ捨てて、裸になってみると、小型飛行機が、とんぼに変化して空が大きなとんぼでいっぱいになります…。
「そこで目が覚めた」と〈すみれの夢〉には記されています。
そして「すみれ」は夢の細部まで覚えているのに、暗い穴の中に吸い込まれて消えていった母親の顔だけは、思い出すことができないのです。母親が口にした大事な言葉もやはり虚無の空白の中に失われてしまっていました。
その〈すみれの夢〉に続いてあるのが、〈床屋はもう穴を掘らない〉という文章です。
紹介した「わたしはひとつ重大な決心をした」という文の前には「この夢を見たあとで、」という言葉があります。つまり「この夢を見たあとで、わたしはひとつ重大な決心をした」と〈床屋はもう穴を掘らない〉は書き出されています。
この「すみれ」の書き残した文章の繋がりは、単純な接続ではないので、それぞれの読者が自分で受け取っていくしかないのですが、でもここで記されていることは、夢の中で会った母親の顔や、夢の中で聴いた母親の言葉を虚無の空白の中に失ってしまったように…その「あちら側」の世界、異界の世界へ、「すみれ」が自分のいる「こちら側」の世界から向かっていくということです。
「すみれ」は「ミュウ」に対しても、自分にとって、本当に大切なものを失わないために、自分の本当の気持ちを伝える勇気を持って、「こちら側」の世界から、「あちら側」の世界に向かっていき、「ミュウ」に自分の心を告げるのです。
もちろん、その気持ちが受け入れられなければ、深く、傷つきます。心に血が流れます。だって、生きている人間なのですから。
「いいですか、人が撃たれたら血は流れるものなんです」という言葉が何度か『スプートニクの恋人』の中で繰り返されます。その言葉がゴチック体で記された後、「だからこそ、わたしは文章を書いてきた」と続いています。
これは「すみれ」の文章の中の言葉ですが、どこか村上春樹自身の言葉のようにも読めます。なぜなら『1Q84』(BOOK3、2010年)の中にも「針で刺したら赤い血が出てくるところ」と名づけられた章があって、そこで編集者の小松から「なあ天吾くん、一人の小説家として、君なら現実というものをどう定義する?」と質問されて、「針で刺したら赤い血が出てくるところが現実の世界です」と天吾が答える場面があるからです。
〈床屋はもう穴を掘らない〉の中で「すみれ」は「もしミュウがわたしを受け入れなかったらどうする?」と自問します。それに対して「すみれ」は「そうしたらわたしは事実をあらためて呑み込むしかないだろう。『いいですか、人が撃たれたら血は流れるものなんです』」と文章が続いているのです。
「すみれ」は現実の中を、自分の心に従って、勇気をもって、「こちら側」から「あちら側」へ向かっていく人です。傷つくこと、血が流れることもありうることを覚悟しながら。
そして、ギリシャの小島で、その「すみれ」の文章を読んだ「ぼく」のほうにも、〈すみれの夢〉と対応しているような場面が訪れます。「すみれ」の文章を読んだ「ぼく」がギリシャのコテージで夜、「すみれ」がいた部屋でモーツァルトの歌曲集を聴きながら、眠ってしまいます。
その後、「音楽の音で目がさめた」と村上春樹は書いていますが、これは「そこで目が覚めた」という〈すみれの夢〉の言葉と重なっても読めますね。
午前1時すぎに目覚めた「ぼく」は、その音に誘われるようにして、音楽の聞こえる方に向かって、戸外の坂道を登っていくと音楽の響きは次第に大きくなってきます。
ひょっとして「すみれ」も数日前に、同じ体験をして、坂道を登ったのではないかと思いますが、歩を止めて背後を振り返ると、下りの坂道が、まるで巨大な虫が這ったあとのように白くぬめりながら町まで続いています。月光の下で、自分の手をみると、「ぼくの手はぼくの手ではなく、ぼくの足はすでにぼくの足ではなかった」と記されています。
「よくわからないところで、誰かがぼくの細胞を並べ替え、誰かがぼくの意識の糸をほどいていた」とも書かれていますし、さらに「時間が前後し、絡み合い、崩壊し、並べなおされた。世界は無限に広がり、同時に限定されていた」とも書いてあります。
〈すみれの夢〉では、亡くなった母親が暗い穴の中に消えていき、そこから〈床屋はもう穴を掘らない〉という「すみれ」の「重大な決心」に繋がっていくのですが、実はこの音楽に導かれて、山頂に向かう「ぼく」にも大きな変化が起きているのではないかと、私は思うのです。「僕の意識の糸」がほどかれて、時間が「並べなおされた」のですから。
「ぼく」がさらに坂道の続きをのぼると、5分ほどで山頂に出ます。
山頂で見た月は、荒々しく、激しい歳月に肌を蝕まれた粗暴な岩球でした。その表面の「不吉な影は、生命の営みの温もりにむけて触手をのばす癌の盲目の細胞だった」とも書かれていて、その山頂の世界は、つまり死の世界、異界のことでしょう。
村上春樹の長編小説では、必ずと言っていいほど、このような死の世界、異界の世界を通過することで、主人公たちの心が変化し、成長していくのですが、この「誰かがぼくの細胞を並べ替え、誰かがぼくの意識の糸をほどいていた」「時間が前後し、絡み合い、崩壊し、並べなおされた」とは、そのような死の世界、異界での経験によって転換される主人公の意識のことを記しているのだと思います。
山頂からコテージに戻った「ぼく」はブランデーを飲んで眠ろうとしますが、東の空が白くなるまで眠ることができません。
前々回も紹介しましたが、「すみれ」が突然、煙のように消えてしまった日の昼間に「すみれ」と「ミュウ」が、猫談義をする場面があります。その日の新聞記事の中から「すみれ」が記事を選んで「ミュウ」に読み上げるのですが、それは、飼い猫に食べられてしまった70歳の女性の話でした。その女性はある日、心臓発作で倒れ、そのまま亡くなってしまうのですが、それから1週間の間、猫たちは飢えに耐えかねて、死んでしまった飼い主の肉をむさぼり食べたという記事です。
そんな話を「ミュウ」から聞いた「ぼく」は、コテージで眠れない中、「ぼく」が死体となって「ねこ」たちに食べられている姿を想像します。その想像の中で、ようやく「ぼくの意識は陽炎のように揺らぎ、薄れていった」のです。
ここで「ぼく」は死の世界と接しているのですが、この時、「ぼく」は1つの転換を迎えていると思います。前回のコラム「村上春樹を読む」で、『1Q84』の男主人公である天吾が、死者の町である「猫の町」に行くことで、「猫の町」にある療養所で死の床にある父親と“対話する”ことで、大きく変化し、成長していったように、ギリシャの山上での月光の下、死の世界に接し、さらに猫たちに自分の体が食べられる世界を想像することで、「ぼく」は変化し、成長していくのです。
具体的に、どのように変化したのでしょう。
そのギリシャの小島の山頂の場面と、さらに重なるような場面が『スプートニクの恋人』の中にあります。それは「ぼく」がアテネのアクロポリスの丘にのぼる場面です。
「ぼく」は飛行機の手配を間違ってしまってか、1日の余裕が生まれ、アクロポリスの丘にのぼるのです。そのアクロポリスの丘の上で「あちら側」にいる「すみれ」のことを思います。「でもその世界への行き方がわからなかった」「ぼくという人間は否応なく、その時間性の継続の中に閉じこめられている。そこから出ていくことができない」と村上春樹は記しています。でもそれに続けてこんふうなことが書いてあるのです。
「いや、違う―そうじゃない。結局のところ、そこから出ていくことをぼくはほんとうには求めなかったのだ」
そのことに気がついたのです。勇気をもって、ほんとうのことを「すみれ」に言うことをしなかったということに気がついたのです。「そこから出ていくことができない」のではなくて、「そこから出ていくことをぼくはほんとうには求めなかった」人間であることに気がついたのです。
物語の前半、「すみれ」が東京の吉祥寺から、代々木上原に引っ越す手伝いを「ぼく」がする場面があります。その時「ぼくはすれみの身体を抱きたいと思った。そしてそのまま床のうえに押し倒したいという激しい衝動に襲われた」とあります。続けて「でもそれはむだなことだと、ぼくにはわかっていた。そんなことをしたって、どこにもいけないのだ」と記されています。そんなふうに思ってしまうのが「ぼく」なのです。
その時、「ぼく」の身体は強い性欲を感じていたのに、「そこから出ていくことを求めない」人間だったのです。
そのことの間違いに「ぼく」はようやく気がついたのです。「そこから出ていくことをぼくはほんとうには求めなかった」ということに気がついたのです。
「ぼく」が「いや、違う―そうじゃない。結局のところ、そこから出ていくことをぼくはほんとうには求めなかったのだ」と自覚したすぐ後のところには「ぼくはもう二度と、これまでの自分には戻れないだろう。明日になればぼくは別な人間になっているだろう。しかしまわりの誰も、ぼくが前とは違う人間になって日本に戻ってきたことには気づかないはずだ。外から見れば何ひとつ変わってはいないのだから」と書かれています。
それに続けて「それにもかかわらず、ぼくの中では何かが焼き尽くされ、消滅してしまっている。どこかで血が流されている」と、あの「すみれ」の文章の言葉である、ほんとうに生きようとする者への自覚が記されているのです。
日本に帰った「ぼく」は、それまでつき合っていた教え子の母親と別れます。その別れの前に、万引きで捕まった教え子をスーパーマーケットまで、その子の母親、つまり「ぼく」のガールフレンドと迎えに行きます。
教え子は「にんじん」という名前で同級生たちに呼ばれているのですが、その「にんじん」の前で、スーパーマーケットの「中村」という警備主任が「ぼく」や「にんじん」の母親に説教する場面があるのですが、その途中に、別の部署の者が来て「中村さん、保管庫の鍵を貸してくれ」と言います。
でも中村警備員が探しても、鍵はなかなか見つかりません。結局、万引きのほうは「もう一回同じことが起きたら」ということで、放免になります。「にんじん」の母親は先に帰るのですが、「にんじん」と2人だけになったときに、「ぼくは子供の頃からずっと一人で生きていたようなものだった」という話を「にんじん」にするのです。好きだった友だちが煙のように消えてしまったこと、その友だちがいなくなってしまったら、「ぼく」にはもう誰も友だちがいないこと。ただの一人もいないことなどを話すのです。
そして、「にんじん」の家まで歩いて一緒に帰るのですが、「にんじん」はポケットに手を突っ込み、赤いプラスチックの名札のついた鍵を取り出します。その鍵には「保管3」と書いてあって、それは中村警備主任が探していた鍵です。何かのすきに「にんじん」がそれを見つけて、素早くポケットに突っ込んだのでしょう。
この場面は、読者に非常に強い印象を残します。「にんじん」の強さに不意打ちに遭うような場面です。「なかなかやるね、この子は」というような感じです。「ぼく」もときどき、なにかの拍子にふと「にんじん」のことを考え、「不思議な子供だ」と思うのです。
そして「にんじん」について「必要とあればそれを素早く的確に実行にうつすだけの行動力が、その子供の中にはあった。そこには深みのようなものさえ感じられた」と村上春樹は記しています。その行動力は「ぼく」には欠けていたものです。でも、そのような行動力に深みのようなものさえ感じられるように「ぼく」は変化し、成長していたのです。
その成長の力によって、「すみれ」は「ぼく」のもとに戻ってくるのです。
☆
もう1つだけ、「すみれ」が帰ってくる力について、私の妄想のようなものがありますので、それを記しておきたいと思います。
この『スプートニクの恋人』というのは、タイトルと物語の関係が、いまひとつ掴みにくい作品です。「スプートニク」とは、1957年10月4日、当時のソ連が打ち上げた世界初の人工衛星の名前です。そのスプートニク1号打ち上げの翌月3日には、ライカ犬を乗せたスプートニク2号の打ち上げにもソ連は成功。そのライカ犬は宇宙空間に出た最初の動物となりましたが、衛星は回収されず、宇宙における生物研究の犠牲となったことが、本の扉に記されています。そこから付けられた題名ですが、そのスプートニクのことは、冒頭近く、「ビートニク」と「スプートニク」の記憶違いの話として出てくるのですが、物語が進んでいくと、「スプートニク」のことはあまり出てこないのです。
でも、そのスプートニクのことが、「ぼく」がアクロポリスの丘で、自分の内なる変化を自覚した時に出てきます。
「ぼく」はアクロポリスの丘の「平らな岩の上に仰向けになって空を見上げ、今も地球の軌道をまわりつづけているはずの多くの人工衛星のことを考えた」とあります。でもまだ空は明るすぎて、人工衛星の光は見えません。「ぼくは眼を閉じ、耳を澄ませ、地球の引力を唯ひとつの絆として天空を通過しつづけているスプートニクの末裔たちのことを思った。彼らは孤独な金属の塊として、さえぎるものもない宇宙の暗黒の中でふとめぐり会い、すれ違い、そして永遠に別れていくのだ。かわす言葉もなく、結ぶ約束ものなく」という文章中に、スプートニクが出てくるのです。そしてこの文章で、ギリシャでの話は終わり、次のページでは、「にんじん」の万引きで呼び出される話が始まっています。
これはいったい何でしょうか…。
私は『スプートニクの恋人』という作品は「引力」をめぐる物語ではないかと考えています。
たとえば、物語の前半部分でも、「すみれ」について「ぼくにいろんな質問をしたし、その質問の答えを求めた。答えが返ってこないと文句を言ったし、その答えが実際に有効でないときには真剣に腹をたてた。そういう意味では彼女はほかの多くの人々とは違っていた。すみれはその質問についてのぼくの意見を心から求めていた」とあります。村上春樹はその「心から」の部分にわざわざ傍点を打って記しています。「心から求める」ということには「引力」があると思います。
なぜなら、「ぼく」がアクロポリスの丘の上で「すみれがぼくにとってどれほど大事な、かけがえのない存在であったかということが、あらためて理解できた。すみれは彼女しかできないやりかたで、ぼくをこの世界につなぎ止めていたのだ」と思うのです。
「すみれ」は「心から求める」という引力で、「ぼく」を世界につなぎ止めていたのです。人工衛星たちが地球の引力で、つなぎ止められているように。
そのように考えてみると、これはちょっと冗談めいた指摘ですが、「にんじん」が犯した非行「万引き」にも「引く」という言葉が含まれていますね。
「ぼく」は「にんじん」に、子供の頃からずっと一人で生きていたようなものだったことを話します。「しかし大学生のときに、ぼくはその友だちと出会って 、それからは少し違う考え方をするようになった。長いあいだ一人でものを考えていると、結局のところ一人ぶんの考え方しかできなくなるんだということが、ぼくにもわかってきた。ひとりぼっちであるというのは、ときとして、ものすごくさびしいことなんだって思うようになった」と「にんじん」に話しかけています。その言葉も、私には人間同士の「引力」について語っているように読めます。
さらに「にんじん」がポケットから出した「保管3」の鍵を「ぼく」は、思い切って川の中に落として、捨てます。
そして「ぼくが手を差し出すと、にんじんはそっとその手をとった」とありますし、「ぼくはその手を握ったまま、彼の家まで歩いた」と記されています。
手を握ったまま、家まで歩くという村上春樹作品の主人公はとても珍しいですが、これも人と人との「引力」の場面のように考えれば、そのまま受け取ることができます。
さて、そして、「すみれ」がなぜ戻ってきたのかです。
それは、「ぼく」が「すみれ」を本当に求める力、その強い引力によって、「すみれ」が僕のもとに戻ってきたのではないかと思います。
「君にとても会いたかった」と「ぼく」が言うと、「わたしもあなたにとても会いたかった」と「すみれ」が言います。「あなたと会わなくなってから、すごくよくわかったの。惑星が気をきかせてずらっと一列に並んでくれたみたいに明確にすらすらと理解できたの」と「すみれ」は言います。「惑星直列」という現象を村上春樹は好きのようで『1Q84』にも登場しますが、これは惑星間の引力関係の特殊ケースですね。さらに「わたしにはあなたが本当に必要なんだって。あなたはわたし自身であり、わたしはあなた自身なんだって」と「すみれ」は言うのです。
これは好きな者同士の「引力」をめぐる会話とも言えます。思えば、「すみれ」は母を求めて階段を上っていきましたが、母の顔を覚えることができず、母の言葉も自分にまでは届きませんでした。「ミュウ」を求めても、受け入れられませんでした。
「ぼく」にも、求められませんでした。でも、今、「すみれ」は、彼女の書き残した文章を読み、そこから変身を遂げた「ぼく」に、本当に強く求められているのです。その「ぼく」の「すみれ」を求める引力によって、「すみれ」は「ぼく」のもとに帰ってきたのだろうと、私は妄想しております。(共同通信編集委員・小山鉄郎)
******************************************************************************
「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓

