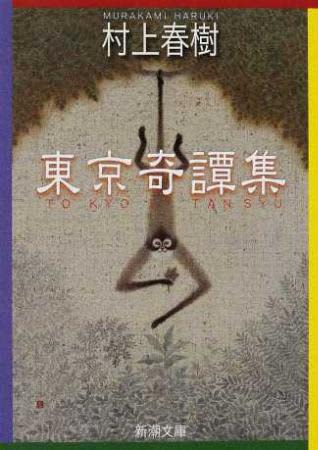
「できるだけ頻繁に移動し続けるんです」。短編集『女のいない男たち』(2014年)の「木野」の中に、カミタ(神田)という人物が出てきて、主人公の木野にこんなことを言います。木野は東京・青山の根津美術館の裏手で、「木野」という自分の名前から付けたバーを1人で経営しています。
店は経営も順調に行きかけていたのですが、店の客で体中に煙草の火を押しつけられてできた火傷のあとがある女と、「木野」の2階の部屋で木野が関係したあたりから、店の周囲に蛇が頻繁に出るようになってきて、少しおかしくなっていきます。
すると店の客であるカミタが「しばらくこの店を閉めて、遠くに行くことです」と言い、さらに「いいですね、遠くまで行って、できるだけ頻繁に移動し続けるんです」と言うのです。それはあまりに唐突な告知で、説明もなく、前後の理屈もよくわからないものでしたが、木野はカミタの言ったことをそのまま信じて、その夜のうちに旅行の荷物をまとめて、夜が明けると、「勝手ながら、当分休養させていただきます」という紙を店のドアにピンでとめて、高速バスに乗って、四国・高松に渡り、それから九州に渡るのです。
この「できるだけ頻繁に移動し続けるんです」という言葉は、作品の中で、意味なく置かれているものではありません。ある夜、熊本のビジネス・ホテルで木野が寝ていると、誰かが部屋のドアを執拗にノックする場面が作品の最終盤に出てきますが、そのノックを聞く前にも「そろそろ次の場所に移らなくてはならない。できるだけ頻繁に移動し続けてください―カミタにそう言われていた」と、その言葉が再び記されているのです。
この「移動」するということ、村上春樹作品の中で「移動」することが持っている意味はどんなものでしょうか。木野もカミタの言葉に対して、唐突で、説明もなく、前後の理屈もよくわからないもののように感じています。村上春樹も「移動」について説明しているわけではありません。ですからこれから記すことは、いつものように、私の読み、つまり妄想のようなものですが、村上春樹作品の中の「移動」について、いくつかの作品を通して考えてみたいのです。
☆
「私は移動する。ゆえに私はある」。「移動」することを、そのように女主人公「青豆」が自分の命題として宣言するところが『1Q84』の冒頭近く、BOOK1の第3章の中にあります。これはデカルトの「我思う、ゆえに我あり」からの引用でしょうか。ともかく、この「私は移動する。ゆえに私はある」という言葉は、その前後が改行されていて、少し目立つ形で表記されていますので、彼女の特徴を示す重要な宣言なのでしょう。
『1Q84』の中では「青豆」はもう1つ重要な宣言をしています。それはBOOK2で「青豆」が10歳の時から想い続ける「天吾」のことを考えながら「私という存在の中心にあるのは愛だ」と思う言葉です。『1Q84』の中に、女殺し屋として登場してくる「青豆」は「私は移動する。ゆえに私はある」「私という存在の中心にあるのは愛だ」という2つの宣言を抱いて生きている人間と言っていいと思います。
今回は村上作品の中の「移動」について考えたいので「青豆」の「私は移動する。ゆえに私はある」について述べてみますと、例えば『1Q84』という大長編は、高速道路を走るタクシーの中で、「青豆」がヤナーチェック「シンフォニエッタ」を聴く場面から物語が始まっています。『1Q84』はBOOK1、2が2009年に刊行されたのですが、そのBOOK2で、「青豆」が最後に登場してくる場面では、高速道路上で拳銃の銃口を口の中に入れた「青豆」が、愛する「天吾」のために死ぬことを思って、拳銃の引き金にあてた指に力を入れるところで終わっています。さらに翌年刊行されたBOOK3の最後は非常階段を昇って、高速道路に出た「青豆」と「天吾」が、高速道路上でタクシーを拾い、その2人が赤坂の高層ホテルの17階で結ばれる場面で終わっています。このように『1Q84』は高速道路にたいへんこだわった物語となっています。それもおそらく「私は移動する。ゆえに私はある」という「青豆」の宣言を反映したものでしょう。
村上春樹には一貫して、動きのないもの、停滞したものへの反発があると思います。1つだけの基準を決めて、全体をそれに合わせるように従わせて、個々の動きを抑制し、個人の自由な動きを許さないもの(例えば、明治以来の日本の近代の中にそのような一面がありました)に対する、強い否(いな)の意志があると思います。
例えば、『海辺のカフカ』(2002年)には、こんな言葉があります。
「移動しているあいだはたぶんそんなに危険じゃないはずだ」「移動を終えたときにそいつははじめて危険になる。すごく危険になる。だから移動しているときを逃しちゃいけない」
『海辺のカフカ』の最終盤に死んだ「ナカタさん」の死体の口から、ぬめぬめと、白く光る物体が出てくる場面があります。体長が1メートル近くもあり、尻尾もついている物体で、それが「ナカタさん」の口から、もぞもぞと身をくねらせて出てくるのです。これがかなり気持ち悪いですね。その白く光る物体を「星野青年」がやっつける前に「トロ」という名の黒猫が「星野青年」にアドバイスする言葉が「移動しているあいだはたぶんそんなに危険じゃないはずだ」「移動を終えたときにそいつははじめて危険になる」です。
だから「移動しているもの」=「悪」のように受け取れる言葉でもありますが、でも純粋に、そこに記された「移動」についての言葉だけを読んでみると、「移動しているあいだはたぶんそんなに危険じゃない」、そして「移動を終えたときにそいつははじめて危険になる」と書かれているのです。ここにも「移動すること」への村上春樹の特別な価値が記されていると思います。
☆
さて、私が一番最初に、村上春樹の「移動」への強い関心を受け取った作品は『ダンス・ダンス・ダンス』(1988年)です。
同作は『羊をめぐる冒険』(1982年)の続編ともいうべき物語ですが、その上巻に村上春樹の永遠のヒーローである「羊男」が出てきて、主人公の「僕」と「羊男」が話をする場面があります。そこで「羊男」が「僕」に、こんなことを言います。
「音楽の鳴っている間はとにかく踊り続けるんだ。おいらの言ってることはわかるかい? 踊るんだ。踊り続けるんだ。何故踊るかなんて考えちゃいけない。意味なんてことは考えちゃいけない。意味なんてもともとないんだ。そんなこと考えだしたら足が停まる。一度足が停まったら、もうおいらには何ともしてあげられなくなってしまう。あんたの繋がりはもう何もなくなってしまう。永遠になくなってしまうんだよ。そうするとあんたはこっちの世界の中でしか生きていけなくなってしまう。どんどんこっちの世界に引き込まれてしまうんだ。だから足を停めちゃいけない。どれだけ馬鹿馬鹿しく思えても、そんなこと気にしちゃいけない。きちんとステップを踏んで踊り続けるんだよ。そして固まってしまったものを少しずつでもいいからほぐしていくんだよ」
そんなことを言います。「こっちの世界」というのが、ちょっとわかりにくいですね。「僕」も「君の言うこっちの世界というのはいったい何なんだい?」と「羊男」に質問しています。「ここは死の世界なのかい?」とも訊いていますが、「違う」と「羊男」は答えています。「ここは死の世界なんかじゃない。あんたも、おいらも、ちゃんと生きている。我々は二人とも、おなじくらいはっきり生きている。二人でこうして息をして、話をしている。これは現実なんだ」とも羊男は答えています。
それに対して「僕には理解できない」と主人公も応えています。死の世界でないとしたら、意識の中の世界、記憶の世界…ということなのでしょうか。でもちょっと「こっちの世界」と「あっちの世界」についての問題は、また別な機会に考えてみるとして、「移動」についての視点から、この「羊男」の言葉を考えみましょう。
ここで羊男は「オドルンダヨ。オンガクノツヅクカギリ」と話しています。踊り続けて、固まってしまったものをほぐしていくんだとも話しています。ここにも、村上春樹の移動していくことへの関心と、固まって、停まってしまうことへの否の気持ちが表明されていると思います。
『ダンス・ダンス・ダンス』の下巻では「もう一度ダンスのステップを取り戻すのだ。みんなが感心するくらいに上手く踊らなくてはならない。ステップ、それが唯一の現実なのだ。それはきちんと決まっていることなのだ。考えるまでもない。それは僕の頭の中に一〇〇〇パーセントの現実として刻みこまれている。踊るのだ。すごく上手に」と「僕」は思います。これは上巻の「羊男」の言葉と対応するように書かれているのでしょう。
さらに「ユキ」というエスパーのような少女と「僕」が会話する場面では「我々はみんな移動して生きているんだ。僕らのまわりにある大抵のものは僕らの移動にあわせてみんないつか消えていく。それはどうしようもないことなんだ。消えるべき時がくれば消える。そして消える時が来るまでは消えないんだよ。たとえば君は成長していく。あと二年もしたら、その素敵なワンピースだってサイズがあわなくなる」などと話しています。
またユミヨシさんという女性に電話をかけて「僕らはどんどん移動しつづけている。そしてその移動にあわせていろんなものが、僕らの回りにあるいろんなものが、消えていく。これはどうしようもないことなんだ。何ひとつとしてとどまらないんだ。意識の中にはとどまる。でもこの現実の世界からは消えていくんだ」と似たようなことを話しています。
でもさらにユミヨシさんには「僕はそれが心配なんだ。ねえ、ユミヨシさん、僕は君を求めている。僕はとても現実的に君を求めている。僕が何かをこんなに求めるなんて殆どないことなんだ。だから君に消えてほしくない」と語っています。
そして現実に、ユミヨシさんと会った時には「ずいぶん時間がかかったけど、僕は現実に帰ってきた。いろんな奇妙なものの中を通り抜けてきた。いろんな人々が死んだ。いろんなものが失われた。とても混乱していたし、その混乱は解消したわけじゃない。たぶん混乱は混乱のままで存続しつづけるだろうと思うんだ。でも僕は感じるんだ。僕は一回りしたんだって。そしてここは現実だ。僕は一回りするあいだくたくたに疲れていた。でも何とか踊り続けた。きちんとステップは踏み外さなかった。だからこそここに戻ってくることができたんだ」と語っています。
この『ダンス・ダンス・ダンス』は作品が始まる前の、扉の部分に「一九八三年三月」と書かれています。そして、『ダンス・ダンス・ダンス』が発表されたのは1988年ですので、発表時点からすると5年前の話を書いた物語です。
前年の1987年に刊行された『ノルウェイの森』が1968年ぐらいのことから書かれているのを考えてみると、『ダンス・ダンス・ダンス』は発表年と作品の時代がいずれも1980年代という、村上春樹が当時と同時代の「現代を書いた小説」でした。
時代はバブル経済の真っ盛りの「高度資本主義社会」で、その中を登場人物たちがどのように生きていくのかという物語です。しかもバブル経済に、批判的な距離を取りながらも、その中を生きる普通の人々にも、しっかり思いを寄せて作品が書かれています。
「いろんな奇妙なものの中を通り抜けてきた。いろんな人々が死んだ。いろんなものが失われた」と「僕」は話していますが、例えば、この『ダンス・ダンス・ダンス』の中に「僕」の中学校の同級生の「五反田君」が出てきます。「五反田君」はいまは映画俳優になっていて、彼と再会するのですが、その「五反田君」はスーパー・カーの「マセラティ」に乗っています。そして「僕」のほうの車は「スバル」です。「五反田君」も昔「スバル」が好きで、最初の映画に出たギャラで、中古の「スバル」を自分の金で買ったことがあって「すごくそれが気に入ってた」と「僕」に話しています。
それが、なぜ「マセラティ」に乗っているかと「僕」が問うても、「五反田君」自身も「わからないな」と答えています。「経費を使う必要があるからだよ」「マネージャーがもっともっと経費を使えっていうんだ」と話すのです。つまり「五反田君」はバブル経済のために、自分が好きでもない自動車に乗らなくてはならないという人物です。
その「五反田君」は「マセラティ」ごと芝浦の海に突っ込んで、自殺してしまいます。そして「スバル」に乗っている「僕」は、くたくたに疲れていたが「でも何とか踊り続けた。きちんとステップは踏み外さなかった。だからこそここに戻ってくることができたんだ」という人間です。「僕」は、バブル経済、真っ盛りの中を移動しながら、でも大切な何かを踏み外さなかったのです。
そしてここがいかにも村上春樹的、私が「村上春樹のブーメラン的作品世界」という部分なのですが、そのバブル経済の側を生き、自殺してしまった「五反田君」に対しても「五反田君は僕自身なのだ」と村上春樹は書いているのです。1つの原理で、自分を正当化して、自分の価値観に合わないものを、自分とは関係のない人間のように切り捨てて考えられる人間もいますが、村上春樹はそういう人間とは違う思考をしていて、その反対側のものも、もしかしたら自分と入れ替わっていた人間かもしれないし、自分と決して無関係ではない人間だと考える作家なのです。
作品の最後、ユキから「五反田君のことを好きだったんでしょう?」と訊かれて、「僕」は突然、声がつまって、涙があふれてきます。「会うたびに好きになっていった」と「僕」は語っているのです。こういうところが実に村上春樹的ですね。
そして、この『ダンス・ダンス・ダンス』という作品は、やはり「移動」ということを強く意識にして書かれているのではないかと思います。そう思える理由をいくつか記しておきましょう。1つは上記したように、1980年代という日本のバブル経済の中を生きていく対照的な2人の人間、「五反田君」と「僕」を「マセラティ」と「スバル」という当時の自動車の車種を対比することによって、描きわけていることです。自動車は「移動性」の象徴ですからね。
もう1つは「ダンス」ということ自体が、動きながら、その動いていくさまそのものが、人が生きている躍動感や美しさを表現しているという点です。動いていくこと、移動することに、ダンス自体の本質があるのです。当時の現代、1980年代を生き抜いていく物語を初めて書いた時に、村上春樹が『ダンス・ダンス・ダンス』と名づけたということ、つまり「踊るんだ・踊るんだ・踊るんだ」というタイトルは、私には「移動するんだ・移動するんだ・移動するんだ」というふうに響いてくるのです。
『ダンス・ダンス・ダンス』は、昭和という時代の、1980年代のバブル経済を描いた作品で、時代はもうそういう時ではないという考えもあるかもしれません。そう考える人もいるかと思います。でも村上春樹という作家は、その1980年代に起きたことにこだわって書いている人ではないかと思います。
例えば、これまでの村上春樹の最も大きな2つの長編である『ねじまき鳥クロニクル』(第1部、第2部1994年。第3部1995年)は1984年の話から始まっています。そして『1Q84』もまたタイトルが示すように1984年の話です。これらは『ダンス・ダンス・ダンス』で描かれた翌年の物語なのです。
☆
もう1つ、作品の中に「移動」という言葉を含む小説を紹介してましょう。それは短編集『東京奇譚集』(2005年)の中の「日々移動する腎臓のかたちをした石」です。
この短編も結構、一筋縄ではいかない作品ですが、好きな短編ですので、「移動」の視点から、私なりの接近をしてみたいと思います。
この作品の語り手は「淳平」という短編小説家です。短編集『神の子どもたちはみな踊る』(2000年)の「蜂蜜パイ」という作品の語り手も小説家の「淳平」ですので、同一の設定と考えてもいいかもしれません。「淳平」は芥川賞候補に「五年間で四回」なったという作家です。「蜂蜜パイ」の淳平も五年間で四回、芥川賞候補になっています。
その淳平は父親から「男が一生に出会う中で、本当に意味を持つ女は三人しかいない。それより多くもないし、少なくもない」と言われます。父とは疎遠な関係なのですが、その言葉だけは「呪(のろ)い」のように淳平の中に残っています。
淳平には大学時代につきあった「本当に意味を持つ」女性がいましたが、彼女はいちばんの親友と結婚してしまった、と記されています。「蜂蜜パイ」を読んだ人なら、淳平の同級生・高槻と結婚した小夜子のことかな…と思うかもしれません。私もそう考えました。
つまり、淳平は以来、「本当に意味を持つ」女性はあと2人になったと考えているのです。新しい女性と知り合うたびに、「この女は自分にとって本当に意味を持つ相手なのだろうか」と考えてしまうのです。このために、淳平はしばらく様子を探るように女性とつきあい、ある地点に達すると自然に関係を解消するということを繰り返しています。
ある時、知人が小さなフレンチ・レストランを開店して、オープニング・パーティーに招かれて、背の高い、人懐っこいキリエという女性と出会います。キリエは「本物の小説家に会ったのは生まれて初めて」と話す快活な女性。淳平は彼女に心を惹かれるのですが、やっぱりこの女は「残された二人のうちの一人なのだろうか?」と思ってしまうのです。
そしてお互いの仕事の話となりますが、キリエのほうは自分の職業を明かしません。でも「ずっと以前から、小さな頃からやりたいと思っていたことを、私は職業にしているわけ。あなたの場合と同じように。ここに来るまでは決して簡単な道のりではなかったけど」というのです。
「それはよかった」と淳平も言って「すごく大事なことだよ、それは。職業というのは本来は愛の行為であるべきなんだ。便宜的な結婚みたいなものじゃなくて」と応えると、キリエは「愛の行為」という言葉に感心して、「それ、素敵な比喩ね」と言います。
こうやって、その夜のうちに2人は淳平の部屋で結ばれるのですが、このキリエとの付き合いや彼女との会話を通して、淳平が書いている短編小説が動きだしていくのです。
「あなたが今書いている小説の話をしてくれる?」とキリエが言うので、話すのですが、その作品は最後まで書けていなくて、「途中で一服したままになってるんだ」と淳平は答えます。でもキリエは「途中までの筋書きを聞きたいんだけれど」と迫ります。
普通は執筆途中の作品については淳平は話さないのですが、どうせ何日か一歩も進んでいないので、その小説について、キリエに話していくのです。
主人公は30代前半の女性。腕の良い内科医で、大病院に勤めている。独身だけど、同じ病院に勤める40代後半の外科医と秘密の関係を持っています。彼のほうは妻帯者です。
そんな彼女が趣味のバードウォッチングで河原を歩いているときに奇妙な石をひとつ見つけます。腎臓のかたちをした石です。内科医という専門職ゆえの発見で、サイズ、色合い、厚みも本物の腎臓そのままの石です。そして彼女は、その腎臓石を拾って持ち帰り、病院の自分の部屋で文鎮として使うことにするのですが、でも数日後、奇妙な事実に気づきます…。実は、そこで小説はストップしていました。
でも黙って話の続きを待っているキリエのために、淳平は物語が行く先を考えて話し始めるのです。
つまり、朝になると、その腎臓石の位置が移動しているのです。帰る時には決まった場所、机の上に石を置いていく。でも朝になると、椅子の上に載っていたり、花瓶のとなりにあったり、床の上に転がっていたり。鍵もかけてあるのに、石の位置が変化しているのです。
それを聞いてキリエは「腎臓石は自分の意思を持っているのよ」「腎臓石は、彼女を揺さぶりたいのよ。少しずつ、時間をかけて揺さぶりたいの。それが腎臓石の意思」と言います。さらに、キリエはくすくす笑いながら「医師を揺さぶる石の意思」なんて言うのです。こういうユーモアセンスのある女性って、素敵ですね。
村上春樹は言葉遊びが好きな作家ですが、この部分を読んで笑ってしまいました。もしかしたら「医師を揺さぶる石の意思」という言葉から、この短編が生まれたのかな…とも思ってしまったほどです。
そのキリエへ話しているうちに、淳平は、なんとか小説の先が書けそうな気がしてきたと話します。キリエも「その腎臓石がどうなるのか、私としては結末がとても知りたい」と言います。そうやって、キリエはこの小説を動かしていく存在です。そのキリエは、なかなかの予言者でもあるようで「私の印象ではあなたはいつか、もっと長い大柄な小説を書くことになると思う」と述べています。
これについて、「淳平」=「村上春樹」と受け取る人もいるかと思いますし、そのように思うのも、また読者の特権でもあるかと思いますが、でも必ずしもキリエの言葉に対して「淳平」と村上春樹自身を重ね合わせて、受け取る必要もないかと思います。
物語というものは動いていく、移動していくことに、その本質があると考えていることが反映しているキリエの発言なのではないかと思うのです。この作品の中でキリエは、中断していた小説を動かしていく存在であり、小説世界とは何かについて小説家・淳平に語りかける人でもあります。実際、動いていくことに、物語というものの本質があるとすれば、そのことを理解している小説家であるなら短編小説の世界だけにとどまってはいられないのではないの…、そんなことをキリエが語っているようにも受け取れるのです。
そして、キリエは「ねえ、淳平くん、この世界のあらゆるものは意思を持っているの」と小声で言います。眠りかけている淳平に向かって「たとえば、風は意思を持っている。私たちはふだんそんなことに気がつかないで生きている。でもあるとき、私たちはそのことに気づかされる。風はひとつのおもわくを持ってあなたを包み、あなたを揺さぶっている。風はあなたの内側にあるすべてを承知している。風だけじゃない。あらゆるもの。石もそのひとつね。彼らは私たちのことをとてもよく知っているのよ。どこからどこまで。あるときがきて、私たちはそのことに思い当たる。私たちはそういうものとともにやっていくしかない。それらを受け入れて、私たちは生き残り、そして深まっていく」と話すのです。
それから5日ばかり、淳平はほとんど外に出ることもなく、腎臓石の物語を書き続けます。キリエが予言したように、腎臓石はその女医を静かに揺さぶり続けます。その日々移動する腎臓石と女医は会話するようになります。つまり彼女がその石に小さな声で語りかけ、石が語りかけてくる「言葉ではない言葉」に耳を澄ますうちに、腎臓のかたちをした黒い石が、今では彼女の生活の多くの部分を支配しているようになっていきます。女医の心は、妻子ある恋人の外科医から離れていくでしょう…。
淳平とキリエの関係はどうなるのか。キリエの職業はどんなものなのか。それらも「日々移動する腎臓のかたちをした石」の中に書かれていますが、全部紹介してしまうのは、未読の読者に失礼ですので、興味のある人は、ぜひ作品を読んでほしいと思います。
ただこれだけは、記しておきたいです。淳平は最後に「男が一生に出会う中で、本当に意味を持つ女は三人しかいない」という父親からの「呪(のろ)い」の言葉から自由になっているのです。大切なのは数ではなくて、「大事なのは誰か一人をそっくり受容しようという気持ちなんだ」という理解に達して、父親の呪いのような言葉からの恐怖を乗り越えているのです。
また「職業というのは本来は愛の行為であるべきなんだ」ということについても、その小説を書くことによって、キリエと出会ったことによって、ほんとうの愛への理解が淳平にやってきています。この作品の「移動」も、固定した考え(つまり「男が一生に出会う中で、本当に意味を持つ女は三人しかいない」という考えや、妻子ある恋人の外科医にとらわれている女医の心)を揺さぶり、愛の力によって動かしています。
☆
この「日々移動する腎臓のかたちをした石」という作品も「移動」と「愛の行為」を書いているのだとすれば、『1Q84』の「青豆」の「私は移動する。ゆえに私はある」「私という存在の中心にあるのは愛だ」という2つの宣言と同じだとも言えますね。「腎臓のかたち」は空豆の種子のような形ですが、「空豆」と「青豆」って、何か関係があるのでしょうかねぇ…。それはともかく、『1Q84』のBOOK2の第16章に「天吾」が小学4年以来、会っていない「青豆」の大切さに気づく場面があります。そこに、こんな印象的な言葉が記されています。
「でもやっとわかってきたんだ。彼女は概念でもないし、象徴でもないし、喩(たと)えでもない。温もりのある肉体と、動きのある魂を持った現実の存在なんだ。そしてその温もりや動きは、僕が見失ってはならないはずのものなんだ。そんな当たり前のことを理解するのに二十年もかかった」という言葉です。
そのように「天吾」が受け取った「動きのある魂」が「私は移動する。ゆえに私はある」「私という存在の中心にあるのは愛だ」という「青豆」の2つの宣言が交差するところにある言葉でしょうか。『1Q84』の「天吾」の「青豆」への気持ちの発見と同じように、「日々移動する腎臓のかたちをした石」も「動きのある魂」をめぐる小説だと思います。
移動することには、動きの停まったものの心を揺り動かしていく力、自分の心の組成を組み替える時の恐怖を乗り越えさせていく力、動きのある魂を回復する力があるのでしょう。「木野」の移動も、そのような力が生まれるものであると思います。
最後に、その短編に登場するキリエの職業について、別な角度からヒントを書いておきたいと思います。それは『海辺のカフカ』の最終盤にゴチック体で記された言葉です。
「比重のある時間が、多義的な古い夢のように君にのりかかってくる。君はその時間をくぐり抜けるように移動をつづける。たとえ世界の縁までいっても、君はそんな時間から逃れることはできないだろう。でも、もしそうだとしても、君はやはり世界の縁まで行かないわけにはいかない。世界の縁まで行かないことにはできないことだってあるのだから」
そして、キリエの職業も世界の縁まで行く仕事です。未読でしたら、「日々移動する腎臓のかたちをした石」を、ぜひお読みください。(共同通信編集委員・小山鉄郎)
******************************************************************************
「村上春樹を読む」が『村上春樹クロニクル』と名前を変えて、春陽堂書店から刊行されます。詳しくはこちらから↓

