
市民がプロの裁判官と共に刑事裁判に参加し、被告の有罪無罪や量刑を決める裁判員裁判。制度の導入から約13年がたち、審理形式の一部に変化も見られるようになった。例えば、被害者の遺体や傷口の写真といった生々しい「刺激証拠」は、裁判員に直接見せず、イラストなどに加工して示す手法が一般的になりつつある。裁判員の心理的な負担を少しでも軽くし、裁判に参加しやすくしてもらうのが狙いだ。
一方で判決を出す上では重要な証拠の一つでもあり、それを見ずに裁くことに対して「誤った判断を招く恐れがある」と遺族や被害者から懸念する声も上がる。裁判員に配慮しながら、いかに公正な裁判を実現するのか。双方が納得できる“着地点”はあるのか。(共同通信=中山拓郎)
▽反省の気持ちを抱いたかもしれない
「裁判員に被害の状況が詳細に伝わらなかったのは残念だ」。2018年に京都市などで女性会社員=当時(27)=の切断遺体が見つかった事件。検察側が懲役13年を求刑したのに対し、裁判員らが下した判決は懲役8年だった。被害者の遺族は判決後の記者会見で、遺体の写真を神戸地裁が証拠として採用しなかったことに不満を漏らした。
「ぎふ犯罪被害者支援センター」(岐阜市)理事として活動する松井克幸さん(57)は、10年前に強盗殺人事件で妹=当時(40)=を亡くした。松井さんも、法廷で遺体の写真が示されなかったことに不満を抱いた。
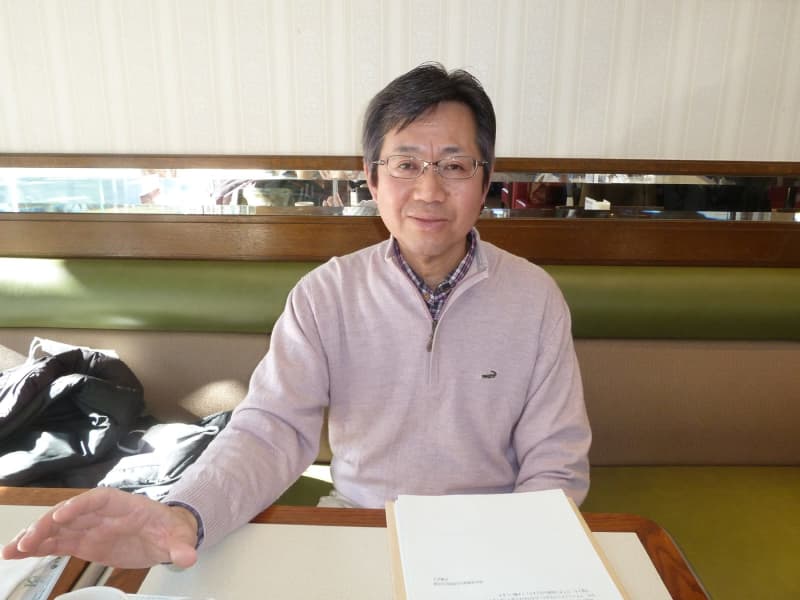
逮捕、起訴されたのは、妹の知人とされる男。裁判員らは計画性と殺意を認め、求刑通り無期懲役の判決を言い渡したが、それでも松井さんには悔しさが残った。
妹の顔には山林を引きずった際に付いたとみられる傷が複数あった。「『百聞は一見にしかず』で、遺体の写真を見れば犯行の残忍さがより正確に裁判員に伝わったはずだ」

男は公判で殺意を否認したが、妹の左胸の傷は心臓まで達していた。弁護側も「口論となった際に誤って刺さってしまった」などと訴えた。松井さんは「法廷で遺体の写真を見ていれば保身に走らず、反省の気持ちを抱いていたかもしれない」と振り返る。
▽「裁判官の余計な配慮」
裁判員制度は、刑事裁判に市民感覚を反映させることを目的に、09年5月に始まった。当初は裁判員に示されていた刺激証拠が、イラストなどに加工して裁判員に示す流れが定着したのは、ある訴訟がきっかけと言われている。
福島県会津美里町で起きた強盗殺人事件。裁判員を務めた女性は「現場の写真を見たことが原因で急性ストレス障害になった」として、国に200万円の損害賠償を求める訴訟を13年に起こした。判決は「立証には必要だった」と指摘し、女性は敗訴したものの、提訴以降「裁判官が及び腰になり、余計な配慮をするようになった」(検察幹部)とされている。
写真の代替手段はイラストに限らない。三重県四日市市で19年に起きた強盗致傷事件では、被害者の娘が口頭でけがの様子を説明した。当時の津地検幹部は「被害の状況は写真に如実に表れている。裁判員に見てもらえず、遺憾だ」と、裁判所の対応を批判した。
▽傷の部分を塗りつぶしたイラスト
一方で、刺激証拠に対する裁判員の反応はさまざまだ。
四日市市の強盗致傷事件を審理した裁判員の一人は「加工されていない証拠を見ていれば、もっと精緻な判断ができたと思う。個人的には見たかった。勝手に配慮がされたのかなと感じた」と話したが、別の裁判員は「刺激証拠を見て落ち込んだりうつになったりすることもある。(配慮は)必要だ」と言い切った。

20年に津市であった強盗致傷事件の裁判員裁判では、検察側が傷のカラー写真を証拠申請したが認められず、傷の部分が塗りつぶされたイラストが裁判員に提示された。裁判員の一人は「カラー写真だったら刺激が強かった。イラストでも被害の状況は十分に理解できた」と語った。
▽あえて感想を語らせる
プロの裁判官はどう考えるのだろう。元裁判官の波床昌則弁護士(和歌山弁護士会)は現役時代、強盗殺人事件の裁判員裁判で「殺意の強さを理解する上で欠かせない」と判断し、遺体の一部が写った写真を証拠採用した経験がある。
検察官は複数枚を申請したが、被害者の顔が写ったものは採用せず、直前に裁判員らに予告した上で提示した。
直後の休憩時間では、裁判員らにあえて写真に対する感想を語ってもらった。裁判員らは「ひどい」「あそこまでやるんですね」などと口々に話したという。
感想を語らせたのには狙いがあった。波床さんは「トラウマにならぬよう、一刻も早く消化させてあげたかった」と回顧する。裁判員からは、写真を証拠採用した波床さんを責めるような意見は出なかったという。
イラストなどの2次証拠については「描いた人の思惑が入りやすい」と指摘した。裁判員裁判の主体は被告で、裁判員は公判の“関係者”にすぎないと述べた上で「裁判員に忖度して、負担軽減に注力しすぎるとおかしなことになる。裁判員を引き受けた人には『裁判は厳しいものなのだ』と理解してもらうしかない」と強調した。

