
19世紀、欧米によって植民地化された東南アジアの二の舞にならないよう、明治政府は「強い国」になろうと中央集権化・国家主義化を推し進めていた。明治政府による上からの国作りに逆行する、国民主体の国のあり方を求める「自由民権活動家」の多くは弾圧を逃れるために米国西海岸に渡った。
「新聞」という媒体自体、もともと政府批判というスタンスが強く、明治初期の日本でも新聞創刊には自由民権運動家が関わることが多かったが、海外の邦字紙にも似たような傾向があった。
その一つ、1887年に米国サンフランシスコ郊外のオークランドで創刊された邦字紙『新日本』は、部数こそ200部と少なかったが、政治的亡命者のオピニオン新聞だった。米国から日本の新聞社や左派運動家に郵送され、そこを中継して大きな影響を日本全体に与えた。そのため明治政府は1888年、同紙を発禁処分にした。
第一次大戦前の北米同胞社会には、日本からの留学生や政治亡命者が多く、全般的に知的レベルが高く、その多くが一時期、邦字紙で禄を食んでいた。北米の体験的知識を叩きこんだ記者は、のちに日本のメディアで活躍したものも多かった。
例えばニューヨーク、ワシントンから外交関係の記事を毎日新聞に寄稿した「河上清」、大正から昭和にかけて朝日新聞外報部長として外交・国際評論を書いた「米田実」、戦前に外交・政治評論家として活躍して戦時中にも軍部統制を解明する貴重な記録である『暗黒日記』を書いて戦後出版した「清沢冽(きよさわ きよし)」などだ。
ロシア革命の功労者といわれる「片山潜(かたやま せん)」も、米国亡命中はサンフランシスコで邦字紙の釜のメシを食い、そこからレニングラードに直行して革命に参加した。
米国日本人移民は、ブラジル移民に比べるといろいろな点が異なった。第一に米国は明治維新後の日本国外交の中軸であり、留学生が常に多く、そこでの知見は日本で認められやすく、帰国することが容易だった。
ところがブラジルは地球の反対側に位置し、地理的に遠すぎて日本外交にとっては常に「周辺国」だった。それにブラジルの日本人移民は一般的に保守的な思想信条の持ち主が多かった。
でも、少ないながらも左派インテリも存在した。その代表格がアンドウ・ゼンパチ(本名=安藤潔、1900―1983年、広島県広島市)だ。彼に関する『アンドウ・ゼンパチ』(古杉征己著)が昨年末、サンパウロ人文科学研究所(人文研)から出版された。
「アカ移民」といわれた安藤全八
ブラジル日系社会唯一の移民史研究機関・人文研の故脇坂勝則顧問と2011年12月に話したおり、興味深いエピソードを教えてくれた。
《アンドウ・ゼンパチは1928年に一時帰国するとき、横浜港の沖で、『なくなくブラジル共産党の党員証をやぶって海に棄てた』といっていたよ。当時の日本にそんなものをもって帰ったら、どうなるか、よく知っていた。当時、アカ移民といわれた人はそう多くないが、彼がその一人であることは間違いないだろう》
本当であれば実に興味深い事実だが、今のところ、それを証明するものは見つかっていない。
アンドウ生誕110周年を記念して、1年間かけて彼の生涯を調べ上げて企画展を実施した古杉征己(人文研理事)は、《陸軍の軍人の子で、幼いころから厳しい教育を受けた。旧制中学の恩師江藤栄吉の影響で中江兆民などを耽読、啓蒙的な思想を抱くようになり、マルクス主義にも傾倒していった》(日本ブラジル中央協会会報『ブラジル特報』2012年5月号)と書く。
それから古杉は仕事や学業のひまを縫って10年がかりで執念の調査を続け、東京や広島にいるアンドウの子孫にも話を聞き、郷里広島の文書館でも調べてこの評伝を執筆し、刊行した。
「自分は金に縁のない男だから、『金』という字を分解して皮肉ってやろう」と筆名「全八」を使い始め、後に漢字すら捨てて「ゼンパチ」を名乗ったとの逸話は、コスモポリタン(世界市民)を理想とする彼の生き様を象徴するものだ。
日伯・三浦鑿に反体制物書きとして薫陶受ける
アンドウは1900年に広島県で、帝国軍人の家系の長男として生まれた。実母は父と離婚、継母に育てられるという複雑な家庭環境にあった。設置されたばかりの東京外国語大学ポルトガル科を卒業してすぐ、1924年に大毎移民団の輸送助監督としてブラジルに留学生として渡航した。
伯剌西爾時報を4カ月で辞め、逆に日伯新聞では2年間以上も三浦鑿社主の薫陶を受けて著述家としてのベースを形成した。28年に〝留学〟を終えて日本に帰国した。
三浦鑿は舌鋒鋭く日本政府批判の社説を書くことで有名で、反三浦派の策動によってブラジル政府から3度も国外退去命令を出された異例のジャーナリストだ。『風狂の記者―ブラジルの新聞人三浦鑿の生涯』(前山隆著、御茶の水書房、2002年)に詳しい。
アンドウの人格形成を古杉はこう要約する。
《家制度への重圧を感じたのは、旧制東京府立第4中学校への受験失敗である。軍人子弟が通う中学へ進学できなかったというトラウマは、家制度への疑問を掻きたてた。学生時代、軍事訓練中に上官の命令にわざと逆らってみせたり、同和教育へ関心を示したりしたのは、士族の格式や軍人の家柄というしがらみにとらわれることなく、自らの思想に従って自由な世界で行きたいという、アンドウの反抗心の表れでもあった。人格・思想形成期が大正デモクラシーの時代と重なったことで、リベラルで左翼的、かつ反体制的な生き方が増幅した》(『アンドウ』106頁)
アンドウは帰国直後、友人と共にブラジル移住を志す若者を教育する横浜外国語学校を創立経営し、初恋も経験した。だが世界大恐慌のあおりを食って32年に閉校となった。
当時、安藤家の戸主だった長男アンドウは学校経営という家業を失い、家柄の問題で継母から初恋の相手との結婚を拒絶された。そんな頃にブラジル時代の恩人・高岡専太郎が訪日した際、再渡航を誘われた。
継母の実子である弟に戸主の座を譲り、渡航1カ月前に別の相手・尾木清子(おぎきよこ)と結婚し、新妻を連れてブラジルへ渡った。生涯で3人の女性と家庭をかまえたアンドウにとって、初婚の相手だった。
再渡伯後、マルクス主義著作家の本領発揮
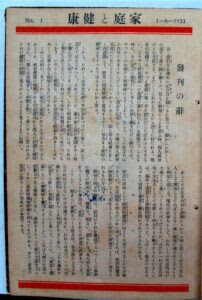
そこからが彼の本領発揮だった。アンドウは新妻を連れて33年に再渡伯。現地で著述家として清貧を貫くアンドウを、良家に生れた清子は家財を売って5人の子供を育てて支えた。この妻の内助の功のおかげで、安藤潔は著述家「アンドウ・ゼンパチ」に変貌していく(112頁)。
33年、高岡と共に日本移民への医療支援組織・互生会を作り、雑誌『家庭と健康』を刊行し、当時としてはベストセラー6千部を発行するまでになった。だが高岡と方向性を巡って決裂し、38年には月刊誌『文化』を創刊した。
コスモポリタン的なアンドウの生き方を象徴するような雑誌であり、反戦主義や同化論を基調にすえていた。ブラジル生まれの青年層にターゲットをあてており、戦前としては画期的な出版物だった(148頁)。

古杉はその雑誌を通して感じられるアンドウの主張をこう総括する。《一般的な移民は、政治・経済的な理由で祖国を後にする。アンドウが考えたコスモポリタン的な生き方とは、何だったのか。ただ単に国民国家というものを超越して、世界市民として生活することだけではない。おそらくは、祖国の文化を背負ってブラジル社会に入り込み、国家形成に大きく寄与することだったろう。それはブラジル社会に孤立した小さな日本を作ることではない。(中略)ブラジル国の一部として、社会へ貢献できる移民社会の形成だった》(154頁)
輪湖俊午郎が1939年に実施した調査では、日本移民の9割が帰国希望と応えている時代に、アンドウはこの雑誌で永住と同化を説いた。軍国化する日本世論に同調を強める当時の邦人社会の方向性に対し、真っ向から対立する軸を打ち出していた。マルクス主義者でコスモポリタンなアンドウらしい雑誌だった。
ヴァルガス独裁政権が1939年に児童への外国語教育を禁止した際、同胞社会は悲嘆にくれた。日本語教育なくして日本文化を継承した子孫を育てることは不可能だというコンセンサスがあったからだ。
だがアンドウは違った。《日本語を教へることができなければ、これこしたことはない。しかし、僕はポルトガル語の肥料をやつても不都合はないと思ふ。殊に、日本文字、日本語による学校教育をしなければ枯れて死んでしまうといふほど絶対的なものじゃないと思ふ。[……]僕はポルトガル語でも、エスペラント語でも、英語でも、日本人的な美しい性格を養ふためには差支えないと思ふよ》(167頁)
そして、古杉は《アンドウの同化論は、同時代の人々には支持を受けにくかったかもしれないが、現代も含め、。後の時代の人々には大いに参考になるに違いない。まさに「故(ふる)きを温め」るべき先人の思想・研究である》(164頁)と評価している。
同化を主張するこの雑誌も、ヴァルガスの外国語出版物規制の強まりと共に39年に廃刊に追い込まれた。
戦後に人文研創立、永住帰国して初恋の人と結婚
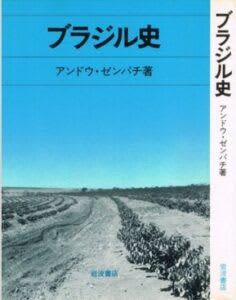
戦後、彼は私的勉強会「土曜会」を組織し、それが後に人文研に変わった。移民50周年を盛大に祝った翌年1959年、「一時帰国」のつもりでアンドウは日本に旅だった。実に26年ぶり。還暦を目前にした初老の年齢になっていた。
ところが日本到着してすぐ、初恋の相手・遠山静子に連絡を取った。彼女は結婚した夫に先立たれ、未亡人になっていた。そしてあろうことかアンドウは日本滞在中、静子の家に世話になり、最終的に結ばれた(281頁)。だが当時、アンドウは二人目の妻ふみと結婚していたのだから、不倫だった。それゆえブラジルでの離婚裁判は泥沼化した。
初恋相手との関係成就に伴って、一時帰国は永住帰国になった。病気をおして、日本でそれまでの集大成のような仕事を成しとげた。『ブラジル史』(岩波書店、1983年)の出版だ。刊行1カ月後、それを見守るように息を引き取った。
アンドウが心配した通り、同胞社会は戦争中に「孤立した小さな日本」を作って勝ち負け抗争を起こした。だがその結果として、50年代からは「ブラジルに骨を埋める」という永住の流れに進んで行った。
その一方で、戦前からあれだけ熱心に「永住論」「同化論」を唱えた本人は、同胞社会の流れと逆行するように、人生の最後で日本に帰った。これもまた人間模様だ。
古杉はそんなアンドウの生涯を振り返り、次のような示唆をする。
《日本には二十万人を越す日系人が生活し、日常生活における文化衝突からデカセギ子弟の教育に至るまで、さまざまな問題が日伯両国の懸念材料になっている。「共生」「共存」といった言葉が流行りになっているのは周知の通りだ。少子高齢化に悩む日本は、労働力不足を解消するために、外国人労働者に頼まざるを得ない。
そんな今だからこそ、先人の知恵に頼ることも重要である。戦前戦後合わせて約二十五万人の日本移民がブラジルへ渡り、世界最大の日系社会を築き上げた。百十年に及ぶ歴史の中で、ブラジル社会への同化(統合・融合)問題や子弟教育は繰り返し議論されて来た。このような日本移民の営為から、学ぶことは少なくない。とりわけアンドウは思想的指導者の一人だったから、調査・研究の対象として大いに価値がある》(『アンドウ』9~10頁)
ロマンに生きた左派移民
移民にインテリが少ないのにはわけがある。異文化に適応するには、ある種の「いい加減さ」「寛容さ」が必要だ。インテリは自分が人格形成した環境をきっちりと移住先に再現したいと考えがちになり、大変な苦労をした末、途中であきらめて帰国することになりがちだからだ。
経済的に言えば、家庭の財政状態がしっかりしていた方が、幼少時から良い教育が受けられ、結果的に高学歴になりやすい。つまり、裕福な家庭の方がインテリになりやすく、経済的な理由に背中を押されて移住する庶民とは一線を画する部分が最初からある。
人格形成の点からいっても、教育が少ない人の方が「理屈がすくない」特徴がある。「高い理想をもとめない」態度が身についている。だから理想と現実が違っていても、素直に「『郷に入っては郷に従え』だからしようがない」と妥協、納得しやすい部分がある。
ブラジルの移民社会の中心層は、貧しく低学歴の地方農村出身の家族であり、家長は農家の次男、三男だった。そんな彼らが最初は「日本型の村社会」を南米の再生しようとしながらも、最終的には「郷に入っては~」と現地適応しながら、日本的な考え方や文化を一部に残してきた流れが移民史といえる。
南米では、北米のような留学生や高学歴者はごく少なく、日本から革新的な政治思想が持ちこまれても広まる素地はなかった。ただ一つ言えるのは、左派移民もまた、異国の苦しい生活の中でロマンに生きた人間臭い人たちだったことだろう。(深)
(『アンドウ』入手に関する問い合わせは人文研まで。住所(Rua São Joaquim, 381, 3º andar, sala 35, CEP 01508-900, São Paulo – SP, Brasil)、電話・FAX番号11・3277・8616、Eメール〈contato@cenb.org.br〉)
