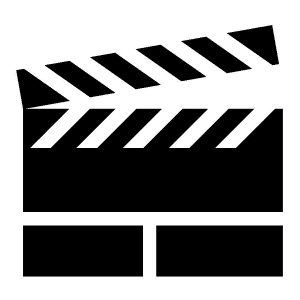はじめに
お疲れ様です。茶一郎でございます。この動画を公開した翌日には『ドライブ・マイ・カー』がアカデミー賞を獲っていると思います(編集註:動画公開は27日。日本時間28日発表のアカデミー賞では国際長編映画賞を受賞)。このチャンネルでは昨年2021年の新作映画ベストでした。視聴者の皆様が選んだベストでも、有名大作が並ぶ中、ベスト10に入り込みました。賞を獲ったからすごいのではなく、ただ単にすごい映画だった。今更感もありますが、魔法としか思えない奇跡的瞬間をフィルムに刻んだ、この『ドライブ・マイ・カー』。その魅力をお話ししたいと思います。短いドライブですが、お付き合い下さい。お願いいたします。

どんな映画? その6本の原作
『ドライブ・マイ・カー』はとてもシンプルな映画です。妻を亡くした舞台演出家兼俳優の主人公・家福が、ある演劇を作る過程で色々な人と出会い、心の傷、喪失と向き合う過程を、3時間弱かけてじーっくり、それこそ信号のない大通りを時速20キロでゆっくり走るように、静かに丁寧に描くシンプルな作品です。観終わった後、心に残るのはこのシンプルな美しいドライブ体験なんですが、その道中、これはこれは複雑な要素と遭遇することになります。
『ドライブ・マイ・カー』、宣伝だと「原作・村上春樹」という文が推されています。ただ村上春樹さん原作の短編「ドライブ・マイ・カー」だけがこの映画の原作ではないんです。ここが厄介であり、この映画の豊さでもあります。最低でもこの映画、原作が6つ、6個原作あると言い切ってしまいましょう。村上春樹さん原作の短編は50ページ弱ですから、それを3時間の映画にするために別の要素も追加されています。
まず他の村上春樹さんの小説ですね。短編「ドライブ・マイ・カー」が収録されている短編集「女のいない男たち」に同じく収録されているあと2つの短編、「シェエラザード」そして「木野」、これらを合わせて3つの村上春樹さんの短編が映画の骨格となっています。合計3つの原作。
それだけではありません。この映画『ドライブ・マイ・カー』は昨年、海外の映画媒体で軒並み2021年ベスト1もしくは2位、3位を独占しておりました。海外の観客に強く作品の魅力が伝わった要因として、この映画『ドライブ・マイ・カー』はロシアのアントン・チェーホフという、あの有名な戯曲家の「ワーニャ伯父さん」という戯曲が、ストーリー・人物関係/変化の基になっていると同時に、ストーリー自体も主人公・家福がこの舞台「ワーニャ伯父さん」を作る過程をそのまま映画にするという、そもそも全世界的に超有名な世界共通言語の演劇が元、原作になっている、映画が『ドライブ・マイ・カー』です。既存の演劇をそのまま映画のストーリーに繋げていくという。
監督の濱口竜介さんは、例えば過去作『寝ても覚めても』でも、同じくチェーホフの「三人姉妹」を引用したり、イプセンの「野鴨」という戯曲を劇中に登場させながら、映画のテーマと重ねました。こういう演劇をベースに、軸にして映画を作るというのがお得意な監督なんですね。
それだけありません。6個ありますからね。実は本作『ドライブ・マイ・カー』の展開と、演劇を作る過程がそのまま映画になるという設定は、濱口竜介監督の過去作、2012年の映画、これ大傑作です、『親密さ』という映画が元になっています。
さらにさらに最後6個目は監督の演出法です。ご覧になった方は驚いたと思うんですが、この映画の中盤は濱口監督の演技演出法がそのまま映画に登場するんですね。しばしば「濱口メソッド」と言われますが、その演出をまとめた監督の著書「カメラの前で演じること」これを原作として監督の演出論を映画の物語に組み込んでいます。
したがって今までザーッとまとめた6個の原作から、この映画『ドライブ・マイ・カー』を表すと、本作は村上春樹さん3つの短編が原作の、現代新解釈版「ワーニャ伯父さん」であり、商業映画にブラッシュアップされた『親密さ』であり、濱口監督の演技演出についてのある種、論文映画だと。とっても観た後は多くの方が感動できるシンプルで力強い映画なんですが、多くの要素を見事に有機的に融合させた、豊かに絡み合わせた監督の集大成と言えると思います。これを達成したことが奇跡のような映画だなと思って僕は観ました。
他にも、この映画は日本映画ですが、あらゆる言語が飛び交いますね。日本語はもちろん英語、韓国語、北京語、マレー語、ドイツ語、タガログ語、何より手話、韓国式手話と、この多様な言語が飛び交うというのも豊かな映画体験を補強しています。ということで、シンプルですが複雑な映画であると。実際、どういった形で監督、映画の魔法を作品に刻んだか、特に最後に挙げた原作、監督の演出論がどう映画に昇華されたのか、具体的に『ドライブ・マイ・カー』の魅力、まとめていきます。少し早いですがここからは映画の具体的な展開に触れます、ここからは絶対に本編、3時間弱の奇跡のドライブをご体験いただいた後にご視聴(ご覧)ください。

以下は本編をご鑑賞後にお読みください。
車というメタファー
『ドライブ・マイ・カー』は「車」がいろいろな意味を持つ見事な「車映画」でしたね。主人公・家福が愛車とする赤いサーブ・900。原作だと黄色でしたが映画では赤色となっています。15年乗っている愛車というこの赤いサーブですが、とても不思議なモチーフですよね。
何度も劇中、このサーブが公道を走っている様子が映りますが、一緒に横を走っている現代的な普通の車たちから浮いている。15年乗っているのにピカピカで傷一つ汚れもない。ドライブ映画にあるまじきガソリンを入れるシーンも、エンストするシーンもない。ちょっとこのサーブだけ現実味がない、ある種、象徴化された「車」としての記号のような存在が家福の車サーブだと思います。
そしてこの映画『ドライブ・マイ・カー』ではその象徴化を加速させるように「車」が車というだけではないいろいろな意味を持ちます。
最もストーリーに関わるのは、主人公を閉じ込める「牢獄」としての「車」ですね。妻を亡くした主人公は、その妻を助けられなかったという罪悪感、そして夫婦間に抱えていたお互いの秘密・疑念を晴らせないまま妻と死別してしまった。その亡き妻が主人公を閉じ込めているイメージがこの「車」に置き換わっています。
とても面白い描写として、主人公は運転しながら車の中で、演劇「ワーニャ伯父さん」のセリフを練習します。妻に頼んで事前に吹き込んでもらった自分以外の役のセリフを、カセットテープで車の中で流し続ける。そうすることでセリフを覚えていくと。したがって妻の死んだ後も妻の声が車で流れる、この車を通じてテキストが死んだ妻から発せられ続ける。車が唯一、死後の妻とつながれる心霊的な装置にも見えてきます。
さらに不気味な事に、本作は全編、この亡き妻が生前録音した「ワーニャ伯父さん」のセリフが流れ続ける映画ですが、その流れるセリフが、映画『ドライブ・マイ・カー』自体の物語展開、そのシーン、そのシーンそれぞれを表すようなセリフになっている。この緻密な構成もさることながら、どこか亡き妻が主人公どころか、映画のさらに上、高次元の存在として映画の展開を予言しているような不気味さすらカセットテープには感じます。
この『ドライブ・マイ・カー』は、時系列が直線状のシンプルな編集の映画で、とても見やすいんですが、ワンシーンだけ時系列が過去に戻るものがあります。過去というか主人公の見る悪夢・夢ですね。主人公が車の中で寝ていると、亡き妻が戯曲「ワーニャ伯父さん」のセリフをカセットテープに録音している過去の様子を見る。サーブ900の回転する車輪/タイヤが回転するカセットテープと重なっていく。やはりこの車が、妻という牢獄、正しくか亡き妻への罪悪感という牢獄を表しているような、とっても怖い編集がありました。
「車」が霊的な装置であり、牢獄であり、後半は演劇の舞台にもなると、こんなに一つの映画で「車」がいろいろな意味を持つのも見事ですね。この象徴化されたサーブ900、これに乗って主人公はテキストを巡る旅を通じて自分自身の喪失を向き合う、精神的なドライブをしていきます。

「テキスト」をめぐる物語
「テキスト」「テキスト」「テキスト」。『ドライブ・マイ・カー』は、観ているとイヤと言うほど「テキスト」という言葉を聞かされます。中盤からは主人公・家福が、舞台「ワーニャ伯父さん」を広島で作る、舞台作り自体が映画のストーリーになります。その稽古で「自分のテキストに集中してみろ」と主人公が俳優・高槻に言う。
ちょっと濱口監督作を見慣れていない方は、この演劇を作る過程そのものがストーリーになるという構成に驚かれたかもしれません。ただ濱口監督作といえば、劇中劇なんですね。この映画では映画内演劇。この構成の元をたどれば、何と濱口監督の学生時代まで振り返ることができます。東京大学の映画サークルの卒業制作として撮られた『何食わぬ顔』という映画です。この『何食わぬ顔』でも主人公が映画を作るという、映画作りそのものがストーリーになって、その映画作りの過程で人間関係が変化していくドラマが描かれます。映画後半はその作った映画内映画をそのまま見せられるという劇中劇構成映画こそ濱口監督作です。
本作『ドライブ・マイ・カー』に最も直接的につながるのは、先ほど原作として名前を挙げた2012年の『親密さ』という映画です。この『親密さ』の主人公も、家福と同じく、演劇の演出家の女性です。恋人の男性は脚本家。演劇『親密さ』という映画内演劇を作る過程そのものが映画のストーリーになると。まさしく『ドライブ・マイ・カー』の展開そのものです。
この『親密さ』でも演劇に出るはずのある俳優が出られなくなってしまうと。主人公の恋人の男性がその代役をするのか、しないのかというドラマになる。もうお分かりの通り、この『ドライブ・マイ・カー』の岡田将生さん演じる俳優・高槻が演劇に出られなくなると。主人公がその代役するのか、しないのか、全く同じ展開を繰り返しているんですね。
『親密さ』の演劇シーンの観客席にいる演出家の主人公を映すショットも、本作では演劇を見るドライバー・みさきのショットとして反復されます。ただ本作はこの『親密さ』のドラマをものすごく分かりやすくエンタメにしていますので、ある種、『親密さ』の商業映画版が本作と言えます。この『親密さ』からつながる劇中劇、映画内演劇を作る過程で何度もセリフに登場する「テキスト」。
もちろん全編、亡き妻が録音した「ワーニャ伯父さん」のテキストが流れ続ける本作。「ワーニャ伯父さん」というテキスト。また妻は生前、主人公と性行為をすることでテキストを授かる。これ映画ご覧にならないと分かりづらい設定ですね。元俳優で脚本家だった亡き妻は主人公と性行為をすることで、まるで二人の子供のように物語・テキストを授かって、そのテキストを主人公に語ると。翌朝、妻は記憶をなくしているので主人公は妻から語られたテキストを再び、妻に教えて上げる。ちょっと性行為で物語を授かるというのは、神から神託を受ける巫女さんみたいでちょっと宗教的ですよね。
ちなみにこの性行為を通してテキストを語る女性という、この妻の設定は先ほど言った村上春樹さんの原作「シェエラザード」から取っています。前世がヤツメウナギの女性の物語ですね。
ともかく本作において、失う事を恐れて関係性が悪くなっている主人公、夫婦をつなぎ止めていたものがテキストだった、と。性行為とオーガズムによって妻がテキストを授かり、それを主人公が覚えて、再びテキストとして翌朝、妻に語ってあげる。このテキストのキャッチボール。子供を亡くした夫婦は、このテキストというまた別の形の子供を通じて唯一のコミュニケーションをしていた、つながっていた。「テキスト」「テキスト」「テキスト」さて一体、何なのか?これが先ほど最後に挙げた原作、濱口監督のとても特殊な演技演出、そして「テキスト」に対する誠実な姿勢が関わって、最終的に家福の物語のラストにつながってきます。

濱口監督の演出法について
濱口竜介監督はとても古典的な演出法を基に、独自の演出をされる監督です。これが「濱口メソッド」なんて言われたりします。中盤の主人公が行う舞台稽古のシーンは、この「濱口メソッド」をそのまま見せるという、監督のことを知らないと映画のストーリーに関係のないように見えてしまいますよね。どういった演出家なのか?
まず監督は絶対に役者さんにセリフを覚えさせないんですね。セリフを覚えさせずに、撮影の前に緻密なリハーサルを行います。そのリハーサルでは、台本を読み合う「本読み」を何回も何回も繰り返します。加えて、その本読みにおいて、絶対のルールがあります。セリフにイントネーション、抑揚をつけてはいけない、感情を入れてはいけないと。自分の読むセリフが他の俳優さんに伝わるように、はっきりとテキストを読む。
映画をご覧になった方は分かると思います。例えば「すごい面白い映画ですね」という台詞があります、これを「すごい面白い映画ですね」とは読まないんですね。「すごい・面白い映画・ですね」と、棒読みで読むんですね。「畜生、畜生め」じゃなくて、「ちくしょう・ちくしょうめ」。こういう風に読むと、これ何の効果があるの?という話ですね。
これは監督曰く、イタリアの演劇界で使用されていた演出法で、「イタリア式本読み」と言うらしいんですね。恥ずかしながら、僕は監督の著書で初めて知ったんですが、ジャン・ルノワールという映画監督が出演しているドキュメンタリー『ジャン・ルノワールの演技指導』という短編で、監督はこれを知ったそうです。感情を入れないことで、俳優に偽物の作り物の感情を用意させない。徹底的に脚本(ほん)・台本というテキストに俳優を向き合わせると。何度もはっきりセリフを読み合って、何度もセリフを「聞く」ことで、その脚本(ほん)にあるテキストが俳優の体の中に入り込んでいくと。
ここで濱口監督の著書「カメラの前で演じること」、2015年の『ハッピーアワー』という映画を撮った際の演出法についての監督の言葉を、ちょっと長いですが、一番この映画を表しているので引用します。「彼女らは(役者さんたちは)自分で自分のセリフを無色透明のまま“聞いて”覚える。(中略)彼女らもまたテキストを聞きながら、変わっていっているようだった。(中略)繰り返される本読みの中でテキストを聞き取り、彼女たちは『テキスト的人間』になりゆくようだった。(中略)それはテキストがテキストのまま、演者に保持されている状態であり、テキストと演者それぞれが別のもののまま、共存しているような状態だ。(中略)それは『自分が自分のまま、別の何かになる』ための準備だったように思われる」。何となくお察しの良い方はこの映画の正体がお分かり頂けたと思います。
濱口メソッド、イタリア式本読みにおいて、テキストに体を差し出して、それに応えることで、監督は「テキスト的人間」と面白い表現をしていますが、そのテキストを自分の中に入れ込んで、実際に舞台でそのテキストを発することで「別の何かになる」。その、生まれ変わるといのが演技なんだ。その俳優に起きた「別の何かになる」生まれ変わり。その魔法のような瞬間を映画に刻むという試みが、本作『ドライブ・マイ・カー』と言えます。
「テキスト」で生まれ変わる
実際に劇中、テキストで生まれ変わる人物が、何人もこの映画には出てきます。最初に登場するのは、舞台に出演する俳優・イ・ユナという、韓国式手話を使う俳優さんです。イ・ユナはダンサーでしたが、妊娠中にお腹の子供を亡くしたことで、動けなくなってしまったと。家福と同じく大きな喪失を抱えた人物ですが、今回この「ワーニャ伯父さん」の稽古、本読みをして、テキストを体に入れ込むことで、段々と動けるようになってきた。劇中のセリフだと、「チェーホフのテキストが私の中に入って、体を動かしてくれる」と手話で伝えます。これは濱口メソッドの理念、理想像と言ってもいいかもしれません、それをそのまま言っているのがイ・ユナのセリフなんです。テキストを自分の中に入れ込み、演技をすることで「別の何かになる」「生まれ変わる」。実際、イ・ユナさんは生まれ変わったと。
濱口監督は2015年の『ハッピーアワー』という、役者さん以外の演技経験のない方、いわゆる素人の方だけを起用して、実際に映画の演技を通じて、その素人の方を生まれ変わらせた演出法「濱口メソッド」をそのまま今回、映画の中でそれを説明して、物語的に実施しているという、ちょっとメタ的な演技演出論映画としての側面が『ドライブ・マイ・カー』にはありました。

「テキスト」のその先を観客へ見せる
そして演出論、生まれ変わりのその先も、今回見せようとします。物語が進むと、本読み稽古が終了して、立ち稽古のシーンになります。広島の平和記念公園のシーン、俳優の2人イ・ユナとジャニスの立ち稽古シーンですね。ここで先ほどの通り、明らかに二人が今までの二人とは違う、「ワーニャ伯父さん」のキャラクターとして生まれ変わっている稽古シーンの長回し、長いワンシーンを見せられます。
まさしく濱口監督の言う「別の何かになっている」2人です。何だこの美しいシーンはと。初見時は涙が出ました。ここで主人公・家福はこう言います。「今2人の間で何かが起こっていた」。この何かは、先ほど言った「演技で俳優が自分以外の別の何かになる」ということですね。「今何かが起きていた。でもそれはまだ俳優の間で起きているだけだ。次はそれを観客に開いていく。一切損なうことなく。それを劇場で起こす」。不思議な台詞ですね。中盤から濱口監督自らの演出論をそのまま見せたと思ったら、お次はそれを観客に見せると、映画の中で言ってしまうんですね。
これも監督の面白い映画の作り方です。しばしば濱口監督作において、映画の中で、この映画は何をしようとしているのか、何を表現しようとしているのか、イントロダクションのようなシーンが入ってきます。これが監督作の特徴です。
特に何度も名前を挙げている『ハッピーアワー』という映画、この映画は主に4人の女性たちを描くドラマで、その4人の内1人がある時、失踪してしまう、その失踪によって今まで均衡を保っていた4人、残された3人の人間関係が変化していく、ぐらついていくと。こういうドラマなんですが、映画の冒頭でその女性たちがあるワークショップに参加するシーンが挿入されます。
一見、物語の本筋とは関係ないこのワークショップのシーンですが、そのワークショップのタイトルは「重心って何だ?」。人間関係における重心について、人と人との心の距離感についての、抽象的なワークショップです。このシーンを冒頭で挿入することで、“なるほど、ここからのドラマは人間関係の重心についてのドラマなんだ”と、映画というのは現実では見えない人間関係の重心を可視化するものだと、観客に暗に示すと。イントロダクションというか、説明ではない説明のシーンとして機能します。
同様に、『不気味なものの肌に触れる』という映画のやっぱりワークショップシーンだったり、濱口監督はその映画自体の解像度を高めるためのイントロダクションを映画の中に入れ込むという、不思議な作り方をする監督でもあります。
今回の『ドライブ・マイ・カー』でそれは立ち稽古、「役者の中にだけ起きた魔法の瞬間を観客に向かって起こす」といったシーンを筆頭に、本読み=テキストを聞くことで体にテキストを入れ込む過程、それ自体が家福の喪失と向き合うドラマのイントロになっていると言えます。これが濱口監督の不思議なところであり、素晴らしいところですね。
映画の解像度を高めるシーンが映画の中にあることで、濱口監督作は観ると毎回、映画に対する姿勢を正されるような映画体験、映画鑑賞という名のセラピー、映画の観方講座、濱口監督による「映画とはこういうものだ」という一つの見方を心に刻まれるような体験になります。これは濱口監督にしか作れない映画体験です。このあと、観客はまさしく家福が“聞く”ことで生まれ変わり、喪失から解放される。その瞬間、映画館の座席に座っている観客の視点は、劇中劇「ワーニャ伯父さん」を見る映画内観客の視点とシンクロして、家福の言う「俳優の間で起きているそれを観客に開いていく」、それを見せられるラストにつながります。

「聞くこと」で生まれ変わる主人公
聞くこと。それはテキストを自分の中に入れ込み、自分を別の何かにする行為です。濱口竜介監督はこの『ドライブ・マイ・カー』制作にあたり、レベッカ・ソルニットの名著「説教したがる男たち」からの影響を公言し、年長の男性である自分は「語るよりも聞く存在になることが問われている」とコメントを寄せています。
聞くこと、聞く存在。まさしく主人公は中盤ずーっと、「ワーニャ伯父さん」、チェーホフのテキストを聞き続けて、高槻からあるテキストを聞きます。この映画『ドライブ・マイ・カー』で唯一と言ってもいい、原作のセリフそのまま、まさしく村上春樹さんの純度100%のテキストを高槻が発します。ここで観ていて驚きましたね。バーではとても自然に会話をしていた主人公と高槻、急にサーブの後部座席に座った瞬間、まるで演劇の稽古のように、お互いがお互いのセリフを待ってセリフを言い合う、日常生活から見ると不自然な会話シーンになります。
濱口監督作ではタクシーの、車の後部座席が演劇的空間になる瞬間があります。『偶然と想像』の1話の冒頭。東京藝術大学の卒業制作の『PASSION』のタクシーのシーン、ルームミラーに映る運転手の視点は観客の視点と重なり、後部座席が演劇の舞台にようになる瞬間がしばしば訪れます。この家福と高槻の演劇的会話は、主人公・家福が高槻から村上春樹さんのテキストを授かる瞬間です。
「結局のところ僕らがやらなくちゃならないのは、自分の心と上手に正直に折り合いをつけていくことじゃないでしょうか。本当に他人を見たいと望むなら、自分自身を深くまっすぐ見つめるしかないんです。僕はそう思います」(村上春樹のテキストを発する高槻-短編「ドライブ・マイ・カー」48ページより)。妻という他人、他者の分からなさ、心のブラックホール。妻の他者性を主人公は、「ドス黒い渦」と表現しました。その他者に飲み込まれるのではなく、自分自身を見つなければいけない。
高槻が舞台に出られなくなり、「ワーニャ伯父さん」のワーニャを演じること、ワーニャとして生まれ変わることを、家福は強いられます。これは先ほど言った過去作『親密さ』の反復です。
最後に家福が聞くテキストは、ドライバーのみさきのテキストでした。みさきも家福同様、母親を見殺しにした罪悪感から牢獄に閉じ込められていた人物であり、みさきの母親は数々の男性と浮気していた家福の妻のように、演技か本当か分からない二重人格を持った人物でもありました。
みさきの故郷・北海道上十二滝村でみさきから聞く最後のテキスト。ここで家福が発するテキストは、再び村上春樹さん原作の『木野』という短編から引用されています。「おれは傷つくべきときに十分に傷つかなかったんだ」(村上春樹のテキストを発する家福-「木野」短編集223ページより)。正しく傷つくべきだったと家福。この地獄のような喪失を抱えた世界で、それでも生きていこうと。まさしくテキストに体を差し出した家福とみさき2人の間だけに起きた、魔法のような瞬間が観客に開かれました。
テキストの長いドライブは、広島から北海道、また広島・原爆ドーム。日本に残っている大きな喪失感の象徴を映して、最終的にチェーホフ「ワーニャ伯父さん」の舞台上で、ワーニャとして生まれ変わる家福を映します。
チェーホフの「ワーニャ伯父さん」は、人生の大半を妹の夫、一人の大学教授に費やしてきたワーニャが、その教授に裏切られ、自分の人生は何だったんだと絶望する、後悔する。その絶望の果てに「それでも生きて行きましょう」と、人生の絶望を耐え忍んで幕を閉じます。「仕方ないわ、生きていかなければ!ワーニャ伯父さん、生きていきましょうよ。長い、果てしないその日をじっと生き通していきましょう」(チェーホフのテキストを聞く家福-「ワーニャ伯父さん」(新潮社)より)。
妻が亡くなっても、目薬の、嘘の涙しか流せなかった男が、喪失と向き合って生まれ変わる。その過程を、「本読み」演技とはテキストを体に入れ込んで、自分が「自分ではない別の何かになるんだ」という濱口メソッドと重ねて、最後に魔法としか形容しようのない美しい瞬間を観客に開いて終わる。家福の言う通り、本当に俳優の間にしかなかったものを、観客に開いてみせたよこの映画!と。
『ドライブ・マイ・カー』はとてもシンプルな映画です。シンプルですが、そこには村上春樹さんの3本の短編と、監督の過去作の集大成、そして監督の演技メソッドを通じて、チェーホフの「ワーニャ伯父さん」というテキストを受け入れた主人公が別の何かになる、演技の可能性、芸術のパワーを高らかに謳い上げる物語でもありました。

そして人生は続く
奇しくも昨年アカデミー作品賞を獲得した『ノマドランド』も、大きな喪失を抱えた主人公が、ドライブの果て、生まれ変わる物語でした。この『ドライブ・マイ・カー』の喪失の物語が、コロナ禍という全世界の人が大きな喪失を抱えている今の時代に、多くの人を感動させたのは当然だったようにも思います。
ようやく家福は「車」という牢獄から解放された。みさきの運転するサーブのその先には、まだまだ人生という長い道が続いています。みさきは、われわれと一緒に、舞台「ワーニャ伯父さん」を、あの観客席で見ていたわけですから、その長い道はわれわれ観客の、『ドライブ・マイ・カー』というテキストを受け入れた観客の、映画館を出たあとに続く人生を重なっていく訳です。
この地獄のような人生どうすればいいのか。「それでも生きて行きましょう」この『ドライブ・マイ・カー』というテキストはわれわれに問うている訳ですね。本当に奇跡のような映画だと思います。
そして先ほど濱口竜介監督の「集大成」と安易に言ってしまいましたが、本当に毎作品毎作品、ご自身の理論、仮説を基に、新しい題材に挑戦されている。常に新作が「集大成」のタイプの作家さんでもあります。ここからまだまだ止まらない進化、本当に楽しみで仕方ありません。今回は主に「テキスト」の長いドライブという観点から見た『ドライブ・マイ・カー』でした。皆様も皆様なりのドライブの楽しみ方を探っていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。
本記事は、圧倒的な情報量と豊富な知識に裏打ちされた考察、流麗な語り口で人気のYouTube映画レビュアーの茶一郎さんによる動画の、公式書き起こしです。読みやすさなどを考慮し、編集部で一部変更・加筆しています。

茶一郎
最新映画を中心に映画の感想・解説動画をYouTubeに投稿している映画レビュアー