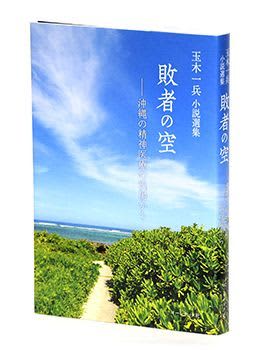
著者は、1980年に『お墓の喫茶店』で第8回琉球新報短編小説賞を受賞した。以来、小説、戯曲、エッセー、詩、俳句、評論など幅広いジャンルで筆を執ってきた書き手である。本職は精神保健福祉士。宜野湾市内の一角「鯨の丘」と呼ぶ精神科病院に身を置き、相談室長、事務長など務めた人。5年前に退職し、45年間におよぶ“二足のわらじ”を脱いだ。
本書は、副題が示すように「沖縄の精神医療の現場から」(なにやら報告書めくのだが)、著者の在職中に書いてきた精神医療に関わる小説15編(未発表含む)をまとめた短編選集である。そこには、心の病を抱えた人たちの人間模様や病院の実相などが、沖縄の風土、暮らし、言葉、四季の光と影、草花、匂(にお)いを織り込みながら、独特の文体で描かれている。狂気と正気、虚と実、そこに境目はない。創作とは言え、長年、医療現場で模索と実践とを重ねた、この人にしか書けないリアルな「一兵ワールド」がある。心の病を持つ人たちに「伴走」し、同じ目線で追求したりする姿が、時にユーモラスな会話が可笑(おか)しい。
作品の一つ一つに触れる紙幅はないが、初期作品『お墓の喫茶店』は、架空の物語ながら、かつての特飲街・桜坂の一角の亀甲墓の裏で「狂人」たちが「病院長誘拐(殺人)計画」を話し合う場に巻き込まれる奇妙な物語。作者の分身「順造」の葛藤、造反者たちの気迫と実行が現実味を帯びて面白い。『日はまた昇る』は、東京から赴任してきた若い斉藤医師は変わり者。白衣を着けずに、ジーパンとポロシャツで病院を徘徊(はいかい)し、患者病棟に寝泊まりする。誰が患者か先生か、なのである。彼も心に過去のしこりを残していた。興味深い物語の展開である。
他に類例のない小説集である。背景に「沖縄戦」「米軍基地」のトラウマが見え隠れする。沖縄の根の深い精神医療の問題を提示している。日本復帰50周年の節目の刊行を意識したのか、優れて今日的課題に映った。文学に何ができるのかを問いかけた作品集にもなった。内包するテーマは重く、深い。
(松島弘明・元琉球新報記者)
たまき・いっぺい 1944年那覇市生まれ。本名・玉木昭道。「お墓の喫茶店」で1980年に琉球新報短編小説賞、「コトリ」で2009年に九州芸術祭文学賞佳作。
