
聴く者にそっと寄り添う静謐な音楽がストリーミングでの再生回数を伸ばしている昨今、ひときわ注目を集めている作曲家/ピアニストが小瀬村晶である。ポスト・クラシカル界隈のシーンでは以前からコアなファンを持つ存在で、海外レーベルや自身で設立したレーベルからリリースされたアルバムは、ピッチフォークなど海外メディアでも高く評価されてきた。国内外の映画、ドラマ、ゲーム、CMの音楽も数多く担当しているので、そこで彼の名前を知った方も多いことだろう。
その小瀬村が、このたびデッカ・レコードと契約。第一弾としてデザイナーの宮下貴裕が手がけるブランド、TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. とのコラボEPがリリースされる。そこで今回は、小瀬村の音楽的ルーツから楽曲制作の過程、今後の展望までじっくり語ってもらった。
_____
―2007年に1stアルバム『It’s On Everything』がオーストラリアのレーベルからリリースされて以来、海外で高く評価されてきた小瀬村さんですが、活動の拠点はずっと日本だったのですか?
はい、東京です。学生のときに曲を作りはじめて、当時はMyspaceという音楽系のSNSが盛り上がっていたので、そこに音源をアップすればいろいろな人に聴いてもらえるかなと思い、興味本位でアップしていたんです。そうしたら海外からの反応がたくさんあって、ローレンス・イングリッシュというオーストラリアのアーティストと交流するようになりました。彼は自分のレーベルからエクスペリメンタルな、エッジのあるサウンドアートのような自作をリリースしていたのですが、「もう少しポップなサブレーベルを作りたいから、その第一弾としてアルバムを出さないか」と言われて。そうしてできたのが『It’s On Everything』です。
―同年、小瀬村さんご自身のレーベル、Schole Recordsも設立されました。ジャケットのアートワークにもこだわり、音楽だけでなく、音楽のあるライフスタイルそのものを提案するようなレーベルのコンセプトに共感したリスナーも多かったですね。
CDで育ってきた世代なので、CDを作ってみたいという気持ちがいちばん最初にありました。だからオーストラリアのレーベルでCDを作ってもらったときは、とても嬉しかったのと同時に、「自分たちだったらこういうものを作ってみたい」というイメージが湧いてきた。それを仲間と一緒に立ち上げたレーベルで形にしていった感じですね。デザイナーも一緒にいろいろ試行錯誤して、フィジカルにこだわったレーベルです。
―それからは海外のレーベルとご自身のレーベル、両輪で活動されてきたと。
そうですね、自分の会社を拠点にして、たまにローレンス・イングリッシュと作品を作ったり。彼が海外のプレスに積極的にプッシュしてくれたので、そこから海外の音楽関係者とのつながりが生まれていった部分もあると思います。そんなスタートだったので、日本の音楽業界の人たちとのつながりはほとんどありませんでした。

―2007年というと、ポスト・クラシカルというムーヴメントの最初期ですよね。小瀬村さんはなぜ、静けさをたたえたインストゥルメンタル・ミュージックを作ろうと思われたのですか?
もともと映画音楽がすごく好きで。子どものとき、はじめて買ってもらったCDが『ロスト・ワールド/ジュラシック・パーク』のサントラだったのですが、パッケージを開くと恐竜がポンと飛び出してくるCDを今も大切にとってあります。ジョン・ウィリアムズの音楽ってかっこいいなあと思ったり、『タイタニック』を観てからはジェームズ・ホーナーの甘美な音楽に感銘を受けたり、それが中学生ぐらいのときでした。けれど高校時代はバンドを組んで、ハードコアみたいなかなりうるさい音楽をやっていたんですけれど。
―小瀬村さんにハードコア、想像がつきません(笑)。
しかもヴォーカルで、エフェクターを使っていたので、歌うというよりほとんど叫んでいるような(笑)。
その後、大学に入った頃には、DJカルチャーやエレクトロニカが盛り上がって、僕自身はそういった音楽に近い人間ではなかったのですが、すごく刺激を受けました。それで自分だったらどんな音楽ができるだろうと思って、フィールドレコーディングをしてみたり、少し習っていたピアノを弾いてみたり、ソフトを買ってシンセサイザーを鳴らしてみたりといったことをはじめたんです。環境音が鳴っていて、少し楽器の音が入っている、映像がないサウンドトラックみたいな感じですかね。そうやってできた音源をMyspaceで発表していたら、ローレンス・イングリッシュが声をかけてくれたという。
―なるほど。ご自身のなかでは自然な流れで作りはじめた音楽が、ちょうどポスト・クラシカルのムーヴメントとも合致したような。
そうですね。僕は当時まだ学生で、音楽を専門的に勉強していたわけでもなかったので、ミニマル・ミュージックとかも全然知らなかったんですよ。知らずに、なんとなく感覚的にミニマル的な音楽を作っていて、あとからスティーヴ・ライヒやフィリップ・グラスといったミニマルの巨匠たちの存在を知った。「ああ、自分の音楽は何もないところを漂っているのではなく、ちゃんと偉大なる先人たちがいたんだ。こういう流れを汲む文脈に位置づけられるんだ」と思って納得しましたね。
―たしかにポスト・クラシカルは、クラシックの現代音楽の延長線上で語られることも多く、音大で学んだアーティストも多いですが、小瀬村さんはそれとはまた違うところから生まれてきたように感じます。
子どもの頃にピアノを習っていたぐらいで、それもあまり好きではなかったですし、クラシック音楽との直接的な関わりはあまりなかったかもしれません。むしろクラシックを聴くようになったのは最近で、長い歴史のなかで積み重なってきたものが、やっぱり自分の音楽のなかにも生きているなあと感じることはあります。あらゆる音楽のなかにクラシックの要素が含まれていますから、影響の、そのまた影響を受けていたりもするのでしょう。
―話を元に戻しますと、今回はデッカ・レコードからのリリースになりますが、契約に至る経緯をお聞かせいただけますか。
先ほどお話したように、自分のレーベルではフィジカルにこだわってCDやレコードを作っていたのですが、以前から知り合いだったライブラリー・テープスというスウェーデンのアーティストから、「新しくレーベルを立ち上げるから参加してくれないか」と声をかけられたんです。それが2015年頃で、彼が立ち上げた1631 Recordingsはポスト・クラシカル専門のレーベルとして、その後、急成長していきました。
そのオファーをもらったときに、ライブラリー・テープスから世界の音楽市場の状況について教えられました。ヨーロッパでは音楽市場のメインストリームはすでにデジタルプラットフォームに移行しているので、新しくデジタルに根ざしたレーベルを作りたいとのこと。当時はまだSpotifyすら日本には上陸していなかったのですが、僕のアーティストページをスクリーンショットで送ってくれて、「ヨーロッパではいまたくさんの人がSpotifyを使っていて、アキラはいま、毎月これだけのリスナーに聴かれているよ」と教えてくれました。「どうすればいいの?」と聞いたら、「なにか良い曲ができたら送ってほしい。アルバムのようなまとまった作品である必要はないから」とのことだったので、興味本位で参加してみることにしました。
―その見立てが見事に的中したわけですね。
やがて1631 Recordingsはユニバーサル ミュージックと提携するようになり、音楽出版社がデッカ・パブリッシングになりました。僕もそこに協力するうちに海外のユニバーサル ミュージック グループに知り合いが増えてきて。それで、2020年の夏頃にデッカ・レコードのA&Rから連絡がきて、「今後なにか一緒にできないか」とお話をいただいたという経緯です。
とはいえ、今回リリースされるEP 『Pause (almost equal to) Play』に関しては、デッカとの企画というよりも、宮下貴裕さんのブランド、TAKAHIROMIYASHITATheSoloist. とのコラボレーションという側面が強いですが。
<YouTube:Akira Kosemura - pause (almost equal to) play (Visualizer)>
―2021年9月に行なわれた、2022年春夏コレクションのために制作された4曲とのことですが、宮下さんとはどのようなやり取りがあったのですか?
宮下さんとは2017年頃から交流があって、イタリア・フィレンツェで開催された「ピッティ・ウオモ」でのショーで僕の曲を使ってくださったこともありました。僕はファッションには疎いですが、以前に宮下さんが手がけていたNUMBER (N)INEというブランドの服は、高校時代にいちばんクールなブランドだったので、バイト代を貯めて買ったこともありました。宮下さんにとって服というものはおそらくアートなんですよね。僕にとって宮下さんはデザイナーというより、アーティストという感覚です。
そして去年、宮下さんが東京で何年かぶりにコレクションを開催されることになり、「ランウェイを一緒に作りたい」と言っていただきました。でも僕はちょうどその頃、ものすごく仕事が立て込んで心身ともに参ってしまい、1ヶ月ぐらい休養をとっていた時期だったんです。「ちょっと僕、疲れちゃって……」みたいな話をしたら、宮下さんは「大丈夫?」と心配しておすすめの漢方を送ってくださったり。
―優しいですね。
とても優しい方です。でも宮下さんは「絶対にやってほしい」と言ってくださっていたので、僕に無理しないでほしいという思いとの間で葛藤があったのではないかと思います。僕としても、この仕事に関してはどうしてもやりたいという気持ちがあったので、休養している間に生活習慣を見直して、ヨガや水泳をして身体優先の生活に変えながら、調子を整えていきました。そうして、しばらく休んだ後に曲を作りはじめたら、出てくる音楽が今までとはちょっと違うものになったんです。僕はインプロヴィゼーションでピアノを弾きながら録音していくことが多いのですが、弾き方だったり、メロディやコードが、自分で選んでいるというより、自然と湧き出てくる感じで。身体の悪い部分がデトックスされたのかもしれません。
その話を宮下さんにしたら、「じつは僕もコロナ禍でコレクションができない間、映像作品にチャレンジしたりしてきたけれど、改めてランウェイに立ち返って、そこで勝負したいと気持ちが高まっている」とおっしゃっていました。『Pause (almost equal to) Play』というタイトルは、きっとそういった心境からきているのではないかと思います。
―Pause(一時停止)からPlay(再生)へ、おふたりのモードが一致したと。
服の制作過程や試着の画像を共有していただいたりしながら、宮下さんが作る世界に共鳴するような感覚で作っていきました。1トラック目の「vi (almost equal to) ix」はショーのオープニングのために書いた曲で、宮下さんから今回のシーズンのキーワードとして「靴」というワードをもらっていたので、タップの音を使ったんです。タップシューズの音をものすごくいろいろ加工して、さざ波のような音にしたのですが、あまりに元の音と違うので誰も気づかないかもしれません。子どもが機械で遊んでいるような感覚で、オーディオ素材をプロセッシングしていくのが好きなんです。
―作曲は、ピアノを弾きながら即興的に作っていくのでしょうか。
そういうことが多いですね。ピアノを弾いて出てきたフレーズをとりあえず録音して、そのまま弾きながら構成していくこともありますし、あとからカットしたり、配置し直したりして構成することもあります。そして軸となるピアノの音に、採集してきたいろいろな音の素材やシンセサイザーなどを重ねていく。そのようにエディットしたりプロセッシングしていく手法は、エレクトロニカで培った部分があるかもしれません。
とはいえ、じつは自分でもどうやって作曲しているのか分かっていないこともあって。最初の頃は、作曲の依頼をいただいたときに、「この曲を聴いてとても良いと思ったので、こういう感じの曲を作ってくれますか」と言われても、どうやって作ったか覚えていないので困っていました(笑)。
―では最後に、今後デッカでやっていきたいこと、作りたい音楽についてお聞かせください。
デッカのスタッフと話していたのは、ずっと東京で暮らしてきた自分ならではの音楽があるのではないかということ。アジア人的な視点で、欧米の人たちに音楽を提案したいという気持ちが高まっています。僕がヨーロッパのレーベルから作品をリリースする意味というか。そういった日本人としての感覚を、ピアノ・ソロでも、それ以外の形でも大切にした作品作りができればと思っています。
―今後をますます楽しみにしています! ありがとうございました。
Interviewed & Written By 原典子(音楽ライター)
____
■リリース情報
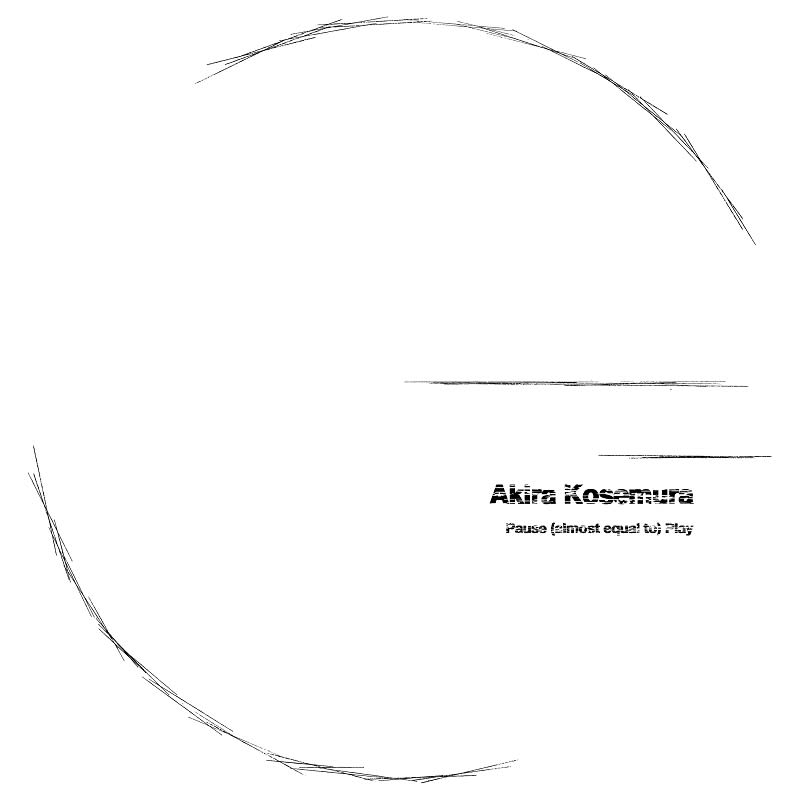
小瀬村晶 EP『Pause (almost equal to) Play』
2022年5月27日配信リリース
