
多額の献金によるトラブルや家族の断絶を引き起こすなど、反社会的な性格を持った一部の宗教団体は「カルト」と呼ばれている。
安倍晋三元首相銃撃事件では、山上徹也容疑者(41)が凶行に及んだ動機について、母親がはまり込んだ世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への恨みだったことが指摘されている。勧誘方法や集金システムが問題視され、元信者から起こされた訴訟にも相次ぎ敗訴してきた旧統一教会だが、これまで規制は加えられてこなかった。
宗教観や歴史は国ごとに異なり一筋縄ではいかないカルト対策だが、カルト問題を研究している北海道大大学院の桜井義秀教授や、宗教と政治の関係に詳しい東京大伊達聖伸教授への取材などから、フランスとアメリカの状況を紹介し、日本が取り得べき方向性についてまとめてみたい。(共同通信=水谷茜)
▽900人以上の死
伊達教授によれば、20世紀後半になると、欧米では日曜礼拝など、通うのが当たり前とされていた教会から距離を取る人が出始めた。さらに急速な近代化に疑問を持ち、自然回帰の志向を持つ人たちの一部が、新しい宗教によりどころを求めた。
桜井教授の著書「カルト問題と公共性」によると、欧米の人々がカルトに目を向ける大きなきっかけになったのが、1978年に南米北部のガイアナで起きた事件だった。

教団は70年にアメリカで作られた「人民寺院」。元々プロテスタントの牧師だった教祖ジム・ジョーンズが社会主義に傾倒し、独自の宗教観を創り上げた。しかし、報道などで実態が知られるにつれ、国内で摩擦やいざこざを生じるようになった。ジョーンズは北ガイアナに作った村「ジョーンズタウン」で、革命的自殺と称して、多数の子供を含む900人以上の集団自殺(一部は他殺)を引き起こした。
▽勢いを失う市民活動
それでは、米国ではカルトにどう向き合ってきたのだろうか。桜井教授によると、市民運動が大きな役割を果たしてきたという。信教の自由が保障されている米国では、市民が自由に社会活動を行う中で自然と秩序が生まれていくとの考えがベースにある。行政は宗教団体に介入しない。自由競争が優れたものを生み出すという米国式の価値観のもとでは、伝統的な宗教も新宗教も対等な扱いが求められる。
一方で1980年代になると、新宗教の実態が報道などで明るみに出て、入信した子供を取り返そうとする親たちによる草の根運動が盛り上がった。反カルトの動きも組織化されていった。
信者の脱会の取り組みやカルト批判が盛んになった一方で、当のカルトから「信者をカルトから引き離して隔離し、洗脳から解放する〝強引な〟手法が取られている。人権侵害だ」などと非難され、損害賠償訴訟を起こされる事例も相次いだ。最も有力な反カルトのグループは100万ドル以上の賠償を命じられ、破産した。
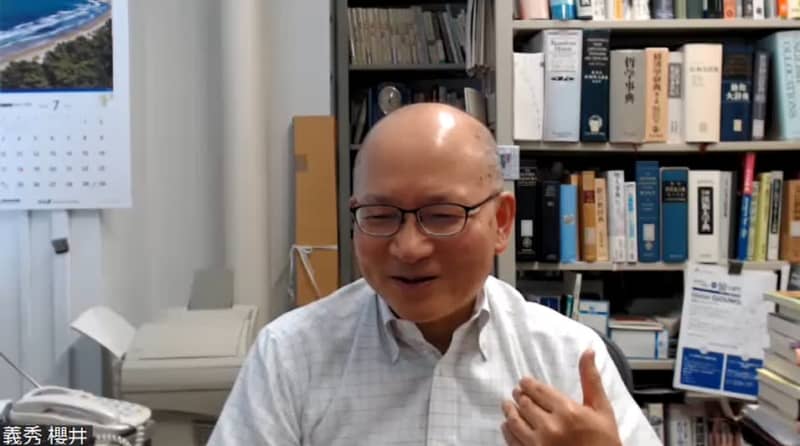
ただ、こうしたカウンターの動きにより、「アメリカの反カルト運動では脱会カウンセリングが難しくなった。多文化主義の社会なので、反カルト運動も宗教に対する不寛容として批判にさらされてしまう」と、桜井教授は指摘する。
▽信教の自由VS精神の自由
フランスはアメリカと対照的で、反セクト法を備える。フランスではカルトのことを、セクトと呼ぶ。海外から流入する新宗教によって信者が精神操作を受けているのではないかと疑ったフランスでは、議会が1995年にカルトに関する踏み込んだ報告書をまとめた。
セクトの定義として、(信者に)法外な金銭的要求をする/反社会的な説教/裁判沙汰が多い/行政への進出を企てる、など10の基準を示したのだ。
報告書は危険視する団体を100以上名指ししたことでも注目された。この中に旧統一教会も含まれる。一方で報告書は、「信教の自由」を侵害するとして、専門家や他国からは批判を受けた。
カルト対策を取る際、常に立ちはだかるのが信教の自由の壁だ。そこで、信教の自由に対抗して「精神の自由」を掲げた。精神の自由とは、個人の自由意志が守られている状況を指し、桜井教授は「他人から見ても『(当人が)自由に考えられる中で、その宗教を信じている』かどうかが大事であるとの発想に基づく」とした上で「精神の自由の方が信教の自由より普遍的と考えられているので、精神の自由を守る国家が宗教に介入することができると考えられている」と解説する。

一方、伊達教授は背景に政治と宗教の歴史的な関係性が影響していると指摘する。フランスはかつてカトリックが国教で、宗教が国の主権をも脅かしかねないと懸念され、1905年の政教分離法で政治権力は宗教的な権威から距離を置くことが定められた。
こうした経緯から、伊達教授は「政治的な権力を構成する一人一人の市民が自分の判断で思考し、宗教的な自立性を持つことが重視されている」と話す。個人より団体の利益を重視する傾向を持つセクトは、精神の自由と対立する存在なのだという。
フランス議会はさらに2001年、違法行為があった場合に直接関わった人物を罰するだけでなく、法人の解散まで命じられる「セクト規制法」を成立させた。95年に名指しされた団体で解散に追い込まれた例はないが、桜井教授は「国として、セクトに対する強い意志を示した象徴的な法律だ」と評価する。
▽曖昧な宗教観でカルトに立ち向かう
カルトを規制する法がなく、宗教に対する国民認識も曖昧な日本では、どのような対策が考えられるだろうか。
戦前の日本は1925年に成立した治安維持法などに基づき、反体制の団体・活動家などを国が強権で取り締まった。加えて宗教団体へも介入、規制した。19世紀末に始まった神道系の新宗教を例に取れば、信徒を増やす中で、二度にわたり当局から激しい弾圧を受け、多くが投獄されるなどし壊滅的な打撃を受けた。

桜井教授によると、その反省から戦後は公権力の行使は抑制的となり、現在も宗教団体を監視したり統制したりする権限を持つ役所はなく、法律もない。そのため、フランスのように法でカルト規制に取り組むことは難しい、と指摘する。

唯一の例外はオウム真理教だ。14人が死亡、6000人以上が被害を受けた1995年の地下鉄サリン事件を始め、弁護士一家殺害事件など数々の事件を引き起こして教団幹部13人の死刑が執行された。
宗教法人法に基づいて東京都知事が東京地裁に解散命令の請求を行い、最高裁で解散が決定し、アレフやひかりの輪などの後継団体に対しては、団体規制法に基づく観察処分が現在も続いている。

桜井教授は、日本人が宗教批判をタブー視する傾向にあることがカルト対策を考える上で壁になっている、と指摘する。欧米では生活の中に宗教が身近にあり、「正統な宗教」を明確に捉えることができるのに対し、日本人の多くは冠婚葬祭などで仏教や神道、キリスト教などの習慣に従うだけで、「日本では宗教に対する心構えなど家庭でも学校でも教えられておらず、宗教が『敬して遠ざけられる』一方である」(桜井教授)。そのために、カルト問題も認識しづらくなっているのだという。
「困難はあるが…」としつつも、桜井教授は「日本社会がカルトに対して無力ということではない」とも強調する。
例えば、カルトは大学生への勧誘活動などが問題視されているが、今回の安倍元首相銃撃事件の報道をきっかけとしてカルトの実態に社会が関心を持ち、入信者や献金が減れば、教団の力は衰える。さらに「カルトと関わりのある政治家を選ばないことで、教団は味方を失う」とも指摘する。
桜井教授は「『国が、行政が』と言うのではなく、市民一人一人が社会をつくる気概と宗教リテラシーを持って、カルト問題に臨んでほしい」と語った。
