
スイスのシンクタンク、世界経済フォーラム(WEF)が公表した2022年の「男女格差(ジェンダー・ギャップ)報告」で、日本は調査対象の146カ国中、116位だった。この順位は、先進7カ国(G7)や東南アジアを含むアジア太平洋地域の19カ国で最下位だ。
低順位の大きな要因は、国会議員や閣僚の男女比などで算出される「政治」分野の格差。有権者の約半数は女性なのに、女性の国会議員は約14%しかいない。ここが大幅に改善されない限り、政策に多様な声が反映されにくい「ジェンダー後進国」のままだ。
なぜ女性議員は少ないままなのか。女性の政治参加を阻むハードルはなんなのか。7月の参院選にチャレンジした女性候補らに経験を聞いた。(共同通信=山口恵)
▽「女性議員を増やすには時間がかかる。クオータ制が必要」

シンクタンク代表の向山淳さん(38)は、自民党の全国比例で初出馬した。政治を志したのは、4年前に娘を産んだことがきっかけ。政治がより身近になり、「子どもたちの未来のために働きたい」と考えるようになった。
公認が出たのは5月末。自民党が比例の候補者の3割を女性にすることを決め、向山さんら女性4人に追加公認が出たためだ。「党としても、私のような大きな組織を持たない候補にとっても、女性を増やそうとする大きな一歩だった」
参院選は、都道府県が基本単位の選挙区と、全国比例で争う。そうなると、世襲や著名人、現職、団体の組織内候補らがどうしても比例では有利になる。
向山さんは、オンラインツールを選挙活動でフル活用した。支えてくれたボランティアの多くが子育て世代だったため、コミュニケーションツール「スラック」上でのやりとりが事実上の“選挙対策本部”に。LINEのオープンチャットでボランティアを集め、打ち合わせは会議ツール「ズーム」で実施した。
インスタグラムやツイッターなど、交流サイト(SNS)での発信にも力を入れた。今まで選挙にちゃんと行ったことがない人、子育て世代の人たちとつながることができたのは大きな収穫だったという。
一方で、育児との両立は大変だった。選挙前、娘の通う保育園に「正直、当選は厳しいと思うけど、やってみたい」と出馬を伝えると、園長先生はこう言って背中を押してくれた。「お母さんが挑戦することに意味がある。お子さんは絶対に分かってくれる。お子さんのことは任せて」
選挙期間中、マイクを持って街宣活動ができるのは午前8時から午後8時までだが、SNSの更新や音声配信などの活動はその後も続く。娘の保育園への送り迎えや寝かしつけは夫や両親に手伝ってもらった。「ケア労働を家族が引き受けてくれたからこそ、出来た選挙戦だった」と振り返った。
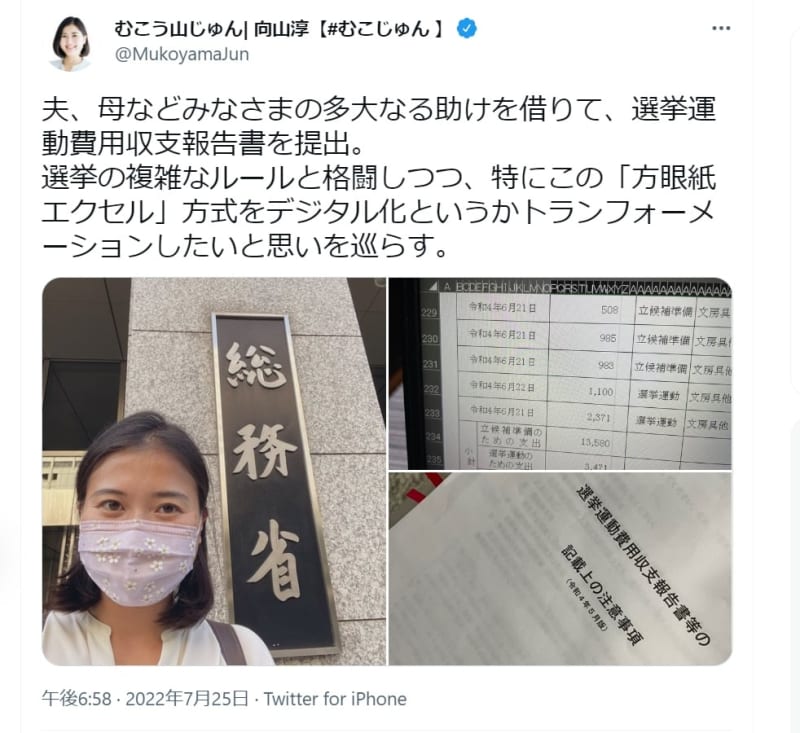
結果は約2万票。当選には及ばなかった。自民党の全国比例の当選者では、最も得票の少ない人でも約11万9千票を集めていた。
向山さんは「厳しい闘いだと覚悟していたが、準備も力も足りなかった」と同時に、こうも感じた。「現状のシステムの中で、女性議員を増やそうとするとやはり時間がかかる」
今回の経験を経て「一定の比率の議席や候補者を女性に割り当てる『クオータ制』の導入を検討すべきだ」と考えるようになった。
向山さんの出馬は、自民党の女性局が主催する政治家養成講座に参加していたことがきっかけだった。「私自身、政治家になりたくてもどこにアクセスすれば良いか分からなかった。政党側も、こうした養成講座をただ行うだけでなく、立候補の希望者を集め、実際の選挙に送り出すための仕組みとして位置付け、運営していくことが大事だと思う」
▽選挙運動中に子どもを抱っこしたら違法?
著名タレントら34人が定数6を巡って争った東京選挙区では、元NPO職員、田村真菜さん(34)が諸派で挑んだ。鳩山由紀夫元首相が代表を務める共和党から出馬。選挙後、「普通の若い人が政治に参加しにくい仕組みになっている」と振り返った。
家が貧しく、子どものころは月三千円の給食費が払えなかったことも。学校から足が遠のき、12歳までほぼ学校に通わずに育った。2011年の東日本大震災を機にNPOの活動を始め、今は子どもの貧困や不登校問題解消、ひとり親支援などに関わる。政策提言などで政治家に会う機会もあるが、当事者目線を十分に持つ人は少ないと感じていた。

もともと、家族を犠牲にするような選挙戦はしたくないと思っていた。保育園に通う4歳の息子は、当日になって「行きたくない」と言う日もある。だから、選挙戦も最初から子連れで臨むつもりだったが、東京都選挙管理員会から「選挙期間中、子どもを抱っこしたり、一緒に歩いたりすると、公職選挙法違反になる可能性があります」と注意された。
公職選挙法は、ポスター貼りなどの単純労務を除き、18歳未満の選挙活動を禁じている。候補者が演説するそばでボランティアが候補者の子どもを見ていることや、保育園の送迎すら違反になる可能性があると言われた。
選挙期間中、街頭活動は数回しかしなかったが、子どもがぐずるため、やむを得ず少しだけおんぶをしながら演説したこともあった。
こうした動きが報じられ、批判的な問い合わせが選挙管理委員会に相次いだとみられる。選管は投開票後の7月12日、ホームページに「単に候補者やスタッフと子どもが同行すること自体は禁止されていない」「無言でも、選挙カーに乗って手を振ったり、街頭演説で原稿を読み上げたりすると、違反になる可能性がある」との見解を明記した。
田村さんは「選挙前にこうした方針を出してくれたら随分やりやすかったのに」と感じた。「子どもを保育園に入れられなかった人や、ひとり親などは事実上、出馬が不可能。ケア労働を誰かに手渡せる人でないと、選挙に参加できないのはおかしい」
これ以外にも、既存の選挙の「当たり前」は、田村さんにとって違和感の連続だった。東京都内に約1万4千カ所あるポスター掲示板の地図と住所リストは、選挙管理委員会から分厚い紙資料で渡された。「グーグルマップに落とすとか、せめてPDFで提供してもらえないものか。全陣営が原資料からスキャンしたり、マッピングしたりすると考えると、あまりに非効率」
また、主に、公示日の午前中に行う出陣式。著名候補らはJR新宿駅などで行うことが多く、先輩議員からも「人が多くいる場所でやるものだ」と教わったが、田村さんはオンラインの「メタバース」上で行った。「平日の昼間に集まれる人がどれだけいるのだろう。年配の人しか来られないのでは」と考えたからだ。
さらに、ある男性議員からは「政治家になりたいのなら、子どもが大きくなってから挑戦すればいい」と言われた。しかし、妊娠から出産、子育てと、その時々で直面する課題は変わる。子育てが一段落した人しか政治家になれないのだとしたら、子育て真っ最中の人の声が政治に届きにくい現在の構造は、これからも変わらないままだ。
「小さなハードルを少しずつ変えていく必要がある」と田村さん。次のチャンスを狙いつつ、立候補したい人を支える側にも回りたいと思っている。
▽地方から「社会を変えられる」
来年春には統一地方選が予定されている。4年に一度で、道府県や市町村の首長、議員の選挙が、各地でほぼ一斉に行われる。
内閣府の2020年末のデータによると、全国に約1700ある市区町村議会のうち、女性が一人もいない「ゼロ議会」は17%を占める。統一地方選は、女性の政治参加の裾野を広げる意味でも重要な意味を持つ。
超党派の女性議員のネットワーク「ウーマンシフト」代表で、東京都台東区議の本目さよさんは「少数派の声を聞き、代弁する議員がいることが大事。子育てや教育など生活で直面する課題は、当事者でないと分からないことが多い」と話す。

本目さんは、地方議員こそ女性が参画しやすいと感じている。「議員活動の場と生活が近く、比較的、両立しやすい。まずは地方議員に立候補しやすい環境を整えることが大切。その中から、国政に挑戦する人も出てくるのではないか」
団体では、市民の声を政治につなげる取り組みにも力を入れる。議員が主に育児休業中のママを受け入れるインターンもそのひとつ。オンラインでの活動がメインで、これまでに全国の16人の議員の元で、約80人が経験した。
子どもを持つと、それまでと比べ、健康診断や保育園探しなど行政に関わる機会が増える。ママたちが抱える日々の「モヤモヤ」を気軽に議員に伝えてもらい、改善につなげようという活動だ。
「今後は全都道府県にママインターンを受け入れる議員を広げたい。こうしたつながりから、政治や議員を身近に感じ、『自分でもやってみよう』と思う人が出てくるかもしれない」。
投票をちらつかせてハラスメントをする「票ハラ」など、女性議員をめぐる困難ばかりがクローズアップされるが、「それだけじゃない」と本目さんは言う。「子育て支援など区民の声を代弁し、実際に施策に反映されたり、予算がついたりすると『頑張って良かった』と実感する。社会を変えられる、というこの仕事のやりがいもきちんと伝えていきたい」

