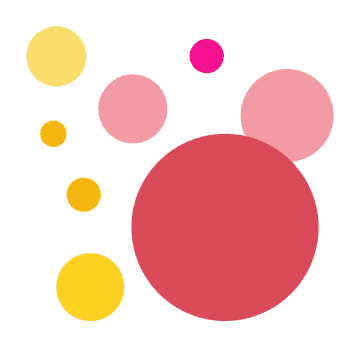高良健吾、玉木宏、土屋太鳳、中川大志、野村萬斎が、WOWOWで2023年に放送・配信される「アクターズ・ショート・フィルム3」(日時未定)で、監督に挑戦することが分かった。
21年に同局が開局30周年を記念して行なったプロジェクト「アクターズ・ショート・フィルム」。その第3弾となる今回も、予算・撮影日数など同条件で5人が25分以内のショートフィルムを制作し、世界から6000本超のショートフィルムが集まる米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティバル & アジア」(SSFF & ASIA)のグランプリ、“ジョージ・ルーカス アワード”を目指す。
高良は「『アクターズ・ショート・フィルム』の存在を知ってから、この企画で自分がもし監督をするとしたらどんなものを作るだろう。そう思いながら日々を過ごしていました。大げさではなく本当にそう思って生きていました」と告白し、「オリジナル脚本であるというルール。このルールにとてもひかれました。日々脚本に向き合いながら、その作業は簡単なものではないけど、自分の中の新しい感覚が生まれたり、もともとある感覚の中から何かを探したり。結局は、自分が今まで映画に対して向き合ってきた姿勢がこんなにも出てしまうものかと。ここまでさらけ出さないといけないのかと。恥ずかしい気持ちにもなります」と率直な心境を明かす。そして、「ただ、このような機会を与えてくれたことには感謝しかありません。どんなことがあろうとも、この機会は自分の人生の大きな出来事の一つになります。いろんな人に助けてもらいながら、憧れだけで終わらせることなく、自分のやりたいことを悔いなくやろうと思います」と誓う。
玉木は「私自身が、以前から興味深く注視していたショートフィルムいうカテゴリーで監督オファーをいただき、うれしく思います。現時点では、30分ほどの限られた時間の中で『何を』『どうやって』伝えるのか、これまでの俳優として演じることとは違う形で、今の自分の心情を投影する場所になるのだろうと想像しています」と思いを巡らせ、「頭の中の想像をゼロの状態から形にしていく作業は、とても楽しく、やりがいを感じています。同時に、いつも演じる際にはあまり見えていなかった、撮影に至るまでの下準備の大変さも感じ、日頃現場を整えて支えてくれている監督やスタッフに感謝しなければいけないと、あらためて思いました。この先の撮影と編集、自分の描きたい世界を、心強いスタッフ、キャストに協力していただき、楽しんで臨みたいと思います」と意気込んでいる。
土屋は「お話をいただいた時は耳を疑いました。自分の人生において『監督』とか『脚本』という言葉は、川の対岸にあるような、見えるけど近いけど、遠い言葉だと思っていたからです」とオファーに驚きつつも、「でも、遠いはずの『監督』や『脚本』について考え始めると、今まで表現したくても機会がなかったものが、自分の中に意外なほど蓄積していることが分かりました。もしこの機会に、その一部を少しでも表現していいのだとしたら、思い切って挑戦しようと思います。基礎を学んでキャリアを積んで、やっとたどり着くのが監督業だということは、痛いほど知っています。私が安易に挑戦していいものだとは思っていません。そして、いざ取り組むスタートに立ってみると、心の中に眠るものを言葉として目覚めさせることがこんなにも大変なことだったのか、ゼロから作品の世界を探っていくことがこんなにも難しいことだったのか、あらためて痛感しています。魂を込め、真摯(しんし)に向き合いたいと思います」と気を引き締めている。
中川は「小学生の頃、初めて映画の現場に立った時のことを鮮明に覚えています。戦場のシーンでした。カメラは、今よりも、うんと大きく見えました。クレーンは高くそびえ立って、火薬の匂いが充満する草原を、たくさんの大人たちが、大きな声を出しながら走り回っていました。僕は一瞬で心を奪われてしまいました。あれからずっと、お客様に届く瞬間を想像しながら、制作費と時間と労力をかけてエンターテイメントを創り上げる時間が僕は大好きです。こんなにもぜいたくな環境で監督に挑戦させてもらえることに感謝します。俳優だからこそ見える景色を大切に、今しか撮れない瞬間を切り取りたいです」と気合十分。
萬斎は「これまで、演出家として舞台芸術の演出は何本もしてきましたが、映像の演出は憧れだったのでオファーをうれしく思い、ホイホイと受けてしまいました(笑)。台本作り、撮影方法など、作品ができていく過程が楽しく、演者ではなく作り手として参加することをうれしく思います。狂言より舞台、舞台より映画と、より大勢の人たちが関わって作っていく醍醐味(だいごみ)を、今、味わっています。作品としては、舞台でも長年温めてきたテーマを映像化することに挑戦しています。野村萬斎ならではの目線が現れれば、また一興かと。失敗を恐れず、遊び心満載で作ってまいります」と伝えている。