
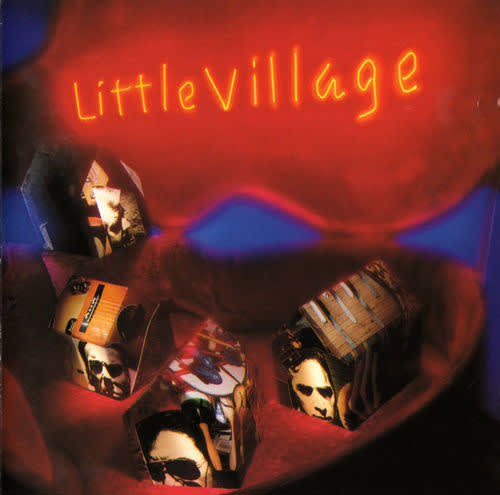
スーパーバンド/グループ。アルバムのレコーディングのために集まったというのではなく、人気アーティストがタッグを組んでアルバム制作だけでなく、コンサートツアーもやり、うまく行けば恒久的な活動を続ける、というものだろう。それは夢のある、というか期待感を抱かせるもので、ロック界でも何度もそういうグループは生まれたものだが、大抵の場合はせいぜいアルバム1枚、コンサートを1回やったぐらいで空中分解…という場合がほとんどだ。そりゃあ、エゴの強いアーティスト同志が自己主張をやり合えば、まとまるものはまとまらず、ヘタすると殴り合いの喧嘩別れに終わるということも少なくないわけだ。クロスビー(デビッド)・スティルス(スティーヴン)・ナッシュ(グラハム)&ヤング(ニール)はまぎれもなくスーパーバンドだったし、素晴らしい結果を残した。ただ、ヤング抜きの3人組(CSN)と彼を加えた4人組(CSN&Y;)を比べると微妙な違いが出る。後者には凄みも増し、グレードが違うというか…。しかし、ヤングが入ることによるケミストリーが負の作用をすると、まさに殴り合いの喧嘩に発展したのも事実なのだ。
ローリングストーンズの企画したイベント『ロックンロール・サーカス』で臨時結成されたダーティ・マック(ジョン・レノン、エリック、クラプトン、キース・リチャーズ、ミッチ・ミッチェル、ヨーコ・オノ)などは、夢のあるポピュラー音楽史上最高のスーパーバンドのひとつだった。残されたライヴ音源の質も悪くない。他にもありとあらゆるスーパーバンドがあり、それらを振り返ってみると、ほとんどがアルバムはなかなか良いものを残しはするものの、人間関係は崩壊というパターンが多いだろうか。唯一、人間関係も崩壊せず成功したのはトラベリング・ウィルベリーズ(ボブ・ディラン、ジョージ・ハリスン、トム・ペティ、ジェフ・リン、ロイ・オービソン、ジム・ケルトナー)ぐらいだろう。
レーベルの儲け話に乗った4人の男たち
今回取り上げる「リトル・ヴィレッジ」は、実はそのトラベリング・ウィルベリーズの成功を見て、レーベルが所属アーティストに「君たちもやってみないか」と呼びかけ、実現したスーパーバンドである。つまり、レーベルは儲けも期待し、2匹目の泥鰌(どじょう)を狙ったのだ。残念ながら、結果は目論見ほどは売れず、御多分に洩れず、メンバー間に不協和音が出て自然消滅してしまったのだが、1枚だけ残されたアルバム『Little Village』は、これがなかなかの傑作なのである。
メンバーはライ・クーダー、ジョン・ハイアット、ニック・ロウ、ジム・ケルトナーという、改めて見てもマジかよ、と言いたくなる面子である。
ただ、売れなかったのは致し方ないと思う。皆、超トッププレイヤーであるし、ケルトナー(dr)以外の3人は単独でもライヴができるネームバリューと肩書きの持ち主だが、ミュージシャンズ・ミュージシャンと言うべきか、玄人好みされる人たちだからだ。
ライ・クーダーはもはや説明不要というべきアーティストだろう。ギタリストとしてはポピュラー/ロック界で5本の指に入るヴァーチュオーゾであることは多くが認めるところであろうし、特にボトルネック/スライドギターの達人である。また、リトル・ヴィレッジから5年後にはキューバの老ミュージシャンたちとコラボレーションした、音楽史に残る大プロジェクト『ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ』を成功させたことなど、またいつかここで取り上げたいものだ。ジョン・ハイアットは今やアメリカーナを代表するシンガーソングライターのひとりだ。文中でも少し触れているが、通算8作目となった1987年のソロ作『Bring The Family』はプレ・リトル・ヴィレッジという内容であるとともに、翌年に出る『Slow Turning』、続く『Stolen Moments』と傑作3連作ともいうべきアルバムによって、世界的に知られる存在になった。ニック・ロウは英パブロック・シーンに燦然と輝くブリンズレー・シュワーツ、ロック・パイルなどの活動をへて、ニューウェイブ期のインディーズの草分けとも言うべきスティッフ・レーベルの看板アーティスト、プロデューサーとして活動を続けてきた。ソロでもリリースされたアルバムはライヴも含めると現在までに20枚ほどあるほか、全米13位を記録した「Cruel To Be Kind 邦題:恋するふたり)」のヒットがあるなど、ソングライターとしての評価も高い。ジム・ケルトナーも説明不要なロック界を代表するドラマーだが、ライ・クーダーとの長い付き合い、ビートルズのメンバー他、彼がセッションで関わったアーティストは枚挙にいとまがないだろう。
話を戻すと、レーベルが所属アーティストに「やってみないか」と呼びかけた、と先に書いたが、それというのがジョン・ハイアットのソロ作『Bring The Family』のレコーディング・セッションに参加していたのが彼らだったのだ。手慣れのセッション・プレイヤーである彼らはわずか4日でアルバム用の曲を取り終えてしまう。仕上がりも上々で、和気あいあいとしたスタジオの空気を見てとったレーベルの人間がトラベリング・ウィルベリーズのネタを振り、「こんなに息もぴったりなんだから君たちもやってみない?」と振ったわけだ。ライヴをやるにしても、何も特別なリハーサルだって必要ない。さっきまでやったセッションの続きみたいなものなのだから。
「悪くないね。一丁やってやるか(プロモーションにもなるしな)」
「面白いかもな(小遣い稼ぎみたいなものさ)」
「でかいツアーをやったりしなければ、俺は構わないぜ(ちゃんとギャラが出るならいいさ)」
「君たちがやるっていうんなら、付き合ってやってもいいぜ(どうせセッション仕事と同じさ)」
と、勝手に想像してみるに、皆、そんな腹づもりだったのではないか。こうしてリトル・ヴィレッジは結成されることになった。
ただ、全員がスタジオに集まってレコーディングすることは叶わず、全米、英国と散らばるメンバーは音源をやり取りしながら作業をしたらしい。インターネットのない時代だから電話、ファックス、FedExなどを使ってのことで、まれに都合がつけば顔を合わせて、という作業を1年近くかけてアルバムは完成する。この段階ではバンドは協調的というか、それぞれオリジナルを持ち込み、あるいは共作し、リードヴォーカルも分け合うなどまとまっていたという。しばしばジョン・ハイアットの主張が強くなる傾向があり、やがてそれはライ・クーダーとぶつかり、バンドが自然消滅する主な原因となっていくのだが、皆をリードするハイアットのような人間がいなかったらまとまるものもまとならなかったかもしれない、と後年、ライ・クーダーとニック・ロウは述懐している。
世評では売れなかったということになっているが、ビルボードのアルバムチャートで最高位66位。シングルも出さず、大々的なプロモーション/ツアーをやるわけでもないのに100位以内に入っていることを、私などは大健闘であり、むしろ売れたと言っていいのではないかと思うのだが。しかも、1993年にグラミー賞の“Best Rock Vocal Performance by a Duo or a Group”に候補指名され、UKアルバムチャートでは最高位23位にまで達している。
名曲、名演が惜しみなく披露される、
単なる“企画モノ”と思わせないプロフェッショナルの仕事ぶり
収録曲は以下の通り
1. Solar Sex Panel
2. Action
3. Inside Job
4. Big Love
5. Take Another Look
6. Do You Want My Job
7. Don’t Go Away Mad
8. Fool Who Knows
9. She Runs Hot
10. Don’t Think About Her When You’re Trying to Drive
11. Don’t Bug Me While I’m Working
かいつまんで各曲を辿ってみるとしよう。全曲通して良い曲が揃う。タイトルも魅力的な冒頭の「Solar Sex Panel」はハイアットがヴォーカルを取る、ノリ、キレ味のいいロックナンバー。メリハリをつけるように、続いてライ・クーダーがブルージーに歌う「The Action」、ケルトナーとニックのイントロに導かれて始まる3曲目「Inside Job」は再びハイアットが歌い、ライがボトルネックでソロを決める。躍動感のある、これもいい曲だ。
4曲目「Big Love」もハイアットがヴォーカルを取る。重厚で、4人のコラボレーションを感じさせる秀作で、ハイアットが弾くアコギベースのアンサンブルながら、ライのエレキ・ボトルネックが大きなスケールを演出するように抜群の効果を生んでいる。ニック・ロウとケルトナーによるシンプルかつ堅実なリズム隊もいい仕事をしている。そのニック・ロウがヴォーカルを取る5曲目「Take Another Look」もいかにもライ・クーダーらしいギターのピッキングが冴え、聴き応えのあるナンバーに仕上がっている。
6曲目はライが歌う、タイトルもウィットに富んだ「Do You Want My Job」。ライのソロアルバムに入っていても不思議じゃないくらい実に彼らしい曲。ライはエレキ・ブズーキを弾き、ギターはハイアット。コーラスもいい感じで決まり、こういうのを聴くとアルバム1枚で終わってしまったことが残念というか、レコーディングの段階ではライとハイアットの関係が良かったことをうかがわせる。
7曲目はアップテンポの「Don’t Go Away Mad」。ハイアットがヴォーカル、当初はこの曲をシングルで出す予定だったそうだ。8曲目はニック・ロウがおおらかに歌う自信作(たぶん)の「Fool Who Knows」。自身のソロ作でもよい曲を書いている人だが、特別なことなどやっていないのだが、キラッとしたものを感じさせるというか、程よいポップさ、洒落たセンスを感じさせ、アルバムの中でいいバランスになっている。9曲目は「She Runs Hot」。最初にハイアットが歌い、2番からライとニックが歌うという流れで、友好的なコラボレーションを感じさせる曲だ。疾走感のあるロックで、間奏のソロはライのボトルネック。もっともっと、と思うが、短く、絞り込んだような渋いフレージングがさすがである。
10曲目「Don’t Think About Her When You’re Tring To Drive」はハイアットの味わい深い歌のうまさが光る。これは特に名曲だろう。遊び半分でやったプロジェクトだったはずだが、案外、本気モードだったのではないかと思うくらい、素晴らしい出来である。ラストはエンディングの雰囲気にふさわしい「Don’t Bug Me I’m Working」。ニック、ライの順で歌い、ハイアットはコーラスのパートを中心に歌っている。ロックっぽい鋭さを秘めたファンキーな仕上がりだ。締めで誰のものか「Little Village…」と台詞が入る。
バンド・アンサンブルの お手本のような、うまさ、 センスが味わえる
自分のソロ作『Bring The Family』の出来映えに気を良くしていた充足感もあってのことだと思うが、ハイアットも音楽キャリアの何度目かのピークを迎えていたのだと思う。とにかく彼が絶好調なのだ。それを支えるライやケルトナーは百戦錬磨のプレイヤーであり、歌伴に回った時にどのようにギターのオブリガートを加えればいいのか、瞬時に掴むのだろう。実にツボを押さえた心憎い演奏をしている。そんな裏方仕事に注視して耳を傾けてみるのもこのアルバムの聴きどころだと言える。
また、このアルバムを魅力的にしているのはハイアット、ライ、ニックの3人のヴォーカルが偶然にも同じ声質を持っていて、コーラスが実にナチュラルなのだ。普段の各自のソロ作ではなかなかコーラスを聴くことが少ないだけに、これも偶然の産物だったのだなと、ため息まで出てしまう。そういうわけで、この原稿を書くために久しぶりにアルバムを繰り返し聴いたが、本人たちは「それほどでも…」と謙遜しているようだが、これは聴きどころ満載の名盤だ。
ちなみにアルバムは本作1枚しか出なかった(アウトテイクはいっぱいありそうだ)はずだが、何とボストンでの放送用の音源がライヴ盤『Crazy 'Bout an Automobile (Remastered) [Live. Boston, Massachusetts, April 1992]』として、公式にApple Musicにアップされている。公式とはいえ、ブートレッグには違いないと思われるので、おおっぴらにオススメできるものではないが、一時的にせよ、彼らがいかに素晴らしいバンドであったかが分かる内容になっている。
TEXT:片山 明
アルバム『Little Village』
1992年発表作品
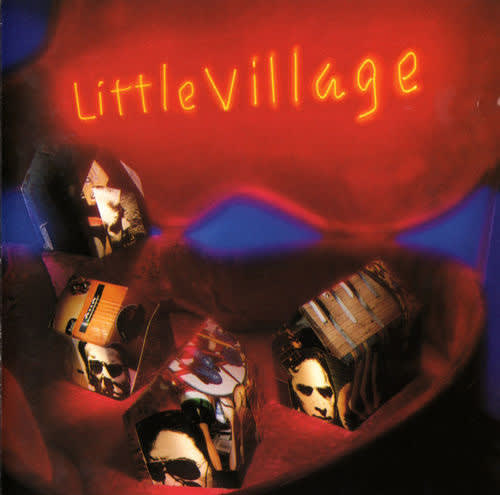
<収録曲>
1. Solar Sex Panel
2. The Action
3. Inside Job
4. Big Love
5. Take Another Look
6. Do You Want My Job
7. Don’t Go Away Mad
8. Fool Who Knows
9. She Runs Hot
10. Don’t Think About Her When You’re Trying to Drive
11. Don’t Bug Me While I’m Working

