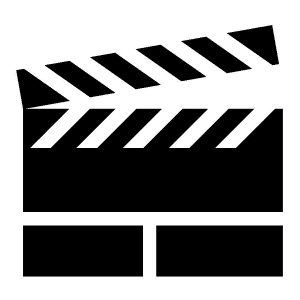はじめに
お疲れ様です。今週の新作『バビロン』は、『ラ・ラ・ランド』でアカデミー監督賞を最年少で獲得したデイミアン・チャゼルの新作にして、「どうしたデイミアン・チャゼル!?」と思わずスクリーンを二度見する「下品」「悪趣味」「散らかっている」作品でした。無声映画から発声映画への移行期を余りにも下品に描く、低俗ブラックコメディ版『雨に唄えば』と言うべき問題作でしょう。しかしここで言う「下品」「汚い」という表現は本作にとって褒め言葉になってしまうくらい、確信犯的な悪意とパワフルさがあります。サイレント映画お好きな方は激怒するでしょうし、10人に8人は顔をしかめながらの鑑賞となるかもしれませんが、僕は結構ノレてしまいました。しかもマンマと泣きました。どんな映画だったのか?今週の新作『バビロン』でお願いします。
基本設定
『バビロン』は1926年、ハリウッドを夢見てメキシコから来た青年マヌエルが、同じくハリウッドを夢見るネリーと、とある乱痴気パーティで出会う所から始まります。そのパーティには映画スター、ブラッド・ピット演じるジャック・コンラッド。トランペット奏者のシドニーがいました。本作は主にこのマニー、ネリー、ジャック、シドニー4人の登場人物を軸に、20年代ハリウッドから30年代へ。サイレント映画からトーキー(発声映画)移行期を描く群像劇です。
どんな映画?
「20年代ハリウッド」「サイレント映画」が舞台という事で、僕も肩に力を入れていくつか映画史の書籍を読んでから本作に挑みましたが、結果的にほとんど予習は意味がなかったです。これからご覧になる方は肩の力を抜いて下さい。この映画、冒頭からトンデモなく下品なんですね、もし映画館の座席が固定されていなかったら「新婚さんいらっしゃい」みたいに椅子と一緒に転げ落ちていたと思います。
というのも本作『バビロン』お尻の穴から始まります。そしてこれは比喩とかではなく観客に排泄物をぶつけて始まります。映画ご覧になっていない方は「なにそれ?」という感じだと思いますが、言葉通り観客に非常に汚いものをぶつけて始まるんですね。もうこの段階から真面目に観るのは諦めるというか、苦手な方は「出口はあちらですよー」と映画館の出口に映画自らが誘導するような明確な悪意をもって本作始まります。
監督のインタビューを見ると色々とリサーチをされたようですが、正直、時代考証をしっかり反映しているようには見えない描写の数々。登場人物もとても当時の人には見えない。劇中、撮影されたサイレント映画が劇中劇として登場しますが、とてもサイレント映画には見えない、ただの白黒の映像、何じゃこりゃと。デイミアン・チャゼル監督、サイレント映画にリスペクトを持っている印象が全くこの冒頭からずっと感じられない、そういうタイプの映画でした。故にブラックコメディ版『雨に唄えば』と言いました。
本作でも「引用」と言うには長すぎる引用がされます、『雨に唄えば』は同じくサイレント-トーキーの移行期を描いたミュージカルコメディですが、特に中盤までそのブラックコメディである本作はブラックコメディでも下品な方、より低俗な方のブラックコメディと言えます。「お尻の穴」もそうですし、この映画何と「お尻の穴」で始まり「お尻の穴」で終わります。何ちゅう映画だよと。言葉遣いも汚いですよ。本作をご覧になる時に限ってはポップコーンを買わない方が良いと思います「排泄物」「吐瀉物」ギャグ多数。もっと言うと「人の死」ですね。人が死ぬことをギャグにしている、何度も。そういうタイプのブラックコメディが『バビロン』でした。
日本の宣伝コピーは「夢と音楽のエンタテインメント」と書かれていますが、正直、「お尻の穴と吐瀉物のブラックコメディ」と言った方が正しい序盤。びっくりしましたし、ズッコケましたし、「サイレント映画」ファンの方は激怒して映画館を去って良いと思います。まずこういう映画が『バビロン』です。
影の原作について
本作『バビロン』は原作表記がないオリジナル脚本とされていますが、多くの方が『バビロン』と聞いて、ケネス・アンガーの超有名な「ハリウッド・バビロン」を連想するかと思います。実際、チャゼル監督もこの「ハリウッド・バビロン」に影響を受けたと。この書籍は10年代、20年代ハリウッドの黄金時代。それをD・W・グリフィスの『イントレランス』という映画の一つのパート「バビロン篇」で使用されたバビロンの都の超巨大セットをモチーフに、これ高さ90メートルくらいのとんでもないセットですが、映画のためだけに作られた「バビロン」からハリウッドを「新バビロン」と表現しました。
一見、豪華絢爛、夢と幻想の都に見えるが、裏には俳優の薬物使用、自死、乱交、そういったスキャンダルがあるとという、嘘か本当かわからないスキャンダルをまとめたゴシップ集が「ハリウッド・バビロン」。この書籍をタイトルに引っ張って、かつほぼ原作にしていると、そういう映画です。言うならば、100年後の日本人が週刊実話だけを元に時代劇を作ったみたいな感じで、おまけに本作「ハリウッド・バビロン」にはあった先人へのリスペクト無しに、そのスタンスで映画を作っています。決して正史に基づいたお堅い時代劇ではないと、下品!悪烈!と言っても「だって『ハリウッド・バビロン』からタイトルを持ってきている映画だと」と、悪趣味は褒め言葉。僕は「真面目に観るのは辞めた、考えるのをやめた」みたいな『バビロン』の序盤でした。
物語について
ただ映画全体のパワフルさは魅力で、3時間は長いです、2時間半くらいにしてほしい題材ですが、体感時間1時間半くらいには仕上がっているスピードがあります。何より本作『バビロン』の音楽は大好きです。デイミアン・チャゼル監督と学生時代からタッグを組んでいるジャスティン・ハーウィッツの音楽によるパワーが大きいです。
冒頭のパーティから繰り返される♪Voodoo Mamaは頭にこびりつく、まさしくブードゥというタイトルの通り、どこかの土着的な宗教のお祭りの音楽のように観客を煽る、だんじりバビロン祭ですね。作品のスピード感とテンションを高める最高のスコアでした。そしてその“ねぶたバビロン祭”と、作品の中心に存在する、劇中で表現されるように「野生児」的な踊りで最強の存在感を見せるネリー演じるマーゴット・ロビー。もう最高ではなかった時はないマーゴット・ロビーですが、彼女なしではこの3時間相当キツかったと思います。
本作の登場人物のモデルになった実在の人物は全てパンフレットに記載がありますので、言及は避けますが、パンフレットには、ネリーはクララ・ボウがモデルとありますが、監督のインタビューを見るとちょっと違って、クララ・ボウももちろんモデルですが、複数のサイレント時代の女優さん、セダ・バラ、アルマ・ルーベンス、ジャンヌ・イーグルス、ニュージャージー出身という点はノーマ・タルマッジ、あらゆるサイレント時代のスターを掛け合わせて作られた、時代を象徴する女神じゃないですが、そんな集合体として象徴的に作られたキャラクターという事です。
この辺りは、同じくマーゴット・ロビーが時代を象徴する、その時代の純粋無垢な象徴として作品の中心に存在した『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』に近いキャラクター造形にも思います。マーゴット・ロビーの肉体・存在に相当救われている映画だなと思って観ていました。ジャスティン・ハーウィッツの“祭ビート”によって駆け抜ける、スピードが速い3時間。やはりマーゴット・ロビーから連想するマーティン・スコセッシの一連の栄枯盛衰の群像劇『ウルフ・オブ・ウォルストリート』から『グッドフェローズ』、『カジノ』。あの辺りの映画と比較しても遜色ないスピード感。本作全編です。
「穴」というモチーフ、その「穴」に吸い込まれるカメラワークが多用されていて、この観客をハリウッドを夢見る登場人物もろとも吸い込んでいく吸引力が映像からも伝わります。先ほど言った冒頭と終盤にある2つの「お尻の穴」というのもありますし、カメラのレンズ、その「円」に吸い込まれるようなカメラワーク、そしてトランペットの穴に吸い込まれるイメージ、これは『ラ・ラ・ランド』の夢のシークエンスでもありましたし、監督が学生時代にジャスティン・ハーウィッツと作った処女作『Guy and Madeline on a Park Bench』のダンスシーンからずっとやっている高速パンと合わせて監督のキーイメージですね。
劇中何度も何度もカメラはシドニーの演奏するトランペットに吸い込まれる。真ん中がぽっかり空いた「円」はハリウッドのスターたちのどこか空虚さを意識させながら、そこに吸い込まれる、このハリウッドの魔力に引きつけられる吸引が作品の疾走感を強化します。特に速いのはマニーとネリーが初めて映画撮影のセットに行く序盤のシークエンス、二人が行った二つの現場を交互に見せる、ここの疾走感は編集の緩急含め個人的に一番好きなシークエンスでした。
ただちょっとサイレント映画の撮影をコメディのためにデフォルメし過ぎているという問題は本作、ここだけではなく全編あって、本作はサイレント映画の現場をただ単に技術が遅れている、まるで原始人のような野蛮なものとしてデフォルメしているんですよね。この辺りはサイレント映画ファンは怒っていいかな。というのも映画史の書籍を読むと、この時代の撮影、演出は技術的にもとても優れている、演出だけ見ると下手したら今より優れていると思えるような証言もあります。僕が一番オススメするのはケヴィン・ブラウンロウという方の『サイレント映画の黄金時代』という書籍です。これを読むと本当に当時の撮影・および映画作りの技術は優れているものだったなと思い知り、当時の映画制作の高揚感含め本当にワクワク読み進められる書籍でした。
ちなみにインタビュー見ると、デイミアン・チャゼル監督もこの書籍も読んでいるみたいなんですよね。「それでこの描写になるか?」というちょっと疑問ですね、本作の撮影現場を茶化す一連のコメディシークエンスはウィル・フェレルとアダム・マッケイの「俺たち」シリーズみたいな、「俺たちサイレント映画スター」じゃないですが、そのもっと低俗版みたいな、昨年話題になった『怪獣のあとしまつ』と比較しても良いリスペクトの無さっぷりを感じました。
観ていて怒る人がいないかヒヤヒヤしながら楽しんでしまいましたが、デイミアン・チャゼル監督、前作の「ファースト・マン』は美術、音楽から撮影まで時代へのリスペクトを感じる一本でしたが、本作『バビロン』では「こうなるのか?」という、確信犯的な意地悪さ、ハリウッドの黄金時代をこれだけお金かけて茶化せるデイミアン・チャゼルの生意気さの良さと悪さが混ざり合った怪作だと思いました。ということで、ここまでは本当に序盤までの内容で作品の輪郭を説明しました。ここからはもう少し中盤以降の展開も言及しながらまとめますので、本編をご鑑賞後にご覧いただければと思います。
参考にした映画から見る本作
本作『バビロン』を先ほどはスコセッシ作品と重ねましたが、一番近いのは、多くの方が連想されると思いますが、何かパンフレットでもどなたかも指摘されていました、ポール・トーマス・アンダーソン監督の『ブギーナイツ』ですね。『ラ・ラ・ランド』の「♪Someone In The Crowd」のシーンでも『ブギーナイツ』のプールシーンからの引用があったので、そこで連想してしまったというのもあります。
本作はサイレント映画時代、『ブギーナイツ』はポルノ映画業界の栄枯盛衰ということで、特に本作の「二つ目のお尻の穴」に入っていくシークエンスは『ブギーナイツ』そのままで、本作の展開はかなり『ブギーナイツ』から持って来ているという印象があります。
いつものようにデイミアン・チャゼル監督、作品の参考にした映画を公言されています。5本の映画を公言していますね。アフリカ系のバンドを描いた1929年の短編『Black and Tan』は、直接的に本作『バビロン』におけるトランペット奏者シドニーの映画スターとしての出世に影響を与えています。先ほどチラっと名前を挙げた『イントレランス』、そして『天井桟敷の人々』、4つの異なる時代を交互に映す超大作『イントレランス』ですが、この『バビロン』の4人の群像劇は後者の『天井桟敷の人々』の、同じ舞台や劇団を軸にした群像劇に近いものに思います。セリフが美しい『天井桟敷の人々』と、言葉が汚い本作を比較して良いのかという問題もありますが。
4つ目の参考にした作品はフェリーニの『甘い生活』。これは本作にかなり近いですね。イタリアに旅行に行く前に絶対に観たい映画No.1『甘い生活』ですが、この『甘い生活』は田舎からローマに来たジャーナリスト志望の主人公が上級階級、芸能の世界に浸かってどんどんと退廃的になっていくという、本作のマニーのビフォーアフターに最も近いです。ハリウッドという夢を追ってきたはずのマニーは、マヌエルという本名を捨て、メキシコ出身であることを隠し、スペイン出身と嘘をつく、どんどんとアイデンティティをハリウッドに食われていく。『甘い生活』で登場するハリウッド女優にしてとても自由奔放なシルヴィアの、トレヴィの泉のシーンが有名ですが、このシルヴィアは本作におけるネリーと重ねられます。
特に『甘い生活』と似ているのは上下の構造だなと思って、『甘い生活』も冒頭でヘリコプターに乗って、上空にいた主人公がどんどんと物語が進んでいくと、下に行くんですね、言葉通り下に行くと、本作『バビロン』でも冒頭は丘の上にあるパーティが開かれるお屋敷に向かってマニーは上がっていくんですが、物語終盤になると、こちらもどんどんと下に行くという、分かりやすいですね、終盤の「LAのお尻の穴」に入るシーンでは、もっと下、もっと下、とトビー・マグワイアに下の階に行かされる、中盤までは「人の死」をギャグとして描いていた『バビロン』も、中盤のジャックの親友の死から、積み重なる死体の山が悲劇的なものとして描写が一変します。どれくらい監督が意識しているか分かりませんが、凄い『甘い生活』に似ているなと思って観ていました。
最後の一本はまたもやスコセッシの初期作『ミーン・ストリート』という映画だそうです。他の作品は群像劇で、金持ちの退廃的な生活を描くと、本作に似ているので分かりやすいですが、『ミーン・ストリート』は何だろうと、観る前思っていましたが、これは中盤以降のマニーとネリーの関係性だと思われます。ブラックコメディとして展開していく本作ですが、中盤からはジャンルが変わったかのように悲劇として展開していきます。『ミーン・ストリート』はロバート・デ・ニーロ演じる主人公の親友が借金を積み重ねていく、それを唯一、主人公は庇いますが、それでも親友は主人公を裏切るような行動を繰り返すと、本作でもマニーは自由奔放なネリーを何とか改心させようと試みますが、その度に裏切られていく、結構、観ていて僕は終盤のネリーにはイライラさせられてしまったのですが、かつての女神はどうやっても昔の輝きを取り戻させることはできない、そういった関係性は『ミーン・ストリート』からであり、『ラ・ラ・ランド』のミアとセブのラストも重ねてしまいます。
テーマについて
パワフルながらもやや散らかった豪華すぎるブラックコメディであり悲劇だった『バビロン』を、勢いに押されながらやや首を傾げながら観ていたわけですが、ラストにはマンマと泣かされてしまったチョロい私です。本作についてデイミアン。チャゼル監督は「夢の中に生きる人々の物語に引き込まれた」と語っていますが、あくまでサイレント時代からトーキーへの移行期のそういった時代は、やはり監督が一貫して描く物語に集約していきます。
おそらく監督はサイレント映画というより、この物語にしか興味がないのでしょう。本作でもマニーが「重要で長く続くものの一部になりたい。より大きなものの一部になること」と語りますが、『セッション』から描かれる「創造的な行為のために代償が必要という強迫観念的な考え」、夢のために人生の全てを投げ打つ登場人物。夢のために時に狂気とも思える行為すら許される、それを肯定していく、夢追い人に乾杯。本作のラストを観て、多くの方が『セッション』、『ラ・ラ・ランド』、監督は脚本を書いていないですが『ファースト・マン』などを重ねたことかと思います。
エンディングについて
非常にラストはズルい感動の持っていきかたをしていて、悔しいなと思いつつ、マニーを演じたディエゴ・カルバさんの表情にヤラれてしまいました。本作の唯一の貢献は、ディエゴ・カルバさんをスターに押し上げたことだと思います。
ゴシップ屋エリノアの言う通り、マニーの、ネリーの、ジャックの消えてなくなった今までの人生が「より大きなものの一部」となり、映画『雨に唄えば』としてスクリーンに映っている。マニーが撮影に立ち会った『ハリウッド・レヴィユー』の劇中歌「♪雨に唄えば」も、その「より大きなものの一部」となり『雨に唄えば』の劇中歌としてスクリーンに映り、多くの観客を喜ばせている、ここでマニー以外の観客の様子を映すのもズルい。このシークエンスで少しばかり、この悪趣味な映画『バビロン』も救われていると思います。
さらにここからはトンデモないエンディングでしたね。カッドバックならぬカットフォワードか、マニーの目に、我々観客の目に、「より大きなものの」の変遷、過去から未来の映画の歴史が現れるという。少しこれは『ラ・ラ・ランド』の夢のシーンで、ミアとセブが自分たちの未来を映像として見るシーンも想起します。ちなみにこの未来を見る登場人物の描写は監督曰く、まさしくサイレント映画の『サンライズ』からの引用だそうです。
ともかくデイミアン・チャゼル監督の独自性がある訳ではないので、映像のチョイスはやや退屈。主に技術面での映画の発展の歴史、映画技術の講義を受けた人なら一度は観たことがある映像が目の前に現れます。『NOPE/ノープ』の記憶が新しいエドワード・マイブリッジによる連続写真、エジソンの『アニー・オークレイ』、リュミエール兄弟による『ラ・シオタ駅への列車の到着』、『月世界旅行』、『大列車強盗』、『イントレランス』。この辺りからサイレントの名作が並んで、『オズの魔法使』も印象的でした。『THIS IS CINERAMA』からジェットコースターの映像、『ベン・ハー』。よく弊チャンネルのオープニングで使っている『アンダルシアの犬』からヒッチコック『サイコ』につながる。ゴダールはおそらく2作品で、『女と男のいる鋪道』と、こちらもOPでよく使っている『ウィークエンド』が確認できました。エド・エムシュウィラーの『Sunstone』も長く使用されていました。SF映画は『2001年』から『トロン』、『マトリックス』、スピルバーグからは『ジュラシック・パーク』、『レイダース』、ジェームズ・キャメロンは何故か『アビス』が抜かれて『ターミネーター2』と『アバター』だけでした。
抜け漏れているものが沢山あると思いますが、こういった具合に映画技術の発展、その未来を見るというトンデモないエンディング。そしてラストはまさかの弊チャンネルで何度も名前を出している『仮面/ペルソナ』でしたね。このチョイスはちょっと嬉しかったですね。少年がスクリーンに触っている映像ですが、この『仮面/ペルソナ』という映画は演じることと映画についての映画であると同時に、監督であるイングマール・ベルイマンが心を病んでいた中、映画を作ることによって心を癒していったそんな重要な作品でもあります。映画作りは人の心を癒していくんだ、そんな『仮面/ペルソナ』の映像が最後にある事で、映画を作っていたジャック、ネリーの人生、マニーの人生が癒やされていく感覚もあります。
映画の歴史、歴史と言うにはまだまだ短いものですが、そういったものの一部になったと初めて実感するマニーと、自分も観客として、どこか映画という「より大きなもの」の一部になる。映画鑑賞という行為をちょっと肯定してくれるようなパワーがありました。ちょっとだけ「これからも胸を張って映画を観て良いのかな?」と。映画は、特に日本において洋画文化というのは絶滅寸前、これからどんどんと消えてなくなっていくものだと思いますが、そんな文化の走馬灯のようにもラストの映像が見えてしまって、肯定感と共に切なさも感じました。ということで、とても下品で悪趣味で散らかった『バビロン』。最後にはちょっと感動もお土産で残してくれたという、僕の『バビロン』体験でした。
さいごに
本当に「バビロンの都」を作ってしまった『イントレランス』も興行的には失敗でしたが、本作『バビロン』も製作費8000万ドルの内、現在、全世界興行収入約5000万ドルと、見事な惨敗となっています。奇しくも本作自体が「バビロン」になってしまったという、興行収入が本作のテーマを最も語ってしまった一本でもありました。今週の新作『バビロン』でございました。食事しながらは観ない方が良いかもしれません。また来週の新作でお会いいたしましょう。
【作品情報】
バビロン
2023年2月10日(金)
© 2023 Paramount Pictures Corporation. All rights reserved.

茶一郎
最新映画を中心に映画の感想・解説動画をYouTubeに投稿している映画レビュアー