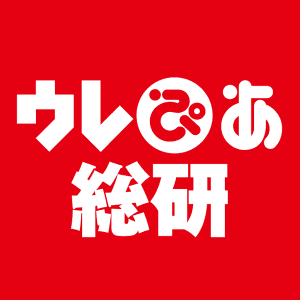人とうまく関わることができない、恋愛でも友達でも好意を向ける人とリラックスする関係を築けない。
自分の在り方に自信がないと、誰と向き合うときも本音や本心を出せずにスムーズなコミュニケーションがとれず、いつしか相手と疎遠になっていきます。
自信のなさは誰もが悩むことですが、そんな自分を変えたいと思うときは、具体的に何から意識するのが良いのでしょうか。
自信が持てない…そんな人は自分のことを見ていない!?
自分への自信が失われる理由
たとえば、仲のいい女友達と楽しく過ごせていたけれど、その子が悩んでいるときに必死の思いでしたアドバイスが「何でそんなことを言うの」とまったく違う方向に受け取られてしまい、その後何も言えなくなってしまう。
好きな人に精一杯のアプローチをしていたけれど、気がつけば都合のいい存在にされかけていて自分の好意は弄ばれていたと知る。
そんな自分を目の当たりにすれば、「私なんて何をやってもダメなのだ」「人に好かれることはないのだ」と落ち込みますよね。
自分なりに努力をした結果が想像と正反対の結果になる、誠意を持って関わっていても相手の受け止め方がこちらの考えとは違っている、そんなときに人は自信を失います。
誰だって自分の考え方や価値観を理想通りに受け取ってほしいのは当たり前で、それが叶わないのを「自分が悪い」と思うから在り方に悩み、人と交わることに臆病になるのですね。
相手の受け止め方が悪いのだ、と開き直る人もいますが、そうであっても結局「受け入れてもらえなかった自分」の見え方は変わらず、相手と距離ができる終わりしかありません。
あからさまに拒絶されなくても、「相手を喜ばせることができなかった」「相手の期待に応えることができなかった」と自分を責めてしまい、ネガティブな感情に支配されて「こんな自分は嫌い」となってしまいます。
それでも、人間はどうしたってひとりでは生きられず、誰かと関わり人と交わって日々を送るもの。
こんな自分を変えたい、何とかして自信を持ちたいと思うとき、何から始めるのが正解なのでしょうか。

「誰もが自分に自信を持っているわけではない」ことを知ろう
人の輪のなかで笑顔で会話をしている人、相手の求めることを察してすぐ動ける人、自分の意見を臆さず口にする人を見れば、それができる理由に「自分に自信があるのだろうな」と感じます。
行動力は心の方向の現れであり、動けるのはそうする自分に違和感がないからです。
ではその人がこれまでもずっとそうだったのか、自分と同じように悩んだり苦しんだりする時期はなかったのかと考えると、答えはわかりません。
もしかしたら、自分よりもっとひどい劣等感や虚無感で暗い沼の底をさまよっていたのかもしれず、そこから這い上がった姿が今である可能性は捨てられません。
自信があるように見えても、その人の過去はどうだったのか、背負っている背景には何があるのか、わからないのであれば「最初からこうだった」とは言い切れないはずです。
人それぞれ考え方や価値観は違っていて、すれ違いも衝突も当たり前に起こります。
自分のような経験をほかの人もしているのでは、という視点は、「誰もが自信を持っているわけではない」と視野が広がります。
筆者の場合でいえば、以前は他人に依存することがやめられず、相手に好かれることで自分の価値を確認していました。
自分の在り方を他人に決めてもらう状態で、胸を張って自分に「それでいい」と言える瞬間などありませんでした。
その自分に嫌気がさして変わった今は、人と関わりたい意欲を正面から「それでいい」と受け止め、できることに力を尽くしています。
自分の在り方に自信を持つことに他人の承認は決して必要ではなく、まず誰よりも自分自身がOKを出せることが、自己肯定感といえます。
悩むのも苦しむのも、変わりたいと思うからです。
ダメな自分でもいいと本当に思っているのなら、在り方を変化させる努力など考えません。
いま目の前で穏やかな笑顔で話をしている人が、そうなるためにどんな努力を自分に強いてきたか、「誰もが最初から自信を持ってそこにいるわけではない」と思えば、自分もそうなれるのだという可能性に気がつきます。

「自分を信じる」のが自信
「私なんてダメなのだ」と思ってしまうのは、「私」でない誰かのなかで価値のない自分を突きつけられるから。
それを自分の責任にするのは間違いで、相手の受け止め方はどこまでも相手の問題であり、「私なりに精一杯やった」と思うのであれば、そちらを見るのが正解です。
相手は自分と違う人間なら、考え方もものの感じ方も違って当然、どう受け止めるかはこちらでは決められません。
だからこそ自分のできる範囲で力を尽くすことしかこちらにできる選択はなく、結果が想像通りでなくても、「やれたこと」に満足するのが正しく自分を愛する姿勢になります。
相手のなかに自分の価値を置いてしまうから自信が左右されるのであり、そうではなく自分の価値は自分で決める、「私」の言動そのものをまず自分で肯定できる強さが、他人とも居心地よく関われる境界線をつくることにつながるのです。
そんな自分が、他人から見れば「自信のある人」「心の安定した人」と映り、前向きな関心を引き、同じような心を持った人との交流を生みます。
劣等感や卑屈感に支配されると、何をするにもまず相手の感情を気にして顔色を伺い、自分のやりたいことではなく「相手からOKの出る振る舞い」を優先します。
その結果やはり拒絶される自分を見れば、「あなたのためにやったのに」と相手を責める感情が生まれ、失敗の責任を負わせようとします。
それが依存であって、「私」の価値を相手に委ねている限り自信は育ちません。
相手の在り方に関係なく「私」の言動は自分で決めていく、相手の受け取り方に左右されず「これでいい」と動けた自分を認めてあげる。
相手からの評価と自分に向ける評価を切り離すのは本当に難しいですが、「これでいい」ときちんと納得ができる「私」になると、相手が想像通りに受け止めてくれなかったとしても責める気持ちは起こらず、そのまま置いておける強さになります。
そのまま置いておける強さは不毛な衝突を避ける距離感になり、ネガティブな感情のやり取りを避けられます。
そうやって「その自分」で居心地よく関わっていける人だけが周囲に残り、あたたかいコミュニケーションを楽しめることが、健全な人間関係ではないでしょうか。
自分を信じるのが自信であって、そこに相手の承認は不要であること、「動ける自分」をまっすぐに見る力が、そのまま他人の存在を受け入れ慈しむ心の器となる、と筆者は考えます。

「動ける力」はどこから生まれるのか
筆者の経験で恐縮ですが、言動を自分で決められるようになったのは、「こう在りたい」という本音を掴んだ後からでした。
相手の思惑に関係なく「私はどう在りたいのか」、自分の気持ちを客観的に見て居心地のよさを考える、それを叶えるためにどう振る舞えばいいのかを想像できてから、自信を持って動けるようになりました。
それは相手ではなく自分のためであり、相手に依存して存在するのではなく「私」の足で立つ力です。
これをエゴイズム、自己主義だと感じる人もいますが、心が自立していない人ほど自信を持って動く人を「自分のできないことをしている」と歪んだ目で否定してくるので、そんな人は「合わない人」として置いておくのが正解です。
本音に従って動けば、後悔が残りません。
「ああすればよかった」と思うことほど自分を苦しめる時間はなく、それが在り方を不安定にします。
「動ける力」は自分で作るのが当たり前、その姿勢が結果に苦しまない心の器を強くします。
自信がないのは自分を信じることができない状態、それは「私はこう在りたい」を知らないから。
本音や本心をしっかりと見つめることは、もうひとりの自分との対話です。「もうひとりの私」はどんな言葉を持っているのか、何を自分に伝えたいのか、向き合う力がその後の行動力を生みます。
人は等しく尊重される存在なら、まずは自分自身が「私」を大切にしてあげる、本音に耳を傾けてそれを叶えてあげようとする意思を、大切にしたいですね。
*
自信を失うとき、必ず「ダメな自分」がいます。ですが、それは本当に「ダメ」なのか、決めるのは誰なのか、を忘れてはいけません。
自分を信じて動いたことならそれでいいとする強さが、どんなときでもむやみに落ち込むのを避けるコツ。
自分の本音を知ることから逃げない力を持ちたいですね。
(mimot.(ミモット)/ 弘田 香)