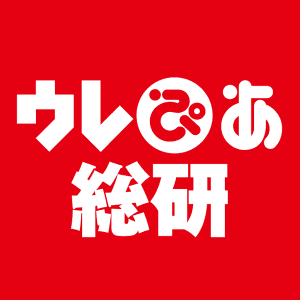くしゃみ、鼻水、鼻づまりなど、つらい花粉症の症状に頭を抱えてはいませんか? 自分なりの対策をしていても、症状が改善されずに毎年悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
スギ花粉は2~4月にピークを迎え、ヒノキは3~5月、ブタクサやヨモギなどは8~10月と、年中何かしらの花粉が飛んでいます。
花粉症は、早めに対策することと、適切に薬剤を使うことで症状を大幅に軽減することができるのです。
今回は、日常生活での花粉症対策について詳しくご紹介します。

花粉症の放置はNG! 早めの対策がカギ
花粉症とは、花粉に対して免疫が過剰に反応する症状です。花粉症になると、花粉を排除するために、くしゃみや鼻水などで吹き飛ばそうとします。
花粉症を放置しておくと、鼻や喉の粘膜に継続して炎症が起こってしまうため、粘膜のバリア機能が低下します。すると、少しの気温差や刺激に対しても過剰に反応するようになり、慢性鼻炎やアレルギー性鼻炎になる場合もあります。
また、鼻水や鼻づまりは集中力の低下を招き、日中の眠気が増すこともあります。
慢性化を防ぎ、症状を悪化させないためにも、花粉症は早めに対策することが大切です。

外出時にできる花粉症対策
日常生活でできる花粉症対策のポイントは、できるだけ花粉に触れないことと、触れる機会や量を減らすことです。
テレビやインターネットなどで、花粉の飛散量などの情報も入手し、飛散量の多い日や、飛散が多い時間帯(午後1〜3時くらい)の外出はなるべく避けましょう。
1:帽子やメガネを使う
外出時には、完全防備をしてなるべく露出部分を減らしてください。
帽子やメガネ、マスクやマフラーなどを着用して花粉との接触を防ぎましょう。メガネやマスクは、できるだけ顔にフィットして隙間を作らないものを選ぶと、吸い込む花粉の量を減らせます。
2:花粉のつきにくい素材の服を選ぶ
服の素材は、なるべくツルツルしたものがいいでしょう。
とくに、コートや上着の素材は、綿やウールなどより、花粉が付着しにくいポリエステルやビニールなどの化学繊維のものがおすすめです。
3:帰宅時は玄関で衣類をよく払う
外出時に衣類や髪などについた花粉を室内に持ち込まないために、帰宅時は衣類などをよく払いましょう。
自分だけでなく、ペットなどにも要注意です。玄関先にブラシを用意しておき、家に入る前に丁寧にブラッシングをすると花粉がしっかり落ちます。
4:帰宅後は洗顔やうがいをする
帰宅後はすぐに手洗い、洗顔、うがいをして、顔や喉などからだについた花粉もしっかり洗い流しましょう。スチームなどで喉や鼻の粘膜をケアすることもおすすめです。

自宅でできる花粉症対策
花粉症対策は、自宅でもこまめに行うことが大切です。できるだけ室内に花粉を持ち込まないことに加え、花粉の影響をなるべく少なくするための対策も行いましょう。
1:加湿する
加湿器を用いて適度な湿度を保つことで、花粉が舞い上がるのを防ぐことができます。また、加湿することは粘膜ケアにもつながります。
2:洗濯物を部屋干しする
洗濯物に花粉がついてしまうと、花粉を吸い込んで悪影響が出る可能性があります。花粉の飛散する時期は、外干しは避け、部屋干しや乾燥機などを使いましょう。
3:深夜や早朝に換気する
花粉の飛散量が多い時間帯は、窓やドアをしっかり閉めておきましょう。
換気は、比較的花粉の量が少ない深夜や早朝に行うのがおすすめです。換気は窓を小さく開け、できるだけ短時間で済ませましょう。
4:免疫力を高める
花粉症対策には、からだを強化して症状を感じにくくすることも大切です。
規則正しい生活、バランスのとれた食生活、良質な睡眠などは、正常な免疫機能を維持するために欠かせません。
また、アルコールや喫煙は、喉や鼻の粘膜を荒らして症状を悪化させることがあるため、なるべく控えましょう。

花粉症対策には漢方薬もおすすめ!
花粉症の症状を軽減させるためには、抗アレルギー薬である抗ヒスタミン剤などがよく使用されています。しかし、これらの薬剤は眠気や集中力の低下といった副作用が気になる場合もあるでしょう。
漢方薬のなかには、鼻水や鼻炎に効果が期待できるものがあります。眠気を気にせず服用できることもメリットです。
花粉症対策に用いられる漢方薬は、主に鼻水や鼻づまり、くしゃみなどの症状を抑えるものと、花粉症などのアレルギー体質を根本から改善するものとがあります。
西洋薬では目には目薬、鼻には点鼻薬など、その症状を和らげることを目的とした薬が用いられます。
一方、漢方薬の場合は「鼻水や鼻づまり、くしゃみなどの症状を抑える」作用のものだけでなく、
- 炎症を和らげたり、炎症を起こしにくい体質に変えたりする
- 消化・吸収機能を良くして抵抗力を高める
- 水分の循環を良くしてアレルゲンや老廃物を排出する
といった作用を持つものを活用して、根本からの改善を目指します。
漢方薬は、からだ全体のバランスを整えてくれるので、すべての症状にアプローチできます。さらに、体質改善にも役立つので、つらい症状の予防や根本改善が期待できるうえ、花粉症以外の不調の改善にもつながるでしょう。
花粉症対策におすすめの漢方薬
・小青竜湯(しょうせいりゅうとう)
体力が中等度の方に向いています。
くしゃみ、鼻閉、水様鼻水、アレルギー性鼻炎などに効果があります。
無色透明の鼻水がサラサラと水のように流れ、止まらないような症状や、アレルギー性鼻炎に使用されます。
・葛根湯加川芎辛夷(かっこんとうかせんきゅうしんい)
比較的体力がある方に向いています。
慢性鼻炎や蓄膿症に効果があります。
鼻水は少し粘り気があって無色から白色であり、冷やされることで症状が悪化する寒証タイプに使用されます。
・荊芥連翹湯(けいがいれんぎょうとう)
比較的、体力が中等度くらいの方によく用いられます。
慢性鼻炎や慢性副扁桃炎、蓄膿症に効果があります。
粘り強く、黄色から緑色の鼻水に向いています。
しかし、同じ鼻水や鼻づまりの症状でも、鼻水の色や粘度、からだの冷えなどを考慮して漢方薬を選ぶのは難しいですよね。
からだが冷えると症状がひどくなるのか、花粉症の初期に症状が出るのか、慢性的に鼻づまりがあるのかなども、漢方薬を選ぶ際には必要な情報となります。
漢方薬を選ぶときに重要なのは、その人の状態や体質に合っているか、ということです。うまく合っていないと、効果を感じられないだけでなく、場合によっては副作用が生じることもあります。
スマホで気軽に専門家に相談できる「あんしん漢方」のような、オンライン個別相談も話題です。あんしん漢方はAI(人工知能)を活用し、漢方のプロが効く漢方を見極めて自宅に郵送してくれるオンライン漢方サービス。
スマホで完結できるので、対面では話しづらいことも気軽に相談できますよ。お手頃価格で不調を改善したい方は、医薬品の漢方をチェックしてみましょう。

花粉症対策は症状が出る前から始めましょう
花粉症の症状を軽く抑えるためには、シーズンに入る数週間前から対策を開始することが大切です。
自分が何に対してアレルギー反応を起こすのかわからない場合は、医療機関で血液中の抗体検査をするのもおすすめです。
自分のアレルゲンは何かを知り、早めのセルフケアを行うことで、くしゃみ、鼻水、鼻づまりだけでなく、かゆみや粘膜の負担などを軽減することもできます。
また、体質改善を目指したい場合は、漢方薬をとり入れてみるのもおすすめです。
参考サイト
- ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)
- ツムラ葛根湯加川きゅう辛夷エキス顆粒(医療用)
- ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用)
- 厚生労働省:平成22年度花粉症対策
■この記事を書いた人

あんしん漢方薬剤師:相田 彩(あいだ あや)
昭和薬科大学薬学科卒業。総合リハビリテーション病院・精神科専門病院・調剤薬局の現場で漢方薬が使用される症例を多く経験。
医薬品での治療だけではなく、体質や症状に適した漢方薬を活用し根本改善を目指すことの重要性を実感する。
現在は、症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホ一つで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「オンラインAI漢方「あんしん漢方」」でサポートを行っている。
(mimot.(ミモット)/ あんしん漢方)