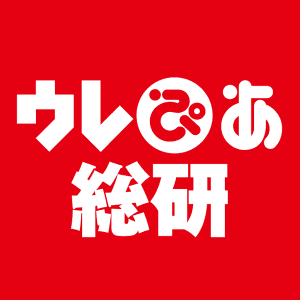主演・綾野剛、共演・柄本佑、監督脚本・荒井晴彦という、映画好きであれば気になってたまらないタッグが組まれた映画『花腐し』11月10日(金)より全国公開される。
芥川賞受賞作『花腐し』を、日本を代表する脚本家の一人である荒井が新たな解釈を加えて脚色し、『火口のふたり』(2019年公開)に続き、監督も務める。
綾野が演じる物語の主人公・栩谷は売れないピンク映画の監督。恋人の祥子(さとうほなみ)が友人と心中した上、住む場所にも困るという状況の中、何者とも言えない男・伊関(柄本)と出会う。そして、実は伊関も過去に祥子と恋人関係だったことがのちに判明する。
現代パートをモノクロで、回想パートをカラーで見せるという手法で、希望があった過去と、どうにもならない現実と向き合う現在との対比を見せるところや、ピンク映画の監督が本人役で出演したり、名作映画を引用したシーンを入れるなど、かなり“映画的”な作品だ。
最初に脚本を読んだ時点で綾野は「どうやっても映画になる」と感じたと言い、柄本は「いち映画ファンとしてやらなくてはいけない仕事でした」と明言する本作に対して、二人はどのように向き合ったのか。現場を振り返りながらじっくりと語ってもらった。
シンプルに言うとマッチョで繊細な脚本でした

――最初に脚本を読んだときはどんな印象を持ちましたか。
綾野:久々に“脚本”に出会い、読み物として完成していたので、これを映画化した時、この完成度をどこまで追求できるのかということと対峙させられました。でも、佑くんやほなみさん、監督を始めとする“映画人”の方々の中に入れることは、自分にとって畏怖心よりはるかに豊かで、幸せなことだと思って飛び込みました。
――「怖い」という想いもあったのですね。
綾野:(脚本に)今まで発声したことがないような会話と対話が書かれていました。どう理解しその言葉が自然と生まれてくるのかということから始めないといけませんでした。佑くんは“直線距離でセリフを言ってみる”ということをシンプルにできる人なので、そこがとにかくカッコいいです。
僕は言葉を発するまでにいろんな感情が往来するのですが、監督や現場の皆さんが「自由にやっていいんだよ」と潔く仰るので、真っ直ぐ打ち込めました。
あとはシンプルに好きな人たちがたくさんいる環境だったので、できないことだけを自問するのではなく、できること、できるようになること、できたあと、いろいろな角度から受け止め、楽しみ、臨めました。芝居における不安も安心して共有できる現場という信頼が自分の中で生まれていたので。それに現場で佑くんと不安を共有できるなんて特別なことです。

――柄本さんは映画『火口のふたり』(2019年公開)に続いて、荒井晴彦脚本・監督作品への出演となりますが、最初に脚本を読んだときはどう思いましたか。
柄本:難しいんですよね(苦笑)。これまでの取材でも聞かれてはいるんですけど、いまいちその答えが見つかっていないというか。「ただただ面白い」ということしかお伝えできないんです。
いろんな言い方はあるとは思うんです。原作はあるけどオリジナリティのある作品になっていることとか。二人の男性と一人の女性との別れとか。一つの時代が終わっていくことと、ピンク映画の業界が終わっていくことを絡ませているとか。
でも、そんなことを言ってもしょうがないって感じもするんです。さっき綾野さんがおっしゃったように、「映画の脚本としてものすごく面白かった」というのが、一番だなと。ただ、それだけだとあまりにもコメントとして投げっぱなしだとも思うし(苦笑)。
綾野:(笑)。シンプルに言うとマッチョで繊細な脚本ですよね。
柄本:ホントに(笑)。非常にストイックな。だからそういう脚本は役者のことをかなり縛ってもくるんですけど、縛られるとわりと自由にもなれるという。
綾野:すごくわかります。
柄本:これだけ強度の強いセリフを言っておけば、とりあえずそういうふうになるだろうって。無責任にもなれるんです。

――柄本さんは本作に対して「いち映画ファンとしてやらなくてはいけない仕事でした」というコメントをされていましたよね。
綾野:佑くんのコメントって本当に秀逸ですよね。他の作品へのコメントもよく拝見しているんですけど、いつも素敵だなって。ファニーさも、ユニークさもあって、それでいて芯をくっている。佑くん自身がまさにそういう方なんですよね。
柄本:いやいや(照笑)。
――このコメントの真意を改めて聞かせていただけますか。
柄本:先ほども言いましたけどやはり面白い脚本ということですかね。それと(監督・脚本が)荒井晴彦だということ。それに尽きます。だって(映画が)好きでやっていますからね。そういうところには踏み込みます(笑)。
こんなチャンスをいただけるのであれば、「ありがとうございます」「ごちそうさまです」ということです。こういう作品をちゃんとやっておかないと、何のために(役者を)やっているのかわからなくなります。
綾野:僕もオファーをいただいたとき、ご褒美だと思いました。どうやっても映画になるという確証が脚本の時点で湧き立っている。例えると、すでに確変が入っているパチンコ台のようなもので、そこから何回転するかは現場と役者次第という。
柄本:そうそうそう。
脚本にそう書かれていたから、そうなった

――それぞれ演じた役にはどのように向き合いましたか。栩谷は登場シーンの短いやり取りだけで、何となくこんな人なのでは?というのが見て取れた気がしました。
綾野:脚本の時点で確変状態なので、佑くんの言葉を借りればセリフを言うだけで成立する精度の高さが基本的にはありました。完成作を観たとき、佑くんが演じた伊関が出てきたところは、何者かまったくわからない底知れぬミステリアスさがあって、いろんな想像を掻き立てられる。栩谷はどんな人物か予想しやすい。そうゆう意味では少し感情の体温が高かったような気がします。
伊関と一緒に話はじめると、自然とフラットになり、お互い感情を取り戻していくのを感じたので、栩谷はスタートから出会うまで、もう少し抑えたチューニングもあったかなと。
柄本:(完成作を観て)そういう細かいところまでいちいち気になってしまうことありますよね(苦笑)。僕も伊関が出てくるまでは普通に観られていたのに、出てきた途端、自分ばっかり追ってしまって。で、また自分以外の人のシーンになると、その間に自分の反省をして、また出てくると追ってしまう(笑)。
綾野:インタビューで吐露してしまいました。
柄本:ありますよ、それは。

――一つ気になったところなのですが、栩谷の体つきは意識して作られたものですよね。
綾野:現在のモノクロは、フィジカルさを無くした諦められた身体を目指しました。肩とか胸には大した肉がついてなくて、お腹周りは水太りで覇気のない肉体イメージ。祥子と出会った頃の、若いときは少し締めたクリーンな体つきを目指しました。
――すごくリアリティがあるなと感じました。でも、身体づくりって年々大変になっていきませんか。
綾野:そうですね。若いときは短期間でできていた肉体作りが、今ではできません。トレーニングの時間や食事を摂取するタイミングなど、トライ&エラーを繰り返して、年齢に合わせたメニューを更新する。
年齢とともに変わっていく自分の身体を知り続けることを放棄しないことが大事です。若いときと同じにはできない代わりに、知見と探求心で進化を諦めないことですね。

――置かれている境遇からすると、伊関は栩谷によりもひどい状況だとは思うのですが、何か飄々としていて、よくわからないパワーのようなものを感じました。
柄本:今おっしゃられたようなことは、脚本でそういうふうに書かれているってことなんですよね。そう書かれていたから、そうなったという。ただ前回の『火口のふたり』のときの反省というか、心残りのようなものもあったので、(伊関を演じるに当たって)自分から持っていったものもありました。
具体的なもので言うと、過去の、伊関がまだ映画人を志しているころは、映画のTシャツを着ていて、現在の、腐ってしまったときには、ちょっとくたっとした格好をしていて。あのコートとパンツは自前のものなんです。「こんなんがいいのかな?」というのを持っていきました。前回は全くの受け身でいたんですけど、今回は衣装とか、そっちの方にも踏み込ませてもらいました。

――栩谷、伊関の元恋人・祥子を演じたさとうほなみさんの印象を聞かせてください。
綾野:「カッコいい人」ですね。
柄本:うん。カッコいいですね。
綾野:地に足のついた直観力。
柄本:それでいて大らかなところもあって。

――センシティブなシーンも多いので、演じる上で話し合いをする機会も多かったのではないでしょうか。
綾野:性的描写のあるシーンに関しては、インティマシーコーディネーターの方に入っていただいて、リハとコンセンサスを取り合った中で撮影し「よーい、スタート」ってなって、ストンとその世界観に入るスピード感はすごいなと感じました。
柄本:あと、馬力がある。
綾野:本当にスパンとしていて気持ちのいい方です。
柄本:そうですね。明るいし。
別れのキスはするのか、しないのか

――撮影をしていて印象に残っているシーンはありますか。
綾野:佑くんとは何度か共演していますが、実質、向き合っての共演は初めてでした。佑くんから「自然に溶け込めた」という言葉をいただいたときに、同感でした。
自分が出ていないシーンは客観的に観られたので、情感を揺さぶられる場面がたくさんありました。特に、伊関と祥子が別れを前にする最後のシーンは、何もない部屋で、肉体の塊として会話をしているというか。実際セリフはないんですが、会話が聞こえてくる。息をするのも忘れて見入ってしまいました。あのシーンはものすごく鮮明に残っています。
柄本:あのシーンの裏話的なことを言うと、前日の撮影が終わったあとに荒井さんが控室に来たから「明日のこのシーンのことなんですけど……」って質問をしたんです。あのシーンだけ、珍しく脚本にト書きが少なかったから。
他のベッドシーンに関しては、前戯から挿入のタイミング、そこからどういう流れになるかまで、セリフと同じような感じで細かくト書きが書かれていたんだけど、あのシーンだけそれがなかったから、「キスはするんですかね?」って訊いたら、「難しいことを聞くなぁ」って返されて(笑)。
そこから、別れのキスはするのか、しないのか、ということを、さとうさんとインティマシー・コーディネーターの方も一緒になって考えたとき、さとうさんは「最後のセックスでしょう? とりあえず思い残すことがないくらいキスするんじゃないかな?」とおっしゃって。
そしたらインティマシーの方も「別れのセックスシーンはキスをする気がする」とおっしゃって。それで、あそこは祥子が初めて伊関とのセックスでエクスタシーに達するという瞬間でもあるんですけど、そのあとキスをするという流れになりました。

――柄本さんが印象に残っているシーンはありますか。
柄本:僕は最終日に撮影した地獄の14ページ。セリフが出てこなくて。綾野さんにずっときゅうりの入った水をガバガバ飲ませてしまって(苦笑)。申し訳ないなと。あのきゅうりも食べるようにって言われているんだけど、水を含んでいるから美味しくなくて(苦笑)。その都度、ホッケも食べたり、「本当にすいません!」って思いながら、最終日にやらかしちゃったなと。
綾野:僕は「終わらなくていい」って。「1秒でも長くこの時間が続け」って思っていたので、全然ですよ(笑)。終わってほしくない現場でしたから。

――韓国スナックで栩谷と伊関がお酒を飲むシーンですよね。
柄本:そうです。そこに1個、長台詞があって。万葉集の話をするところなんですけど。
綾野:隣で初見で聞いても直ぐに意味が直結しない話だから、あれを自分の言葉で話すってなったら大変ですよね。
柄本:万葉集なんて知らないし(笑)。でも脚本に書いてあるから、荒井さんは万葉集が好きなのかな?って思っていたんだけど、この間、映画祭でこの部分について荒井さんが話しているのを聞いたら、原作の要素を残したほうがいいと思って入れただけで、万葉集のことはよく知らないっておっしゃっていて。
綾野:(笑)。その話、すごく面白い。
佑くんが相手だと何をやっても成立する

――そうやって万葉集のくだりとかが出てくるので絶対にアドリブではないことはわかるんですけど、ほぼお二人のセリフのやり取りだけで、それが結構長い時間続くけど、あまりにナチュラルだから、アドリブにも見えてきて。焼酎にきゅうりを入れるタイミングとか、タバコを消すタイミングとか、全部、絶妙なんですよね。
綾野:ナチュラルというよりは、空気を読むと言ったら変ですけど、それに近いような感覚でやっています。「このタイミングだったら会話を邪魔しないだろうな」と考えて手を伸ばしたり、逆に「ここは前に被ったほうが自然だな」と思ってわざとやったり。そういう企みの積み重ねなんです。
だから一緒にやる相手が変わると全部変わってきます。佑くんが相手だと何をやっても成立する空気感が顕著にあって、二人でしゃべっていると、勝手に自然に見えてくる。話を聞く以外の余計なことをしていても、佑くんが相手だとお芝居に見えないような感じに受けてくださるんです。
柄本:でも相手の話を聞いている、自分のセリフを言わなくていい瞬間は、結構やりがいはあるんです。セリフを言っているところは別に芝居でもないというか、逆にしゃべってない時間のほうが芝居だなという気がします。
綾野:そうですよね。受けがすべてに近いです。
柄本:何回かやっていると然るべきタイミングがわかるというか。飲むタイミングにしろ、食べるタイミングにしろ。
綾野:導線がきれいにくっきり見えるときがありますよね。「それ以外に絶対にない」というくらいの完璧な流れがあるんですけど、ちょっとしたことでその瞬間を逃してしまうとすごく焦るということもあります(笑)。だからタバコを消すとか何気ない動きも演じる側からすると大芝居なんですよ。セリフとセリフの間の間(ま)とか。間があけばあくほど大芝居。
柄本:トム・クルーズが『ミッション:インポッシブル』でやっているような、バイクで崖から落ちるとか、実際に飛んでいる飛行機に捕まるとかと、「この会話でここに手を置くのはどのタイミングか」とかは、同じレベルです(笑)。
綾野:(笑)。これはこれで映画全体の大きな要素なので。だからタイミングを逃すと、「もう絶対に動かせない」ってこともあります。

――改めて、お二人が本作を通して感じたことを伺えますか。
柄本:荒井さんの正直さですかね。「つかないケジメをつける」ということを荒井さんはされていて。「腐ってしまっても息をしている限りは生きていかなきゃ」みたいなところがこの作品にはあると思います。ピンク映画のくだりでも、「上野にもっと撮らせてあげれば良かった」というセリフが出てくるんですけど、あれは僕も大好きな上野俊哉さん(2013年逝去)という名監督のことを言っていたり。
とにかくそいつに関して話してやることが、生きている奴らができる一番の弔いじゃないですけど、そうやって気持ちの整理がつかなくても、俺らは生きているからしゃべろうぜっていうこととか。そこら辺がやっぱり荒井さんはカッコいいですよね。本当に正直な映画だと思います。
綾野:あらゆる事へのレクイエム映画です。終わりと始まり。送ることと、迎えること。僕はそんな本作を一人でも多くの方たちに届けたいと思っています。そう思えたのは、きっと今、佑くんが話してくれたことを現場からも、作品からも感じていたからだと。改めて佑くんのお話を聞いて結実しました。

*
写真撮影の際にもお話が止まらないお二人。ただ単に仲良しというより、お互いへのリスペクトが根底にあることが感じられる素敵な関係性でした。映画の中では、“映画的”な作品を、より映画として完成させるお二人の演技にどんどん引き込まれていきます。映画ではければ描けない物語を、ぜひ映画館で堪能してください。
作品紹介
映画『花腐し』
2023年11月10日(金)より全国公開
(Medery./ 瀧本 幸恵)