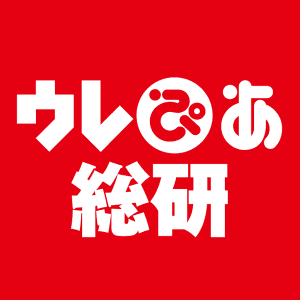東海岸沿いをのんびり南下していた筆者だが、旅程が半ばであるにもかかわらず、台湾を半周もしていないことに気づいて一気に南下し、台頭を経由して台湾第二の都市・高雄へ向かった。
東海岸の名もない町から台東、高雄へ
無計画な旅というのは、締め切りが一週間後に迫った原稿に似ている。
まだ一週間ある、と思って最初のうちは時間をかけて推敲するのだが、一週間を半分過ぎたのに原稿が進まないと焦ってくる。
台湾一周の旅も、最初は「この駅で降りてみたい」「あの町もよさそう」とちょこちょこ途中下車をするのだが、日程が半分を過ぎてもまだ半周できていないと、移動距離を延ばすことになる。
東台湾でのんびりしていたら、もう4日目なのに高雄にたどり着いていないことに気づき、あわてて関山から高雄までの切符を買った。途中の台東駅で乗り換えのために下車。
しかし、台東の街でのんびりする時間はない。せめてもと名物の池上飯包(弁当)を買い込み、高雄行きの列車に乗り込んだ。

台東→高雄の車窓にうっとり
「何日あれば台湾を一周できますか?」とよく聞かれる。列車に乗りっぱなしでもいいなら、2日もあれば一周できるのだが、よほどの鉄道好きでなければ味気ない。
とはいえ、台東から高雄間の車窓は、ずっと眺めていても飽きないくらい美しい。台東エリアには荘厳な山々と車窓いっぱいに広がる田園風景。秋ならば黄金の稲穂が揺れるのが見えるかもしれない。
そして延々と水平線が続く太平洋と椰子の木が並ぶ海岸線を望むこともできる。

果樹園やビンロウの林、養魚場なども風景に入り込んできて、目まぐるしい変化にいちいちカメラを向けてしまう。
台鉄の自強号は新幹線ほどスピードが速くないので、車窓もゆっくりと流れていく。
朝の9時過ぎに関山を出発し、台東で乗り継ぎのために30分ほど待ったため、高雄に到着したのは13時少し前。およそ3時間半の旅だ。
この3時間半を「移動」と考えるとずいぶん長い気がするが、車窓を楽しんだり、次の町で食べたいものを考えたりする休息時間と考えると、旅はとっても優雅になる。
もちろん、しっかり眠って体力をチャージするのもいい。
高雄の定宿でひと息
市内に両替ができる銀行もない田舎町・関山から大都会・高雄に来た私は、カラフルな広告が流れるLCDモニターや電光掲示板に目をチカチカさせてしまう。
2本の地下鉄を乗り継いで、高雄の定宿である『叁捌旅居』に向かった。
高雄港に近い、鹽埕(イェンチェン)というエリアにあるレトロなビルをリモデリングした民宿だ。

かつてのウェディング・サロンを三代目(オーナーの孫・ダニエル氏)がレトロモダンな宿へと作り替えた。
サロン時代の間取りやドレスの収納ボックス、トルソーなどをそのまま使ったインテリアのセンスのよさには脱帽してしまう。
鹽埕は1960〜70年代にかけて大いに栄えた港町だ。
日本時代も、そしてアメリカの第7艦隊が港に駐留した時代も、新しいものが真っ先に届き、人々の暮らしも文化経済も潤っていた。
華やかな時代はやがて終わりを告げたが、鹽埕には今も往時の空気が流れている。
そして、ダニエルのような若者が古いものを丁寧に磨き、味を出し、再び世に出そうとがんばっている。
昔ながらの商店街には何十年もパンを焼き続ける店や、サバヒー(台湾南部の白身魚)のスープを出す店が健在で、そのすぐ隣にはおしゃれなイタリアン屋台や、古風な雑貨を売るお店があったりする。

母と息子の緑豆チマキ
お昼はとっくに過ぎていて、夕食にはまだ早い時間帯。日本でもそうだが、営業中の店が少なくなるので食事に苦労する。
鹽埕の錆びついたアーケードを歩いていると、まだチマキの店が開いていた。
「店」と言っても、アーケードの下に看板をぶらさげて、通りの隅っこに細いカウンター席が3つ、4つあるだけの、屋台とも言えないような小さなスペースだ。
チマキは南部と北部で作り方や味がだいぶ違う。
この店のチマキはもちろん南部チマキだが、「茹でチマキ」という特徴のほかに、使われている食材も変わっている。

南部というより、この店のオリジナルらしい。
チマキは普通、もち米に肉や干ししいたけをプラスして笹の葉で包んだものだが、ここではもち米の代わりに緑豆を使っているのだ。
ポロポロとした、しかし茹でられてホクホクした緑豆でできたチマキに柔らかく煮たピーナッツが詰まっていて、さらにピーナッツ粉と甘いタレがトッピングされている。
こうなると、食事というよりおやつに近い。中途半端な時間帯なので他の客の姿はなく、私はカウンターを独占してもち米のチマキと緑豆チマキをゆっくりと食べ比べた。
店主の女将さんいわく、緑豆チマキは息子さんが考案したのだそうだ。
チマキ店の後を継ぐのかと聞けば、「息子はモデルなの、だからチマキ店なんか継がないわよ」とはにかんで笑う。
恥ずかしそうに、でも誇らしげにスマホの画面で息子さんの写真を見せてくれた。
台北のイベント会場で派手な衣装を着てポーズを決める20代のイケメン男性だ。きっと自慢の息子さんなのだろう。台北で活躍しながらも、母親が営むチマキ屋台の新メニューを考える。
南部チマキのようにあたたかい親子関係だ。
(つづく)
(うまいめし/ 光瀬 憲子)