
【Boston GP 156 Performance Edition II】(都内某所 マイペースなアマピアニストAさん 〇〇歳)

以前で投稿させていただいた者です。「前の記事に書ききれなかったことを書きたい!」という欲求を我慢できずに2ヶ月越しに只今こうして筆を執っております(笑)。
まず、Bostonというブランドから説明しましょう。
Boston PianoはSteinway&sons社がセカンドラインとして日本の大手(YAMAHA、KAWAIなど)と同じ層をターゲットにし、1991年に販売を開始したメーカーです。Steinway&sonsは製造台数世界3位、コンサートでのシェア95%という驚きの数値をもつ世界三大ピアノの一角として君臨しています。
さて、SteinwayがBostonを創設するにあたっては、大きく2つの壁がありました。
1つ目は価格。Steinway&sonsのグランドピアノの新品はゆうに1500万円以上。烏丸編集長の腰が10回ぐらいやられそうなプライスでは流石にターゲット層は無理をしても買えません。その値段の高さはハンドメイド故です。一方、同じ層にターゲティングしているYAMAHA、KAWAIなどは機械生産を取り入れています。しかしながらSteinwayの敷地にBoston専用の工場を建てるわけにも行きません。そこでSteinwayが取った戦略はKAWAIによるOEM生産です。自分たちは設計をして、他のところで生産するというわけで、値段の大幅な値下げを実現しました(そのため、鍵盤蓋には「Designed by Steinway&sons」の文字が刻まれています)。もちろん、材料や音色はSteinwayに比べて劣るのは否めませんが。
2つ目の壁である生産台数もOEM生産によって解決しました。Steinwayの生産台数は年間2000台ちょっと。流石にミドルクラスとしては供給不足です。しかし、これもKAWAIによるOEM&機械を活用した生産によって解決しています。
さて、そんなわけで1991年に産声を上げたBoston。しかし、初っ端から問題を出してしまいます。音の立ち上がりが遅い。次にGP178(注1)の次高音域がズレやすい等。これらは、生産初期でまだフィードバックが足りていなかったせいだと考えられています。Bostonはこれらの問題を解決するためにBoston IIシリーズを発表。全体的に改良が加えられ、狂いが減って音が安定したとの評価を受けます。また、初期はBoston Piano Co.によって逆輸入する形で日本国内での販売をしていましたが、ここからは親会社のSteinwayの日本支社が大元となって販売するようになりました。ここまでは調律師泣かせのジャジャ馬ピアノという感じだったそうですが、さらに2009年、打鍵部分(アクション)に大きな改良を加えたPerformance Editionを発表。ここで最大モデルのGP218が215にリニューアルされます。さらにピンブロック(チューニングピンを差し込んでおくホールド部分。ここで音のズレやすさがだいたい決まる)にも改良が加えられ、それまで硬すぎたのがちょうどよい硬さにリニューアルされています。ちなみにピンブロックは米国特許取得済みだそうです。
その後、さらにPerformance Edition II に改良。全体的に完成度が上がっているそうです。細かい変更点としては、クロス類がKAWAIと同じ黒になっているところです。私が持っているのもこの世代です。
では、製造におけるこだわりポイント。リムにはマホガニーとハードメープル、響板はシトカ産スプルース材、レンナー社製の高級ハンマーフェルト、響棒はマホガニー製、鍵盤には人工黒檀、人工象牙を採用し、アクションは総木製。鍵盤もスプルース製。さらにワイドテイル設計、オクタグリップピンブロック、ねずみ鋳鉄製のフレームと低張力。
一つずつ解説しましょう。
・リム リムとは、グランドピアノの曲がっている横の部分のことで、圧力により整形されます。使用されているマホガニーもハードメープルも密度が高く、音が失われにくいのです。
・響板 ギター好きの皆サマはご存知だと思いますが、弦の振動を増幅させ、美しい音色を作る部分です。ピアノ業界で最高とされるシトカ産スプルース材が使用されています(シトカはアラスカ州にある都市)。低音にかけて薄くなるテーパー型です。
・ハンマーフェルト 弦を打鍵し、音を出すハンマーです。業界最大手のレンナー社がプレミアムウールを使用して製造した物を採用しています。
・響棒 響板に均等な音を届ける役目があります。マホガニー製のどっしりとした響棒です。
・鍵盤 独自開発の人工象牙 と人工黒檀を使用しています。これもスプルース材を使用しており指に吸い付くようなフィーリングです。
・アクション アクションは指から鍵盤に力を伝えて打鍵する機構です。KAWAIは現在、カーボンプラスチック製のアクションを採用していますが、SteinwayのこだわりによりBostonは総木製になっています。ちなみに木材はSteinwayが指定しているそうです。
・ワイドテイル設計。 ワイドテイル設計とはおしりを潰して響板面積を増やし、音の豊かさとパワーを出す手法ですが、あまりやりすぎると音が立ち上がりにくくなります。PE IIではかなりフィードバックが溜まってきているようで、よい塩梅になっています。
・米国特許取得済みのオクタグリップピンブロックは、メープル材を60度ずつ回転させて11層に重ねることで高いホールド力を実現しているそうです。昔はピン味(ピンを回すときのフィーリング)が硬すぎて、ピンだけねじれてしまうことで引いている途中でもすぐ戻って狂ってしまったそうですが、現在では狂いにくくなっています。
・ねずみ鋳鉄のフレームと低張力 フレームは最大20tにも及ぶピアノの張力を受け止める屋台骨。ヒビが入っただけで音色が安定しなくなります。そうすると新品のピアノ並みの値段を出して修理するか、買い替えるかです。そんなピアノの屋台骨には鋳鉄が使われています。この素材はSteinwayでも同種のものが使用されています。弦の張力は低めの約17t。豊かな響きを実現するためです。これらの要因は倍音を多くすることを目的に設計されていますが、あまり多すぎるとガヤガヤしすぎて、あまり少なすぎるとつまらなくなってしまうので調律師の腕が試されるピアノだそうです。
最後に自分のピアノのノロケを一つ。すごくダイナミックでパワフルな音で、もはやこのサイズのピアノが出せる音とは信じられないほどです。某BBCの自動車番組(T◯p Gear)の司会よろしく「POWER IS THE BEST!!!!」なピアノかと思えば、繊細なショパンが弾けたりする。自分の手足のようによく動くピアノです。重厚感のある低音部。流石に全長156cmだと少々低音部の余裕はないですが、満足できます。何より華やかな中高音部!先程述べたワイドテイル設計によるものですね。少々腕は使いますが、非常に良いピアノです。とはいえ、落ち着くまでに2,3年かかるそうなので、落ち着いたら続報をお送りしたいものです。私の好きなピアノの漫画、『ピアノのムシ』にこんなセリフが出てきます。「新品のピアノはまだ幼子のようなもの。だがお前にとって生涯の伴侶となり、お前自身を映す鏡ともなろう。」読者の方々も新品のピアノを買ったときには精一杯愛でてあげましょう。100点満点でなくても良い。ジャジャ馬でいい。そんなピアノがたまらなく好きだ!という方々にはおすすめできるピアノです。もともと中学校で担任に目をつけられるくらいには問題児だったワタクシ。ピアノはオーナーに似るものです。
人によってはピアノに名前をつけて可愛がりますが、私は「コロンとしてて外が黒くて中のフレームが金色だから」という理由で「カヌレ」と名付けました。毎日可愛がらないとすぐすねてしまうかわいいやつです。このサイズのピアノはベビーグランドというのですが、まるで赤ちゃんのようにかまってあげないといけません。非常に可愛くて頼もしいです。 最後にもう一回言います。可愛いです。
P.S. 最近防音装置を増設しました。写真の白いものと下の追加の支柱の上に隠れているものです。
おまけで烏丸編集長がで言っていた疑問「なぜヴィンテージピアノは注目されないのか」に素人考えながら回答したいと思います。
まず、ギターやヴァイオリンとは違い、ピアノの調性は専門家である調律師が担当します。ピアノが出始めの極初期、(もしかしたらチェンバロ)」つまりモーツァルト以前なんかは演奏家が調律を担当したこともあるそうですが、現在のピアノは構造が非常に複雑になっています。このため自分で調律できるのは調律師でありながらピアニストであるなんていう非常に限られた人々だけになってしまいます。お金もかかりますから、調律をコンスタントにし続けるのは難しいのです。それすなわち、ベストコンディションを維持するのが大変というわけです(現に中学校に有ったピアノはフレームが割れていたのです!!)。
次にピアノは非常にデリケートな楽器であり、理想ならば温度は25℃前後、湿度は45~50%が最適です。しかし、これらの条件を外すことは家庭では日常茶飯事です。そのため、ヴァイオリンのようにエイジングされた古いピアノは状態が悪いことが多いのです。また、一部には「1世紀たてばピアノはだめ」なんていうコメントが有ったりしますが、コンサートホールなどにある管理がしっかりされたピアノはその限りではないと思います。しかし、大多数はあまり管理された状態に置かれないのであまり騒がれないのだと思います。管理された状態できちんと調律がされ、最上級の部品が使われた古いピアノは使われていた材料が昔のほうが上質であったこともあり、とても良い音がします。
ちなみにオーバーホール(大規模修繕)を行うと音色は大きく回復しますが、それこそウン百万円のお金がかかることも珍しくありません。よっぽど自分のピアノにこだわりがあるピアニストでない限り、そんなお金を払ってまで修理するのなら買い替えるのが普通であると思います。
脚注:1)Bostonの命名規則はグランドだったらGP、アップライトだったらUP+グランドだったら全長、アップライトだったら全高の数字3桁(cm)

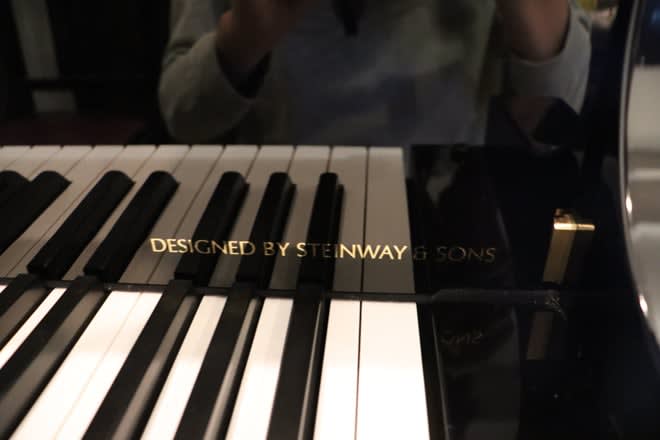


◆ ◆ ◆
ほうほう、うんうん、なるほど…と読み進んでおりましたが、実はさっぱり分かっていないという悲しさ。でもこのピアノがとにかく素晴らしくて可愛くて仕方がないということだけはしかと伝わった。それが一番大事。で、弾けば弾くほど楽器も育って、いつしか自分のサウンドを奏でる欠かせない相棒になるという点も、他の楽器と全く変わらないんですね。今ではマホガニーもエボニーもローズウッドも優れた材の入手が困難になってきていますから、ピアノ製造にも大きな影響が出ているんでしょうね。そういう意味でも現在のアコースティック楽器は、本来の魅力を保持している最後の時代なのかもしれません。(BARKS 烏丸哲也)
★皆さんの楽器を紹介させてください
「俺の楽器・私の愛機」コーナーでは、皆さんご自慢の楽器を募集しています。BARKS楽器人編集部までガンガンお寄せください。編集部のコメントとともにご紹介させていただきますので、以下の要素をお待ちしております。
(1)投稿タイトル
(例)必死にバイトしてやっと買った憧れのジャガー
(例)絵を書いたら世界一かわいくなったカリンバ
(2)楽器名(ブランド・モデル名)
(例)トラヴィス・ビーン TB-1000
(例)自作タンバリン 手作り3号
(3)お名前 所在 年齢
(例)練習嫌いさん 静岡県 21歳
(例)山田太郎さん 北区赤羽市 X歳
(4)説明・自慢トーク
※文章量問いません。エピソード/こだわり/自慢ポイントなど、何でも構いません。パッションあふれる投稿をお待ちしております。
(5)写真
※最大5枚まで
