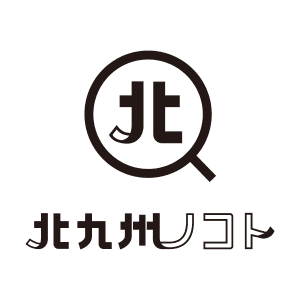北九州市で「カッパ」といえば、高塔山の「河童封じ地蔵」や、若松区のマスコットキャラクター「わかっぱ」などを思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。
門司区大積の天疫神社の境内横にある「水天宮」は、平家伝説ゆかりの地としてだけでなく、河童とも縁の深い場所として語りつがれています。今回、水天宮からほど近くに「河童の証文石」があると聞き、訪ねてみました。

河童が祀られている水天宮

筆者が子どもの頃、水天宮は「河童神社」の愛称で親しまれており、毎年5月に開催されている日本3大港祭の1つとされている「門司みなと祭」のパレードで、地域の女の子は両手に杓文字を持って踊る「シャギリ隊」、男の子は河童に扮した「カッパ隊」となるのが習わしでした。
水天宮に河童が祀られていると知った時は、子ども心に怖いような、見てみたいような、恐怖と好奇心の入り混じった気持ちになったことを思い出します。

(5月3日に開催された「しものせき海峡まつり」の源平船合戦の様子)
水天宮には、寿永4年に壇ノ浦の戦いで敗れて入水した女官たちが大積の乙女山の浜辺に流れ着き、里の人々が葬って石碑を建てたと伝えられています。

女官は河童に化身したという伝説が残されており、平教経の妻は「海御前(あまごぜ)」と呼ばれ河童の総帥として境内に祀られています。

門司区大積地区に伝えられる河童にまつわる伝説
門司区の大積地区には、河童にまつわる伝説がいくつかあるそうで、その中の1つ「河童の証文石」の話を地域の方に伺いました。
昔、大積の殿様の馬を乙女川(現在の奥畑川)で洗っていると河童が現れ、いたずらに馬を川に引き込もうとして失敗し、殿様の家来に捉えられました。そこで河童は懇願し、傍にあった石を指して「この岩が腐るまで領地内ではいたずらはしない」と殿様に命乞いをしたという言い伝えがあるそうです。

河童神社のことは知っていた筆者ですが、証文石の話は初めて耳にしました。水天宮からほど近い場所に現在も証文石が祀られているということで、早速現地まで案内していただき、行ってみることに。
「河童の証文石」を見に行ってみた
「河童の証文石」とはいったいどんなものなのか……幼い頃に感じたドキドキ感を胸に、足を進めました。

水天宮を左手に川沿いの小道を数分進んだ場所に、それは在りました。証文石の横にある河童のオブジェは、老朽化のため新しくなっており、現在はユーモアのあるオブジェとなっています。

地域の方の話によると、子ども達の通学を見守る役割もしているそうで、通学時には「おはようございます」「行ってきます」と、子ども達が声をかけているとのことでした。
■天疫神社住所:門司区大積1272
※証文石への道のりは私有地を含みます。公共のマナーを守って散策してください。
※2024年5月30日現在の情報です
(ライター・kohalu.7)