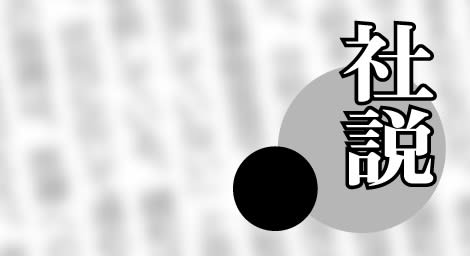
1人当たり4万円の定額減税が今月始まった。年収2千万円以下の納税者とその扶養家族を対象に、所得税が3万円、住民税は1万円引かれる。春闘の賃上げとの相乗効果で、消費に回るお金が増えるようにする目的だ。
ただ制度の複雑さに加え、ここにきて給与明細への記載が求められたことで混乱が広がっている。想定された効果は見通せていない。
国民の生活は物価高に圧迫され厳しくなっている。物価の変動を考慮した実質賃金は24カ月続けて前年を下回り、過去最長となった。6月に値上げされる食品も多い。
減税されたことが分かるのは年金受給者が支給日の14日、会社員は25日の場合が多いだろう。ただ電気、ガス料金の補助金は今月使用分(7月請求)から廃止される。減税分が消費に回るかどうか。政策としてちぐはぐさは否めない。
岸田文雄首相が導入決定時に強調した「税収増を国民に還元する」との説明は破綻している。増収分は国債の償還などに既に使われたからだ。
政府が見積もる減税規模は3兆2840億円。これだけ財源があれば、能登半島地震の被災地復興や教育、子育て、介護などさまざまな課題に対応できただろう。
減税の月を迎え、企業や自治体の事務作業は混乱している。所得が少なく税額より減税額が多い場合は現金給付になったり、海外に住む扶養家族は対象外だったりと、制度が複雑なためだ。
岸田氏が給与明細に減税分を記載するよう求めたことで、さらに手間が増えた。働き方改革で仕事の効率化が求められる中で、煩雑な作業を強いる形になった。
岸田氏は手取り額の増加を可視化し消費に振り向ける考えを示すが、「恩恵の押し付け」と受け止める向きも多い。増税も同じように記載しないのでは、筋が通るまい。
一律での現金給付にせず、減税の手法を採ったのは、防衛費倍増などの増税イメージを払拭することにこだわったためといわれる。通常国会会期末に恩恵を実感させ、衆院解散・総選挙に踏み切る想定もあったのだろう。政権浮揚に利用する思惑を国民は見透かしている。
定額減税は、橋本龍太郎内閣も1998年に実施した。しかし減税の恒久化を巡る発言が迷走したことで、自民党は参院選で大敗し、橋本氏は首相を退いた。
岸田氏の側近からは、経済状況次第で来年度も定額減税を続ける可能性を示唆する動きが出てきた。支持率の低迷で衆院解散が難しくなり、伏線を張り直しているように見える。だが税は政治そのものだ。小手先の人気取りに利用すればひずみを生む。
物価高を上回る賃上げとともに、政府が社会保障の持続性を示さなければ、国民は安心してお金を消費に回せない。負担増を伴うとしても、ごまかさず議論し、丁寧に理解を得ていくしかあるまい。求められるのは、将来を見据えた、バランスの取れた財政運営である。
