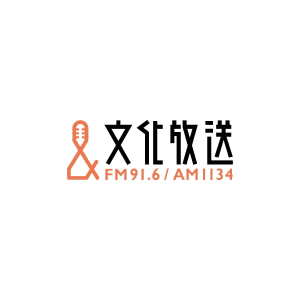働き方改革の一環でドライバーの働ける時間が減り、物流が滞る“2024年問題”。6月4日の「大竹まことゴールデンラジオ(文化放送)」では、「日本企業の物流軽視が招く“モノが運べない”危機」の著者でロジスティックスコンサルタントの久保田精一に物流の問題点を聞いた。
大竹「日本企業が物流を軽視しているのはなぜですか?」
久保田「ひとつは物流部門の立場の弱さみたいなところがあります。欧米やアジア企業では物流を管理してる人たちって花形で出世コースだという認識なんですね」
大竹「はい、はい」
久保田「でも日本の場合は逆で非常に立場が弱くて、それが典型的にわかるのが物流の担当の役員の少なさです。上場企業で調べると物流を専業でやってる役員って大体2~3%しかいないんです。これは欧米のグローバル企業とは大きく違う」
大竹「どうして日本の物流の役員は少なくて、あまり出世もしないんですか?」
久保田「採用の問題も密接に関わっていて、新卒一括採用の時に物流の専門で雇うっていうことがあまりないんですね。事務系総合職みたいな形で雇った人に例えば営業と物流とかを色々まとめてやってもらう。ジョブローテーションみたいな形で物流をちょっとやって、営業に戻って、総務に行ってみたいな人が多いんです。大学を出た時点でそもそも専門ではないですし、企業の中でもそんなに専門性が養われないっていうのが多分一番大きな問題ですね」
小島慶子「第二次世界大戦の時も兵站が凄く軽視されて、たくさんの方が亡くなりました。物を運ぶ人を低く見るっていうのは、いったいどこからきてるんですか?」
久保田「もともと文明って物流がベースにあるわけじゃないですか。物を運ばないと生活が成り立たない。例えばローマ帝国は道を作ってから統治をしていきました。日本って昔から結構そこがおざなりで江戸時代くらいから物流網が脆弱でした。船が物流をやってましたからね」
小島「あっ、なるほど。船が便利すぎたが故に陸路が軽視されがちだったってことですか?」
久保田「それもあると思います」