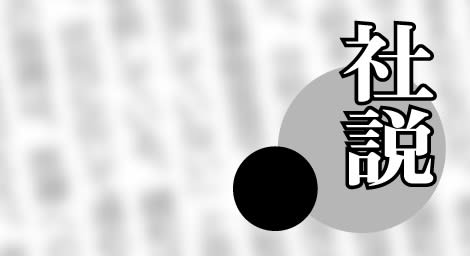
高い安全性に定評がある日本車の信頼を大きく損なう事態である。トヨタ自動車やマツダをはじめ5社が、大量生産に必要な「型式指定」の認証申請で不正を行っていた。
不正は計38車種に上り、500万台を超すという。うち生産中の6車種が国土交通省から出荷中止を指示された。
さらにきのう、国交省は道路運送車両法に基づき、愛知県豊田市のトヨタ本社を立ち入り検査した。他の4社も順次、検査する。5社は全て、事態の深刻さを重く受け止めなければならない。
型式指定は、まずブレーキ性能のサンプル検査データなどを国に提出。法令で定めた保安基準を満たしていれば、国の認証が得られ、一台一台チェックする手間が省ける。
今回の不正は、社によって異なる。トヨタはエンジン出力試験での数値改ざんなどを2014年から行っていた。マツダは14年以降、エンジン制御ソフトの書き換えなどがあった。不正車両の台数・車種とも最多のホンダは09年以降、騒音やエンジン出力試験などで不正をしていた。
トヨタの豊田章男会長は記者会見で「認証制度の根底を揺るがすもので、自動車メーカーとして絶対にやってはいけないこと」と謝罪した。マツダの毛籠(もろ)勝弘社長は「業務の手順書に基準がなく、現場レベルで独自の解釈をしてしまった」と陳謝した。
気になるのは「安全に問題ない」との各社の主張だ。根拠として、衝突時の乗員保護など法定基準より厳しい条件での試験を挙げている。
確かに今回、そんな事例が含まれている。ただ、たとえ型式指定の認証制度に問題があったとしても、法令違反は決して許されない。
ここ10年ほど、自動車メーカーの不正が後を絶たない。5社以外では、三菱自動車の燃費データ偽装、日産自動車とSUBARU(スバル)の新車の無資格検査、日野自動車のエンジンの性能データ改ざんなどがあった。もはや業界全体の体質といえよう。
特にダイハツ工業の不正は衝撃的だった。昨年発覚した30年以上前からの品質・安全確認試験などの不正は170件を超えた。国が、型式指定を申請している85社に不正の有無を調査するよう指示し、今回の5社の不正が発覚するきっかけにもなった。
多少のルール違反をしても安全性に問題あるまい、というおごりが、業界全体の緩みにつながっている―。経営学者が指摘しているほどだ。
毎年のように不正が相次いでいるのに、再発防止は一向に進まない。自浄能力を欠いていると言わざるを得ない。
自動車メーカーは日本の産業のエンジンである。電機産業が往時の勢いを失った今、重みを増している。下請けの部品メーカーや販売会社など裾野が広く、それぞれの地域の活力を支えている。
電気自動車(EV)の普及など国際競争が激化し、コストダウンや合理化にとらわれるあまり、ものづくりの原点を見失っていないか。安全や品質最優先の姿勢を改めて徹底しなければならない。
