By 柴田 誠
カメラ記者クラブが主催する「カメラグランプリ2024」の贈呈式が、2024年5月31日に都内で開催された。

40周年を迎えたカメラグランプリ
カメラグランプリは今年で40周年ということで、昨年とは趣きを変え、立食のパーティ形式で贈呈式が行われた。

コロナ禍の中ではTIPAからビデオメッセージが送られていたが、今年はTIPAの副議長に就任したエマニュエル・コスタンツォさんが来日して挨拶。やっとコロナ禍が明けて、以前のような日常が戻ってきたと思わせてくれた。

大賞&あなたが選ぶベストカメラ賞「ソニー α9 III」
カメラグランプリ2024「大賞」と「あなたが選ぶベストカメラ賞」を受賞したソニー「α9 III」。ダブル受賞の喜びと、昨年の「α7R V」に続いて大賞を受賞した喜びを語ったのはソニー イメージングエンタテインメント事業部長の大島正昭さん。グローバルシャッターと、モンスターのようなイメージセンサーをいかにパッケージングするかに苦労したそうだ。すでに次の開発がスタートしており、「賞をいただいたところで立ち止まらず、引き続きイノベーションを起こして感動を広げるために取り組んでいきたい」と、今後に期待させるコメントをしてくれた。ソニーはこの12年間で7機種が受賞している。

ユーザーに受け入れてもらえる画質を追求
「α9 III」の開発秘話を披露してくれたのは、ソニーセミコンダクタソリューションズ モバイルシステム副事業部長の木村匡雄さん。民生向けのカメラにグローバルシャッター方式のイメージセンサーを入れ込むのは非常に難易度が高かったとのこと。ただグローバルシャッターを積むだけでなく、ユーザーに受け入れてもらえる画質を提供することに腐心したそうだ。「新しいアーキテクチャの投入と我々の強みである画素技術を合わせ込んで、商品に結実させました。高速シャッターを実現するには駆動タイミングを合わせるのが難しいところでしたが、セット開発のメンバーとの協力で実現でき、非常に良かったと思います」と述べた。

ホールド感やシャッターの感触にもこだわった
同じく開発秘話を披露してくれたのは、ソニー 技術センター 商品設計第3部門 商品設計2部 4課の齋藤靖好さん。「α9 III」の魅力が革新的なイメージセンサーだけでないことをわかりやすく解説してくれた。ソフト面の進化としては、120fpsのAF/AE連動の高速連写を実現するために短時間で画像処理をしなければならないため、CPUやメモリーの使い方を詳細に分析してチューニングしたそうだ。また、ハード面では人間工学に基づいた設計を重視。手の大きさや指の長さを数値化して、グリップのホールド感の最適値を求めて設計に落とし込んだとのこと。「シャッターでは、切れの良い感触とは何かを分析して設計しました。部品が数十μmずれるだけで感触が変わることから、よりバラツキのない部品構成にしました」と、ホールド感と繊細なレリーズ操作を実現するための裏話を披露してくれた。


レンズ賞&あなたが選ぶベストレンズ賞「ニコン NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena」
「レンズ賞」と、新設された「あなたが選ぶベストレンズ賞」を受賞したニコン「NIKKOR Z 135mm f/1.8 S Plena」。ニコン 光学本部長の恩田稔さんは、「多くの光を取り込めるZマウントがあって、初めてチャレンジできたレンズです」と開発の裏話を披露。「最適な光学配置によって、難しいとされた開放絞りでの大きな丸いボケと、高い解像力、柔らかく自然なボケ味を実現でき、何気ない日常を特別な瞬間に変えることができます」と述べた。「これからも新次元の光学性能を目指し、ユーザーの期待を超える製品を提供していきます」と、今後の開発にも期待させるコメントで締め括った。

被写体を思い通りに輝かせることを念頭に開発した
開発秘話を披露してくれたのは、ニコン 光学副本部長の石山敏朗さん。135mmの焦点距離で撮影されるシーンを分析し、その際の画作りの理解に努めることで、どのようにすれば新たな表現に到達できるかを議論したとのこと。単に口径食が小さいだけではなく、ピント面はシャープに、玉ボケはやわらかくなるように、どちらもきれいな描写を目指して開発したそうだ。「収差バランス、特殊硝材、反射防止コートなどニコンの技術を総動員し、被写体を思い通りに輝かせることを念頭に開発しました。それが実現できたときには、大きな達成感がありました」と当時の思い出を語った。プロだけでなく新しい表現に挑戦したいユーザーにもこのレンズを体験して欲しいと、開発者としての思いも述べられた。


カメラ記者クラブ賞【企画賞】富士フイルム INSTAX Pal

紆余曲折を経てデザインや機能をブラッシュアップしていった
「カメラ記者クラブ賞」の企画賞を受賞したのは、富士フイルム「INSTAX Pal」。会社にとっては「INSTAX Pal」が衝撃的な製品だったと開発秘話を披露してくれたのは、富士フイルム イメージングソリューション事業部 コンシューマーイメージンググループ マネージャーの力丸陽太さん。当初はカメラを歩かせたり飛ばしたりできないかといったさまざまなアイデアを考えてデモ機を作っていたそうだが、大きなおにぎりのようになってしまったという。また、小さくすると監視カメラのようになってしまったため、デザインや機能をどうやってブラッシュアップして、ユーザーに楽しんでもらえるかを考えたそうだ。「超小型、持ち歩きやすい、愛着のあるデザイン、スマホに繋がる、広角レンズ搭載という、今までにない撮影体験を目指すカメラになりました。チェキの商品企画では、毎年5〜6個は新商品を出そうとアイデアを仕込んでいますので今後も期待してほしいと思います」とのことだ。


カメラ記者クラブ賞【企画賞】DJI Osmo Pocket 3

大型センサーとレンズの重心バランスが課題だった
DJIの「Osmo Pocket 3」もカメラ記者クラブ賞の企画賞を受賞した。DJI JAPAN代表取締役の本庄謙一さんが開発秘話を披露してくれた。コンパクトなサイズを維持しながら1型センサーの搭載を実現した「Osmo Pocket 3」だが、レンズの重心バランスをとって凝縮しなければならなかったのが一番の課題で、3つの異なるフォーカス駆動系を並行して検討したのが苦労した点だったそうだ。また、せっかくの1型センサーなので、暗いところでもクリアに撮れるアルゴリズムの開発にも注力したという。「ようやく3世代目にして我々が納得できるレベルになったと考えています。今後もユーザーの声に応えられるように進化させていきます」と、後継機への期待も感じさせるコメントを語ってくれた。
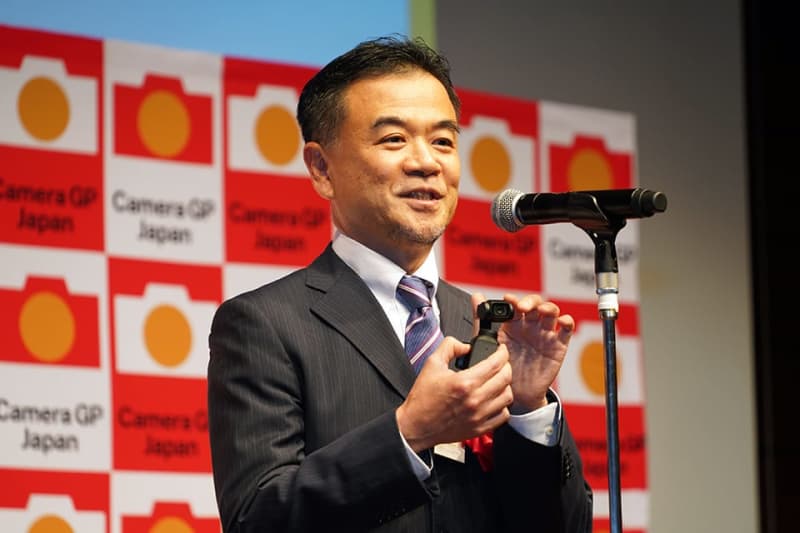

カメラ記者クラブ賞【技術賞】ニコン Z 8 の「オートキャプチャー機能」

さまざまな撮影に挑戦できるようにしたいという想いで開発した
カメラ記者クラブ賞の技術賞を受賞したのは、「ニコン Z 8」の「オートキャプチャー機能」だ。ニコン 映像事業部 開発統括部 第二開発部長の今藤和晴さんが、開発秘話を披露した。もっと自由なアングルで撮影したい、撮影者の危険を回避したい、撮影までの時間を削減したいといった、さまざまな撮影に挑戦できるようにという想いで開発したのが「オートキャプチャー機能」だったとのこと。あらかじめ撮影条件を設定し、それを満たしたときに静止画や動画の撮影が開始されるというもので、今年の2月の大型アップデートで追加された機能だ。開発では、狙った撮影ができなかったり、撮影条件が一致していなくても撮影が始まったりといった苦労があったという。「チューニングを繰り返し、ようやくプロのニーズに応えられる性能に仕上げることができました。AI機能から得られる情報はまだまだありますので、今後ますます進化させることができると考えています」と、さらなる進化を期待させるコメントがあった。


カメラ記者クラブ賞【功労賞】ラムダ

40年にわたる事業を終えたラムダの社長にひときわ大きな拍手が
昨年8月に事業を終了したカメラザックメーカーのラムダに、カメラ記者クラブ賞の功労賞が贈られた。ラムダの佐久間博社長は、「思いも寄らぬ功労賞を頂き、驚き感激しています。ラムダは昨年8月で終業し、40年間の営業でした。ラムダを始めた当初は3年持つか、5年持つかと五里霧中でした。3型カメラザックを発売した頃に、写真家の保坂健さんから新製品を発表するよう勧められて、カメラ記者クラブの例会に製品を持って行ったことで、各誌の新製品コーナーで掲載していただきました。大変お世話になりました」と受賞の喜びを語った。山や高原で、ラムダのザックを背負っている人を見かけると思わず声をかけることがよくあったということや、多くの山岳写真家や写真愛好家、写真関係者に支えられて続けてこられたなど、これまでの活動を振り返ってコメント。挨拶が終わると、ひときわ大きな拍手が贈られた。


これからも素晴らしいカメラが世に送り出されることを期待
最後に、カメラ記者クラブの代表幹事として筆者の柴田が挨拶をした。「カメラグランプリはカメラの主要生産国である日本のメディア、業界関係者、ユーザーが選ぶことに意義があり、その点が海外でも評価されています。主催者の代表として、このスタンスを変えることなく、公正・公平にジャッジする環境を整え、この賞を50年、100年と続けていくことが使命だと感じています。そのためにもカメラ記者クラブを存続させて行くことが私の役割だと思っています」。さらに「これからも皆様の手によって素晴らしいカメラが世に送り出されることを期待しています。来年またこの会場でお会いしましょう」と、贈呈式を締めくくった。

カメラグランプリとは?
「カメラグランプリ」は、写真・カメラ媒体が加盟するカメラ記者クラブ (2024年4月現在で7媒体が加盟) が主催し、カメラグランプリ実行委員会による運営のもと、選考委員を組織している。1984年より開催されており、今年で40周年を迎えた。選考委員は、カメラ記者クラブ会員、加盟媒体の編集長もしくは代表者、外部選考委員、特別選考委員、特別会員のTIPA (欧州を中心とした媒体およびカメラ記者クラブが加盟する写真・映像雑誌の団体) で構成。今回は総勢47名が選考にあたった。
「カメラグランプリ2024」の選考対象は、2023年4月1日~2024年3月31日の1年間に日本国内で新発売された機種。もっとも優れたスチルカメラを選ぶ「大賞」、もっとも優れた交換レンズを選ぶ「レンズ賞」、カメラ記者クラブ会員の合議によって選ぶ「カメラ記者クラブ賞」、一般ユーザーの投票で決定する「あなたが選ぶベストカメラ賞」「あなたが選ぶベストレンズ賞」が設けられている。
・
