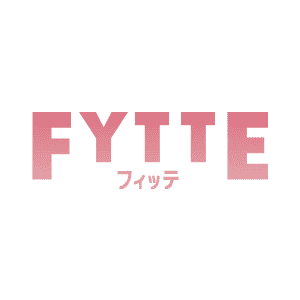By FYTTE 編集部

みなさん、耳の健康を意識したことはありますか? 耳が遠くなる、補聴器が必要…なんてまだまだ先の話と思っているかもしれません。しかし、長時間イヤホンを使用する人が増えたことで、WHOは若者を中心に11億人がイヤホン難聴のリスクにさらされていると発表したというニュースも。今回聴力について調べたさまざまなことから、FYTTE世代にも役立つ情報をお届けします。“きこえケア”におすすめのレシピも合わせてご紹介しているので、ぜひチェックしてみてください♪
味覚と聴力には、じつは密接な関係があった⁉
年齢とともに耳の聞こえが悪くなった、人との会話が難しくなった、という話を聞いたり、自分でも昔と比べると聞こえにくくなったかも…という人もいるかと思います。そんな聴力と味覚はじつは密接な関係にあるということを知っていますか。
医学博士・管理栄養士の本多京子先生によると「味覚と聞こえは相互関係にありますが、無音のところで食べたり飲んだりすると味が弱くなるということもわかりました」とのこと。

「食べる楽しみを持続させるためには音は重要です。聞こえを守ることは味と食を守ることでもあり、料理のときのお湯がわく音、炒める音、食事のときの咀嚼音などが聞こえることがとても大事。
耳からの情報は家事をしながらでも入ってくるため、例えばラジオを聞くことも聴力を衰えさせないために効果的です。テレビなどの目から入る情報だけでは脳でイメージする力が衰えてしまうため、耳から情報を得ることも大切です」(本多先生)。
また「食事も五感を使って行うことで、老化による難聴を予防しましょう」と本多先生。

おいしさの決め手のひとつは、新鮮なサラダのレタスのシャキシャキした音、揚げたてのフライのサクサク、漬物のポリポリという音など、骨の振動で伝わる骨導音だそう。
「食事だけでなく、料理をするときも五感を使うことで、老化による難聴を予防しましょう。野菜を炒めている音で油の香りがふっと立つような感じや、まな板でトントンと切る音、揚げ物のジュージューという音で聴力と空腹感も刺激します。このように毎日の食事で聴覚を刺激することで、聴力の衰えを予防していきましょう」(本多先生)。
血管と神経の若さを保つ「きこえレシピ」で今から耳ケア!
また、日々の食事で血管と神経の若さを保つ栄養を意識したりすることも、耳にとって重要です。
ここからは、実際に日々の食事でどのようなケアを心がければいいのか、おすすめの「きこえレシピ」も含めて本多先生に教えていただきました!

「ビタミンB6が不足すると神経系に異常がおこりやすいと言われています。魚にはビタミンB6以外にEPA が含まれ血管の健康維持に効果があります。また、小松菜やブロッコリーなど緑の野菜に多いビタミンBの一種の葉酸は、アミノ酸の合成を助けたり神経伝達物質のセロトニンやドーパミンを作ったりするのに欠かせないビタミンです。耳のきこえケアには日々の食事で血管と神経の若さを保つ栄養を意識することが重要。そのため、魚のビタミンB6と青菜の葉酸でケアをしましょう」(本多先生)。
ということで、さっそく「きこえレシピ」をライターが作ってみました!
冷凍ブロッコリーとツナ缶の簡単さっぱり和え

<材料:2人分>
・ツナ缶…1缶
・冷凍ブロッコリー…手のひらに乗る程度
・ポン酢…適量
・ローストしたアーモンド…適量
<作り方>
1.冷凍のブロッコリーは解凍し、器に盛りつける。
2.ツナ缶とポン酢を合わせ1に混ぜ合わせる。仕上げにローストしたアーモンドをかける。
※アーモンドのサクサク・カリカリの食感や音が五感を刺激します
★本多先生おすすめポイント★
ビタミン A(カロテン)・C・Eが豊富な冷凍ブロッコリーと、必須脂肪酸の一種で血管や血液の健康をサポートする働きがあり、動脈硬化の予防に役立つIPAやDHAが多いツナ缶を使った簡単レシピです。アーモンドはビタミンEの含有量が高く、また、サクサク&カリカリとした食感や音が五感を刺激します。
さば缶と小松菜のカレー煮

<材料:2人分>
・小松菜…100g
・たまねぎ…100g
・しょうが(みじん切り)…小さじ1
・ニンニク(みじん切り)…小さじ1
・さば缶…1缶
・カレー粉…小さじ2
・料理酒…大さじ2
・砂糖…大さじ1/2
・しょうゆ…大さじ1/2
<作り方>
1.小松菜を茎と葉に分けて食べやすい大きさに切り、玉ねぎはうす切りにする。
2.フライパンに油(分量外)を熱し、弱火でしょうがとニンニクを炒める。カレー粉を加えて香りを出す。
3.2に1の小松菜の茎を加える。料理酒、さば缶1缶、砂糖、しょうゆを入れたら、中火で小松菜の茎に火が通るまで煮る。最後に小松菜の葉の部分を入れて、火が通ったら完成。
★本多先生おすすめポイント★
保存食にもなり、価格も安定しているさば缶は、失敗なくムリなく毎日魚料理が作れます。さば缶は魚を骨ごと食べるメリットもあり、カルシウムもとれるので骨粗鬆症予防にも◎。誰でも大好きなカレー味で冷めてもおいしいのが特徴です。
日々の生活での中で今すぐとり入れることができる「きこえケア」をご紹介しました。ふだんの料理や食事も、五感を使うように意識をすることで、大切な聴力、きこえのケアをしていきましょう。
また、補聴器は「お年寄りのもの」というイメージが強いですが、世界トップクラスのシェアをもつデンマークの補聴器メーカーの日本法人「GNヒアリングジャパン株式会社」では、Bluetoothの最新企画が搭載され、着けていることが自然で目立たない業界最小サイズの「リサウンド・ネクシア™」を新発売するなど、補聴器も進化しています。
自身のきこえを手軽にチェックできるサイトとして、GNヒアリングジャパンが提供するサイト「耳年齢チェック」もありますので、イヤホンを使うことが多い方は、自分の耳年齢をチェックしてみてはいかがでしょうか。
耳年齢チェックサイト:https://www.resound.com/ja-jp/hearing-loss/jp-miminenrei
【監修者プロフィール】
本多京子(ほんだきょうこ) 先生

医学博士・管理栄養士。実践女子大学家政学部食物学科卒業後、東京医科大学で医学博士号を取得。スポーツ選手に対する栄養指導、紅茶やハーブなどの分野を手掛ける。テレビや雑誌では健康と栄養に関するアドバイスやレシピを多数作成。栄養や食に関する著書は70冊を超え、「60代からの暮らしはコンパクトがいい」(三笠書房)やNHKきょうの料理別冊『シニアの健康サポート1人分の簡単レシピ』(NHK出版)、「一食一品つくるだけで栄養がしっかりとれるシニアごはん」(講談社)などがある。
文/FYTTE編集部