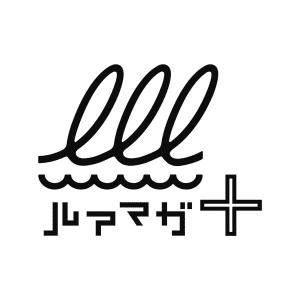世界を旅する釣り人であり、釣り具メーカーのツララ(エクストリーム)のフィールドスタッフもつとめる前野慎太郎さんが、世界各地での釣行で遭遇したエピソードをレポート。今回は、幻の魚「タイメン」を狙ってモンゴルを旅したときの出来事を紹介。どのようなドラマが待ち受けていたのか…!?
●写真/文:前野慎太郎(エクストリーム)

幻の魚の姿を追い求め、モンゴルへ
ルアマガ+をご覧になっている皆様、こんにちは。前野慎太郎です。 今回ご紹介するのはモンゴルを旅したときのできごと。開発や汚染によって近年急激に生息数が減少したといわれる幻の魚「タイメン」ことアムールイトウを釣るために、モンゴル遊牧民の力を借りて挑んだ今回の旅。

私の経験上、最も魚影の少なかったこの国で、四苦八苦しながらタイメンに挑む様子を、日本ではまず体験することのない遊牧民の日常生活とともにご紹介いたしますので、ご覧ください。
― 人よりも家畜の方が多い国
本題に入る前に、まずは軽くモンゴルのご紹介から。中国とロシアに挟まれた内陸国であるモンゴルは、国土の大半を占める広大な草原を中心に、北部はタイガと呼ばれる針葉樹林帯、南部には世界で4番目に大きなゴビ砂漠が広がっています。標高が高いので平均気温は低く、冬はマイナス40℃に達することもあるそうですが、6月から8月の3か月間だけは暖かい日が続きます。

人口は3百万人ほどで、そのほとんどが首都ウランバートルに集中しているため、世界一人口密度が低い国だそうです。高原では遊牧生活を行っている遊牧民がおり、彼らは移動式のテント「ゲル」で寝食しながら、牛、羊、ヤギ、馬などを放牧して、過酷なモンゴル高原で暮らしています。ちなみにモンゴル全体の家畜の数は、把握できているだけでも7千万頭以上。実に人口の30倍以上の家畜が、餌を求めて広大な草原を日々移動しています。
― 環境汚染が深刻化するモンゴルの都市部
東京から飛行機でおよそ6時間。首都ウランバートルに到着した私が最初に感じたのは、想像よりも随分と都会だったことでした。空港を出たとたんに大草原のど真ん中に放り出されると思っていたので少し拍子抜けでしたが、街はコンパクトながらもまとまっていて、とても綺麗な印象です。

中心街は大型のデパートや各国の料理店が並んでおり、食事や買い物に困ることもありません。街にはいたるところにゲストハウスやホテルがあり、アジアやヨーロッパの観光客がかなり多い印象でした。中でも驚いたのは、走っている車の大半がトヨタのプリウスだったことです。近年急激な環境汚染が深刻化しているモンゴルでは、環境に配慮した車が主流となっているそうです。
現地のドライバーを雇い、手探り状態で「幻の魚」を追う
首都ウランバートルのように発展している街の近辺では、おそらくタイメンを拝めることはないでしょう。魚はいつでも人がいない場所ほどたくさん生息するものです。行くとすれば、アムール川につながる東の大河「ヘルレン川」水系、もしくはバイカル湖にそそぐ西の大河「セレンゲ川」水系です。

購入したモンゴルの地図を眺めて迷っていましたが、日本で得られる情報はほとんどが10年以上前のものしかなく、生きた情報は無いに等しい状況です。イチから探すとなれば、支流が多くポイントの選択肢が多そうなセレンゲ水系のほうが良いと判断し、雇ったドライバーの車に乗り込みました。
― 街を抜けると、一気に広がる大草原
ウランバートルは毎日が大渋滞、朝から晩までクラクションの嵐ですが、ひとたび郊外に出ると嘘のように静かな世界が広がります。それからさらに進むと見たことのない大平原が延々と広がり、放牧中の動物たちがわがもの顔で車の前を横切ります。見慣れない景色に最初は大興奮でしたが、走れども走れども代わり映えのしない景色が続きます。2時間もするとすっかり見慣れてしまい、悪路のためにうずく腰をいたわりながら、早く到着してくれと願うのでした。

道中、ちらほらと遊牧民のゲルが見えるのですが、何人かの遊牧民に泊めてもらう機会がありました。というのも、村や町に着けば一応ツーリストキャンプや小さな宿はあるのですが、なにせ広大な国です。人里までが遠く、たどり着けないまま日が暮れる場合もあるので、その場合は遊牧民の方にお世話になるのです。
宿泊費はウォッカ、または小麦粉を差し上げることで落着することが多かったです。詳しくは後述しますが、小麦粉はうどんや揚げパンに、ウォッカはロシアが近いこともあって皆さん大好きですが、中々町まで買いに行けないのでとても喜ばれます。

― 家畜の存在が大きなウェイトを占める遊牧民の生活を紹介
遊牧民は放牧している家畜の肉と、乳から作るバターやチーズ、ヨーグルトを主食として食べていますが、現代では小麦粉で作ったうどんやパンなどもよく食べています。彼らの主収入は家畜や毛皮の売買で、私が実際に行った時の相場はヤギが1頭3千円前後、羊が1万円前後でした。牛はもっと高く、馬は15万円以上だそうです。

ゲルの中は中央に暖炉兼コンロがあり、床は地面がむき出しなので敷物をしています。壁には干し肉がぶら下げてあり、ベッドや食器入れなど、必要最低限のものが置いてあるだけのお宅が多かったですが、中にはソーラーパネルとアンテナを用いて携帯電話やテレビを使える遊牧民もおられました。

遊牧民宅にお邪魔させてもらうと、必ずと言っていいほど出てくるのがツァイというモンゴル風ミルクティーです。お茶の葉を家畜の乳で入れるのですが、特徴的なのは味付け。基本的にミルクティーは甘いものが主流だと思いますが、モンゴルでは薄い塩味となっています。

朝でも夜でも、ウォッカを飲むとき以外はツァイが出てきて、それと一緒に小麦粉で作ったパンを自家製バターやヨーグルトにつけて食べるのがモンゴルスタイルなのです。