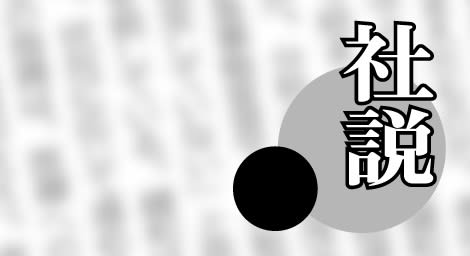
実質賃金が25カ月続けて前年を下回り、マイナスの期間が過去最長を更新した。賃金の上昇が物価高に追い付かず、国民の生活が苦しくなり続けている。早急に改善しなければならない。
名目賃金に当たる現金給与総額は、大企業の春闘で満額回答が相次いだ効果もあって2・1%増と一定に伸びた。プラスは28カ月連続となる。それでも実質賃金が減るのは物価高が止まらないためだ。
物価高は家庭を直撃している。家計の消費に占める食費の割合を示すエンゲル係数は2023年に27・8%と40年ぶりの高さだった。食品の値上げは今も多い。家庭には節約ムードが広がっている。
困窮世帯はさらに厳しい。NPO法人が3月に実施したひとり親家庭への聞き取りでは「3食は食べさせてあげられない」「この冬は暖房を使わなかった」との回答が並ぶ。全国で生活保護の申請は4年連続で増えている。
賃上げは十分ではない。日本商工会議所がおととい発表した中小企業の今春闘の結果は正社員の月給の平均賃上げ率が3・62%だった。一定に評価する声もあるが、経団連によると大企業の賃上げ率は5・58%に上り、会社の規模による格差が鮮明になった。
税金や社会保険料の負担も重い。個人や企業の所得に占める負担の割合を示す「国民負担率」は23年度までの20年間で12ポイント上がり46・1%になった。その前の20年間の上昇は1ポイントにとどまる。多くの国民が負担増を実感しているだろう。「子ども・子育て支援金」など新たな負担もある。
一方、電気、ガス料金の補助金は今月使用分から廃止される。本年度は1人当たり4万円の定額減税があるにしても、家計に厳しい方向性が際立つ。
実質賃金を上げるには、賃金の増額とともに、物価高を抑えることが有効だ。
今の物価高の背景には歴史的な円安がある。政府・日銀はデフレに陥った経済を立て直すため、低金利で円安になりやすくして、輸出産業を守ってきた。原油など資源価格の高騰が問題になった21年以降も円安基調は続き、輸入コストが物価高を加速させた。
海外で稼ぐ大企業が多い経団連から「1ドル=150円を超える水準は円安過ぎる」と注文がつくのは異例の事態と言える。
政府・日銀が4月下旬以降に過去最大規模の為替介入に踏み切ったのは、行き過ぎた円安を阻止するため、適切な措置だっただろう。
日銀は3月に異次元緩和策を終え、金融政策を正常化する方針を打ち出した。「金利のある世界」を軌道に乗せ、米国などとの金利差を縮小し、円安を是正していくことが国民の生活を守ることにつながるはずだ。
岸田文雄首相は本年度予算を成立させた際の記者会見で国民に「物価高を乗り越える二つの約束」をした。一つは「今年、物価上昇を上回る所得を必ず実現する」。もう一つは「来年以降に物価上昇を上回る賃上げを必ず定着させる」。忘れずに注視したい。
