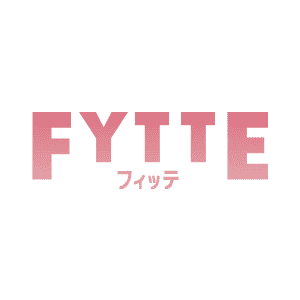By FYTTE 比較チーム

鮮度が良い=おいしい野菜というイメージから、多くの人が野菜を買うときに鮮度を最も重視しているのでは。野菜の中には、収穫直後よりも時間が経ってからおいしくなるものもあり、それを知ることで野菜の選び方などが変わるかも。この記事では、野菜の鮮度や保存などに関する豆知識を、まとめて紹介します。
未熟な状態を食べる野菜がある?

日本では150種類以上の野菜が食べられています。発芽して間もないものを食べるものから完熟したものを食べるものまで多彩です。
[収穫時期別の主な野菜の食べごろ]
・発芽してすぐ:もやしなど
・成長している途中:なす、とうもろこし、アスパラガス、ほうれん草など
・成熟したもの:トマト、カリフラワー、にんじん、タマネギ、じゃがいもなど
memo
きゅうりはMサイズで19~22cm、80~100gのまっすぐ伸びたものが標準とされていたため(※)、それに合わせて未熟な状態で収穫していました。
※「野菜出荷規格ハンドブック」より。2002年に野菜の標準規格は廃止され、出荷団体ごとに規格を設けています。
野菜の鮮度はなぜ落ちる?

①水分の蒸発
野菜は収穫後も呼吸を続けることで水分が蒸発します。特にほうれん草や小松菜、レタスなどの葉菜類は、比較的呼吸が盛んなため、水分が多く蒸発します。水分が失われるときゅうりやなすは表面の光沢がなくなり、葉菜類はしぼんでしまうことも。収穫時の水分から約5%が失われると、多くの野菜の商品性が失われるとされています。
●保存する場合
湿度が高いほうが水分の蒸発が抑えられ、長持ちします。
②エチレンの生成
エチレンとは、ガス状の植物ホルモン。野菜や果実の成熟を進める役割がある一方で、劣化を早めることも。収穫後の乾燥、果実の成熟などの変化によって生成が増加します。
●保存する場合
トマトやきゅうり、キャベツといったエチレン感受性が高い(エチレンの影響を受けやすい)ものと、 りんごなどエチレン生成量が多いものを、一緒に保存する場合は注意しましょう。
エチレン感受性の高い野菜はコチラ
③適温で保存されていない
一定の温度以下で保存されると低温障害を起こす野菜もあります。なすの種子の周りが茶色になり、表面に茶色の凹みができるのも低温障害です。
●保存する場合
下記を参考に、それぞれの野菜に適した温度で保存しましょう。
野菜の最適貯蔵温度の例(最適湿度で保存された場合)
・アスパラガス 2.5℃
・オクラ 7~10℃
・かぼちゃ 12~15℃
・きゅうり 10~12℃
・じゃがいも 4~8℃
・トマト(完熟) 8~10℃
・トマト(緑熟) 10~13℃
・なす 10~12℃
置いておくことでおいしくなる野菜もある?

収穫直後より、時間をおいたほうが食べごろになる野菜もあります。
・トマト
品種によって、食べごろになる前に収穫するものがあります。その場合、収穫後に追熟することで赤く変わりおいしくなります。
・じゃがいも
収穫後、2℃程度の低温で貯蔵することで、でんぷんの一部が分解し糖含有量が増加する品種(※)があります。
※インカのめざめ、インカのひとみ、ノーザンルビー、シャドークイーン、キタアカリ、スタールビーの6種類で実験。
最後に
それぞれの野菜の鮮度と保存の関係を知って、おいしく食べてください。