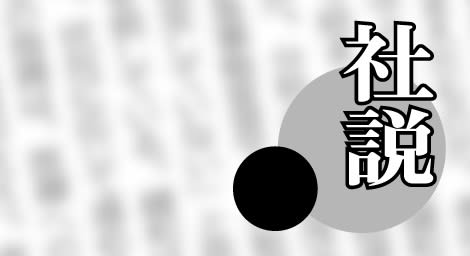
森林環境税の徴収が今月始まった。低所得者を除く約6200万人が対象で、1人当たり年千円が住民税に上乗せされる。毎年約620億円の税収が自治体に配分される。有効に活用せねばならない。
森林は木材の供給に加え、土砂災害を防ぎ、地球温暖化のもとになる二酸化炭素を吸収するなど、さまざまな機能を持つ。健全な形で維持していく必要があるのは間違いない。しかし林業の担い手不足は深刻で、管理が行き届いていない。里山が荒廃し、野生のクマが都市部に出没する例も増えている。
森林を守るため、間伐や林業の担い手確保、国産材の活用などの資金を配分する制度は、別の財源で先行して2019年度に始まっているが、既に問題が浮上している。
最大の課題は、お金を使い切れていないことだ。19~22年度に都道府県と市町村へ配分された額は計1500億円。うち35%に当たる525億円が活用されず、基金に積み立てられた。
背景には、私有の人工林面積や人口などに応じて税が配分される仕組みがある。人口が多く取り分が増えやすい都市部には、森林が少ない。学校など公共施設の木造化といった木材の消費に充てることが想定されるものの、使い道が決まらないまま積立額が増え続けるケースも目立つ。
一方、人口の少ない地方の自治体は配分額が少なく、動きが取りにくい。政府は本年度、人口に応じて配る金額の割合を30%から25%に減らし、山間部への配分が増えるようにした。当然の見直しだが、この割合が妥当かどうかは今後も検証が欠かせない。
森林環境税は、東日本大震災の復興増税の一部を切り替える手法を採る。復興増税が必要なくなったのなら、いったん増税分をゼロに戻すのが筋である。「取りやすいところから取る」という発想で、新税を当てはめ、制度設計が甘くなった面はないだろうか。納税者の所得にかかわらず、徴収額が一律である点が公平性に欠けるという指摘もある。
納税者には「二重負担」との受け止めもあるだろう。広島県は国より早く、07年度に「ひろしまの森づくり県民税」を導入した。県民税の納税者から年500円を徴収し、森林機能の維持などに充てている。全国には似た税制を持つ県は多い。納税者の理解を得られる支出をしていかねばならない。
ただ、使い道に制限がある目的税は、事業の規模に対して歳入が少ないと動きが取れず、多過ぎると無駄遣いが起きやすい。森林環境税の用途はインターネットなどで公表するよう義務付けられている。安易に使われないよう注視したい。
森林を守るということは、その地域で暮らす人たちを守ることでもある。木材の生産者や都市部の消費者を含め、多くの人が森林資源を通じてつながっている。将来世代に引き継ぐ森林のありようや、そのために森林環境税をどう使っていくかについて、社会で議論を広げるべきだ。
