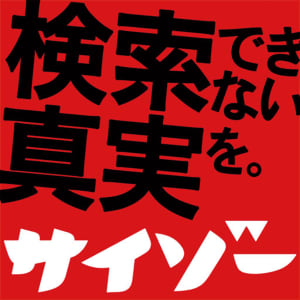──歴史エッセイスト・堀江宏樹が国民的番組・NHK「大河ドラマ」(など)に登場した人や事件をテーマに、ドラマと史実の交差点を探るべく自由勝手に考察していく! 前回はコチラ
前回(第22回)のドラマでは、なにやら口論中の中国勢に、新任の国司・藤原為時(岸谷五朗さん)が中国語で話かけ、それで一目置かれるというシーンが印象に残りました。しかし、その後の宋人たちのやりとりは通詞(通訳)に翻訳させることが中心となり、為時本人も「漢文は読めるが、あまり喋れない」という態度でしたね。
ドラマでは紫式部=まひろ(吉高由里子さん)が出世欲のない謙虚な人柄の父・為時に代わって作った漢詩が、道長(柄本佑さん)の目に留まり、淡路守に任命されたばかりの為時の任国が、淡路から越前国に急遽変更されたという流れだったと記憶しています。
史実でも長徳2年(996年)1月25日、為時が淡路守に任命された記録がある一方、28日にはなんらかの事情で「直物(なおしもの)」が行われ、越前守に役職が変更されました。この背景を正確に語る史料は存在しないのですが、以前にもお話した通り、後世の逸話においては、為時が一条天皇(ドラマでは塩野瑛久さん)に自身の語学力を漢詩を通じてアピールし、宋人商人が来日して問題となっている越前国の国司に任命してほしいと願い出た(鎌倉時代の説話集『古事談』など)ということになっています。
実際、越前国において、史実の為時も得意の漢詩で宋人たちと交流し、特に宋人商人たちのリーダー(書物によって「周世昌」あるいは「羌世昌」とも)から喜ばれたという認識があったようです。実際、ドラマのようにいい雰囲気になったのではないでしょうか。このときに詠まれた為時の漢詩は、『本朝麗藻』など、日本人が作った漢詩文を収録した書物にも見られ、為時自身だけでなく、他の日本人も彼の漢詩を優秀だと考えていたことがうかがえるのですが、中国側の本当の評価は辛辣なものでした。
中国側の記録『宋史』にも世昌と為時とのやりとりが記録されているのですが、「世昌以其国人唱和詩来上、詞甚雕刻膚浅無我取」などとあります。この部分を意訳すると、「世昌は為時と(漢)詩を唱和しあったが、為時の言葉選びには深みが足らず(描写が浅く)、評価に値しないと感じてしまった」そうです。それゆえ、史実の紫式部も苦戦する父親の姿を見てショックを受けたのではないかと考える研究者もいるのです。
ちなみに宋時代の中国は海外との貿易を建前上は禁止していたので、中国の公式歴史書でもある『宋史』には、本当は貿易目的で来日した世昌も、漂流した末に日本に漂着してしまったということになっています。また、中国史における外国の記述は、古代から中国を持ち上げ、他国を貶める内容ばかりですから、漢詩人・為時の評価についても故意に低く書かれていて当然と読むべき部分かもしれませんが……。
為時の漢詩文の真の評価とは別に、朝廷のお抱え学者の漢文能力の微妙さについて筆者が思い出してしまうのは、鎌倉時代の末に、中国・元王朝のフビライ・ハーン(クビライ・ハーン)から「元寇」を受けた時の逸話です。フビライは自国兵だけでなく、高麗(朝鮮)などの属国からも軍船などの物資、そして兵士を動員させた“連合国軍”を作り上げました。そんなさなかの文永8年(1271年)、“パルチザン(非正規軍)”を率いて元と戦っていた三別抄という武将が、窮地の日本側に共闘を呼びかける手紙を送ってきたことがありました。しかし、漢文で書かれたこの手紙の表現が難しすぎて、ときの朝廷の御用学者たちは理解することができず、三別抄からのありがたい申し出を無視してしまったのです。
三別抄は高麗人(朝鮮人)で、母語が中国語ではないため、彼の漢文には独自の言いまわしがあったのかもしれませんが、手紙の現物は現存せず、公家の日記に一部が引用されているだけ……というあたりからも、朝廷の御用学者が自分たちの無能力を上層部から責められることを恐れ、廃棄したというシナリオが想像されてしまうのでした。
「元寇」があった鎌倉時代後期と、紫式部や為時が生きた平安時代後期は、多少は離れた時代ではありますが、朝廷付属の大学などの専門機関で長年かけて学んだエリートでも、実地経験のない語学能力というのはあまりパッとしないのが「ふつう」だったのではないでしょうか。
もちろん、日本国内で勉強しただけでも、中国本土にわたり、現地の中国人を驚愕させるほどの漢詩文の才能で知られた空海などの日本人もいるにはいますが、それはレアケースでしかなかったのです。
さて、前回のドラマでは道長と別れ、都を離れたまひろが、松下洸平さん演じる見習い医師・周明(ヂョウミン)と出会い、早くも「いい感じ」になっていたので驚いた読者も多いでしょう。周明はドラマのオリジナルキャラクターでモデルなどはいないようですが、当初は日本語はわからないという身振りだったのに、いざとなると流暢な日本語が口から飛び出てくるという設定で、まひろならずとも「エッ……」となりました。周明とまひろにはロマンスの気配も濃厚ですけれど、平安時代に外国人と恋愛をした日本人はいるものなのでしょうか。
史実の紫式部自身にはそういう噂が存在しないのは残念ですが、思い出すだけでもチラホラと有名人にも「該当者」はいるようです。
背丈が「五尺八寸(約176センチ)」、胸板もきわめて厚く、体重は多い時で201斤(約120キロ)もあったという記録のある平安時代前期の武将・坂上田村麻呂などは、「目は蒼鷹の眸」「髭(髪という説も)は黄金の縷を繋ぐ」ような外見だったそうです(嵯峨天皇が著したとされる『田邑麻呂伝記』)。深いブルーの瞳、髭もしくは頭髪はブロンドという、あまりに東アジア系離れした容貌の坂上田村麻呂は、系図にも母親の記録がなく、日本人の父親と外国人女性の恋愛の末に生まれた子だったのではないか……という想像が止まりません。
坂上田村麻呂には(主にアメリカなどで)由来不明の黒人説もあるのですが、ペルシャ系か、ヨーロッパ系の血を引いていたのではないかと思われます。そういう坂上田村麻呂の血統を引いた清和天皇の子孫が、後に清和源氏の一派を形成し、その血統から多くの武人が生まれていったのは興味深い話ではあります。
また坂上田村麻呂が青年だった宝亀9年(778年)11月には、日本から遣唐使として派遣された藤原清河という人物と、中国人女性(氏名不詳)との間に生まれた、その名も喜娘(一説に「きじょう」)という女性が、海難事故を乗り越え、来日したという記録もあります。残念ながら、その後の喜娘の人生については不明なのですが、中国に帰ったという話はないため、おそらく日本のどこかでひっそりと生涯を終えたのでしょう。
中国の役人が外国を訪れ、現地の女性との間に子をもうけることも多かったようです。しかし、妻子を連れて中国に戻ってはいけない、つまり現地に妻子は置いて単身で帰りなさいという厳しい掟がありましたが、それはあくまで「公人」である役人の話で、ドラマのように商人とか医師見習いといった「私人」と外国人との関係はまた別枠だったかもしれません。ちょっとマニアックな話になってしまいましたが、今回はこの辺で……。
<過去記事はコチラ>