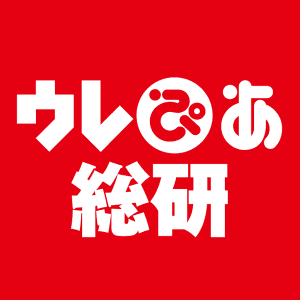心身の不調を感じる「5月病」。新入社員が発症しやすい不調として知られていますが、最近は5月病よりさらに深刻な「6月病」という不調もあります。
今回は、6月病の定義や、5月病との違い、6月病チェックリスト、そして6月病の予防法やセルフケアについてご紹介します。
その疲れ、6月病かも?
「5月病」とは、新社会人や学生が、4月からはじまった新生活の人間関係や環境の変化に対応しきれず、5月の大型連休明けにからだ・精神に不調を引き起こす現象です。
そもそも、5月病は正式な医学用語ではありません。病院では、「適応障害」や「抑うつ状態」と診断されることもあり、全身の倦怠感や疲労、肩こり、頭痛、食欲低下、睡眠障害、抑うつ、無気力、集中力低下など、さまざまな不調が起こります。
そして、「6月病」は心身のストレスに耐え我慢を重ねた末、徐々に症状が悪化している状態を指します。6月病の症状は5月病と似たところも多く、適応障害が原因とされていますが、5月病は一過性のものが多く、6月病は慢性化しやすい点が特徴(※1)です。「6月病はうつ病の入口」(※2)といわれることもあり、若い世代だけでなく、30代以降の世代にも6月病は見られます。
また、6月病は梅雨の気圧変化や湿度の上昇などの気候変化で自律神経が乱れることも原因のひとつといわれています。
あなたは大丈夫?6月病チェックリスト
ここからは、6月病のチェックリストをご紹介します。ご自身がいくつ当てはまるか、チェックしてみてください。
・いつもイライラしている
・会社に行くことがつらく、眠れない
・変化を面倒に感じる
・常に物事をネガティブに受け止めてしまう
・些細なことが気になる
・休日でも仕事のメールチェックをしてしまう
・趣味がない、楽しめなくなった
・やる気が起きない
・食欲が湧かない
・胸の動悸が激しくなるときがある
・めまいを感じる
ひとつでも当てはまるものがある場合、6月病の可能性があります。「気のせい」と思わずに、きちんとした対策を行うことが肝心です。
6月病を予防するには?
続いては、6月病の予防や対策方法をご紹介します。
1.生活リズムの改善
仕事中心の生活になると、生活リズムが崩れがちになることも。しかし、しっかりと休息をとることはとても大切です。睡眠時間はきちんと確保し、なるべく同じ時間に寝起きすることが生活リズムの乱れを防ぎます。
また、睡眠ホルモンの材料になる「セロトニン」も重要です。セロトニンは日中に太陽の光を浴びることで作られるので、目覚めてすぐに朝日を浴びる、早朝に散歩するなどの行動を習慣づけましょう。
セロトニンは、別名「幸せホルモン」といい、睡眠周期を整えるだけでなく、不安をとり去って精神を安定させる作用を持っているので、気分が塞ぎ込みがちな方はとくに意識してみましょう。

2.適度な運動
ウォーキングやジョギング、ヨガやストレッチなどの軽い運動は、自律神経を整えて血液循環をよくし、脳の酸素供給量を増やします。集中力や意欲をアップさせ、ストレスを軽減する効果が期待できるでしょう。
あまり激しすぎる運動は不向きです。無理のない範囲で行い、からだに負担をかけすぎないように注意しましょう。
3.他者とのコミュニケーション
リモートワーク中心で、面と向かって人と話す機会が減っている場合は、他者とコミュニケーションをとる機会を増やすのも重要です。ひとりで塞ぎ込まずに、気の知れた仲間とコミュニケーションすることで、気晴らしになります。
苦手な人と無理にコミュニケーションしても、かえって余計なストレスを抱える可能性があるので、家族や友人、社外の知人など、悩み事を気軽に相談できるような関係性の人とコミュニケーションをとりましょう。

6月病におすすめの漢方薬
6月病の緩和には、漢方薬もおすすめです。漢方薬は、植物や鉱物などの自然由来の生薬で作られていて、一般的に西洋薬よりも副作用のリスクが低いといわれています。
また、漢方薬は毎日決まった量を飲むだけなので、生活習慣を大きく変えなくても簡単に実践できるところがメリットです。
6月病の緩和には、「血流をよくして自律神経の乱れを整える」「鎮静作用で心を穏やかにする」「気分の落ち込みを改善する」「消化・吸収機能を改善してからだの内側から心を元気にする」といった漢方薬を選び、根本改善を目指しましょう。
<6月病が心配な方におすすめの漢方薬>
・抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ):神経の高ぶりを抑え、からだに滞った熱を冷まし、精神を落ち着かせます。やや消化器系が弱く、虚弱な体質の方に向いています。
・柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう):血液の循環やエネルギーの流れを整え、からだの熱を冷まし、ストレス不調にはたらきかけます。脳の興奮や緊張から来る不眠にも用いられます。
スマホで気軽に専門家に相談できる「あんしん漢方」のような、オンライン個別相談も話題です。あんしん漢方はAI(人工知能)を活用し、漢方のプロが効く漢方を見極めて自宅に郵送してくれるオンライン漢方サービス。
スマホで完結できるので、対面では話しづらいことも気軽に相談できますよ。お手頃価格で不調を改善したい方は、医薬品の漢方をチェックしてみましょう。
生活習慣を見直し、6月病を予防!
6月病は、5月病の症状と似ているものの、慢性化しやすい点が特徴です。生活リズムの改善、適度な運動、他者とのコミュニケーションを中心に、生活習慣を改善し、対処していきましょう。
【参考】
(※1)(公社)小田原青色申告会「健康のツボ:環境変化で心身に負担『6月病』が危ない」
(※2)サワイ健康推進課「増える『6月病』あなたは大丈夫? | 睡眠・休息・メンタルケア」
■この記事を書いた人

あんしん漢方薬剤師:山形 ゆかり
薬剤師・薬膳アドバイザー・フードコーディネーター。病院薬剤師として在勤中、食養生の大切さに気付き薬膳の道へ入り、牛角・吉野家他薬膳レストラン等15社以上のメニュー開発にも携わる。
「健康は食から」をモットーに健康・美容情報を発信するMedical Health -メディヘルス-Youtubeチャンネルで簡単薬膳レシピ動画を公開するなど精力的に活動している。
症状・体質に合ったパーソナルな漢方をスマホ一つで相談、症状緩和と根本改善を目指すオンラインAI漢方「あんしん漢方」でも薬剤師としてサポートを行う。
(mimot.(ミモット)/ あんしん漢方)