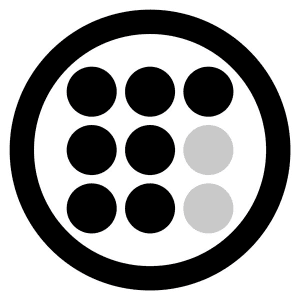西武の「兄やん」松沼博久氏…取手二高に「常にバット」の木内監督がいた
ライオンズが「西武」球団となった1979年に弟の雅之氏と一緒にプロ入りし、「兄やん(アニヤン)」の愛称で親しまれた野球評論家の松沼博久氏は、アンダースローの先発として新人王に輝くなど西武一筋で112勝をマークした。「僕はピッチャーはやりたくなかったんですよ」。実は投手は、高校2年生の途中に“後の名将”からの命令で渋々始めたのだという。
松沼氏は1952年生まれ。東京都墨田区出身で、子どもの頃は巨人・王貞治内野手(現ソフトバンク球団会長)が大好き。「王さんのご実家でもある中華料理店『五十番』が自宅から近かったので、歩いて見に行ったことがありますね」。小2の終わり頃に千葉・流山に移住。小学校時代は俊足を買われ、走り幅跳び・高跳びなど陸上競技に取り組んだ。中学でも当初は陸上部で活動していたのだが、「もともと野球が好きだったので、途中から入部したのです」。中3では「1番・遊撃」の定位置を掴んだ。
高校の進路選択。「習志野に行こうと一瞬考えたけど、家から遠かった。レベルも高そうだったので無理かな、と」。習志野は松沼氏が中3の1967年夏の甲子園で優勝していた。そこで、千葉・市川市内の私立の進学校に合格。だが、利根川を挟んだお隣・茨城県の取手二高の入試はそれより遅かった。「中学の先輩が1人いて誘われていたし、家からも30分。市川の学校の後で試験を受けたら受かった。『まあ、ここでいいや』と進学しました」。
取手二高は1984年夏の甲子園決勝で、桑田真澄投手(巨人2軍監督)、清原和博内野手(元西武、巨人、オリックス)の“KKコンビ”を擁したPL学園(大阪)を破り優勝。率いた木内幸男監督は、その後に移った常総学院(茨城)でも春、夏と日本一に導いた名将だ。その名将も取手二高も、松沼氏が入学した1968年当時、甲子園出場は夢物語で無名に近かった。
木内監督は当時30代後半。どんな存在だったのか。「凄い元気でしたね。茨城訛り丸出しで『ごじゃっぺ』(間抜け等の意味)とか、いろいろ叱られました。とにかく口が悪いんですよ。『全員野球なんて嘘っぱちだから』とかね。『お前なんて辞めちまえ』なんて言われると、田舎の子は素直だから本当に辞めていっちゃうんですよ」。松沼氏の同期は十数人いたが、3年時には2人にまで減った。「先輩後輩の上下関係は厳しくなかった。木内さんの言葉が一番厳しくて、辞めた選手はほとんどそれが原因でしょう」。
木内監督はノックバットが“相棒”だった。「常に持ち歩いてました。普段はグリップの方を握っているじゃないですか。これが太い方に持ち替えた時は逃げない限り、やられちゃうんです。もっとも逃げられないんですけどね。やっぱり怖かったですよ」。“指導”が飛んで来るタイミングを選手たちは分かっていた。
オーバースローで投手開始も制球難…遊撃の要領でサイドからアンダーに
松沼氏は2年夏には強肩の遊撃手としてレギュラーを確保。木内監督は潜在能力に着目していた。「僕は右打者でしたが、硬式球だと打球が内野をなかなか越えなかった。すると『お前は右手が強いから左打ちに変えろ』と。そういう所は、やっぱり見る目があるんですよね」。夏の県大会終了後、選手生命を変える指令が下る。「同級生の左腕しか投手がいなくなったのです。それで『ピッチャーをやれ』と。投手はずーっと走ってばかりの練習が多いので、やりたくなかったんですけど。まあ、しょうがないか、と」。
オーバースローで始めた。「でも、いざ投手として投げようとすると、全然ストライクが入らない。それで遊撃で併殺を取る時の送球のように、腕を下げて横から投げたらコントロールできてきた。『ああ、こんな感じでいいのかな』と。さらに進めたらアンダースローの形になった。僕は、ピッチャーに関しては全くの素人でしたから」。
木内監督は投法の変化に付いては一切注文せず、知人の「ホンダさん」を連れてきた。松沼氏の記憶では「都市対抗で頑張った社会人野球・東京ガスの元投手」だった。「その方はサイドスロー。月に数回教えに訪れた。『投げ終わったら左足1本で立て。体が右に流れないように』と、フォームのバランスを丁寧に指導して頂きました」。
高3の最後の夏。松沼氏は主将でショート兼投手なのに背番号「10」だった。「何故ですかね。木内監督の考えですから分かりません。自分は6番か3番と思ってました。だから最初は僕は『もう、いい』って頭にきて、家に帰っちゃったの。後輩が困って電話してきたので戻ったら、木内さんが『大学では10番はキャプテン番号なんだぞ』って言うんです。『俺は高校生なんだけどな』と聞き流してましたけど」。強烈な指揮官も、気骨ある松沼氏には気圧されて理由を取り繕ったのか。
練習でエースが指を骨折し、投手は松沼氏頼みとなった。県大会3回戦で鉾田一高の梶間健一(元ヤクルト)と投げ合い、4-5で敗れた。「延長10回に満塁で、左バッターのお尻にぶつけてサヨナラ負けでした」。激闘が終わった後のこと。「木内さんは栄養ドリンクを冷やしていたんですけど、僕の所には来なかったです」と笑いながら回想する。
松沼氏と4歳違いの弟で、投手の雅之氏も兄を追って取手二高に入学。1974年夏の茨城大会決勝で惜敗も甲子園にあと一歩まで迫った。「弟が奮闘したことで取手は有名になり、部員が沢山入るようになった。木内さんも、それからは部員を辞めさせないようにしたらしいんですよ。“鬼の木内”じゃない。僕らの頃に比べたら言葉が全然厳しくなくなってました」。
兄弟が西武に在籍していた1983年に球団が発行した「ライオンズ・ファンブック」に木内監督は寄稿している。「取手の土台を築いてくれたのは、松沼兄弟の力があったからだと思っています」と。松沼氏も木内監督の指令がなければ投手ではない。出会いには運命を変える力がある。(西村大輔 / Taisuke Nishimura)