少子高齢化が進む日本…13年連続で人口が減少

2023年、総務省の統計局の発表によると、13年連続で人口が減少しており、現在の総人口は1億2435万2000人とのことです。この数字は、前年から59万5000人もの人口が減少している結果であり、減少幅も12年連続で拡大しているといいます。
さらに、前述した人口の中でも生まれた人口よりも死亡者数が上回ってしまう自然減少が顕著に見られ、こちらは17年連続で減少幅が拡大しているそうです。これは深刻な問題である少子高齢化社会が如実に表れたと言えるでしょう。
50年後は1億人を下回る危険性が予測されている
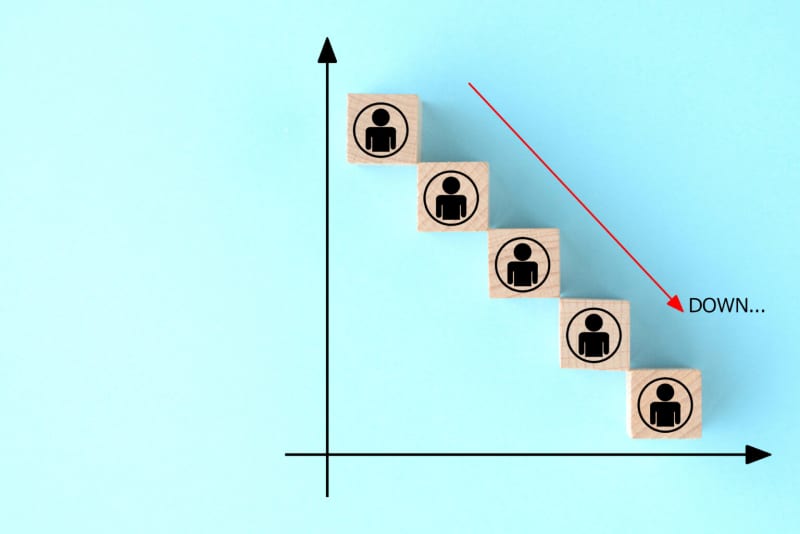
さらに、今後の人口推移を予測した「日本の将来推計人口」も厚労省より公表されました。その発表によると、約50年後の2070年には、日本国内の人口が約8700万人まで減少すると予測されたとのことです。
人口数の内訳を見てみると、海外からの労働や留学目的での外国人は増加傾向にあるため、2066年には日本の総人口の約1割が外国人になるという予測も立てられています。
しかし、日本の根本的な人口減少を抑えることが必要です。子育て政策の強化や現代社会にあった抜本的な改革が必要だとさまざまな意見が交わされています。
人口が大幅に減少した場合、どのような悪影響が出るの?

紹介したように、このまま進むと日本の総人口は大幅に減少すると予測されています。では、人口が大幅に減少した場合、どのようなリスクや悪影響が懸念されているのでしょうか。
国内の買い物需要の減少による経済リスク
人口数が減少すれば、その分、国内で買い物をする人が減少するということ。つまり、今よりもさらに国内で経済が回せなくなり、倒産や人件費削減による失業など、さまざまな経済リスクが懸念されています。
給料も上がらず、しかし物価は高騰しつつある現状が、さらに悪化してしまう危険性もあると考えられるのです。考えただけでも恐ろしいですよね。
人手不足により労働力の減少
人口減少の大きな原因は、自然減少の拡大による少子高齢化です。現在、すでに人手不足によって労働力が減少していると言われていますが、今後はより若い世代が減少することが予測されているため、さらに労働力が足りない事態に陥る可能性も。
近年は科学技術の進歩によって、AI技術を有効活用した人手不足対策も行われていますが、やはり人の手が介入しなければ成り立たない職業も多く存在します。
そのような職業で人手不足に陥れば、不法な長時間労働や人手が足りないことによって企業経営が回らなくなるなどのリスクも考えられるでしょう。
少子高齢化による社会保障制度などのバランス崩壊
自然減少の拡大により、少子高齢化問題が深刻化しています。この問題に隠された特に大きな懸念点は、若い世代からの税収が減少することにより、社会保障制度などの今まで行ってきた行政サービスの崩壊です。
現在、日本人が恩恵を受けている社会保険(健康保険)や年金受給などは、働く世代が収めている税金によって成り立っています。
しかし、この保障制度を支える世代が減少することによって、より人口の多い高齢者世代を支えることができなくなってしまうのです。
すると、介護サービスや医療などを十分に受けられず、さらに年金によって生活することが困難になることが予測されるので、老後はもちろん、シニア前の世代もさまざまな悪影響を受けることになります。
税収減少による財政危機
先ほどお話ししたように、人口が減少すると税収も減少します。納めた税金は一般的に公共施設などの修繕や行政サービスなどに活用されています。
しかし、税収減少によって、以下のような財政危機が懸念されるのです。
- 公共施設やインフラの老朽化
- 行政サービスの低下
公共施設やインフラが老朽化すれば、安全に日常生活を送ることが難しくなります。また、現在当たり前のように恩恵を受けている行政サービスがなくなることで、生活困難者が増える恐れも懸念されます。
国際社会での競争力の低下
以上のことを踏まえて考えると、国際社会での競争力の低下にもつながりかねません。貿易収支が低下したり、日本の株価が下落するといった事態が懸念されます。
すでに歴史的な円安に陥っている日本の今後は、専門家の間でも意見が分かれるほど予測できない状態です。国際社会での影響力がなくなってしまい、日本産の商品ニーズが低下してしまえば、さらなる経済悪化を招きかねません。
人口減少は深刻な問題…原因を解消する抜本的政策を
現在、深刻化している人口減少問題は、今後より懸念される事態に陥ると予測されています。さまざまな政策が打ち出されていますが、原因を解消する抜本的な政策を施行し、日本人が子どもを産み育てたいと思うような環境が求められます。

