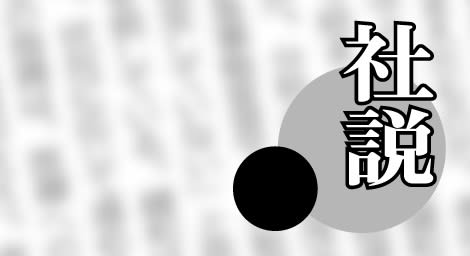
大津市で保護司の男性が自宅で殺害され、男性が担当していた近所の無職の男が容疑者として逮捕された。衝撃の展開で、痛ましい。
男は容疑を否認している。事件の全容は見えていないが、民間人のボランティアで成り立つ保護司制度に深刻な影響を与えかねない。保護司は罪を犯した人の立ち直りを地域で支え、再犯を防止する更生保護の要である。安心して活動できるよう、安全確保策を急ぐ必要がある。
男性はレストランを経営する傍ら、18年にわたり保護司を務めていた。容疑者は5年前に強盗罪で執行猶予付きの有罪判決を受け、保護観察中だった。死亡推定日に男性の自宅で面接が組まれていたことが分かっている。保護観察は7月9日までだった。
観察対象者の近くに住む保護司が担当を務めることが多い。地域の実情に通じているからだ。定期的な面接で生活状況や交友関係を把握する。住まいの確保や就職の手助けもする。法相の委嘱を受けた非常勤の国家公務員だが、交通費など実費以外は無償だ。
事件を受け、法務省は保護司が扱う事案でトラブルがないか聞き取り調査を始めた。リスクの芽を摘み、必要な支援を急がなければならない。
保護司の多くは面接場所に自宅を使う。対象者の秘密を守るのと同時に、信頼関係を築く狙いもあろう。保護司を30年務め、少年院や刑務所の出所者ら約300人の更生に携わった広島市の中本忠子(ちかこ)さんは、自宅で手料理を振る舞い、立ち直るきっかけをつくってきたことで知られる。
ただ、善意や使命感に支えられている仕組みの揺らぎに危機感を持たざるを得ない。
国が5年前に実施した保護司へのアンケートで、4人に1人は「1人で面接することに不安や負担を感じる」と回答していた。事件が起こる前から対策が必要だったのではないか。面接場所として、各地の更生保護サポートセンターや公民館などの施設を使いやすくすることも検討したい。
ケースに応じ、保護司がチームを組む複数担当制の普及も進めたい。広島県保護司会連合会はベテランが経験の浅い人をサポートするなど、保護司間の連携を強化する。専門知識を持つ保護観察官の支援充実も求められよう。
保護司のなり手は年々減っている。活動中なのは約4万7千人と、法定定員を5千人以上割り込んでいる。平均年齢は65歳を超えた。
法務省の有識者検討会で人材確保策や待遇の見直しを議論するさなかに事件は起きた。現役世代の参加を促すには安全対策とともに、活動時の休暇取得や制度の広報で企業、自治体の協力が不可欠だ。
今回の事件で現役の保護司が萎縮したり、志す人が二の足を踏む動きが出たりすることは避けねばならない。保護司の伴走で社会復帰が円滑に進んだ人は少なくないはずだ。観察対象者への偏見が広がらないようにすることも大切だろう。現制度の良さを生かしつつ、持続可能な制度にするために何をするべきか。社会全体で考えたい。
