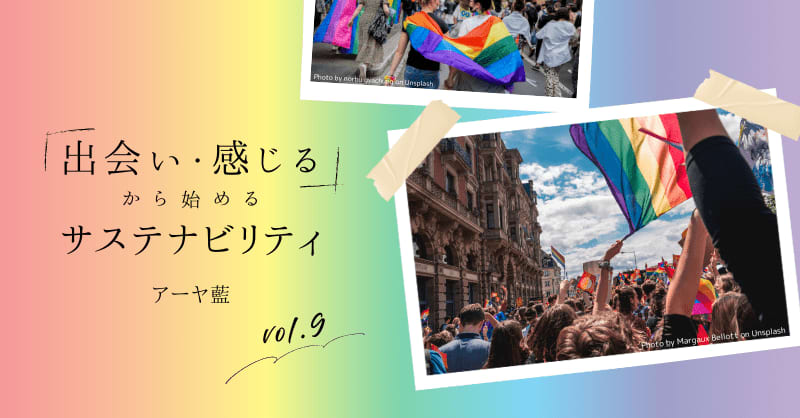
社会課題への関心をより深く長く“サステナブル”なものにする鍵は「自ら出会い、心が動くこと」。そんな「出会える機会」や「心のひだに触れるもの」になるような映画や書籍等を紹介する本コラム。
6月はPride Month、プライド月間です。世界的にLGBTQ+の権利を啓発し、コミュニティを支援するさまざまなイベントや取り組みが行われます。
私が多様なセクシュアリティがあることを知ったのは大学生の時。尊敬し憧れていた先輩がLGBTQ当事者だったことを知り、先輩のことをもっと知りたいという思いの延長線でイベント等に参加するようになりました。
ただ、セクシュアリティのグラデーションを知ることで心が楽になっていったのは私の方でした。恋愛関係やパートナーシップのあり方について「こういうのが普通」「こうあるべき」といった枠に無意識にとらわれていたことに気づき、その枠を解きほぐしてもらったからです。また、セクシュアリティに目を向けることは、自分自身や大切な誰かのことを深く考えることなのだとも思うようになりました。
そうした経験があったことから、映画配給を行うユナイテッドピープルに入ってからも、いつかLGBTQに関わる作品を配給したいと思っていました。その夢が叶ったのが映画『ジェンダー・マリアージュ ~全米を揺るがした同性婚裁判~』です。
舞台は同性婚が法的に認められているアメリカ・カリフォルニア州。しかし2008年11月に、結婚を再び男女間に限定する州憲法修正案が議会で可決されてしまい、同性婚が法的に認められなくなってしまいます。これに対して人権侵害であるとして州を訴えた2組の同性カップルと弁護士たちの、5年間にわたる闘いを追ったドキュメンタリーです。

同性婚が無効になってしまったのちも、いわゆるパートナーシップ制度は存在しました。しかし原告の一人は「パートナー登録をすることは、結婚する権利がない“二流市民”であることを認めることだと思う。とても受け入れられない」と話します。また、別の原告は「結婚という人生最大の決断を同様にできたなら、今より自信をもって豊かな人生を送れるはずだ」と話し、未来の世代にその環境があることを願います。
国は違えど、裁判のプロセスで語られ議論される内容には、「なぜ同性婚が必要なのか」「同性婚が認められないことはなぜ問題なのか」を考える普遍的なヒントが詰まっています。

日本で同作を公開したのは2016年1月。それから8年強が経ち、日本でも今、同性婚、すなわち婚姻の平等を求める裁判が起きています。新聞やテレビなどの世論調査では、支持する政党などによらず推し並べて6割以上の人が同性婚に賛成だという結果が出ています。ただ、その「賛成」の中の理由や気持ちの度合いにはグラデーションがあることでしょう。
「婚姻の平等が認められないこと」が「結婚できる/できない」という1つの行為の可否だけでなく、その前後につながる人生全体に影響しているのだということを、もっと認知あるいは意識できたら、「賛成」の強度が高まり、さらなる「前進」につながるのではないかと私は考えます。『ジェンダー・マリアージュ』はその後押しをしてくれる作品だと信じています。
さて、同性婚の観点から見るとポジティブな変化が起きているのを感じる一方で、ここ数年、胸が「きゅっ」とすることが多いのがトランスジェンダーに関わる話題です。生まれた時に割り当てられた性別と自認する性が異なるトランスジェンダー。
昨今、トイレや温泉を巡る「不安」の声をよく見聞きしますが、その「不安」は実はメディアやカルチャーで描かれてきた、偏った、あるいは誤ったトランスジェンダー像に基づくものではないかと考えさせられる映画があります。Netflix映画『トランスジェンダーとハリウッド:過去、現在、そして』(原題:Disclosure)です。

俳優、映画監督、ライター、プロデューサーなどのトランスジェンダー当事者が、具体的な映画やドラマを挙げながら、そこで描かれてきたトランスジェンダー像の問題を指摘していきます。
例えば『ミセス・ダウト』や『ビッグママ・ハウス』、『ミックス・ナッツ/イブに逢えたら』などでは女性装をした男性が登場しますが、いずれも「笑わせる」役として描かれています。こうした映画を通じて「トランスジェンダーの人は笑っていい存在だ」と幾度もインプットされていると、現実世界でも同じように反応してしまうのです。本作に登場する当事者の一人は、性別移行初期に地下鉄に乗り込んだだけで周りから爆笑された経験をはじめ、これまで数多く笑われてきたと語ります。
トランスジェンダーの人の性別の「秘密」を知った人が「裏切られて傷つく」あるいは「嘔吐(おうと)する」という反応を描いている作品や、トランスジェンダーを危険な変質者や殺人者として描くサスペンスやホラー作品なども同様の問題を抱えています。

本作によればアメリカ人の8割はトランスジェンダーの知り合いがいないとのこと。それゆえメディアにある情報を頼りにし、そこに潜む偏ったイメージによって、トランスジェンダーを笑いの対象であったり、嫌悪や攻撃していい対象のように認知してしまっているのです。
加えて本作では、トランスジェンダーの人たちの描かれ方の中に混ざっている女性蔑視や人種差別的な眼差しなどについても指摘しています。表現は一歩間違えれば誰かへの暴力になることを強く感じます。一方で、映画の長い歴史をたどっていく中で、少なからず前進していることを感じられる面もあります。ここから“後戻り”しないためにも、これまでの歩みに存在していた問題をしっかり知ることが、第一歩として大切ではないでしょうか。
映画やドラマに限らず大量の情報に囲まれ、また誰もが発信者側に立てる時代でもある今、自分が無意識に受けてしまっている影響や生み出してしまっている偏見などに、プライド月間の今月、改めて意識を向けてみませんか?
なお「映画より本派」という方や、映画を観た後にこの問題についてもっと深めて考えたいという方は『トランスジェンダー問題 議論は正義のために』(ショーン・フェイ著、明石書店)をぜひ。
▼ 映画『ジェンダー・マリアージュ ~全米を揺るがした同性婚裁判~』
(2013 年製作/112 分/アメリカ)
▼ 映画『トランスジェンダーとハリウッド:過去、現在、そして』
(2020 年製作/107 分/アメリカ) ※予告編に日本語字幕はありません
アーヤ 藍(あーや・あい)

1990年生。慶応義塾大学総合政策学部卒業。在学中、農業、討論型世論調査、アラブイスラーム圏の地域研究など、計5つのゼミに所属しながら学ぶ。在学中に訪れたシリアが帰国直後に内戦状態になったことをきっかけに、社会問題をテーマにした映画の配給宣伝を手がけるユナイテッドピープル会社に入社。約3年間、環境問題や人権問題など、社会的イシューをテーマとした映画の配給・宣伝に携わる。同社取締役副社長も務める。2018年より独立し、社会問題に関わる映画イベントの企画運営や記事執筆等で活動中。2020年より大丸有SDGs映画祭アンバサダーも務める。
コラムニストの記事一覧へ
