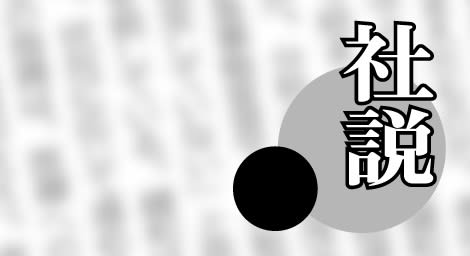安全な資産とされる米国債などへの投資で、これほどの損失は想定外だっただろう。
農林中央金庫(農林中金)が2025年3月期の連結純損益が5千億円を超す赤字に陥る見通しを明らかにした。外国債券を中心に2兆円余りの含み損が生じ、これを処理するためという。財務基盤強化のため出資者のJAなどを引受先として1兆2千億円規模の資本増強にも取り組む。
農林中金は、各地のJAや漁協などから資金を集め、それを運用して経営を支えている。巨額赤字はJAや漁協にも影響が大きい。問題点を洗い出し、安定的な運用体制の再構築を急いでもらいたい。
農林中金の市場運用資産残高は24年3月末時点で56兆円にも達する。「ノーチュー」として世界中に知られる、巨額の運用者である。
金利が低い時期に購入した外国債が、米国の急激な金利上昇などを受けて暴落したことなどが響いた。結果から見れば運用資産の大きさにあぐらをかき、金利が上がれば価格が下がる債券市場への対応を誤ったということになる。
農林中金が手堅い運用を心がけていたことは分かる。株式よりもリスクが小さい債券が運用資産の56%を占め、株式はわずか2%。外国株式はほぼゼロだった。
見込み違いは、米国の急激な金利上昇である。低金利の商品を売って高金利の商品に買い替える動きが加速し、保有する外国債の価格が下がって含み損が拡大した。為替変動に対応するコストも膨らんだようだ。
外国債運用には多くの地方銀行も失敗したが、それでも好調な株式の運用益で帳尻を合わせたとみられる。農林中金の損失が突出したのは、債券に片寄った資産運用が、結果的に裏目に出たと言える。
各地のJAなどは農業従事者が減る課題に直面する。営農事業で出る赤字を、金融や共済などの収益でカバーしている。そのJAなどから資金を預かっている責任の重さを忘れてもらっては困る。
農林中金に資金を預けている出資者は、JAや漁協など3千団体を上回る。農林中金の巨額赤字の影響を、1次産業従事者の多くが被るような事態は、避けなくてはならない。
農林中金は今後、高収益性商品を中心にした運用に切り替えるという。運用内容を吟味し、国際金融の流れに柔軟に対応できる体質に改めていくことに異論はない。
ただ、農林中金の巨額損失は今回が初めてではない。リーマン・ショックの影響で有価証券関連の損失が膨らんだ際も、JAなどの支援で2兆円近い資本増強が行われた。損失を出すたびに、増資を求められることに疑問を感じる出資者もいるのではないか。
農林中央金庫法には「農林水産業の発展に寄与し、もって国民経済の発展に資する」という設立目的がうたわれている。農林中金は丁寧に増資の説明を尽くし、組織の原点に立ち返る契機とすべきだ。全体のごく一部にとどまる農林水産業への融資を広げていく努力も忘れてはなるまい。