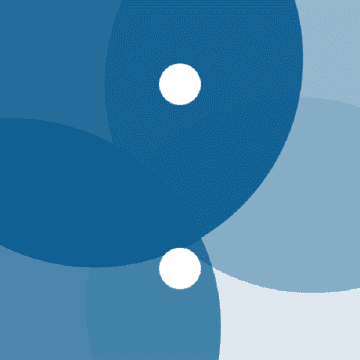ホンダが2024年6月13日、『CB650R』と『CBR650R』に「Honda E-Clutch」(イー・クラッチ)を初搭載し発売した。クラッチレバー操作を不要とするという点においてはかつてのDCTと同じだが、シフトペダルの操作はMTと同じだ。「操る楽しさを求める幅広いライダーにワンランク上の走りを提供」するというE-Clutchだが、既存のDCTとはどこが違うのか? クローズドコースでの試乗を経て、開発陣に話を聞いた。
ドゥカティ、終末世界を駆けるコンセプトバイク発表...『RR24I』初公開
◆ホンダが目指したイージーライディングとスポーツ性能の両立

2010年7月29日、ホンダは世界初の二輪車用DCT(デュアルクラッチトランスミッション)を搭載する大型のスポーツツーリングバイク『VFR1200F DCT』の販売を国内市場で開始した。同年3月より発売していた「VFR1200F」のマニュアルトランスミッションをDCTに置き換えた追加バリエーションで、構造上の特徴はクラッチレバーとシフトペダルがない点だ。
DCTの狙いはわかりやすく、イージーライディングとスポーツ性能の両立にあった。発進から停止までクラッチレバー操作の必要がなく、システムが行う自動変速に身を任せるだけで、MTと同じダイレクトな駆動フィールが得られる。
反面、仕組みが複雑でトランスミッション単体としても大きく重量がかさみ、制御も難しくコスト高だった。四輪車であればまだ、搭載スペースの確保や、高まるコストを車両価格に転嫁して吸収することができたが、車体が小さく、値上げもまなならない二輪車となれば話は別だ。

VFR1200F DCTでは、メインシャフトの二重構造化、油圧クラッチの直列配置、油圧回路のエンジン右側集約化でサイズの制約にチャレンジした。また、発進から微速、加速、巡航、減速に至るまでの緻密なシステムコントロールには最先端の制御ロジックを用いて課題を克服。後に制御ロジックは数回のソフトウェアアップデートが施され、運転のしやすさも格段に向上した。懸案だった重量もMTモデル比10kg増に抑えている。
しかし車両価格は高かった。VFR1200Fの157万5000円に対して、DCTモデルは10万5000円高い168万円。ホンダとしては涙ぐましいコストダウンを図った結果が、市場からは「高価」との声も聞かれた。もっとも、比較対象車のない世界初の二輪車用DCTだから評価が定まらなかったわけで、認知度の高まりと共に「得られる性能からすれば適正価格」との声も出始めた。
筆者(西村直人)はそのVFR1200F DCTを2010年8月~2015年8月までの愛車とし、2015年8月から現在に至るまでVFR1200F DCTをベースにしたクロスオーバーモデルで同じくDCTの『VFR1200X』に乗り続けている。

そんなホンダがCB650R/CBR650Rに搭載したE-Clutch。DCTとの違い、そしてその開発目標はどこにあったのか。CB650R/CBR650R 開発責任者の筒井則吉氏、同開発責任者代行の吉田昌弘氏、E-Clutch 開発責任者の小野惇也氏に、話を聞いた。
(聞き手:西村直人)
◆「MTモデルの楽しさをまったくスポイルしていない」

\----:“欲しいところで確実なアシストが入る進化型MT”。これがクローズドコースでE-Clutchを搭載したCB650R/CBR650Rに試乗した際に抱いた正直な感想です。愛車であるDCT(VFR1200X)も快適性では未だにピカイチですが、ガチャガチャとした油圧制御がライダーの運転操作とはリンクせずに入るため電子制御でドーピングされたマシンのようです(笑)。メカ好きの私としてはお気に入りポイントですが、どこか乗せられている感覚は拭えません。
対して、E-Clutchは基本MTで時々アシストが入る。左手のクラッチ操作だけを代わりにやってくれるので「出しゃばらない、やさしい電子制御システム」だと感じました。車両価格はCB650R/CBR650RのMTモデルに対して55,000円高(=DCTの半分)に抑え、重量にしても2kg増に留まっている。ここも高く評価しています。
E-Clutch 開発責任者 小野惇也(以下、小野):ありがとうございます! でも、量産化への道のりは険しかったです。通称「ラピュタ」と呼んでいた技術検証の最初期モデルはシステム全体のサイズが大きく、コストも高め。ここから量産に向けたチャレンジが始まりました。開発目標では、現在MTに乗り慣れている多くのライダーが大切にされているダイレクトな乗り味はそのままに、MTのマイナス要素を消してプラスの要素を伸ばすことを念頭に置きました。

\----:MTのマイナス要素として、たとえばストップ&ゴーの連続する渋滞路での頻繁なクラッチレバー操作で左手が痛くなってきた時や、エンストしないようタイミングを合わせてサッと発進したい交差点での右折時などが挙げられます。でも、疲れや焦りを感じていない時は、むしろそういった操作を積極的に、うまくこなしたいという衝動にかられます。
E-Clutchはクラッチレバーを装備し、いつでもシステムをオーバーライドしたマニュアル操作、つまり一般的なMTモデルとまったく同じ運転操作を受け付けてくれる。これがうれしい。ただし、現在の法規ではクラッチレバーの有無が要因となりAT限定大型二輪免許では運転できません。一方、現在ホンダが販売するDCTはAT限定大型二輪免許で運転可能です。よってE-Clutchがきっかけとなり限定解除へ、という流れが生まれるといいなと個人的には感じました。
CB650R/CBR650R 開発責任者代行 吉田昌弘(以下、吉田):E-Clutchは本当に必要なのか、お客様に喜んで頂ける体感性能が得られるのか、当初、大いに疑問でした。しかし開発を進めていくに従い、クラッチレバーを残しているおかげでMTモデルの楽しさをまったくスポイルしていない。量産化が見えて来た頃には「これは大物だ」と思えてきました。
◆なぜE-Clutch初号機に「CB650R/CBR650R」が選ばれたのか

\----:E-Clutchは吉田さんからもお墨付きを得たわけですね。
吉田:よく量産化に辿り着けたと思います。開発陣はものすごい苦労を重ねてきました。車両ごとの適合工程を別として考えれば、技術的にはクラッチ操作を2つの小型電動モーターで制御しているので、どのMTモデルにも理屈の上では搭載可能です。
\----:私は「出しゃばらない、やさしい電子制御システム」だと感じましたが、それは狙いですか?
吉田:はい(笑)。確かに出しゃばってはいませんが、じつはシステムの裏側ではものすごい緻密な制御を行っています! ただ、完成したE-Clutchではスゴさを誇示すのでなく、むしろ奥ゆかしいと感じて頂ける点もよかったなと感じています。先行販売している欧州やタイでも同様のご評価を頂いています。

\----:なぜ、CB650R/CBR650RがE-Clutch搭載の初号機だったのでしょうか?
CB650R/CBR650R 開発責任者 筒井則吉:答えは明確です。CB650R/CBR650Rはともにオンロードの代表ブランドであり、これまで高い技術をお客様に提供してきました。CB650Rではロードモデルとしての気持ちよさの追求。一方のCBR650Rではスポーツモデル『CBR900RR』(1992年)を起源としたピュアスポーツを継承しています。
また現在、CB/CBRブランドとして1300ccまでの排気量モデルを揃えますが、CB650R/CBR650Rは世界市場で年間3万台を越える販売台数があり中核モデルです。ビギナーからベテラン、女性ライダーからも多数、支持を頂いています。そういったユーザー層が多いところに新しい技術であるE-Clutchを投入し、提供価値のアップデートでバイクライフを豊かにしたい、そう考えてCB650R/CBR650Rに初めて搭載しました。
\----:E-Clutchがこの先、たくさんのHonda二輪に搭載されることを願っています。ありがとうございました。