
長谷川博己が主演を務めるTBS系日曜劇場『アンチヒーロー』。物語も終盤になり、主人公・明墨正樹(あきずみまさき)の“本当の目的”が、12年前、捜査機関の証拠隠ぺいにより「糸井一家殺人事件」で犯人とされ死刑判決が下された志水(緒方直人)の「冤罪」を明らかにすることだったと明らかになった。
このストーリーに対し、SNS等では「袴田事件」など現実に起きた冤罪事件を想起したという視聴者らの声も多く見受けられる。くしくも先月23日、袴田事件の再審=やり直し裁判の最終弁論が行われ、証拠の隠ぺい、ねつ造を行ったと指摘される検察側が改めて袴田さんに対し死刑を求刑。大きな波紋を呼んだ。
これまで自白の強要などで冤罪を生んできた「捜査機関による取り調べのあり方」を問う訴訟(日本の黙秘権を問う訴訟)を担当し、『アンチヒーロー』も鑑賞しているという髙野傑弁護士に、冤罪とは何か話を聞いた。
「冤罪事件」が起きる背景
──髙野弁護士は、『アンチヒーロー』を第1話からご覧になって、note(ドラマ「アンチヒーロー」から尋問を学ぶ:物を利用した証人尋問)も書かれていましたね。
髙野傑弁護士(以下、髙野弁護士):弁護士モノだからというよりは、同じ日曜劇場の枠で昨年放送された『VIVANT』が面白かったから…くらいのきっかけで観始めたのですが、『アンチヒーロー』は法律監修の先生がかなりしっかり関わっていらっしゃる印象を受けました。
たとえば、ドラマではよく法廷で突然新たな証人を連れてきたり証拠を提出する場面があります。あれは実際にはできないんです。新たに証人を申請することや証拠を提出することは事前に相手方に伝えなければなりませんし、書面であれば中身も見せなければなりません。そうした点が忠実に作られているのは素晴らしいと思っています。
──ドラマは終盤を迎え、主人公・明墨の目的(冤罪で死刑判決を下された志水を救うこと)が見えてきました。髙野弁護士も冤罪事件の裁判に関わっていらっしゃいますが、そもそも「冤罪」とは何でしょうか。
髙野弁護士:狭義では、冤罪(無実の罪)であることがきちんと法律上の手続きによって明らかにされているところまで行って冤罪だとは思いますが、現場で実際に被疑者・被告人と接している中で、残念ながら弁護士の力が及ばず有罪になってしまう人も当然いるわけです。そうした場合、弁護士から見たらそれは間違いなく冤罪だと思っていますが、社会一般としてそれを冤罪と理解してもらえるのかどうか。そこには隔たりがあることを感じます。
──髙野弁護士は、不当に逮捕された場合、黙秘権(※)を行使することをすすめていますが、「黙秘=悪いもの、卑怯なもの」「捜査官=ヒーロー」みたいにとらえている人も多いと指摘されていますね。
※「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」(憲法第38条第1項)、「被告人は、終始沈黙し、又は個々の質問に対し、供述を拒むことができる。」(刑事訴訟法第311条第1項)として、被疑者・被告人は捜査機関の捜査および裁判での尋問に対し、黙秘することが権利として認められている。
髙野弁護士:実際の事件はドラマと違って、防犯カメラの映像などの誰の目から見ても明らかな証拠というものがないことも多いんです。そういう事件の場合、供述が重要な証拠となります。そこで、取り調べで黙秘をすると、人格を否定されたり、能力について侮辱を受けたり、反省していないと批判されることが珍しくありません。被疑者が黙秘をしている取り調べでは、20日間の身体拘束中に怒鳴られたり、脅されたり、人格を否定されたりということが今でも数多く行われています。これは、取調べの録音録画動画を見ているわれわれ弁護士からは、疑いようのない事実です。
──ドラマでも殺人を否認し続ける志水に、当時の明墨をはじめとした検察官らが脅しをかけていますね。過去の話ではなく、今でも普通に行われているということに驚きます。
髙野弁護士:ドラマでは志水さんの逮捕当時の弁護士について今のところ指摘がありません。現実には黙秘をやめるように、被疑者本人と弁護士の信頼関係を崩そうとしてくることも多いです。被疑者にこの弁護士を信頼していいのかという不安を持たせ、引き離そうとするんですね。多くの事件では、捕まってから初対面の弁護士に依頼する形になるので、その弁護士がどういう人かは被疑者にもわからない。そこで、「お前の弁護士は~」などと吹聴し、不安にさせるんです。
──それは常套手段なのですか。
髙野弁護士:そうですね。ただ、われわれもそれを把握しているので、黙秘してもらう際のアドバイスとして、ショックを受けないよう、「絶対こういうことを言われるけど、それは常套手段だから気にしないで」と先出ししておくということはやっています。
──そうした常套手段を知らないと、取り調べの中で黙秘を破られることも多そうです。
髙野弁護士:弁護士が被疑者に会えるのは、現実問題として1日に長くても2時間程度ですが、警察は1日中ずっと取り調べしていれば5、6時間も一緒にいるわけなので、人間関係として同じ空気を共有できる時間に大きな差があるんです。そうした中で揺さぶられると、崩れてしまう方は少なくないと思います。
そもそもなぜ弁護士は「黙秘」をすすめるのか?
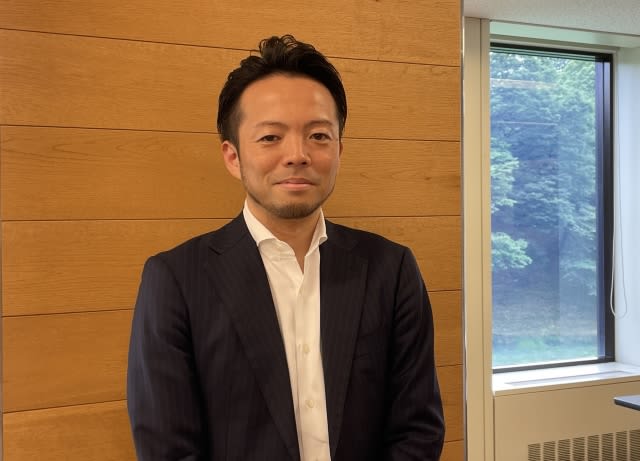
──「黙秘」はそもそもなぜ重要なのでしょうか。
髙野弁護士:たとえば今、皆さんが「1年前の6月3日午後3時ぐらいにどこにいたのか教えて」と言われたとき、何の資料も見られない状況では到底話せないですよね。そのとき、「〇〇で取材をしていました」と話して、「違うよ」と防犯カメラの映像を見せられ、「そこから10キロ離れたコンビニにいたよ」と言われてしまう。こうなれば「この人は取り調べを受けている最中に嘘をついていました」という話になってしまうわけですね。
──1年前どころか、1週間前でも何も見ずに答える自信はないです……。
髙野弁護士:そうですよね。取り調べでは基本的に、手帳やスマホのカレンダーや写真、LINEのトークなどを見て答えることはできません。しかも、それで事実と違うことを言ってしまうと、「記憶が間違っていた」「勘違いでした」では済まなくて、「この人は意図的に嘘をついた」という評価をされてしまうんです。
──通常の人間の認知機能でそれはほぼ無理では……。
髙野弁護士:そう、無理なんですよ。無理なことを求められて、「嘘をついた」という形が残ってしまうなら、もう何も言えませんよね。人間の歴史として、そうした理由で冤罪が生まれてきているのは間違いない。だからこそ、黙秘することが基本的な人権として尊重されているんです。
──なるほど。資料も見ずに正確なことは何も言えないから、基本は「黙秘」が重要なのですね。その後、取り調べの中で黙秘をやめる流れになるのですか。
髙野弁護士:どこかのタイミングで黙秘をやめて話すことも、ないわけではないと思います。ただ、その決断をどうやってするかというと、1番わかりやすいポイントが証拠との矛盾がないかを弁護士が確認できるかどうかです。捜査機関がどういう証拠を持っているか、たとえば証拠になっている防犯カメラの映像を私たち弁護士が見ることができて初めて、「これはこういう記憶で間違いなさそうだ」ということが判断できて話が進められるわけです。しかし弁護士が証拠を見ることができるのは起訴された後です。そうすると、取り調べで黙秘を解除する判断をできる場面は多くないですよね。
──では、基本はずっと黙秘の状態が良いということですね。
髙野弁護士:そうです。捜査段階でその問題を完全に払拭して話ができるのは、相当レアなケースです。ただ、捜査機関、特に警察官は、供述調書という形での記録を作ることが自分たちの仕事だと思っている方が圧倒的に多いので、「黙秘」はそれに真っ向から反することになります。憲法で定められたものだとしても、黙秘権を行使する被疑者に対して不愉快に思っている人がほとんどだと思います。だからこそ喋らせようとしてくるんです。
弁護士が暴言よりも「嫌がる」取り調べ
──髙野弁護士は弁護士会で行われる研修の講師などもされているそうですが、その際にどんな指導をするのでしょうか。
髙野弁護士:まずは被疑者に黙秘してもらうよう言います。それに付随し、黙秘を被疑者たちに頑張ってもらう以上、弁護士は頻繁に警察署へ面会に行くよう言っています。本人が警察にいろいろ言われるうちに、大丈夫かという不安が少しずつ溜まってきて、弁護士を信じられなくなるからです。そうした不安が3日、1週間と溜まってしまうと、それで耐えられなくなる人はたくさんいますから。頻繁に会いに行き、小さい疑問の時点で解消していくことは、黙秘を維持するために必須です。
──警察や検察は被疑者にどんなことを言って弁護士を疑わせたり、不安を持たせたりするのでしょうか。
髙野弁護士:典型的なのは、「お前の弁護士はまだ若いからわかっていないんじゃないか」とか。私も1、2年目のときはよく言われました。また、黙秘していると不利になることもあるといったネットの情報を見せること。おそらくどんな場面でも黙秘が良いわけではないと書いてあるのだと思いますが、都合の良いところだけ切り取って見せるんですね。
他に典型的なのは、家族の話を持ち出すこと。これは『アンチヒーロー』で検察官だったころの明墨も使った手ですね。「家族にこの間会ってきたよ。家族は黙秘なんかやめて、事件のことをちゃんと話して反省してくれと言っているよ」みたいなことを、家族はそんなこと言っていないのに言う人もいるんですよ。
──事実でもないことを言うのは酷いですね。
髙野弁護士:そうしたことを私たち弁護士が把握したときには、当然抗議します。検察官のやり方としてよくあるのは「黙秘するのは自由だから良いよ。ただ、黙秘を本当にあなた自身がしたくてしているのか、弁護士に言われてしているだけなのか。弁護士に言われているだけだとしたら、弁護士は最終的に責任を取ってくれない。あなた自身が本当はどっちがいいのか考えてみて」と揺さぶってくることです。それまでに被疑者本人に「黙秘がベストの選択なんだ」と心の底から納得してもらえるよう助言しておかなければなりません。
──取り調べでは、ドラマでよく見るような大声で怒鳴るとか机を叩くとかはあまりないのですか。
髙野弁護士:怒鳴ったり机を叩いたりは数は少ないと思います。そもそも、これらの方法は正直、あまり有効ではないんですね。被疑者のパーソナリティーにもよりますが、なんで怒鳴られなきゃいけないんだと反発する人は多いですから。本当に自分はやっていないと思っている人ほど、取り調べに対する反発が黙秘を継続するためのエネルギーになっていくということもあります。
私自身が1番警戒するのは、「心底あなたのことを考えて言っているんだよ」という空気を出してくる警察官・検察官ですかね。そういうときの方が反発もしにくく、疑問を持ち始めてしまい、黙秘が破られる危険がありますから。
──本当にやっていないなら、黙秘するより、やっていないと言えば良いと思う人もいます。
髙野弁護士:そこが難しいところで。たとえば、痴漢を疑われたとき、「やっていない」と言うと、「なんでやっていないと言えるの?」という話になるわけですよね。「だったら、このとき、どこにいたのか」と言われ、いろいろ聞かれていくうちに、どこかに間違いが出てくると「嘘をついた」と言われる。そうすると、最終的に証拠と矛盾してしまえば、「この人は嘘をついています。だからやっていないという主張も信用できません」となってしまうわけですよ。
冤罪を防ぐ“思考”を
──『アンチヒーロー』など、ドラマやエンタメで冤罪事件を描く意義について、髙野弁護士はどうお考えですか。
髙野弁護士:日本に冤罪があるということは、今でこそ「袴田事件」などをきっかけとして、ある程度ニュースになり、一般の人も知るところになっています。でも、頻繁にニュースになるほど進展がある冤罪事件、再審事件が多くあるわけではない中で、 ドラマなどで常にこういう問題があることを描くのは、価値があることだと思います。
──日々さまざまな報道に触れる中で、袴田事件をはじめ、過去の冤罪事件などのニュース、あるいは新たな事件報道を見たとき、どこに注目すると良いでしょうか。
髙野弁護士:何が原因で冤罪になってしまっているのかは事件ごとに違うので、「冤罪ではないか」と疑うべき基準があるわけではありません。ただ、過去も今日も、日本では逮捕された時点でもっとも報道が加熱します。逮捕された段階では、まだ罪を犯したかどうかわからない「推定無罪」の状態にあるのに、日本では多くの人が報道に触れた時点で「この人は罪を犯した」という前提で見てしまう。しかし、その奥に冤罪の事件があるわけです。今皆さんが見ているニュースで犯人とされている人に対しても、この人はまだ罪を犯したと確定したわけではないんだ、冤罪の可能性もあるんだという疑問は持たなければいけないんです。そういう意味で、できるだけ多くの方が「推定無罪」の思考を持つように変わっていってほしいですね。

