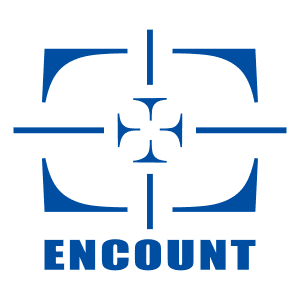元テレビ朝日法務部長・西脇亨輔弁護士が指摘
ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEが12日に公開した新曲『コロンブス』のミュージックビデオ(MV)に批判が相次ぎ、翌日、公開停止となった。MVはメンバーがコロンブス、ナポレオン、ベートーベンとみられる人物に扮し、遭遇した類人猿に人力車を引かせたり、西洋音楽を教えるというもの。これが「植民地主義を連想させる」など炎上し、レコード会社やメンバーが相次いで謝罪する事態になった。同曲をキャンペーンに起用していたコカ・コーラ社もCM放送を止めたが、元テレビ朝日法務部長・西脇亨輔弁護士は同社のコメントに関する違和感を指摘した。
「会社は何も知りませんでした」で済む話なのだろうか。
Mrs. GREEN APPLEの新曲『コロンブス』のMVが「アメリカ大陸を『発見』したコロンブスを賛美し、先住民を類人猿扱いしているのではないか」と炎上すると、同曲をCMに起用していた日本コカ・コーラ社は即座にコメントを出した。その中で同社は「いかなる差別も容認しておりません」とした上で、「これは、我々が大切にしている価値とは異なるものです」「本楽曲を使用したすべての広告素材の放映を停止させていただきました。また、ミュージックビデオの内容に関しては、弊社は事前に把握をしておりません」と発表したと報じられている。
この発表だけを見るとコカ・コーラ社は、(1)たまたまMrs. GREEN APPLEの曲をCMに起用してしまったが、(2)知らないところでMrs. GREEN APPLE側が不適切なMVを作ってしまったので、(3)「CMを止めた」という流れに見える。
しかし、この発表は重大な事実を説明していない。
この『コロンブス』という曲が最初から、コカ・コーラのCMありきで作られたものであろうという点だ。それは同曲を聴けばすぐに気づく。曲の始まりはコカ・コーラの炭酸と思しき効果音。そして、歌詞には次のようなフレーズが並んでいる。
「海原に流れる 炭酸の創造」「愛を飲み干したい 今日も」「渇いたココロに注がれるような」
「ココロ」というカタカナ表記は過去の日本コカ・コーラ社のキャンペーンでも「ココロが踊りだす」(1999年)「ココロが求めてる」(2001年)と繰り返し使われてきた。この歌詞を見れば、曲を作り始める前にコカ・コーラとのタイアップが決まり、コカ・コーラという商品にあわせて曲が作られたと考えるのが自然だ(『コロンブス』というタイトルも、コカ・コーラが生まれた米国を意識しているのかもしれないと推察できる)。
そして、この曲をキャンペーンの主軸に据えていた日本コカ・コーラ社は広告代理店などと組み、曲の制作の進ちょくについても情報共有しながら広告戦略を練っていたと考えられる。そうであれば、その一環として問題のMVも会社担当者が早い段階で見ているのでは……という気もするが、仮にビデオは日本コカ・コーラ社が事前に見ていなかったとしても、今回の問題は「当社は関係ない」とはならないのではないか。
なぜなら、この問題の本質は『コロンブス』という名前を単にポジティブなキーワードとして扱った点にあるからだ。
既にさまざまな記事で指摘されている通り、アメリカ大陸はコロンブスに「発見」される前から先住民が暮らしていた。そして、先住民にとってコロンブスは多くの仲間の命が奪われた原因でしかない。その認識が米国でも広がっており、これまで「コロンブスデー」とされてきた10月12日の祝日は、州によっては「先住民の日」に変更。コロンブスの銅像が撤去された場所もある。米国では「コロンブス」という人名自体、取り扱いが「要注意」となっているはずだ。
そして、日本コカ・コーラ社は米国コカ・コーラカンパニーの100%傘下にある。社長も海外出身だ。であれば、夏のキャンペーンソングのタイトルが『コロンブス』だと聞いた瞬間に「危険だ」と気づくはずだったのではないか。もし、米国で同じキャンペーンを行ったら、日本の炎上どころではすまないだろう。
もちろん、MVの制作などに携わった側も、配慮のない演出に批判を受けるのは仕方ないだろう。このビデオにはナポレオンも登場するが、こちらも奴隷制を復活させた人物として近年、強い批判を浴びていて安易に起用できる人名ではない。
しかし、『コロンブス』という曲には、商品のキャンペーンを前提にアーティスト本人以外の多くの人が事前に触れていた。そして、問題は単にビデオの表現だけでなく「コロンブス」という名前を安易に使うという「歴史の扱い方」に及ぶものだ。こうした騒ぎになる前に警鐘を鳴らすことができた関係者は、アーティストの周りに多くいたはずだ。
それを問題が起きたら、「勝手にアーティストがやったこと」という発表で済ませてしまうのは、“真実の姿”とは異なっているのではないか。
どんな歴史にも表と裏がある。特に人の命が失われた歴史には暗部があるはずだ。そのことに思いを馳せずに歴史上の人物の名前を夏の曲やキャンペーンに使おうとしたこと自体が適切だったのかどうか。一連の経緯を関係各所がきちんと総括する。そうしたことが、歴史との付き合い方を皆で意識し直すためにも必要なのだと思う。
□西脇亨輔(にしわき・きょうすけ)1970年10月5日、千葉・八千代市生まれ。東京大法学部在学中の92年に司法試験合格。司法修習を終えた後、95年4月にアナウンサーとしてテレビ朝日に入社。『ニュースステーション』『やじうま』『ワイドスクランブル』などの番組を担当した後、2007年に法務部へ異動。社内問題解決に加え社外の刑事事件も担当し、強制わいせつ罪、覚せい剤取締法違反などの事件で被告を無罪に導いている。23年3月、国際政治学者の三浦瑠麗氏を提訴した名誉毀損裁判で勝訴確定。同6月、『孤闘 三浦瑠麗裁判1345日』(幻冬舎刊)を上梓。同7月、法務部長に昇進するも「木原事件」の取材を進めることも踏まえ、同11月にテレビ朝日を自主退職。同月、西脇亨輔法律事務所を設立。今年4月末には、YouTube「西脇亨輔チャンネル」を開設した。西脇亨輔