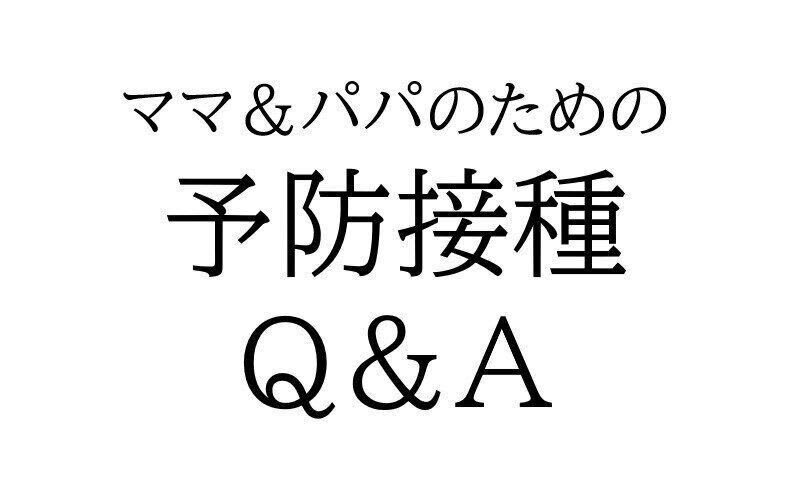
予防接種は子どもの健康のために大切なものだということは理解しているけれど、わからないことも多い…というママやパパは少なくないでしょう。ママやパパが抱きがちな疑問や心配を、小児科医で神奈川県衛生研究所 所長多屋馨子先生に聞きました。
予防接種で防げる病気と免疫に関するQ&A
免疫は、病気を予防するために大切な働きをしています。予防接種をより安心して受けるためにも、病気と免疫の関係について正しい知識を身につけましょう。
Q ワクチンを接種するより病気にかかったほうがいい?
A 病気にかかると重症化する恐れがあります
多くの場合、感染症にかかるとその病気に対する免疫がつきます。ただし、実際に病気にかかると重症化したり、重い後遺症が出たり、最悪の場合は命を落としたりする危険があることを忘れてはいけません。
赤ちゃん・子どものためには、より安全に免疫をつけることができる予防接種で、病気を防ぐほうが望ましいです。
Q 予防接種を1回受けたら、一生その病気にかからない?
A 多くのワクチンは複数回の接種が必要です。また、免疫力は徐々に低下します
大半の予防接種は一生涯有効なわけではありません。たとえば、水痘(水ぼうそう)は1回の接種だと約2割が軽くかかってしまうため、2才までに2回の接種がすすめられています。MRなどで追加接種が行われるのも、1回目の接種後、免疫がつかない人が5%程度いること、数年で免疫力が落ちる人が一部いるからです。肺炎球菌(13価または15価結合型)、B型肝炎、五種混合、日本脳炎など、3~4回の接種が必要なワクチンもたくさんあります。
Q 任意接種のおたふくかぜは、かかって免疫をつけたほうがいいの?
A 病気にかかるほうがはるかにハイリスクです
おたふくかぜに自然感染し、ムンプスウイルスが内耳まで侵入してしまうと、ムンプス難聴を発症します。急激に聴力が低下し、回復はほぼ望めません。そのため、小児科医だけでなく耳鼻咽喉科医も、おたふくかぜワクチンの定期接種化を要望しています。また、無菌性髄膜炎や脳炎、膵炎などを起こすこともあります。思春期以降だと精巣炎や卵巣炎を起こすことがあります。病気にかかることで免疫を得られても、リスクのほうがはるかに大きいのです。
Q 予防接種を受ける前にその病気にかかってしまったら、受ける必要ない?
A 本当にかかったか自己判断は禁物です
破傷風やヒブによる細菌性髄膜炎などを除けば、本当にその病気にかかった場合は免疫ができるので、予防接種は不要です。ただし、麻疹、風疹、おたふくかぜは見た目の診断だけではわからないことがあり、ママやパパの自己判断は禁物。正確な診断をするには、検査で確認する必要があります。
もしかかったことがあっても、症状だけで診断された場合は、よく似た別の病気ということもあります。かかったことが検査で確認されていない場合は、ワクチン接種は必要です。もしかかったことに気づかず、ワクチンを受けても、体への影響はありません。医師に相談してみましょう。
Q 病気にかかっても免疫がつかないこともある?
A すべての病気で免疫がつくとは限りません
免疫がつかない病気の代表的なものは、四種混合ワクチンで予防できる破傷風です。また、ヒブによる細菌性髄膜炎も、発症後に十分な免疫がつかないので、かかったとしてもワクチンを接種したおくほうがいいでしょう。
Q 早産で生まれても満期産の子と同じように予防接種を受けて大丈夫?
A 病気が重症化しやすいので積極的に予防接種を受けて
実際にその病気にかかってしまうことに比べると予防接種は赤ちゃんの体への負担は少ないので、早く生まれた場合でも、満期産の子と同じように受けて大丈夫です。むしろ、小さい赤ちゃんほど感染したときに重症化しやすいため、予防接種はきちんと受けましょう。出生時からの病気がある場合はかかりつけ医に相談し、接種のスケジュールを立ててください。
Q 感染症は手洗いやうがいで防げないの?
A 手洗いやうがいだけで防ぐのは困難です。感染症の中には予防接種がまだ開発されていないものもあります。ワクチンがあるのであれば、これが最も有効な予防手段です
飛沫や接触で感染する感染症には、手洗いやよく触れる場所の消毒は予防に有効な手段。赤ちゃんは手を口に入れることが多いので、よくふいてあげましょう。ママも手洗いやうがい、マスクの着用を心がけるといいですね。
しかし、それでは防げない感染症は数多く存在し、最も感染症予防に効果的なのは予防接種です。また、手洗いや消毒で感染リスクを低下させることができる病気も、ワクチン接種のほうが予防手段としては有効です。
ワクチンの種類や接種のしかたについてのQ&A
接種時期や接種の受け方、接種後の注意点など、ワクチンに関する疑問をスッキリ解決し、安心・納得してから予防接種を受けましょう。
Q 混合ワクチンは赤ちゃんの負担にならないの?
A 混合ワクチンだからという理由で赤ちゃんの負担になることはありません
まれに24時間以内に発熱したり、接種部位に腫れやしこりが出たりする場合がありますが、ほとんどは自然に治まる心配のない副反応です。現在の日本で赤ちゃんに接種するのは多くても五種混合ですが、諸外国では六種混合のワクチンを接種することもあります。
Q 生後2ヶ月から接種可能の13価あるいは15価の肺炎球菌ワクチンは、なぜできるだけ早い時期の接種が推奨されるの?
A 6ヶ月ごろから細菌性髄膜炎にかかる子どもが多くなるからです
肺炎球菌には100種類以上の血清型があります。13価あるいは15価の肺炎球菌ワクチンは、100種類以上の肺炎球菌のうち、13種類あるいは15種類の血清型の肺炎球菌による中耳炎や、細菌性髄膜炎などの重い感染症を予防します。細菌性髄膜炎は赤ちゃんがかかると重症化しやすく、深刻な後遺症が残ったり、命を落としたりする可能性がある怖い病気です。生後6ヶ月ごろから患者数が増えるので、それまでに免疫をつけておくことが重要です。
生後2ヶ月から接種を開始します。7ヶ月未満で始める場合、4週間の間隔で3回の接種のあと、1才から1才3か月の間に1回の合計4回接種が必要。そのため、できるだけ早い時期から接種を開始することが推奨されています。
Q 1才になってからの4回目の五種混合ワクチンを受け忘れたら、0才代に受けたワクチンの効果もなくなる?
A 無効にはなりませんが、4回目は免疫の維持に大切なので必ず接種して
万一、4回目を受け忘れても、0才代の接種が無効にはなりません。五種混合ワクチンは最初の3回で免疫をつけますが、接種後1年を過ぎると免疫が下がってくるので、4回目の接種で免疫を上げ、長年にわたって免疫を維持できるようにします。4回目を接種せずにいると免疫が下がる一方なので、4回目も必ず受けてください。7才半までは定期接種で受けることができます。7歳半以上でも15才未満であれば、受けることは可能ですが、定期接種として受けることができなくなり、自費で受けることになります。
Q MR、おたふくかぜ、水痘ワクチンは、どうして1才からしか接種できないの?
A 1才ごろまではママの免疫が残っています
おたふくかぜや水痘のワクチンは1才以上でないと接種が認められていません。MRは接種ができないわけではありませんが、1才未満だとママからもらった免疫が残っている場合があるため、ワクチンの免疫がつきにくく、期待する効果が得られないと考えられています。ただし、麻疹が流行している場合は、生後6ヶ月以降に単独の麻疹ワクチンを接種することがあります。ただし、0才で受けた麻疹ワクチンは接種回数には含めないことになっていますので、この場合でも、1才以上の定期接種は従来通り受けます。
Q 生後6ヶ月以降の赤ちゃんでもロタウイルスワクチンを受けられる?
A 24週(1価ロタウイルスワクチン)あるいは32週(5価ロタウイルスワクチン)までしか、ロタウイルスワクチンを受けることはできません。腸重積症を発症するリスクが高くなります
ロタウイルス胃腸炎が最も重症化しやすいのは、ママからもらった免疫がなくなったあと初めて感染したとき。そのため、ワクチン接種は早めに終わらせることが重要で、2回接種のワクチンは出生6週以降24週までに、3回接種のワクチンは出生6週以降32週までに接種を完了させる必要があります。
この時期を過ぎてからは、受けられません。
また、初回接種は14週6日までに受けます。15週以降の初回接種については腸重積症を発症するリスクが高まるとされているのでおすすめできません。
Q ロタウイルスワクチンを接種後、ロタウイルスがうんちに排出されるの?
A 排出されます。ていねいな手洗いを心がけて
接種後、約1週間は赤ちゃんのうんちにウイルスが排出されますが、それによって周囲の人が感染し、ロタウイルス胃腸炎を発症するリスクは低いことが確認されています。
とはいえ感染リスクがゼロではないので、ワクチン接種後は、おむつ替えのあとの手洗いを日ごろに増して気をつけ、石けんを使って十分に洗い流しましょう。
Q 同時接種は3種類までと聞いたことがあります。本当?
A 本数の規定はありません
病院の方針にもよりますが、「同時接種は何種類まで」という規定はありません。接種するたびに赤ちゃんは痛い思いをすることになるので、たとえば、1度に4回痛い思いをして終わらせるか、4回に分けてそのたびに痛い思いをするか、どちらが赤ちゃんの負担にならないか考慮して決めましょう。同時接種のほうが早めに免疫をつけることができます。
Q 同時接種をするとき、ワクチン同士の相性はあるの?
A 相性のよしあしはありません。組み合わせは自由です
ワクチン同士の相性のよしあしはなく、そのときに必要なワクチンならどれを組み合わせても大丈夫です。ただし、注射の生ワクチンを接種したら、異なる種類の注射の生ワクチンの接種は中27日以上空けなければいけないので注意が必要です。なお、2020年10月1日から、予防接種の制度が変わりました。同じ種類のワクチンを複数回接種する場合は接種間隔が決まっていますが、飲む生ワクチンや、不活化ワクチンの接種後に異なる種類のワクチンを接種する場合、接種間隔の制限はなくなりました。
怖いの?大丈夫なの?副反応に関するQ&A
予防接種を受けるときは副反応が気になりますね。起こりやすい症状や判断のしかたなどの疑問を解決し、正しい知識を身につけておきましょう。
Q 「副反応かも?」と思ったらだれに相談すればいいの?
A 症状が出たらまずは接種した医師に相談を
副反応と思われる症状が出た場合は、まず接種した医師に相談してください。個別接種のときは受けた病院、集団接種のときは保健所などになります。
Q 副反応は接種後どれくらいで出る可能性がある?
A 強いアレルギー反応は30分以内が多いですが、そのあとに起こることもあります
通常、強いアレルギー反応による副反応は、接種後30分以内に起こることが多いですが、そのあとにもさまざまな原因による副反応が現れる場合があります。
副反応が起こる可能性がある期間は、不活化ワクチンは接種後1週間ごろまで(一部は2~3週間後にも)、生ワクチンはその病気の潜伏期間と同じだけ(接種後7~21日が多く、BCGは3~4カ月ごろまで)です。
Q 1回目の接種で副反応が出なければ、2回目以降も大丈夫?
A そのつど反応が違うので油断しないで
五種混合や日本脳炎などは、2回目のほうが腫れやすいようですが、通常は、1回目の接種後に副反応が見られなければ、同じワクチンの2回目以降の接種で重篤な副反応が起きる可能性は低くなります。
でも、副反応はそのつど症状が違います。1回目に副反応が出なくても油断せず、接種後はその場で30分程度待機し、子どもの様子をよく観察してください。
Q 同時接種で副反応が出た場合、どのワクチンの反応かわかるの?
A 接種部位に現れないと判断できないことがあります
接種部位の腫れやしこりなどは、その部位に接種したワクチンの副反応だと予想がつきますが、発熱などの症状だと、どのワクチンが原因なのかはっきりとはわかりません。
ワクチンで健康被害が起こったときは、任意接種より定期接種のほうが健康被害救済制度が手厚いのですが、定期接種と任意接種を同時接種して重い副反応が出たケースで、どのワクチンによって起こったかがわからない場合は、通常、定期接種の救済制度が適用されます。
Q 体調が悪いときに接種すると、副反応が出やすい?
A 体調が悪いときは接種してはいけません
接種前に診察をして、その結果、接種できたのであれば、体調はそれほど悪くなかったのかもしれませんが、体調がふだんと違うかどうかを一番よく知っているのは、ママやパパなどの家族です。普段と違う症状があるときは、必ず接種前に接種医に相談しましょう。
体調が悪いときは受けてはいけません。体調がふだんと違って気になる時は接種を延期するなど、子どもの体調のいいときに受けるのが原則です。
接種後に気になる体調の変化が見られるときは、接種医あるいはかかりつけの小児科医に相談してください。
Q 接種後の発熱はよくあることなので受診しなくていい?
A つらそうなら自己判断せずに受診しましょう
接種後の発熱はよくあることですが、副反応による発熱なのか、ほかの原因による発熱なのか、見分けるのは難しいです。自己判断でそのままにするのはやめましょう。
赤ちゃんがぐったりしている、顔色が悪いなどの症状がみられる場合は、すぐに受診してください。
Q 受診が必要な腫れ方はある?
A 腕全体が腫れたり、ひじを超えるような腫れの場合、痛がるときは受診して
接種した腕やひじなどの関節部分を超えて全体的に赤くなったり、腫れた(パンパンになった)りしたとき、あるいは、腫れた部分を痛がるときは受診する必要があります。
また、指で押さえても消えない発疹や紫斑などが出たときも受診してください。
予防接種の疑問や不安を解決できると、予防接種は感染症から子どもを守るために欠かせないものだと改めて確認できると思います。接種できる週齢・月齢・年齢になったら、体調がいいときを見計らって、できるだけ早く済ませるようにしましょう。
情報提供/多屋馨子先生
取材・文/東裕美、ひよこクラブ編集部
●記事の内容は掲載当時の情報で、現在と異なる場合があります。

