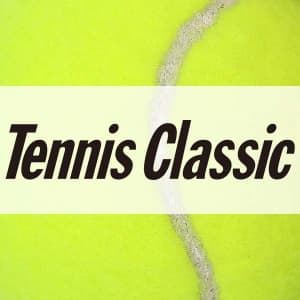サンフランシスコから風光明媚な「ゴールデンゲートブリッジ」を渡ったところにある「マリン郡」。富裕層が住むティブロンという街があり、そこにある会員制名門クラブでは毎年ATPチャレンジャーが開催(過去にはデビスカップ日本代表の添田豪監督が優勝)。そのクラブで2年前からコーチを務める綛谷昌生(かせたに・まさき)さんがいる。
綛谷さんは百貨店でシンガポールとニューヨークの駐在員から一転、2007年よりテニスコーチに。アメリカの名門クラブならではの特殊なテニスクラブの実状についてインタビューをさせていただいた。
――会員制のテニスクラブでコーチとして働くきっかけを教えてください。
「ニューヨークからマリン郡に引っ越して来た2年前の4月、知人から前にこのクラブのコーチをしていた方を紹介していただきました。その方の紹介でこのクラブのテニス担当ディレクターの面接を受け、さらにオンコートでのレッスントライアルを経て正式に採用されました」
――ニューヨークでは日本人や日系の方々を担当していたそうですが、その違いなどはありましたか。
「ニューヨークでの経験を元にちょっとトライしましたが、早速つまずきましたね。アメリカでも有数の超富裕層が住む地域で教えることは初めての経験で、また『テニスをやりたくない子にテニスをどうやって教えたらええねん!』と悩みました」
――アメリカの場合、テニスを「学ぶ」というよりソーシャルとしての部分をメインに親は考える傾向にあるように思います。子供によっては「やりたくないこと」も自由、という感じでしょうか。
「最初の頃は規則も含め『しっかり教えんと』みたいな使命感のようなものがあり、それがテニスコーチだと思っていました。最初は真剣に叱ったりしたんですけども、変な空気になりました。ニューヨークでやっていた当たり前のことがここでは全く通用しなかったという。彼らも、クラブも求めているものはそうじゃなかったんですね」
――「テニスを通じて何か」をアメリカ人は一般的に求めてないというところは一つの大きな違いなのでしょうか。
「基本的な練習をする前にウォームアップで走るトレーニングをやると親御さんが『うちの子を走らせないでください』と言ってきます(笑)ですので、いろいろ試行錯誤が始まるんですね」
――これまでのパターンが通用しない状況です。
「例えば大人、特に女性へのレッスンですと差別というかばかにしているような雰囲気を感じるんです。まずは言葉の問題。私の発音を笑われたり真似されたりしました。アジア人、日本人に対する上から目線というか。球出しのボールで自分の打ちやすいところにボールが来ない!とか、あからさまでした。それも含めて、いい経験もさせてもらいました」
――昨今では表立ってはなくなりつつあるかつてのアメリカのようです。特定の場面ではあり得る話だと思います。
「一言で言うと『リスペクト』です。その場面に遭遇し共通して言えることは、リスペクトが全くない。人を敬った上での畏れというものがないんです。これはこの地域特有のものでもあり、強引な受け取り方で言えば“自分本位”ということです」
「現実的な話、ここでコーチとして生きてくことを考えた時、“商売”と考えて自分の心を無にして、ただただお金のことだけ考えるのであればできると思います。ですが、僕にそれはできなかった。中学生でテニスを始めた時からずっと“テニス”に対して崩してはいけない何かがあって、それを崩さないで教えたいというかね」
――素晴らしいロケーションでクラブのパワーやエネルギーを感じます。
「駐車場には当たり前のように高級車が並んでいます。現在、個人でレッスンに通っている方は日本から初めてアメリカにカニカマを輸入した水産関係の経営者の方で、10台のスポーツカーを所有し毎回違う車でやって来ます(笑) プライベートジェットで『明日からちょっとウィンブルドン行ってくるから』とか休みはハワイの家に行くとかが彼らにとっては普通です。例えば、新缶を開けて一度使うとそれを置いて帰ります。コロナの時、壁打ちするためにボールがぼろぼろの状態でも打てるだけありがたいと思って使い続けましたが、ここにはそんな感覚がない」
――富裕層側から見るテニスの価値観もまた違うでしょうね。
「すべてが整った状態で与えられて当然という考え方を随所に感じます。その考えが子供たちにも受け継がれていますね。クラブの山側には6面のメンバー用コートがあり、ATPのチャレンジャーが開催されるほど綺麗なコートです。もちろん、その中にもヒエラルキーがあり、使えるボールやコーチに力関係が存在します。クラブの特徴のひとつとしてサンフランシスコ特有の霧が出るのですが、これにより朝はレッスンコートの整備は後回しにされることが暗黙の了解。会員優先のクラブの姿勢は、時にコーチ側にタフな場面となることも多々あります」
「コーチ側は高額なレッスン代をいただける反面、住居や生活にかかる費用も高く、この1年間でコーチ4人が辞めました。その理由の一つは、マリン郡に住むのはすごく大変だということ。元ヘッドプロは夏休みの間にハワイへ出稼ぎへ行ったと言っていましたね」
――そのレッスンでは、見学させていただきましたがゲーム形式になると皆さん人が変わったようでした。
「彼らはポイントゲーム形式が大好き。初めてのレッスン後に私へ『これだけ動くレッスンは初めてだった。ありがとう!』と言ってきた。人数に合わせたゲーム形式があり、パターンに変化を持たせて楽しみ工夫しながら自分の強みをポイント中に学んでいきます。ポイントがかからない練習はそもそも気合が入らないというのもアメリカ人の特徴のひとつですね。上手く打てたことより、どのようにポイントを取っていくかというところに気持ちが入ります」
――日本人は練習の方が好きな傾向にあるように思います。
「簡単に言ってしまえば勤勉さでしょうね。ちゃんとこう基礎を固めてからやろうというものの考え方と、それよりもここではテニスはボールを打つことにフォーカスしています。ゲームとかポイントとかやるでしょう。すごいチート(意図的なミスジャッジ)しますよ(笑) そこまでしてでも勝ちたいんですよね。 もう思わず苦笑いしてしまうぐらいです」


――テニスも場所が変われば、また違う見方が出てきますね。
「私自身は、中学生でテニスを始めて大学まで続けた。体育会テニスでそれなりに自分自身の中で確立したとは思うのですが、ニューヨークで教えていた時にはそれをフィードバックするというか、いいように言えば恩返しの考え方でテニスに取り組めた。しかし、ここではそれとは違う部分があるなっていう気がしています。そのテニスというものに対する考え方をわかってもらう、彼らに伝えるということの難しさを感じています。あれはもう違うものとして考えないといけない。ある意味ホスピタリティという仕事か、というような。テニスを“仕事”という捉え方をしたのは自分自身も初めてです」
――テニスへの取り組み方を見つめ直す経験ができるところは素晴らしいと思います。
「言葉のハンディがあるのをわかった上で、私を雇ってくれたなとは思っています。ありがたいことですよね。でも根本的な取り組み方と考え方を変えようとは思ったことはありません。ハンディは感じながらですが時給は高いですよ。今年からカリフォルニアではファーストフード店の時給は20ドル(約3,000円)になります。ティブロンのテニスコーチですと、場合によってはファーストフード店の3〜4倍になりますから」
――このクラブのコーチは選手の実績もある経験豊かな方が多く在籍しているのでしょうか。
「僕より一つ年上ですけど、そうは見えないぐらいおじいちゃんに見える。でも、実はマッケンローと同じ年齢で、彼はカリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)でNo.1選手だったとか。全米大学で(マッケンローとフレミンが在籍する)スタンフォード大学に敗れて、彼は準優勝。それぐらい実績のある人です」
「いろいろ話しているとその昔、UCバークレーのテニスチームで殿堂入りしているそうです。レッスンもいい加減だし、コーチングもお世辞にも高いレベルじゃない。しかし、たまにすごいボールを打つことがある。昔のテニスでフラット系のね。クラブのディレクターにいつも怒られているけど、彼は自分のペースを崩さない」
――日本での綛谷さんはどのような“テニス”を身に着けてきたのでしょうか。
「関西学院大学体育会庭球部出身で、大学3年まで(伊達公子さんらを育てた)小浦猛志さん、大学4年の時は細井禎蔵さんが監督でした。当時は創部以来、初めての関西学生リーグ2部時代でしたが、お二人ともよくコートに来て下さいました。技術論よりも精神的なこと、練習への取り組み方を教わりました」
「小浦監督の指導で今でも思い出に残るのは、割り箸を口に咥え素足でコートに立ってボールを打つ練習です。2学年先輩がやられていたのですが、『足の裏で地面をちゃんと捕まえなあかんで』と。そのほかにも、2時間のサーキット練習のメニューを考えていましたね。1面はストローク、このコートはボレー、こっちは2対1の振り回しみたいな練習がメニューになっていました。今では珍しくないですが、当時の練習の仕方を変えたのは小浦さんが初めてでした」
「それともう1つ、選手に練習ノートが配られ、各自がその日に取り組んだことなどを書き込み、マネージャーを介して小浦監督に渡すんです。監督はそれに気が付いたことを書き込み返してくれます。このノートのやりとりも画期的でした、監督と部員の交換日記ですね。庭球部の部員は約30人で十分な練習ができるのは本戦に上がっている選手のみ。コートの周りを部員が囲んでいる中での練習でした」
――日本では「道具を大切にしなさい」と教わりますが、アメリカではラケットは「モノ」なので簡単に投げたり、蹴ったりする光景を見ます。「全てのものに神が宿る」というような考え方が無いので、それはまた人間のアクションとして賛同はしないけれど許容していかなければいけないところもありますか?
「昨今のプロでも道具を大切にしないというか、見ていて不愉快になることが多々ありますよね。ここの子供たちもほんとにラケットを粗末に扱います。それは一言で言えば“テニス”と“庭球”の違いのように思います。“テニス”を“庭球”と訳した時点で脈々と受け継がれてきたものがあります。うちの大学もそうだし早稲田や慶應も”庭球部”。庭球を教わった私としては、そういう部分で考えていくとでもどうしても捨てられないところがある。むしろ捨ててはいけない部分と捨てられない部分があるような気がするんですよね。だからラケットを単にモノとして扱うことには抵抗があります」
「佐藤次郎さんが世界で活躍した1930年代前半、テニスは庭球でしたね。ウィンブルドンでイギリス国王が入ってきたら試合中にもかかわらずひざまずき挨拶する選手もいたそうです。テニスが“庭球道”として日本で根付き、それが脈々と受け継がれる傍らで世界はどんどん変わって行きました。ヨーロッパの選手たちが頭角を現し、彼らは生きるためにテニスをやり、勝つことに執着します。勝てば官軍。品格など二の次の選手たちがどんどん増え、ラケットを壊すことによる負の側面より、ものすごいストレスを感じながらプレーしていることに関して、彼らに理解をすることが必要とする人も少なくありませんね。それでも私には“庭球”が心の奥底にあり、捨てられないものを持ちながら自分の存在意義は何かと自問しながら日々コートに立っています」
――今後の活動について教えてください。
「中学1年でテニス始めたのが1972年ですからね。その時に64歳になってこういう風にテニスに関わっているということは全く想像できませんでした。そもそもアメリカに来たきっかけはテニスじゃないですからね、なのに、最後に残ったのがテニスという。将来的には日本へ帰国し、日本にいる外国人向けに教えてみたいですね」
――貴重なお話をありがとうございました。