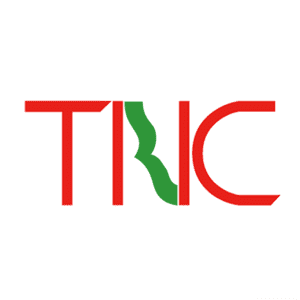猛暑が続く中、注意が必要なのが食中毒です。
飲食店も対策を徹底する中、家庭でも対策が求められています。
北九州市小倉北区の西南女学院大学では、19日の昼休み、太陽が照りつける中、広場にずらりとキッチンカーが並びました。
静岡名物「富士宮やきそば」が人気のキッチンカー。
静岡から取り寄せた専用の麺とソースの相性は抜群。
さらに、オリジナルの塩ダレとからんだ塩焼きソバは、さっぱりとしていて、暑い夏に人気の商品です。
ただ、これからの時期、心配なのが食中毒です。
◆Kitchin Car3776 酒井正三さん
「食中毒が1番怖いので、その辺は一番気にかけてます」
こちらのキッチンカーで1番気を使っているのは、食材の温度管理です。
冷蔵庫の中を見せてもらうと、キャベツや麺が入っていました。
多いときで60食分を用意しているということです。
◆Kitchin Car3776 酒井正三さん
「暑くなると食材が痛んできますので、冷蔵のものは冷蔵でちゃんと保管する」
また、調理過程で食材にきちんと火が通るよう工夫もー。
◆Kitchin Car3776 酒井正三さん
「お湯をかけて水蒸気で蒸していて、火を通りやすくして(具材を)広げて均一に温度が入るように」
さらに、手指の消毒も頻繁に行い、万が一にも食中毒を起こさないよう、とにかく対策を徹底しています。
◆Kitchin Car3776 酒井正三さん
「安心して食べていただけるように、衛生管理の方は徹底しておりますので、安心して来ていただきたい」
北九州市では、気温25℃、湿度70パーセントを2日連続で超えたことを受けて、17日から「食中毒注意報」を発令しています。
食中毒で気を付けていることを、街の人に聞いてみました。
◆街の人
「お弁当。お腹壊したら大変」
◆街の人
「子供のお弁当とか。一旦ご飯を入れたら冷ますとか」
家庭で弁当を作る際、食中毒を防ぐためのポイントを、管理栄養士の室井由起子さんに伺いました。
◆九州栄養福祉大学 管理栄養士 室井由起子 准教授
「きょう作るのは、“食中毒に強い”弁当になります」
大切なのは、菌を増やさない環境づくりだといいます。
◆九州栄養福祉大学 管理栄養士 室井由起子 准教授
「煮物は美味しいけど、汁気が出てしまって、汁の部分から菌が増える原因になる。できたら炒め物がいい」
食中毒菌が繁殖しやすくなる水気を極力減らす必要があるため、きんぴらごぼうなどの炒め物が弁当におすすめだということです。
さらに食中毒を防ぐために欠かせないのがー。
◆九州栄養福祉大学 管理栄養士 室井由起子 准教授
「梅干しを使っていきます。抗菌作用もあって菌を増やさないため、夏の和え物にいいと思います」
梅干しには、細菌の繁殖を抑える抗菌作用があります。
梅干し以外では、酢の物にも同様の効果が期待ができるということです。
さらに注意が必要なのが、前日の夕食で出したおかずの再利用です。
◆九州栄養福祉大学 管理栄養士 室井由起子 准教授
「作り置きで、夕ご飯でいっぱい作ったものを使うとき、再加熱して冷まして入れることがポイント」
冷蔵庫でも、食品の中の菌は繁殖するため、必ず再加熱をしてしっかり冷ます必要があるということです。
◆九州栄養福祉大学 管理栄養士 室井由起子 准教授
「ミニトマトを(そのまま)最後、お弁当に入れてしまいがちですが、ここが最後のポイント。ヘタを取ってもらって、ヘタと間の部分に特に細菌がたまりやすいので、しっかり水分をとることがポイント」
弁当を持ち運ぶ際は保冷剤とともに保冷バックに入れることが望ましいということです。