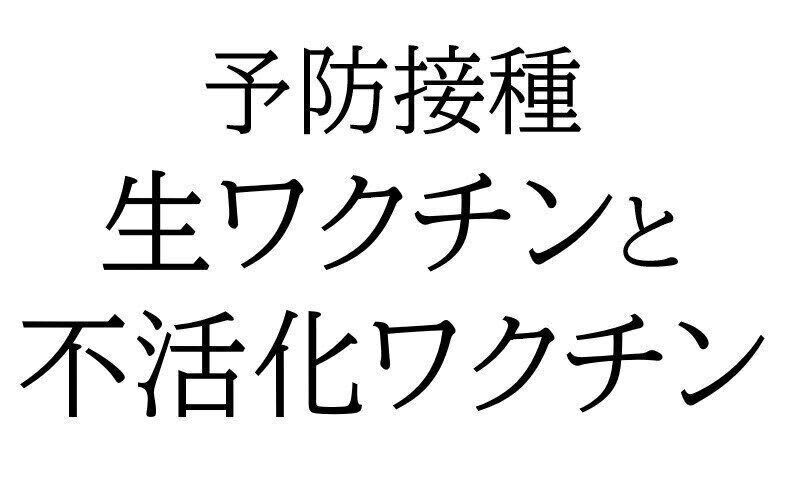
予防接種で使用する「ワクチン」とはどんなもので、どのような方法で接種するのか気になりますね。また、副反応についても心配です。小児科医で神奈川県衛生研究所 所長多屋馨子先生に教えてもらいました。
ワクチンは作られ方によって大きく4つに分類されます
予防接種には「ワクチン」と呼ばれる薬剤を使用します。ワクチンの原材料は感染症の原因となるウイルスや細菌で、作り方によって4つの種類があります。
【生ワクチン】生きた病原体の病原性を弱めて作るもの
生ワクチンは、生きた細菌やウイルスなどの病原性を極力弱めて作るワクチンです。接種によって体内に取り入れて軽く病気にかかったような状態を作ることで、その感染症に対する免疫をつけます。接種することで得られる免疫は強く、自然感染で免疫がつく場合とほとんど変わりません。
注射の生ワクチンの接種後、別の注射の生ワクチンを接種する場合は、中27日以上空けます。
2020年10月から、飲むタイプの生ワクチンは、別の種類のワクチンを接種するまでの間隔に規定がなくなりました。ただし、同じ種類のワクチンを複数回受ける場合は、これまでどおりワクチンごとに接種間隔が決まっているので、注意が必要です。
生ワクチンの代表的なものについて
ロタウイルスワクチン(飲むタイプの生ワクチン)
BCGワクチン(注射の生ワクチン:スタンプ式)
MR(麻疹・風疹混合)ワクチン(注射の生ワクチン)
麻疹ワクチン(注射の生ワクチン)
風疹ワクチン(注射の生ワクチン)
水痘(水ぼうそう)ワクチン(注射の生ワクチン)
おたふくかぜワクチン(注射の生ワクチン)
黄熱ワクチン(注射の生ワクチン)
インフルエンザワクチン(鼻から吸うタイプの生ワクチン)※2024年秋以降の開始
など
【不活化ワクチン】病原性を完全になくして作るもの
病原体をホルマリンなどで処理したり、必要な成分だけ取り出したりして作るワクチンが不活化ワクチンです。接種によって生ワクチンほど十分な免疫は作れず、一定期間を過ぎると免疫力が弱まってくるので、複数回の接種が必要になります。
2020年10月から、別の種類のワクチンを接種するまでの接種間隔に規定がなくなりました。ただし、同じ種類のワクチンを複数回受ける場合は、これまでどおりワクチンごとに接種間隔が決まっているので、注意が必要です。
不活化ワクチンの代表的なものについて
肺炎球菌(13価または15価結合型)ワクチン
B型肝炎ワクチン
五種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ・ヒブ)
四種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風・不活化ポリオ)
三種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風)
不活化ポリオワクチン
日本脳炎ワクチン
HPV(ヒトパピローマウイルス)ワクチン
インフルエンザワクチン
A型肝炎ワクチン
髄膜炎菌ワクチン
狂犬病ワクチン
肺炎球菌(23価莢膜ポリサッカライド)ワクチン
RSウイルスワクチン
など
【トキソイド】細菌の毒素の毒性をなくして作るもの
細菌が生み出す毒素だけを取り出し、その毒性をなくして作るワクチンです。細菌が体に侵入して増殖したときに、ワクチンで作った免疫の働きで毒素を中和し、発病を抑えます。免疫をつける力は不活化ワクチンと同程度です。
2020年10月から、別の種類のワクチンを接種するまでの接種間隔に規定がなくなりました。ただし、同じ種類のワクチンを複数回受ける場合は、これまでどおりワクチンごとに接種間隔が決まっているので、注意が必要です。
トキソイドの代表的なものについて
二種混合ワクチン(ジフテリア・破傷風)
ジフテリア
破傷風
など
【mRNA:メッセンジャーRNA】病原体の遺伝情報をもとに作るもの
病原体のタンパク質を作るもととなる遺伝情報をもとに作ったワクチンです。mRNAは壊れやすいので、脂質からできた膜の中に包まれています。
新しい種類のワクチンなので、最初は同時接種や別の種類のワクチンとの接種間隔に制限がありましたが、現在は、飲む生ワクチンや不活化ワクチンと同様に、別の種類のワクチンを接種するまでの接種間隔に規定がなくなりました。ただし、同じ種類のワクチンを複数回受ける場合は、これまでどおりワクチンごとに接種間隔が決まっているので、注意が必要です。
mRNAワクチンの代表的なものについて
新型コロナウイルス感染症ワクチン
など
注射だけじゃない。ワクチンの接種方法は4種類あります
ワクチンの接種方法は、注射(皮下注射、筋肉内注射)、スタンプ式、経口、経鼻の4つです。
(1)注射<生ワクチン、不活化ワクチン、トキソイド>
・皮下注射
皮膚に斜めに針を刺して注射します。日本では多くのワクチンをこの方法で行います。
・筋肉内注射
垂直に近い角度で針を刺す方法。筋肉内注射は注射部位の腫れが少なく、皮下注射に比べて免疫獲得がやや優れているなどのメリットがあります。世界では、不活化ワクチンの接種は筋肉内注射がスタンダードですが、日本ではほとんどが皮下注射で行われています。
(2)スタンプ式<生ワクチン…BCGワクチン>
上腕の中央部(肩に近い部分はNG)に、スポイトに入れたワクチンを垂らし、針が9本ある管針という接種器のツバでのばします。のばした部分に管針を2カ所押しつけます。針あとが18個残ります。
(3)経口<生ワクチン…ロタウイルスワクチン>
ワクチンがスポイトのようになっていて、直接口に入れて飲ませる方法。針を刺さないので、赤ちゃんが痛い思いをすることはありません。接種後に吐いても再接種はしません。接種前後の飲食は控える必要があります。
(4)経鼻<生ワクチン…インフルエンザワクチン>
2024年の秋から、2才以上19才未満の小児を対象に、鼻から吸うタイプのインフルエンザワクチンが使えるようになります。海外では、以前から使われていたもので、日本でも2024年の秋から接種が可能となります。
同時接種の考え方
[2024年1月30日生まれまで]
1才6ヶ月ごろまでに接種するワクチンは11種類(ヒブ:4回(0才で3回、1才で1回)、肺炎球菌(13価または15価結合型):4回(0才で3回、1才で1回)、B型肝炎:3回(0才)、ロタウイルス:2回または3回(0才)、四種混合:4回(0才で3回、1才で1回)、BCG:1回(0才)、MR:1回(1才)、水痘:2回(1才)、おたふくかぜ:1回(1才)、インフルエンザ:4回(0才で2回、1才で2回)、新型コロナウイルス:3回(6ヶ月~)あり、接種回数は単独で接種すると29~30回にもなります。そのため、同時接種が行われることが多くなっています。同時接種の必要性や、同時接種する際の本数や接種部位などについて理解しておきましょう。
[2024年2月1日生まれから]
1才6ヶ月ごろまでに接種するワクチンは10種類(肺炎球菌(13価または15価結合型):4回(0才で3回、1才で1回)、B型肝炎:3回(0才)、ロタウイルス:2回または3回(0才)、五種混合:4回(0才で3回、1才で1回)、BCG:1回(0才)、MR:1回(1才)、水痘:2回(1才)、おたふくかぜ:1回(1才)、インフルエンザ:4回(0才で2回、1才で2回)、新型コロナウイルス:3回(6ヶ月~)あり、接種回数は単独で接種すると25~26回にもなります。そのため、同時接種が行われることが多くなっています。同時接種の必要性や、同時接種する際の本数や接種部位などについて理解しておきましょう。
同時接種で早く免疫をつけることで、子どもを感染症から早く守ることができる
同時接種とは、2種類以上のワクチンを1回の通院で別々の部位に接種すること。日本もここ数年で赤ちゃんに接種できるワクチンが増えましたが、それぞれ2~3回接種しないと確実に免疫がつかないものも多く、1回に1種類ずつ接種していたら時間がかかってしまい、その間にその病気に感染してしまうリスクがあります。
諸外国では20年以上も前からワクチンの同時接種が行われていて、同時接種の安全性は確かめられています。日本小児科学会も以下のような見解を述べています。
①複数のワクチン(生ワクチンを含む)を同時接種して、それぞれのワクチンに対する有効性について、お互いのワクチンによる干渉はない。
②複数のワクチン(生ワクチンを含む)を同時に接種して、それぞれのワクチンの有害事象、副反応の頻度が上がることはない。
③同時接種において、接種できるワクチン(生ワクチンを含む)の本数に原則制限はない。
<同時接種をすることのメリット>
・1種類ずつ接種するより早く終了でき、子どもを早く感染症から守ることができる
・同時接種することで受け忘れを防ぐことができる
・医療機関に行く回数を減らせる
同時接種をせずにワクチンを接種する場合、2ヶ月から1才6ヶ月ごろまでに25~26回の通院が必要。同時接種にすれば、最少で6~7回の通院にとどめることができます。
同時接種の本数・接種する部位について
●本数
同時接種するワクチンの組み合わせは自由です。生ワクチン+生ワクチン、生ワクチン+不活化ワクチン、不活化ワクチン+不活化ワクチン、どの組み合わせでもOKで、経口と皮下注射、筋肉内注射、経鼻など接種方法を組み合わせても問題ありません。定期接種と任意接種の同時接種もできます。
本数の制限もありません。欧米では、2ヶ月の赤ちゃんに複数のワクチンを同時接種するのが普通です。
●接種する部位
大きな血管や神経がない上腕の外側か太ももの前外側に打ちます。といっても、同時接種するワクチンすべてを体の別の場所に打つ必要はなく、1インチ(2.54cm)離せば、同じ腕や太ももに接種しても問題ありません。同じ注射器の中に複数のワクチンを混ぜて接種することはできません。
ただし、不活化ワクチンを前回と同じ場所に接種すると腫れがひどくなることがあるので、腕を変えたり、太ももに接種したりすることもあります。
ワクチンの副反応について
副反応とは、ワクチンに反応して出る症状のうち、目的としていない反応のこと。ワクチンはウイルスや細菌の病原性を弱めたり、なくしたりしたものを接種するため、軽く病気にかかったような状態になります。そのため、好ましくない反応ができるのは自然のことなのです。ほとんどの場合は、数日で自然に回復します。
ワクチンによって副反応が現れる期間や症状は異なります。
不活化ワクチンでは接種1週間以内に現れることが多く、まれに2~3週間後に現れることもあります。
生ワクチンは1ヶ月以内に現れることが多く、BCGは5~6週間後に副反応が出る可能性もあります。
<副反応の主な症状>
・接種部位が赤く腫れる
・発熱や発疹
・その病気にかかったような症状
・けいれん(発熱時に) など
<副反応の主な要因>
・注射のしかたによるもの
皮下注射を接種した位置に血管があると、内出血を起こすことがあります。また、針を浅めに刺した場合は、赤い腫れが生じやすいようです。いずれもごく軽い症状で済みます。
・ワクチンの成分自体によるもの
接種したワクチンの成分により、その病気の症状が軽く出たり、接種した部位が赤く腫れたり、熱が出るなどの症状が出ることがあります。ただし、接種後に風邪をひくと、副反応のように見えることもあります。
・ワクチンに添加される成分によるアレルギー
ワクチンには主成分以外にも、安定剤や保存剤などの添加物が含まれていることがあり、これらの成分によってアレルギーが起こることがあります。でも最近では可能な限り、添加物を除去する努力がされています。
ワクチンの接種方法には飲むタイプ、皮下に注射するタイプ、筋肉内に注射するタイプ、ハンコのようにスタンプ式で接種するタイプ、吸うタイプがあり、ワクチンの性質に合わせた方法で接種されます。2024年の秋から、鼻から吸うタイプのインフルエンザワクチンが使えるようになります。以前は「1回に1つのワクチンを接種する」のが日本の予防接種の定番でしたが、接種できるワクチンが増えたことで、最近は同時接種が一般的になっています。これらの現状を理解し、確実に必要な予防接種を受けるようにしましょう。
情報提供/多屋馨子先生
取材・文/東裕美、ひよこクラブ編集部
●記事の内容は掲載当時の情報で、現在と異なる場合があります。

