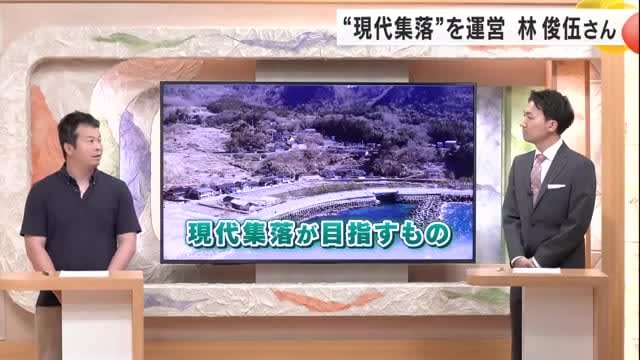
金曜日のイットは、能登に根差した「能登人」をゲストに招き、その思いを伺っています。
金沢市出身の林さんは妻の佳奈さんとともに、町家を使った一棟貸切りの宿やゲストハウス“旅音”を運営しています。
その後、2020年に能登にほれ込み珠洲市に移住し100年後も豊かな営みとは何か、実験し奮闘しています。
きょうは『現代集落』の取り組みについて話したいと思います。
林さんのライフワークは、「100年後も家族で暮らしたい、働きたい地域を作る」ことです。
そのための豊かな暮らしとは何か?を実験しているのが珠洲市真浦町で始めた『限界集落』ならぬ『現代集落』です。
いまは東京や金沢から60人の人たちが運営にかかわっていて、エネルギーや食の自給自足などを話し合ってきました。
例えていうならば、今まで100人で維持していた集落の営みを半分以下の人数でどうテクノロジーをつかって快適に維持していくのか、草刈り機やインフラの維持もテクノロジーを使ってより効率的にできないかを志向し考えています。
林さんは能登半島地震の発生時は金沢にいましたが、現代集落がある真浦町は道路が寸断され、孤立しました。
借りていた古民家は一部の損壊で大丈夫でしたが、私は地震発生後すぐに二次避難者を受け入れる宿泊先を手配したり、衣類の無償提供の取り組みを行ったりしてきました。
今回の能登半島地震はインフラなどのライフラインを一つに頼っていてはいけないのだということを強く感じました。
そして地震後、能登への思いが強くなりました。
能登は半自給自足な里山里海の営みが魅力で、これは本当にかけがえのないものだと思います。
今回の地震で、我々が考えていたビジョンを、10年20年先にやわやわと実装するのでなく、2~3年で実装しないといけないと理解しました。
現代集落を視察してもらったのは東工大の坂村先生と環境エネルギー政策研究所の飯田さんです。
能登半島地震で、奥能登の集落を持続可能な暮らしにするためには「災害時には孤立する可能性がある」ということを前提にしなければいけないと感じました。
そのため、マイクログリッド化、つまり電気、熱、水をある程度自給自足しなければいけないということです。
これは県の復興プランにも明示されています。
今回、専門家の先生にみていただいて、里山里海の暮らしを最新技術でアップデートしていく必要があると思っています。
また奥能登の魅力の一つは街並みだと思っています。
復旧に向けたスピードが遅いことは間違いないのですが、そこに住む人がいなければ、以前のような景色を取り戻すことは難しいと思っています。
そこで古民家一棟貸しなど金沢で「旅音」としてやってきたビジネスモデルを珠洲でも行おうと思っています。
というのも、直したら使える家があるのに使う人がいないために解体が加速度的に進むと考えるからです。
すべて壊してしまっては街並みは戻りません。
まずは復旧・復興に携わる人の宿泊施設を貸し出そうと思っていて、何人かから声がかかっています。
今後は支援者や一時帰宅者の宿泊先として運営を行いながら奥能登の交流人口拡大につなげていけたらと思っています。
現状の回復がままならないなか、未来のことを考えることはとても苦しいと思いますが、我々もあと30年くらいしか生きられません。
だからこそ、その先の先の世代にどんな能登を渡したいかを考え未来を創造し、そこを見据えた復旧からの復興が大切だと思います。
