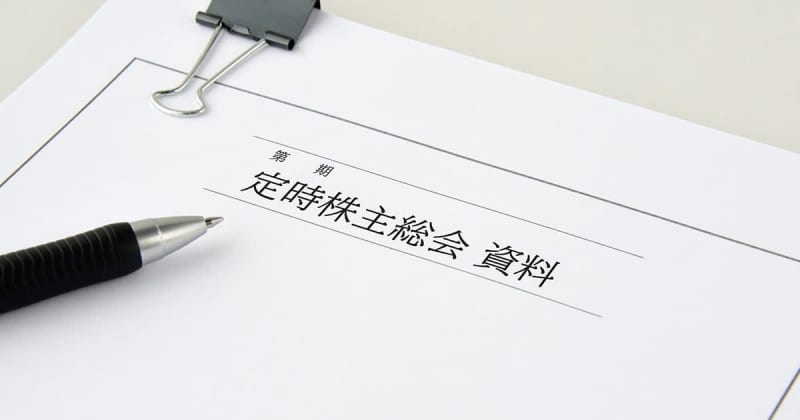
日本の多くの上場会社は決算月末日を基準日としているため、決算月の3か月後に株主総会が開かれるケースが多くなっている。日本では6月が株主総会の季節となっているのは、3月決算会社が多く、3月が基準日となっているためだ。そんな慣例に、日経新聞の上級論説委員兼編集委員である小平龍四郎氏が疑問を投げかける――。
バークシャーの株主総会では「ショッピングイベント」が実施
米著名投資家ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハザウェイが5月4日(現地時間)、米中西部ネブラスカ州のオマハで年次株主総会を開いた。日本からの参加者は大イベントをこう伝えている。
「バークシャー・ハサウェイの株主総会は、大きく3日間に分かれて開催されておりまして、1日目が株主向けのショッピングイベント、そのあとにカクテルパーティ。2日目が株主総会本番、そのあとに屋外で軽食イベント。3日目にチャリティーマラソンということです」
「1日目のショッピングイベントの模樣をご紹介してまいります。そもそもショッピングイベントってなんなのかというお話なんですけれども、主にバークシャーが投資する企業、例えばIBMとかコカ・コーラとかウェルズ・ファーゴとか、いろいろとありますけれども。そういった企業がいろいろなブースを出展しておりまして、そこで特別価格で特別製品を購入できるというイベントということです」
「真ん中のステージにバフェットとマンガーが座って、株主からの質問に回答するわけなんです」
「実際には、もともと最初から受け付けていた(質問)メールとあとは会場(質問)がバフェットやマンガーに投げられていくシステムですね」
(マネックス証券株式会社 フィナンシャル・インテリジェンス部の益嶋裕氏と同社トレーダー・サービス部の西尾貴仁氏の報告記より抜粋)
スケールや議論の中身など、何から何まで日本企業の株主総会と異なり、おいそれと「バークシャーを見習え」とは言えないだろう。しかし、その気になれば日本企業もバークシャーの株主総会に近づける点がひとつある。それは、総会の開催日だ。
バークシャーの株主総会時期が多いのは「投資の神」ゆえのお目こぼし?
米国では四半期の決算ばかりが注目されるため、日本流の本決算への意識はあまり高くない。それが唯一、意識されるのが株主総会のタイミングだ。バークシャーは12月末締めの財務諸表を年次報告書に開示しているので、日本流にいえば「12月期決算会社」だ。
そのバークシャーが株主総会を開いたのが5月4日。決算期末から5か月余り経過したのちだ。日本の感覚ではかなり遅い。投資の神様だから株主総会の開催が遅くても当局からお目こぼしをいただいているのか?
日本は他国に比べ株主総会の開催時期が早い
いや、そんなことはない。決算期から5か月ほど経った後の株主総会は米欧では標準の日程なのである。データを示そう。
米国企業は決算期末から平均135日、4.5カ月後に総会を開く。英国は137日、4.6カ月後、ドイツは151日、5.0カ月後だ(「持続的成長に向けた企業と投資家の対話促進研究会 報告書」2015年4月から)。日本は85.0日、2.8カ月後と短さが際立っている。筆者がこの原稿を書いているのは6月中旬だから、ちょうど3月期決算会社の総会シーズンが始まろうという時期だ。
一般に日本の市場関係者は情報開示が早いほうが良いと考え、あらゆる開示改革は「さらに早く」「もっと多く」の方向性で進められてきた。決算終了から短期間で株主総会を開催するのも望ましいことだと思いがちだが、コトはそれほど単純ではない。主要な機関投資家たちが日本企業に対し「株主総会前に有価証券報告書を開示せよ」と求めているからだ。
3月期決算会社の7月総会には識者も「良い考えだ」
世界の主要年金や資産運用会社が加盟する国際コーポレート・ガバナンス・ネットワーク(ICGN)のケリー・ワリング前最高経営責任者が、岸田文雄首相に「有報の総会前開示」を求めたことがある。日本のガバナンス改革に数々の助言をしてきたICGNがくり返し提案してきたことだが、ほぼ手つかずのまま今日まで来てしまったテーマのひとつだ。現状で総会前に開示しているのは30社程度にすぎないという。
多くの日本企業は定款で決算期末を定時株主総会基準日とし、そこから3カ月以内に総会を開く。定款変更で基準日を後ろにずらすなどすれば、3月期決算会社が7月に総会を開ける。そうなれば6月に有報を開示し、それに基づいて株主が議決権行使の考えを決めることができる。
筆者がワリング氏に確認したところ、総会30日前から議決権行使のために有報を読めるのであれば、3月期決算会社の7月総会は「良い考えだ」と語っていた。加盟社の運用総額が77兆ドル(約1.2京円)に達する国際的投資家団体のトップがこう言うのだから、7月総会に株主から大きな異論が出るとは考えにくい。
それでもなお6月総会へのこだわりがあるとすれば「1年間の会社行事のスケジュールを変えたくない」「総会で難しい質問が増えると困る」といった、現状追認バイアスが作用している可能性もある。
独自の進化を遂げた日本企業の招集通知に対しては“一定の支持”
「商事法務」(2024年6月5日号)の匿名コラム『スクランブル』には、株主総会の7月開催についてこんな指摘もあった。
「テクニカルには配当基準日と議決権基準日のずれの適否、年度末を越えてなお半年近く経営陣の人気が続くことへの妥当性のほか、株主総会の準備期間が長期に及ぶことへの負担感、年度が明けて将来に向けて切り替えて経営を再スタートすべき時期とのバランス、そして日本固有化もしれないが真夏の真っ只中で開催することへの健康問題(特に高齢の来場株主や外回りスタッフの熱中症の懸念)等があり、歩みは進まない現状ではないかと思われる」
「有価証券報告書の総会前提出を論じる前に、ガラパゴス的に独自の進化を遂げた日本企業の招集通知を拡充していくアプローチも考えられてよいのではないか」
大企業で株主総会を長年取り仕切ってきた総務部的な発想のコメントであり、支持する向きも多いのではないかと思われる。
はたして「9月総会」は実施できないのであろうか
これに対して、米欧の投資家と接点の多い企業のIR(投資家向け広報)担当者からは、こんな声がある。
「7月総会が気候の面で問題があるというのであれば、いっそのこと9月総会という手もあるはず」
「欧米企業の株主は年次報告書の内容をみて議決権行使を決めている。内容はあまり変わらないとはいえ、日本流の招集通知では違和感が残る」
この問題、株主総会を取り仕切る総務部と、投資家と接点を持つIR担当部署との感性が反映されているようであり、実に興味深い。6月の一か月間集中している株主総会が7~9月に分散するようになれば、総会に向けての企業と株主との対話がさらに促進されるし、日本企業の変身も印象づけられる。
一社でも二社でも「9月総会」に移行する企業は現われないものだろうか。

