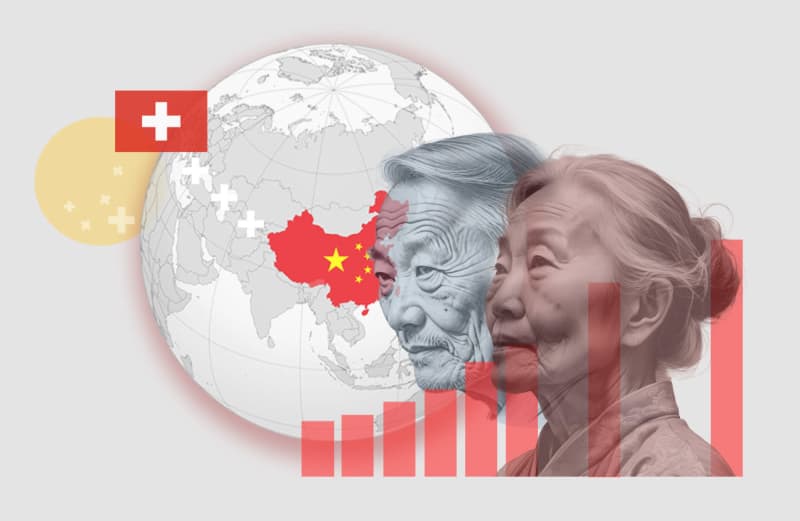
急速な高齢化と中流階級層の拡大が進む中国で、これに目を付けた2つのスイスの医療機器メーカーが新たな商機を探っている。
高齢化は世界共通の現象だが、中国は突出している。中国の国家衛生健康委員会は60歳以上の国民が2035年までに全人口の3分の1に当たる約4億人に増えると推計する。13年間で1億人も増加する計算で、4億人は欧州連合(EU)総人口に匹敵する数だ。
高齢化に伴い医療需要も増えると予想され、世界の大手医療・製薬企業がこの急成長市場に目を向ける。世界最大の補聴器メーカーであるソノヴァや、糖尿病患者向けインスリンポンプを製造するイプソメッドなど、スイス勢も例外ではない。
ソノヴァ中国支社の方芳氏は「中国が戦略的に重要である最大の理由は高齢化だ」と話す。「毎年、フランスやドイツの総人口の半分に匹敵する人数が当社の顧客層となる年齢に達する」
マッキンゼー・ヘルス・インスティテュートは、アジアの65歳以上の人口は2050年までに16億人に倍増すると予測し、「歴史上最も重大な人口動態変化の1つ」になるとみる。新興経済国の中で最も高齢化の速度が速い中国では、その傾向が最も顕著に表れる。
平均寿命の延びも拍車をかける。2021年時点の中国国民の平均寿命は78歳超と、2010年より4年近く延びた。中国疾病予防管理センターと南京理工大学によると、2035年までには81歳に延びる可能性がある。
寿命が延びれば、それだけ病気にかかる可能性も増える。世界保健機関(WHO)の試算によると、中国の60歳以上人口の約75%が糖尿病やがん、心血管疾患など慢性疾患を抱える。米国では60歳以上の国民の95%(全米高齢者評議会調べ)が少なくとも1つの慢性疾患を抱える。
これらは中国経済や消費、政府支出に多大な影響をもたらす可能性がある。マッキンゼー・グローバル・インスティテュートが昨年発表した報告書「多国籍企業にとっての中国の重要性」は、「特定の分野では需要が増減する。例えば医療支出が増加する一方、高齢化社会にとって緊急性の低い商品・サービス支出は減る」と予想する。
中国企業との信頼関係
糖尿病の自己治療用注射・点滴システムを製造するイプメソッドは、そんな中国の人口動態の変化を追い風とする企業の1つだ。シモン・ミシェル最高経営責任者(CEO)は「中国の潜在力は非常に大きく、間違いなく当社の急成長事業の1つだ」と語る。
「当社は中国でインスリンのペン型注射器と液体薬剤の塗布機器を製造する唯一の西洋企業だ。非常に優れたネットワークを持ち、中国の大手製薬会社と緊密な関係を築いてきた」
中国は世界最大の糖尿病市場だ。国際糖尿病連合(IDF)財団によると20~79歳の成人の13%、実数にして1億4000万人超が糖尿病に罹患する。スイスではわずか6%だ。IDFは人口の高齢化や不健康な食生活の増加、運動不足により、中国の糖尿病患者は2045年には1億7400万人以上に増えると推計する。
スイスのプライベートバンク、フォントベルのシニアアナリスト、シビル・ビショフベルガー氏は「中国の製薬会社はイプソメッド製ペン型注射器を気に入っている。ハイエンド製品であり、中国の同業他社と差別化が図れるからだ」と話す。
イプソメッドにとって中国は欧州外で最大の市場だ。ペン型注射器は使い捨て5億本、再利用型1000万本が現在流通しているとみる。中国製薬会社への売上げは約5000万ドル(約80億円)と、グループ全体の9%を占める。ミシェル氏は10年後にはこれが15%に伸びると予測。肥満、糖尿病、アルツハイマー病、がんなど「注射が必要な新薬が数多く登場し、需要が激増している」と話す。
同社は中国の需要増の取り込みに懸命だ。2023年4月には上海の北西約190キロメートルに位置する常州(人口530万人)に新製造工場を建設した。直近の年次報告書は、現地生産により時間や輸送費が節減され、中国のパートナーとの信頼関係も向上すると位置づけた。製品が中国内で登録されるため、中国の規制変更にも適応しやすいという。
新工場の建設にこれまで1億フランを投じた。今年10月に製造を開始する予定で、最終的に約200人を雇用する。ミシェル氏は、来年にはさらなる拡張計画を決定すると話す。
「当社は確実に肥満分野で成長を続け、大きな役割を果たすようになる。そのために土地の投資・買収を増やす予定だ。年間数百万本の注射器を生産することも検討している」
補聴器への偏見
中国の人口動態の変化に乗じるもう1つの企業がソノヴァだ。「フォナック」「ゼンハイザー」「ユニトロン」といったブランドで補聴器を販売する世界最大手で、年間総売上高は37億フランに上る。100カ国以上で事業を展開。最大の市場はドイツと米国だが、重点を置くのは多大な成長可能性を秘めた中国だ。
2022年からソノヴァの中国事業を率いる方氏は「中国には60歳以上人口が2億8000万人を超え、団塊世代が65歳以上になれば顧客はさらに増える。世帯収入も過去10年で激増した」と話す。
政府統計によると、2023年の中国の平均可処分所得は年3万9218元(約85万円)と、2010年の1万2520元に比べ3倍以上に増えた。中国政府は2023年に発表した長期計画で、2035年までに国民1人当たり所得を2020年比で倍増させる目標を立てている。「自家用車を持てるようになった家庭は、やがて補聴器など医療サービスへの支出を増やす」(方氏)
方氏自身、重度の難聴を抱える義父を持つ。片耳は完全に聞こえず、40年前からソノヴァ製補聴器を愛用する。「義父は6歳から14歳になるまで解決策がなかった。ごくわずかの聴力が残る片耳だけで幼少期を過ごし、苦労が多かった」
ソノヴァはいち早く中国の成長可能性に着目し、2003年には中国初となる蘇州工場を建設した。2014年には現地向け補聴器の開発も始め、中国での存在感を高めた。
最大の飛躍は2022年、販売拠点を増やすために実施したハイサウンドグループ買収だ。これにより中国70都市に約200カ所に販売網が広がった。中国での雇用数は650人と、同社が全世界で雇用する社員の1割を占める規模に膨らんだ。
補聴器の需要は世界的に拡大を続けている。欧州補聴器製造者協会(EHIMA)によると、2017年に1505万個だった販売数は2022年に2025万個に増えた。高齢者の聴覚ケアへの意識が高まれば市場はさらに広がりそうだ。EHIMAの調査によると現在中国人口の4.2%が難聴に悩むが、補聴器を使うのはその1割弱にとどまる。
方氏は、中国は潜在力を秘めつつも、事業拡大には時間がかかるとみている。ソノヴァは中国の難聴患者のうち聞こえ環境を調整できる補聴器を持つ人は3%未満だと推計する。普及率の低さには、補聴器が必要なほど難聴が深刻であると患者が認めたがらないこと、補聴器は不快だという先入観があることなどが背景にある。
調達制度の課題
中国では補聴器にも偏見があり、補聴器の必要な人が使用をためらう原因となっている。方氏は、最初の診断から補聴器を初めて購入するまでに6~7年かかると見積もる。「以前は、補聴器を付けている人は障がい者とみなされていた。私たちはその偏見をなくさなければならない」
「中国の補聴器市場はまだまだ発展途上だ」。スイスのチューリヒ州立銀行で医療技術・機器企業のシニアアナリストを務めていたダニエル・ブフタ氏はこう話す。だが「人口規模や急速な高齢化、そして聴覚を改善するための代替手段について医療専門家や消費者を教育する動きが広がっている」ため、伸びしろは大きいとみる。
ソノヴァは中国で聴覚ケアの専門家不足にも取り組んでいる。蘇州に「グローバル聴覚研究所」を設立し、専門家育成に当たる。上海、南京、武漢の3都市(人口計約5000万人)には、聴力を自己検査できる店舗「聴覚の世界」を開設した。
方氏は「患者や潜在的なユーザーが難聴についての認識を高められるよう取り組んでいる。聴力を保つための予防措置や、生活の質を大幅に向上させる方法を周知している」と説明する。
中国に進出する外国の医療企業は売上げを伸ばすだけでなく、中国政府が2018年に導入した「購入量ベース調達制度(VBP)」にも適応しなければならない。製薬会社に一定量の販売枠を約束する代わりに薬価引き下げを求める調達制度で、2019年に医療機器にも対象が拡大した。
フォントベルのビショフベルガー氏は「VBP導入は大きな挑戦だった」と話す。外国企業には中国企業は支払う必要のない輸入税もかかるため、さらに不利になる。「中国は、外国の同業他社から中国企業を守ろうとしているようにもみえる」
イプソメッドが「中国のための中国」戦略を掲げたのも、VBPへの対応が最大の動機だ。ミシェルCEOは、重要な商品を中国内で生産するよう政府が暗に圧力をかけているとみる。
ブフタ氏は「中国では歯科、聴覚、眼科、医薬品などのほとんどの分野が供給不足で、高齢化が大きな牽引役になっている。富の増加により1人当たりイノベーション支出も増加し、スイス企業はその恩恵を受けるはずだ」と予想する。
Edited by Nerys Avery/vm、英語からの翻訳:ムートゥ朋子、校正:宇田薫
