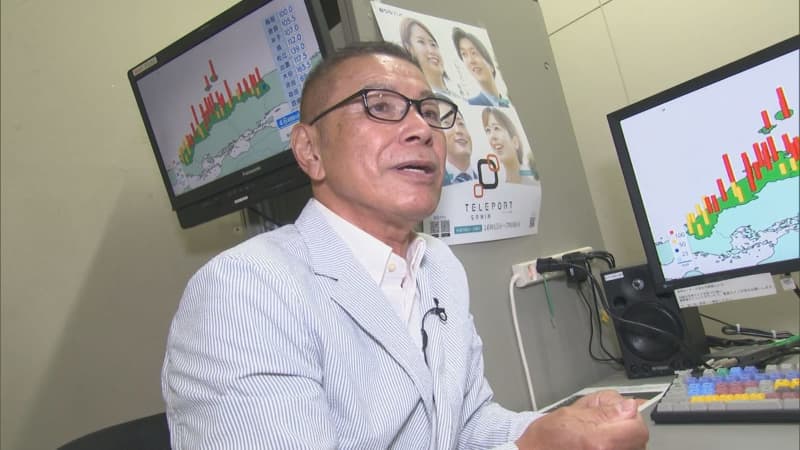
遅い梅雨入りのあと22日から23日にかけて山陰地方に降った今回の雨。
専門家からみると意外な降り方だったとのことです。
国土交通省 気象防災アドバイザー 近藤豊さん
「通常梅雨に入りますと中国地方の梅雨入りですので、瀬戸内海を中心として雨域が広がって、山陰地方に対しては曇りであったり若干雨がある程度という梅雨入りというのが、例年の雨のパターンなんですよね。」
「ところが今年は2週間遅れて梅雨に入った途端に、前線が日本海まで北上したという珍しいパターンです。」
今回の降り方はこれまでなら梅雨末期のようなパターンとのことです。
国土交通省 気象防災アドバイザー 近藤豊さん
「当初気象台あたりも警戒していたのは島根県西部を中心とした南下してくるタイプで前線の雨が降るのではないかとみていたが、実際は前線がどちらかというと東進しながらずり上がるように北上した。」
「200ミリを超えた雨雲が北陸に集まっているんですよね。こういうパターンは非常に梅雨末期に北陸とか上越、東北とかで降るというパターンと非常に似てましてですね。」
こうしたこれまでと違う降り方となる原因には地球温暖化の影響も考えられるのではないかと、近藤さんは考えています。
国土交通省 気象防災アドバイザー 近藤豊さん
「地球温暖化による影響は何かというと全体的な地球の温度もですけど、海水温なんですよ。今回梅雨前線の北上がちょっと遅かったなというのは、太平洋側の海水温は平年と比べて高くないんです。ところが、日本海側は例年に比べて3度も4度も高い。今回そういう高い海水温が影響したのかもしれないですけど、梅雨末期のような雨になって、こう降ったというところもあるかと思います」
そして遅かった梅雨入りの今年。梅雨明けはどうなのか、また、雨の降り方どうなるのでしょうか?
国土交通省 気象防災アドバイザー 近藤豊さん
「近年の梅雨の入り、明け、梅雨期間の降水量というのは、ものすごく波がある。1年ごとに大雨が降ったら次はカラ梅雨になるという形ですね。非常にパターン的に読めないところがある。通常の今までのような考え方で梅雨期を考えていると、警戒遅れであったり、逃げ遅れであったり、そういうことが起こりやすいということがいえます。」
近藤さんは、自分にとって危険なのは、洪水なのか、土砂災害なのかなど、それぞれの地域のハザードマップでチェックしておくことが重要だと呼びかけています。

