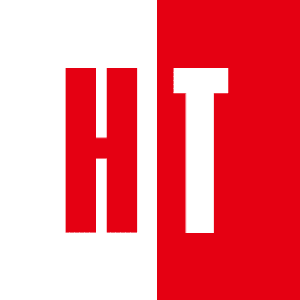2024年度が始まり、住宅関連の業界団体の総会が相次いでいる。社会環境、市場環境などが激変し、さまざまな課題が山積するなか、それぞれの業界はどこを目指し、何を行おうとしているのか―。総会や懇親会の場で、業界トップの言葉を拾った。

(一社)プレハブ建築協会「住生活向上推進プランを力強く推進」
(一社)プレハブ建築協会
仲井嘉浩 会長
本日をもって新会長に就任した。まず、就任にあたり「住生活向上推進プラン2025」をしっかり推進していきたいと考えている。このプランは、いわゆる良質なストック形成を一番大きな柱としている。プレハブ建築協会は、工業化住宅のメーカー、工業化住宅に資する部材のメーカーが集まっている団体で、良質なストック形成に向けて一番力を発揮できる団体だと思う。
プレハブ住宅、工業化住宅のもう一つの特徴として短工期、つまりリードタイムが短いということがあげられる。労働力不足が深刻な今の時代、短工期の技術が非常に強く求められている。また、能登半島地震のような甚大な自然災害において、緊急性が求められる応急仮設住宅の建築についても力を発揮できる存在ではないかと思う。
石川県からの要請もあり4200戸あまりの応急仮設住宅の供給に取り組んでおり、進捗状況は、5月末現在の完成引き渡しが累計3800戸。一日でも早く被災者の方々が安心して入居いただけるよう建設を進めたいと考えている。
「住生活向上推進プラン2025」の積極的に推進を図ることで、プレハブ住宅の普及促進に努めていきたい。
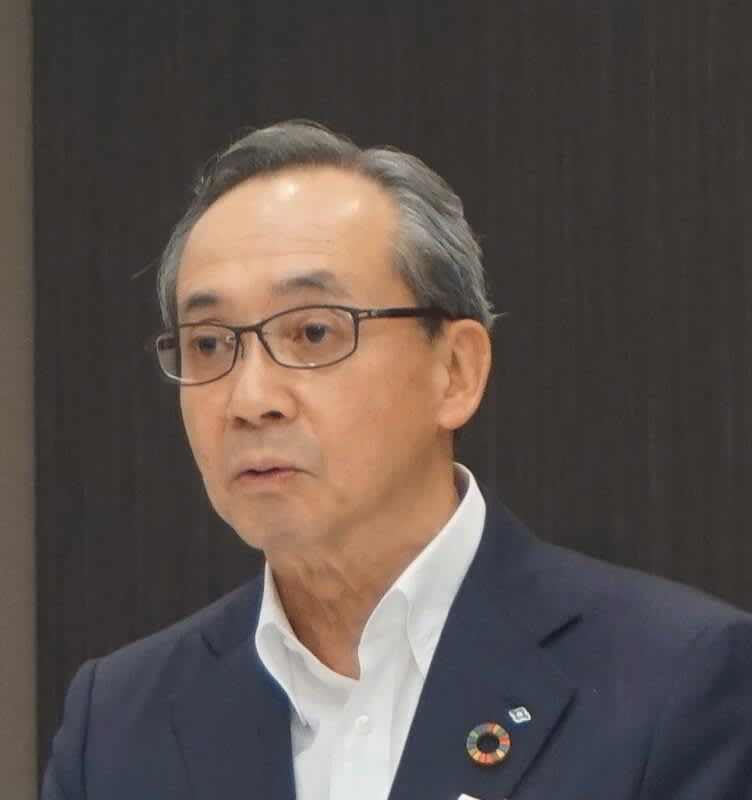
(一社)日本木造住宅産業協会「公共建築の木造化の気運を高めたい」
(一社)日本木造住宅産業協会
市川晃 会長
住宅業界は非常に厳しい状況にあるが、こと木造住宅業界に関しては、3省連携の「住宅省エネ2024キャンペーン」、また、林野庁の花粉症対策も含め、国産材の利用促進に向けた各種の支援策が行われている。
目指すところは、やはり住宅を必要とされている方々に向けてどれだけ良い木質の住宅を届けるかにある。厳しい状況にはあるが、協会全員の力でしっかりと取り組んでいく。
一方、最近、私が少し気になっているのが公共建築物における木造化だ。本来であれば、もっと増えていってほしいという気持ちがある。
例えば、学校関係の施設でいうと、一時は20%を超えていた木造校舎が最近のデータでは15%にまで落ちている。コロナの感染拡大や木材価格の高騰もあるが、もっと公共建築物の木造化の気運を高めていきたい。
木造戸建住宅のアスベスト除去を除く解体費用は200万から300万円程度であるのに対してRCは2倍以上かかる。木造住宅はしっかりと手を入れることで50年、100年もつが、いつかは建替え、循環をさせていくことが必要になる。解体費用まで見込んだ場合にどのような建物が一番適切なのかを考える必要がある。
一般建築についても、少なくとも中大規模クラスの建物であればRC造や鉄骨造に比べて耐用年数などについては十分対応できる。ライフサイクルで考え、CO2の吸収や固定なども考えコストを考えると、木造の価値が見直されていくのではないかと思っている。

日本繊維板工業会「〝炭素固定〟を武器に木質ボードを訴求」
__日本繊維板工業会
億田正則 会長__
2023年度の新設住宅着工戸数は約82万戸と、3年ぶりに減少に転じた。すでにウッドショックにより80万戸切りが予想されていたわけだが、若干先延ばしになったとはいえ、我々の業界にとって深刻な状況にあることは間違いない。
木質ボードが炭素を固定することが学術的にも証明された。厳しい状況下にはあるものの、これを大きな武器としてお客様に木質ボードをさらに訴求していきたい。
一方で、原材である木材のチップは、バイオマス発電と取り合いになっている。バイオエタノールの活用なども進みつつあるが、先々については分からない。木質系の環境を配慮した燃料の研究が進んでいるとのことだが、我々の分野との取り合いが起こるかもしれない。
我々はサーマルリサイクルではなくマテリアルリサイクルを推進している工業会であり、これからも新設住宅向けだけに限らない用途開発を、精一杯進めていきたいと考えている。

(一社)石膏ボード工業会「再エネ利用、リサイクルなどを推進」
__(一社)石膏ボード工業会
須藤永作 会長__
2023年度を振り返ると、緊迫する国際情勢のなか円安も加わり、原材料や燃料、物流などのコスト高騰により実質賃金が低下、建築価格が上昇して住宅の買い控えが続いている。こうしたなか、残念ながら石膏ボードの出荷も2019年の約5億円から4億4000万円へと低下している。
住宅関係では厳しい問題が山積みしているが、さまざまな優遇施策を続けていただいており、実質賃金上昇により住宅着工戸数が今年度の早い時期から上昇に転じてもらいたいと心から期待している。
一方、非住宅分野については、ゼネコン、設計事務所との連携を密にして中大規模の木造建築を推進。
また、都市再開発での提案に工業会として取り組んでいく。その一環として今年度より、石膏ボード賞に建築賞を創設、優れた作品を表彰して広く紹介させていただきたいと考えている。
環境保全について積極的に取り組んでおり、再生可能エネルギーを積極的に利用することによる製造時のカーボンニュートラルを推進していく。また、すでに約70%近くの国産石膏や、石膏ボードのリサイクル材を使用しているが、さらにリサイクル材の採用を推進することで、最終処分量の削減に貢献していきたい。
今後とも地球環境に調和した生産、販売活動、安全・あんしん、快適な住空間を提供するなくてはならない建材、石膏ボードを安定的に供給すべく、一層努力していく考えだ。

(一社)日本インテリア協会「ピンチをチャンスに変える発想力を持って」
__(一社)日本インテリア協会
永嶋元博 会長__
新型コロナが5類感染症に移行して1年が経った。生活行動様式を本来の形に戻していこうという動きとともに、コロナ禍で生まれた新たなスタイルを一緒にミックスするという新たな価値観も生まれつつある。こうした状況をよく認識したうえでインテリア業界にプラスをもたらすアイデアづくりが非常に重要だと感じている。
2024年問題が大きくクローズアップされているが、これはインテリア業界にも密接に関わるものであり、建設現場における工程管理、物流面での効率化、これらの待ったなしの取り組みが求められている。竣工間際の最終仕上げ工程のなかで、私共の製品を納めていただく工事業者様に適正な工期や納期が確保されているか、あるいは重くてかさばるもののデリバリーや搬入をどう改善していくか、それらにしっかりと取り組む必要があると考えている。ピンチをチャンスに変える、そうした発想力を持って会員とともに取り組んでいく。
11月にはジャパンテックス2024が開催される。昨年の企画展示は環境への取り組みでコーナーを設けたが、今年はさらに一歩踏み込んだ運営を検討中だ。業界をあげての祭典を大いに盛り上げていきたい。

(一社)日本シヤッター・ドア協会「施工者の確保・育成に注力」
__(一社)日本シヤッター・ドア協会
潮崎敏彦 会長__
わが国の景気は緩やかに回復しているとされるものの、2023年度は建築着工、住宅着工の減速傾向もあり、シャッターの出荷量は対前年度比10・5%減、ドアは2・7%増となり、特にシャッターはそれまでの底堅い動きから弱含みとなっている。
鋼材価格の高止まりが続いていることに加え、建築着工等の動向、あらゆる分野の人手不足、さらなる物価高の影響も懸念され、これらの動きを注視していく必要がある。
2024年度の当協会の活動は、まず、シャッターおよびドアの各種基準類の策定・改定、製品安全の確保に向けた取り組み。所定の性能を有するシャッターおよびドアの認定等は協会の基盤となる事業であり、引き続き着実に推進していく。
私たちの業界が抱える課題としては、まずは防火設備、定期検査報告制度の適切な実施などストック対策の推進。2番目にシャッター施工者の確保、育成に向けた資格制度の導入。3番目が浸水防止用設備等防災・減災に寄与する製品の普及などであり、これらに重点的に取り組んでいく。
定期検査報告制度は、検査の高度化、デジタル化を進める観点から制度の見直しが予定されている。従来からのストック対策に加え、より適切かつ円滑に実施されるよう会員への情報提供、情報共有につとめていく。
施工者の確保・育成や、施工品質の向上を図るため、昨年度、協会資格であるシャッター施工技能者資格認定制度を開始した。この資格の実績をベースに、今年度は、国家資格である技能検定制度への移行を目指し、そのための指定試験機関となる申請手続きを進めていく。さらには、建設キャリアアップシステムなどの導入につなげ、施工者の適切な能力評価や処遇改善に結び付けていきたいと考えている。