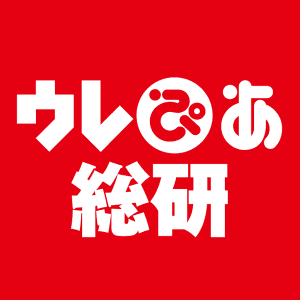「夫婦は一番近くの他人」という言葉があります。親や子は血がつながっているけれど、夫と妻は血縁上の関係はなし。戸籍という紙一枚でつながっている他人同士です。遺伝による性格や価値観、考え方の類似はありません。
そのため、どうしても分かり合えないことがありますが、今回取り上げる育児もそのひとつでしょう。付き合っているときは彼氏と彼女、結婚したら夫と妻、子どもが産まれたら父と母という感じに役割が変わっていきますが、残念ながら、役割の変化に対応できないケースもあります。
育児をする人の46%が精神的に疲れている現実
内閣府の調べ(令和5年、「子ども・子育ての現状と若者・子育て当事者の声・意識」)によると、子育てをして負担に思うこととして全体の46%が「自分の自由な時間が持てない」42%が「身体の疲れが大きい」、そして43%が「精神的疲れが大きい」と答えています。
とくに子どもは目が離せず、コミュニケーションもとれない時期は顕著でしょう。一番大変なときは夫婦が足並みを揃え、協力して乗り切らなければなりません。
出産後は子ども中心の生活になるのは当然です。子どものことを第一に考えて欲しいのに夫がまだ父親になりきれておらず、自分のことばかりを考えていたらどうでしょうか。
筆者は行政書士、ファイナンシャルプランナーとして夫婦の相談にのっていますが、育児をめぐって意見が合わず、喧嘩になる夫婦をたくさん見てきました。今回の相談者・平松樹里さん(仮名/会社員/34歳)もそんな一人です。
樹里さんは夫(仮名/会社員/36歳)と娘の礼音ちゃん(仮名/4歳)と一緒に暮らしていました。樹里さんの仕事はシフト制、夫はカレンダー通りなので、お互いに休みの日は娘さんを保育園に預けず、自分たちで面倒をみるように心がけていました。
しかし、夫が足を引っ張るせいで育児の負担が2倍、3倍に膨らむことに不満を抱えていました。なぜでしょうか?
4歳児に冷凍食品ばかり与える野菜嫌いな夫
まず第一に、樹里さんと夫は食育の考え方が大きく違っていました。樹里さんは「いろいろな種類の野菜や果物、肉や魚を、いろいろな料理にして子どもに食べさせてあげたい」と思っていました。とくに小さいうちは栄養バランスのいい食事を与えてあげたいそうです。
一方、夫はどうでしょうか?
樹里さんが不在の日、食卓に出てきたのは温めただけの冷凍食品ばかりだったそう。夫は台所で煮たり、焼いたり、揚げたりして手間を加えることをしようとしませんでした。もともと夫はかなりの偏食で、ほとんどの野菜を食べることができないので、付け合わせの野菜もなかったそう。
そこで樹里さんは「これじゃ礼音の栄養バランスが偏ってしまうし、このままじゃ近い将来に食わず嫌いになっちゃうよ!」と叱ったのですが、夫は「俺だって疲れているんだよ、休みの日くらいはゆっくりさせてくれよ!」と聞く耳を持たなかったそう。
「保育園で教えればいい」と夫はしつけを放棄
第二に、しつけに対する考え方も樹里さんと夫は正反対でした。娘さんが小学校、中学校、高校と進学するにあたり、恥ずかしくないようしつけをしなければなりません。身の回りのことなど最低限のことができないと、周囲に迷惑をかけてしまいます。
樹里さんは娘さんに「靴を脱いだら揃えて置くこと」を教えたところ、それ以降、玄関で靴を脱ぐときは、きちんと揃えてから家にあがるようになったそうです。
ところが夫はどうでしょうか。大の大人なのに靴を脱いだら脱ぎっぱなしで揃えようともせず、そのまま放置したことがありました。しかも運悪く、娘さんがその行動を目にしてしまったのです。
そこで樹里さんが「せっかく教えたのに!」と注意したのですが、夫は「そんなことは保育園で教えてもらったらいい!」と意に介さない様子。
樹里さんは「保育園よりも、まずは家で親が基本的なことを教えるべきでしょ!」と畳みかけたのですが、夫は両手で両耳をふさぎ、自室へ逃げ込んでしまいました。

妻の育児の邪魔をする夫と喧嘩が絶えない日々
第三に親としての姿勢です。これは子どもにどう思われたいかですが、樹里さんは娘さんの手本となるように努めていましたが、一方の夫はそうではありませんでした。
例えば、樹里さんが礼音ちゃんに箸の持ち方を教え、ようやく補助がついた子供の用の箸を使えるようになった頃のこと。夫は「そんなことはしないでいい! スプーンを使ったらいい!」「箸で突き刺したらいい!」などと言い放ったのです。
夫は何もしなければ、少なくとも無害かもしれません。しかし、夫のやることは樹里さんの邪魔であり、娘さんにマイナスの影響を与えかねません。樹里さんと夫が娘さんの前で言っていることとやっていることは180度異なります。
両親の板ばさみにあえば、礼音ちゃんもどちらを信用していいかわからず混乱します。その結果、成長が遅れる可能性もあります。
このように樹里さんと夫は育児をめぐり、事あるごとに喧嘩を繰り返し、挙句の果てには夫が「もういい」と家を出て行ってしまったのです。樹里さんも「娘のことを考えると(夫は)いない方がいい」と思い、夫を連れ戻そうとはせず、そのまま離婚に至ったのです。
「育った環境が当たり前」という考えは覆せない
ここまで樹里さんが夫との意見の相違で疲れ果てる様を見てきましたが、夫は子どもに冷凍食品ばかりを食べさせること、保育園でしつけてもらうこと、そして目の前で喧嘩をすることを悪いと思っていないのでしょう。
なぜなら、自分も同じような家庭で育っただろうからです。正しいと思っている相手に「間違っている」と言っても暖簾に腕押し。何回、何十回、同じことを言っても、残念ながら通じません。
このように考えると、いざ結婚する前に相手がどのような家庭で育ったのか。どんな教育を受け、生活を営み、何を与えられたのか(与えられなかったのか)をきちんと聞き出すことが大事ですね。
(ハピママ*/ 露木 幸彦)