これが最後かもしれないと渾身の思いで歌詞を書き上げた
──フルアルバムを作る構想はいつ頃からあったんですか。
秀樹:さすがにもう避けて通れないなと(笑)。これまで『PHALLUS KICKER』(2020年春発表)、『LOVE FROM FAR EAST』(2022年7月発表)とミニアルバムを2枚出してきて、極東ファロスキッカーなるものはどんなバンドなのかを一つの形としてそろそろ残さなきゃいけないんじゃないかとはここ数年考えていました。その結果、コロナも明けたこのタイミングで取り掛かろうと自分たちを奮い立たせて。
宙也:もうフルを作る段階なの? って感じはちょっとあったけどね。コロナもあったし、結成からもう5年も経つの? っていう感覚だったので。
レイコ:せいぜい2年くらいしか経ってない感じだったし。
秀樹:まだ自分ちの狭い庭で遊んでいて、やっと今になって外へ出始めましたみたいな感覚ではあるんですよね。個人的にはもうワンクッション置いてからフルでもいいかなと思っていたんですけど、タイミング的にはこれで良かった気がします。
──2022年の春に宙也さんがアルコール依存症のために入院したことも大きかったですか。バンドの顔役がいつまでも万全の体調で活動できないのかもしれないという危機感に直面したことがフルアルバムの制作に取り掛かる一つの契機になったのではないかと思うのですが。
秀樹:ああ、それは大きかったかもしれない。
宙也:個人的には生死に関わることだったし、その経験がアルバム制作に向かう上で大なり小なり影を落としているのは確か。これが最後かもしれないと、渾身の思いで歌詞を書いたから。いま思えば、入院先のベッドで『LOVE FROM FAR EAST』のジャケットをチェックしたりしたね。そのときはこのままのペースでバンドをやれるのか不安だったし、ライブのスケジュールは増える一方だったので体調を持ち直すのがキツかった。でもこの2年間ずっと治療に励んできたし、フルアルバムの作詞とレコーディングを完了させてやっと自分自身の復活、再生を果たすんだと考えていたし、そこで新たなスタートを切りたかった。
レイコ:「Godspeed U」のMVは、宙也さんが救急車に搬送される映像が頭に入っているんですよ。たまたまその現場に諸沢さん(極東ファロスキッカーのMVを数多く手がけている諸沢利彦)がいて、宙也さんがライブハウスで倒れて運ばれるまでの映像を押さえていたんです。その映像をいつか使いたいと話していて、宙也さんが入院から1年経ってアルコール依存症を告白したのでMVとして発表したんです。
──フルアルバムの収録曲ですが、資料によるとその多くをライブでこなしてからレコーディングに臨んだとのことですが。
ERY:事前にライブでやっていたのはおよそ半分ですね。「À Bout de Souffle」、「デウスエクスマキナ」、「ゲシュタルト崩壊」、「無限デシベル」、「ろくでなしピエロ」、「Sweet FREQ」、「美神オルフェ」をまっさらな新曲として録りました。「愛 Misery」は初期からあった曲です。
──冒頭の「À Bout de Souffle」はジャジーなラウンジ・ミュージックにフランス語の囁きが重なる小粋な小品ですが、こうしたスマートなイントロダクションはプロデューサーである秀樹さんの采配ですか。
秀樹:宙也さんが、何かSEみたいなものを頭に付けたいと急に言い出して(笑)。
ERY:レコーディングが全部終わって、スタジオの帰り道でしたよね。
──タイトルをゴダールの『勝手にしやがれ』から引用したのは?
秀樹:「極東ファロスキッカーのテーマ」のベースをモチーフに、ちょっと違う解釈で跳ねる感じにしたらジャズっぽくなったので。それをワンコードにするとゴダールっぽいかなと。
──喋っているのはERYさんですか?
ERY:いや、Mandah(マンダ)さんというフランス生まれの音楽ジャーナリストです。『VISUAL MUSIC JAPAN』というWEBメディアでファロキのインタビューをしてくれた方で。
宙也:街の雑踏から何がしかの音が聴こえてくるという設定は秀樹のアイディアで、「何か聴こえる…」というフランス語をMandahに喋ってもらって。
秀樹:ジャケ写の撮影をしたときのヘアメイクがフランスの方で、フランス語で録ってもらいましょうよと宙也さんに話したら、Mandahにお願いしてくれたんです。ボイスメールで録った声をこちらで編集しました。
各自の持つ楽器こそが最大の武器
──「コードネーム:SlimGenie」はここ最近のライブで1曲目を飾ることが多いですが、終盤に曲調が二転三転する構成となっています。ああいうユニークな楽曲はリハーサルで試行錯誤の末に生まれるものなんですか。
レイコ:「〜SlimGenie」は完全に秀樹君の頭の中で組み上げられたものですね。
ERY:私たちが軸になってセッションみたいな感じで作ることはほとんどなくて、「〜SlimGenie」も秀樹さんがデモの段階であそこまで作り込んであったんです。
──秀樹さんの持ち寄った曲に宙也さんが詞を付けて、それにERYさんとレイコさんが肉付けしていくのがファロキの基本構造?
秀樹:それが基本の流れです。ただ、ERYとレイコさんによるプラスαの素材が凄くあるし、それを補強するとどうなるのかという楽しみが常にあるんです。みんな引き出しが多いし、こちらの意図してなかった違うアプローチの解釈をしてくれることが面白い結果に繋がることがよくあるので。まさにバンドマジックと言うか。
宙也:もう5年も一緒にやっているからね。ERYとレイコが演奏するのをかなり想定していると言うか、細かいフレーズまで入れたデモを秀樹が作ってくるんだよ。「ゲシュタルト崩壊」のスネアとか、見事にハマったなあと感じるものも多い。
──“SlimGenie”とは察するに、全世界を股にかけるアンドロイドのスパイみたいな存在なのでしょうか。
宙也:そう捉えてもらってもいいし、どう解釈してもらっても構わない。
──「愛のプロレタリア」の主人公と相通ずるものがありますよね。
ERY:そうですね。「ボクは元スパイ 国際的なプレイボーイ」という台詞もありましたし。
宙也:結成当時に秀樹と申し合わせをしたわけではないんだけど、昭和のハードボイルド・スパイ活劇みたいなものをバンドのコンセプトの一つにするのが面白いんじゃないかと思って。「〜SlimGenie」に関して言うと、サイコビリーという楽曲的な切り口にスパイ活劇みたいな言葉を掛け合わせたら面白くなるかもしれないと考えた。クランプスみたいなサイコビリーはゴシックやエログロと相性がいいし、スパイ物の世界観と親和性が高いんだよね。
──軽快な旋律が特徴の「デウスエクスマキナ」は本作のリード・チューンを担うべく作れたものですか。
秀樹:アルバムのキラー・チューンが欲しかったのと、この手のメロディラインはあまり作ってなかったなと思って。あと、ERYのコーラスを活かす曲を増やしたかった。今回はそういう男性と女性の絡みをポイントの一つに置きたくて、「デウスエクスマキナ」はその狙いが凄くハマったなと自分でも感じています。
──「〜SlimGenie」のハミングに始まり、今回はERYさんのコーラスが全編にわたって重要なポイントになっていますね。「極東ファロスキッカーのテーマ」のカウントもそうですか?
ERY:あれはレイコさんです。最初はサンプリング音声が使われていたんですけど、レイコさんが生でカウントしたほうが良くない? って話になって最後に急遽録ったんですよ。
──レイコさんの声は他にもあるんですか。
レイコ:あのカウントだけです。
ERY:歌メロのコーラスは全部私です。もともとコーラスとして入っていた部分もありましたけど、レコーディングしていくうちに「ここも唄いたい」とどんどん足していっちゃって。
秀樹:歌のお姉さんとして大活躍してもらいました(笑)。
──「デウスエクスマキナ」はわがFlowers LoftでMVの撮影までしていただきまして。しかもARBのキースさんが半裸で新宿LOFTのフロアを駆け回る謎のシーンまで挿入されていますが(笑)、老若男女が薔薇を抱えて疾走する演出が終始施されていますよね。
宙也:あの演出もストーリーも全部、諸沢さんによるもの。それから互いにアイディアを出し合って、いろんな世代の多種多様な人たちが出てきて、中にはノンバイナリージェンダーもいることにした。諸沢さんの最初のコンテには本物の戦場の画も描いてあったんだけど、歌に出てくる戦場とは都会なんじゃないかという意見を秀樹が出して、都会の雑踏に佇む4人を描くことになった。各自の持つ楽器こそが最大の武器であるという意味を込めて。
──ガザの空爆を想起させる歌詞もあるし、2024年という現在を象徴する意味でも「デウスエクスマキナ」は本作の中で特別な位置に値する楽曲ですね。
レイコ:「デウスエクスマキナ」ができるまで、段階的に何曲かできてきてライブでもやっていたんですけど、フルアルバムを作ろうとするタイミングではメインとなる曲が今一つないよねという話だったんです。それからほんの数カ月で「デウスエクスマキナ」も含めた推しとなるような曲が秀樹君から送られてきて、キタ! と思いました。
秀樹:ERYは「ろくでなしピエロ」が一推しだったけどね(笑)。
何とか唄うことができたのが唯一の救いだった
──“Fu, fu, fu...”というハミングが耳に残る「ゲシュタルト崩壊」はグラムロックのエッセンスが感じられるミッド・チューンで、これもまたライブ映えしそうな一曲ですね。
秀樹:「ゲシュタルト崩壊」は自分の中で新しいことに挑戦してみた曲なんですよ。ロックンロールのリフに対してサビに入るとメロディックになるという、コードがいわゆるツーファイブワンみたいなジャズっぽい感じと言うか。
宙也:ああ、そうなんだ。俺はT・レックスみたいな感じで唄ってたけど。
秀樹:ポピュラーな音楽にはわりとよく使われている、王道なコード進行なんですけどね。それをただ繰り返しているだけなんです。
宙也:だからなのかな、繰り返しが飽きない。歌詞を書く立場からすると、秀樹の曲はどれもそう感じる。それはとどのつまり、ポップということなんだと思う。
──グイグイと攻め入るような性急なナンバー「Alien Beauty」は、地球の東の果てに落ちてきた宇宙人に向けた求愛の歌ということですが。
ERY:ライブで先行してよくやっていた曲ですね。自分にとってはライブ・パフォーマンスがやりやすい曲なんです。
秀樹:まさにライブを想定して作りたかった曲です。全体的に言えることなんですけど、僕らの年齢だと若い子たちがノレるハードでラウドな曲調はレパートリーとして作れない(笑)。だけど自分たちにはノレるスタイルの曲というのがあって、「Alien Beauty」はそんな一曲ですね。ハードと言うよりもドライブ感に溢れたという言葉が似合う曲。
──その「Alien Beauty」から一転、「極北ロマンス」はサンタナを彷彿とさせるエロティックな激情バラッドですね。これは珍しく秀樹さんが作詞にクレジットされていますが。
宙也:秀樹が7割くらい書いてきた歌詞に俺が少し加筆した感じ。昭和のムード歌謡を意識してみた。
秀樹:宙也さんに、もっとねちっこい感じにしてもらって(笑)。
宙也:ちょいとエロ注入(笑)。あと、デモのタイトルがなぜか「所沢ブルース」だった(笑)。
ERY:そうそう。♪トッコロザワブル〜ス、って感じで。
秀樹:デモで仮歌を唄っているときは五木ひろしになりきってましたから。
ERY:そのイメージが「極北ロマンス」になってからも消えませんでしたよ(笑)。
秀樹:でも、ムード歌謡は意外とハマると思ったんですよ。宙也さんが唄うと従来のムード歌謡っぽくならなくなる、唄っただけでティム・バートンの世界になると思って(笑)。そういう新たなトライも大事かなと。
──メロディアスで劇的な展開の佳曲「愛 Misery」は結成初期から存在していたそうですが、なぜずっと寝かせておいたのですか。
秀樹:「愛 Misery」は最初に作った4曲の中の1曲なんですけど、まだ手探りだった結成当初に宙也さんの世界観に寄せて作ってみたんです。
ERY:最初の何回かライブでやって、それからやらなくなったんですよね。
宙也:対バン形式の短いライブが多くて、その中では「愛 Misery」みたいにメロウな曲がちょっと合わなかったのもあるね。
秀樹:世界観がしっかりとある曲なので、「愛 Misery」をやるとその印象だけが強く残ってしまう懸念もあって。だからフルアルバムに入れるのに適した曲とも言えますね。収録にあたっては宙也さんが歌詞を書き直した部分もあるんですけど。
──当初は宙也さんがまだアルコール中毒だった頃に書いた、とても絶望的な歌詞だったそうですね。
宙也:うん。元は自分のネガティブな側面が全面に出た感じだった。
秀樹:それでタイトルに“愛”が付け足されてポジティブになったんだ?(笑)
ERY:デモのタイトルは「ミザリー」だけでしたもんね。
宙也:今回、最後にかすかな希望が残るように歌詞を書き直した。歌入れ前日のギリギリに、タイトルに“愛”を加えた。
──それほどアルコール依存症の治療が功を奏していると言えますね。
宙也:完治こそしないけど治療次第で回復はできるから。単純にアルコールが身体から抜けると脳がクリアになるし、ネガティブなことに対面してもそれを避けて次の場面を考えられる。アル中だとネガティブはネガティブなままなんだよ。治療を受けた最初の頃はそれが空回りしちゃって、一つのことを考えていたのに別のことを次々と考えちゃって、最初に考えていたことを蔑ろにしてあれもできるこれもできると自分で勝手に混乱してしまうこともあった。今はそういう思考を一つ一つ整理しているけど、脳のダメージはもう戻らない。それでも何とか唄うことはできたので、それだけが唯一の救い。秀樹からどんどん新曲が送られてくるし、もうやるしかない。
SNSというバーチャルの世界もまたガザと同じ“戦場”かもしれない
──宙也さんの描く作詞の作風の変化はみなさん感じましたか。
秀樹:いつも以上に才気が爆発したと言うか、覚醒した感はありますね。
レイコ:今回は特に、文言がキラキラしてるんですよね。歌詞の輪郭がどれもはっきりしてる。
──そうなんですよね。ストーリーテラーとしての従来の才能がさらに切れ味と凄みを増した感があるし、良質な短編小説を味わえる醍醐味と余韻をどの曲にも感じるんです。話が戻ってしまいますが、この世界と自分自身を救うものを主題にしたという「デウスエクスマキナ」がとりわけ格別で、絵空事のような現実と現実のような絵空事を行き来する2024年現在の社会が虚構であるはずの歌としてとてつもないリアリティを伴い表現されている。虚の世界が現実以上の現実となって聴き手の目の前に現れる。もちろんそれは歌だけではなくギターとベースとドラムが混然となってこそ初めて成し得ることで、そんな楽曲の持つ力や歌のポジティブさをこれまで以上に実感します。
宙也:「デウスエクスマキナ」は間奏が終わってもう一度Aメロが来るでしょ? それは秀樹の曲には珍しいケースなんだよ。
秀樹:だいたいBメロに行っちゃいますからね。
宙也:だからストーリーを作りたくなっちゃう。Bメロで違う話をしてサビがもう一度来るなら間奏までの世界を繰り返せばいいんだけど、間奏の後にまたAメロが来るということは、その後の展開を綴りたくなる。
ERY:時が進んでいる感じですよね。
宙也:そうそう。あと、冒頭の「あの日のあの空の下」の“空”と、間奏の後の「あの日のあの空の下」の“空”は違う空なんだよね。第二次世界大戦とガザ空爆という時空を超えた空を表現している。
──宙也さんが「デウスエクスマキナ」を録り終えた後に観たという是枝裕和監督の映画『怪物』がご自身の中でイメージと重なったそうですね。
宙也:『怪物』は戦争映画ではないけれど、あれはびっくりした。あの映画には男の子同士の恋愛話もあり、モンスターペアレンツによる虐待の話もあり、放火事件の犯人は誰なのか? 誰が本当の“怪物”なのか? という話もあるんだけど、物語の本筋は犯人探しではない。事件とは直接関係のない、噂話をしている人たちこそが真の“怪物”なんだという落とし所なんだよね。昨今のSNSと同じで、ありもしない話を噂にして周囲の人たちを信じ込ませることで誰かに大きな迷惑をかけるという。今やそういう“戦場”も世に蔓延っているんだという視点が「デウスエクスマキナ」のイメージと重なったわけ。SNSというバーチャルの世界にも人の生命を脅かす攻撃や危険な行為があるという意味で、それはもはやガザと同じ“戦場”じゃないかと思って。
──なるほど。ここからアルバムの後半です。「極東ファロスキッカーのテーマ」はライブのオープニングSEとして多用されていますが、先ほど宙也さんが話していた“昭和のハードボイルド・スパイ活劇”を彷彿とさせるナンバーですね。
宙也:秀樹が『キイハンター』のオープニングテーマ(「非情のライセンス」のインストゥルメンタル)にインスパイアされて作った。
──ライブ同様に冒頭に配置するのではなく、あえて真ん中に置くのが捻りが効いていいなと思って。
秀樹:曲の並びは、宙也さんが何度も聴いた上で決めてくれました。
宙也:今回はフルだったので余計に大変だったし、「極東ファロスキッカーのテーマ」はどこに入れようか特に悩んだ。1曲目にすると、俺の声まで遠いなと思って(笑)。
──最初からずっとインストですからね(笑)。
宙也:アルバムの頭を「À Bout de Souffle」、「〜SlimGenie」という流れにすれば、どちらも女性の声で始まってインパクトが強いでしょう? 「〜SlimGenie」でやっと曲が始まったのかと思えば、俺ではなくERYのハミングから入るっていうのもいいしさ。
──サビの“Body, body, body...... body and soul”という掛け声がキャッチーな「無限デシベル」ですが、“デジベル”と聞くと自ずと宙也さんが1996年に発表したソロ作『ゼロ・デジベル』を連想しますね。
宙也:タイトルも含めて、90年代の自分をオマージュしていると言うのかな。この曲に限らず、今回は自分の人生の集大成と言うか、自分らしさみたいなものを全部出してしまおうと考えた。「無限デシベル」だけではなく、自分のやってきたことや自分らしい言葉を実は随所に散りばめてある。
──「ろくでなしピエロ」の歌詞に“エルドラド”(アレルギーが1985年に発表したファースト・フルアルバムのタイトルトラック)があるのは気づきました。
宙也:40年以上いろんなバンドをやってきたし、新たなバンドをやるときは前のバンドの曲を絶対にやらないとか、常にそれまでのイメージを一新しながら前へ向いて進んできた。でも今回はそういうことも引っくるめて自分のすべてを出してしまおうというのがあった。
──これまでの禁じ手を打ち破った、新たなトライアルだったと。
宙也:うん。今回は秀樹が作ってきた曲を聴いて「え、今さらこういうタイプの曲を俺に渡す?」というケースもあったんだけど(笑)、それは過去にあったことなどもう関係なく、すべてを投げ捨てたつもりで新しい曲に取り組んでよ! と言ってくれているのかなと受け止めてね。
昭和のテレビドラマから受けた恩恵が楽曲の世界観に反映
──「魔王リベリオン」もそうした宙也さんによるセルフオマージュ的楽曲の一つなのかなと思いましたが。『KINGDOM』というタイトルのアルバムがDe-LAXにありましたし(1990年発表のサード・アルバム)。
宙也:そこはどう受け取っていただいても(笑)。
秀樹:曲調に関して言うと、90年代頃のイギリスのバンドを意識して作ったんです。インディーズで脚光を浴びてすぐ消えたみたいなバンドの曲って、意外と今も覚えていたりして。この曲もキーとなっているのは、宙也さんとERYが一緒にユニゾンで唄っているところなんです。宙也さんと同じ音程でぴったり合わせて唄っているのに歌の印象が違って聴こえるのが面白い。
宙也:ERYのコーラスが入ったときに「やった!」と思ったもんね。歌詞を書く立場からすると、コーラスが上手くハマると余計に嬉しくなるものなんだよ。ERYはいろいろできる子で、コーラスもいろんなパターンができるんだよね。
ERY:可愛い子系からお姉さん系、やんちゃ系もできますよ(笑)。ブースから「これはどのバージョンでいきますか?」と訊いてから唄って、その中でみんながいいねと感じたキャラが採用される感じでした。私はボーカリストじゃないし、宙也さんと違って自分の色がないから何者にでもなれるんです。
──「魔王リベリオン」の歌詞にある“ジャジャジャーン”はテレビアニメ『ハクション大魔王』でお馴染みの、大魔王が呼ばれて飛び出したときの言葉を引用したそうですね。
宙也:そう。呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーン(笑)。
秀樹:“ジャジャジャーン”という言葉が出てきたときは、宙也さんも完全に振り切ったんだなと思いました(笑)。
──『キイハンター』然り『ハクション大魔王』然り、60年代末から70年代初頭にかけての昭和のテレビドラマから受けた恩恵がファロキの世界観に如実に反映しているのが窺えますね。
秀樹:やっぱり世代として影響が色濃い部分があるんでしょうね。
──宙也さんと秀樹さんは少し世代が違いますけど、そうした昭和カルチャーからの影響は似通ったところがあるんですか。
宙也:秀樹とは6歳差だけど、昭和は昭和だからね。『傷だらけの天使』もリアタイで見たか再放送で見たかの違いくらいで。
秀樹:うちの兄貴が宙也さんと同じくらいの歳なんですよ。だから同じ時代に同じような番組を見ていたと思います。
──そういう昭和的キーワードが楽曲の主題である場合、ERYさんとレイコさんは理解できないことが多々あるのでは?
秀樹:まあ、理解していただこうとはあまり思ってませんけど(笑)。
宙也:むしろ違う理解や解釈をしたほうが面白いからね。
ERY:3人が「ああ、あれね!」と昔流行ったものの話題で盛り上がっているのを、私はよく知らないけどなあ…とか思うこともありますけど(笑)、それでいいかなと思って。自分で掘り下げたいものは訊いてみたりしますけど、知らなくていいかなというものはそのままにしています。ある程度の情報共有をしたいときは、バンドのグループラインで宙也さんが「『キイハンター』とは?」って参考動画のリンクを貼ってくれることもありますし。
レイコ:私はタランティーノの存在も大きい気がして。古今東西の映画をオマージュすることで今に伝える彼の作風が若い世代へ与えた影響は凄く大きいと思います。
──確かに。“A-Cho”はブルース・リーの怪鳥音ですか。
宙也:あれは元からデモに入ってなかった?
秀樹:入ってないです。“Fu...”とか何か入れてほしいとは言いましたけど。
レイコ:“A-Cho”はライブで宙也さんが言い始めたんですよ。
ERY:私は『ブラック・ジャック』のピノコが言う“アッチョンブリケ”だと勝手に思っていたんですけど、違うんですか?
宙也:じゃあ、そういうことにしておこう(笑)。
一番ありきたりに思える楽曲で実験的な試みに挑む捻れた面白さ
──「ろくでなしピエロ」は終盤のフラッシュポイントを担う、ストーンズやスージー・クアトロを彷彿とさせるストレートなロックンロールですね。
秀樹:宙也さんが一番似合う形のロックンロールを作ったつもりなんです。「これを俺が唄うの?」と言われたんですけど(笑)、絶対にハマると思って。おっしゃる通りストレートなロックンロールなんだけど、宙也さんが唄うと変わった形になるんですよ。グラマラスで艶のあるニュアンスが自ずと醸し出されると言うか。
宙也:自分としては、このシンプルで典型的なロックンロールを秀樹が託してきたのはどんな意図があるのだろうと考えたけど、これがシンプルでストレートかどうかは解釈が分かれるところでね。ERYは「ろくでなしピエロ」をありきたりなロックンロールの感じはしないと話していたのが面白かった。世代に関係なくロックンロールの解釈自体は人それぞれだし、同じ世代でも解釈が違う。
ERY:「ろくでなしピエロ」は、私は旅のテーマみたいな印象があるんです。海外へ一人旅へ行ったときの動画にこの曲を当てたこともあるし、自分の中では旅のBGMみたいなイメージですかね。
レイコ:私も「ろくでなしピエロ」をよくあるロックンロールとは思えなかったんです。個人的にこの曲はバスドラが肝で、秀樹君がデモで1、3にバスドラを入れてきたんですよ。そこを最初は1、3、4にさせてもらうかと思ったんだけど、そうなると全然面白くなくなってしまう。それこそありきたりなロックンロールになってしまうことに気づいたんです。これは秀樹君こだわりの1、3だろうと思ってリズムパターンを作り始めたら、自分でも凄く楽しくて。1、3はわりと間延びしそうなところがあるので、そこをまったりしないようにハイハットできっちり煽ると言うか。そのコントラストで楽しい感じを出すのが面白いんです。秀樹君は確信犯だなと思ったし、バスドラが1、3じゃなかったら、もっと普通の曲になっていたかもしれない。
秀樹:モット・ザ・フープルとか70年代前半のグラムの走りの人たちって、ドラムの音がでかいんですよ。細かいことは気にせずにドン! パン! と鳴らすことが多い。その迷いのない感じがインパクトの強さに繋がっているし、その手法をずっとやりたかったんです。ドラマーとしてはそっちのほうが楽しいんじゃないかと思うんだけど。
レイコ:ドラマーはむしろ、バスドラが1、3なら隙間を埋めるように1、3、4にしたくなるか、4発入れてスピード感を出したくなるはずなんですよ。そうならないのはドラマー脳ではない秀樹君が作曲したからこその面白さだと思う。
宙也:仮にスネアが同じ位置でも、キックを入れるタイミング次第で違う感じに聴こえるんだよね。歌詞を書くときや歌を乗せるときはスネアとキックに言葉を一文字ずつ乗せるのが基本だから、「Alien Beauty」、「魔王リベリオン」、「ろくでなしピエロ」は特に、レイコのスネアとキックと自分の言葉の乗せ方を凄く意識した。
レイコ:宙也さんは私のドラムを凄くよく聴いているんですよ。
秀樹:「ろくでなしピエロ」はERYのベースもちょっと変わったことをしているよね。
ERY:そうですね。他の曲はエイトでキメることが多いけど、ここではずっとフレーズを弾きまくったので。
秀樹:そういう実験的なことをやりたかったんだよね。
── 一番ありきたりに思える楽曲で実験的な試みに挑むという、捻れた面白さがあるわけですね。
秀樹:ここまでバンドを長くやっていると、「ろくでなしピエロ」のように初心に返る感じの曲をやらなくなるんですよ。そこをあえて新たなチャレンジを含めてやってみる楽しさを追求してみたと言うか。
宙也:俺の世代はこの手の曲をいかに壊して次へ向かうかが基本的なスタンスだったから。でもこの歳でそれに挑むのが逆に新しかったし、今回は文字通りピエロに徹して、凄く自虐的な歌詞を書くのは初めてで面白かった。
秀樹:宙也さんがここまで自分を曝け出した歌も過去になかったと思うんですよ。40年以上にわたって宙也さんにしか構築できない世界観を確立して、一つのスタイルを保持してきたことを打ち破ったのが斬新だし、バンドの新たな可能性を提示できて良かったなと。
ERY:私としては「ろくでなしピエロ」でお客さんとコール&レスポンスができたらいいなと思いますね。歌詞の中に“I wanna be”、“Yo, wannabe”と掛け声にしやすいフレーズがあるので。コロナ禍が明けてライブで声出しが解禁になったから、そろそろそんなことができたらいいなって。こっちが「Night and day」ってコーラスしたら「Yo, wannabe!」って叫んでよっていう(笑)。そういうのもあって、自分のYouTubeで「ろくでなしピエロ」のリリックビデオを作ってみたんです。ここで“Yo, wannabe”って言うんだよ? わかってるよね? って(笑)。
レイコ:K-POPのアイドルにもコール&レスポンスの練習動画があるからね。「この曲のサビではこういう掛け声でお願いね」と曲の頭でメンバーが話してる。
秀樹:じゃあ俺、“I wanna be”と“Yo, wannabe”のプラカードを作るよ。『元祖どっきりカメラ』みたいな(笑)。
DER ZIBETのISSAYへ捧げた「美神オルフェ」に内在する生命力
──安定の昭和感ですね(笑)。イントロがジーザス&メリーチェインの「Just Like Honey」を思わせる「Sweet FREQ」は悠然としたバラードの逸品で、本作の中では珍しいタイプの曲ですけれども。
宙也:一昨年の秋にデモテープが届いて、秀樹から「クリスマスソングにしてほしい」というリクエストをもらった。ちょうどその年のクリスマスにワンマンが決まっていたので。自分が断酒して以降に初めて完成させた歌詞だね。
レイコ:「Sweet FREQ」はライブでやるごとに曲の表情が変化していった曲ですね。宙也さんの中でさまざまなお別れがあって、その思いを直接聞かずとも感じ取れるものが曲の中にあったんです。凄く大事な曲なんだろうと思ったし。
秀樹:実際、この曲をライブでやると場の空気が一変するよね。
レイコ:うん。客席への伝わり方が格段に違う。宙也さんの中から発せられるものが明確にあるし、私たちも演奏に没頭できるし、客席にその思いがしっかりと伝わる。やり始めた頃と今ではライブでの表情が一番変わった曲じゃないかな。
秀樹:そんないい曲でERYはヘドバンしてますからね(笑)。
ERY:そう、凄く頭を振りやすいんです(笑)。
レイコ:サビでね。私もよくヘドバンしてる(笑)。
宙也:このあいだステージの頭上からの映像を音を出さずにチェックしていたらERYが激しくヘドバンしていて、何の曲かと思えば「Sweet FREQ」で驚いた(笑)。
ERY:私は長いことやっていたんですけど、宙也さんも秀樹さんも横並びだから気づいてなかったのかな?(笑)
──“FREQ”=“Frequency”(周波数)という言葉も詩的でいいですね。互いの心のチューニングを合わせたり、周波数帯によって届ける思いと受け取る思いに高低の違いがあったり。
宙也:自分では純愛をテーマにしたつもりなんだけど、それは秀樹のデモを聴いて何かピュアなものを求められている気がしたから。俺は放っておくとすぐ捻くれた歌を作りがちだけど、曲調や仮歌、仮タイトルからどこか純真でまっすぐなものを主題にするべきなのかな? と思って。
秀樹:どちらかと言えば宙也さんの陽の部分を引き出したいと言うか、ファロキに関してはなるべく明るい方向がいいと思っているんです。宙也さんなりの世界観は確固たるものがすでにあるし、それはもちろん尊重していますけど、ファロキではもっとサニーサイドにフォーカスを当てたい。まあその辺はバランスなんですけどね。
──アルバムの大団円を飾るのは「美神オルフェ」。昨年8月に他界したDER ZIBETのISSAYさんへ捧げたドラマティックなナンバーですが、本作を締め括る上で代替不可の楽曲ですね。
宙也:ISSAYが生まれ育った港町で行なわれた葬儀に参列して、その日はあっちゃん(BUCK-TICKの櫻井敦司)も一緒でね。彼と共にISSAYの骨を拾った。それがあっちゃんと過ごした最後の日でもあった。その青空がきれいだった一日を歌にした。
──ギリシア神話に登場する吟遊詩人のオルフェウス(オルペウス)にISSAYさんの姿を重ね合わせたわけですよね。
宙也:イメージはね。アポロンに授けられた竪琴に合わせて唄うと野獣や草木も聴き惚れたというオルフェウス。歌詞ができて歌入れをしてみんなで聴いたとき、ERYが「この曲が最後がいい!」ってすぐに言ったんだよ。
ERY:はい。「アルバムの最後の曲はこれですよね?」って言いました。
宙也:ERYが「きれいな日本語」って言ってくれたのが嬉しかった。さっきも言ったけど、放っておくと捻くれる作風と言われる中で純な部分も出してみようと言うかさ。これまでの俺は、自分では常にストレートを投げているつもりでもなぜか全部変化球になってしまっていた。それがいつしか歳を重ねて、最初から上手な変化球を投げられるようになったのかな? と。
レイコ:私は「美神オルフェ」を聴いて、夏の空に消えたオルフェを宙也さんが咀嚼できたと言うか、受け入れることができたと言うか、自身の中でやっとオルフェを生かすことができたんだなと思って。彼の不在は悲しいことだけどただ悲しい曲で終わっていない、明るさというのともまた違う、揺るぎない生命力みたいなものを強く感じて大好きな曲です。これからもずっとオルフェと共に生きていくんだという意志を感じますし。あと、よくある3拍子の曲かもしれないけど、宙也さんの文言の力と歌の色合いによって宙也さんにしか生み出し得ない曲になっていますよね。「ろくでなしピエロ」もそうですけど。
扉の向こうにあるものを見たい気持ちが今も常にある
──そこはバンドの一体感、総合力の賜物ですよね。アウトロへ向かうエモーショナルな合奏には得も言われぬ美しさとカタルシスと昂揚を感じますし。
秀樹:ERYもレイコさんもグイグイ来てくれるし、ライブでも大きな見せ場の一つですね。自分としては回数を間違えないように弾こうと必死ですけど(笑)。
ERY:だけど「美神オルフェ」もデモから大きく様変わりした曲ですよね。
──と言うと?
ERY:デモではこんなにも美しく儚い曲じゃなかったんです。
レイコ:レコーディングのときに歌詞を見てびっくりしました(笑)。
ERY:だって、デモは「結婚しようよ」っていう曲だったんですよ? ♪ねえマリア、結婚しようよ〜っていう明るいプロポーズの曲で(笑)。それが結果的にあれだけ壮大な曲になるとは微塵も思わなかったです。
レイコ:私も。
──そんなふうに激変した曲は他にもあるんですか。
秀樹:今回はほぼ全部がそうで、歌詞が乗るだけで豹変したんです。さっきも言ったけどここへ来て宙也さんが覚醒したと言うか、ここまで大胆に攻めた歌詞を書き上げてきたのは嬉しい誤算でした。極東ファロスキッカーでの自分の歌詞の表現方法が見えてきたと言うか、一つのスタイルを確立できたのかなと思いますね。前作のミニアルバムでだいぶ確立されてはいたけど、今回は言葉の攻め方が半端じゃないなっていう。
レイコ:結果的にファロキの音楽性がポップになったよね。良い意味で凄く聴きやすくなったと思うし。
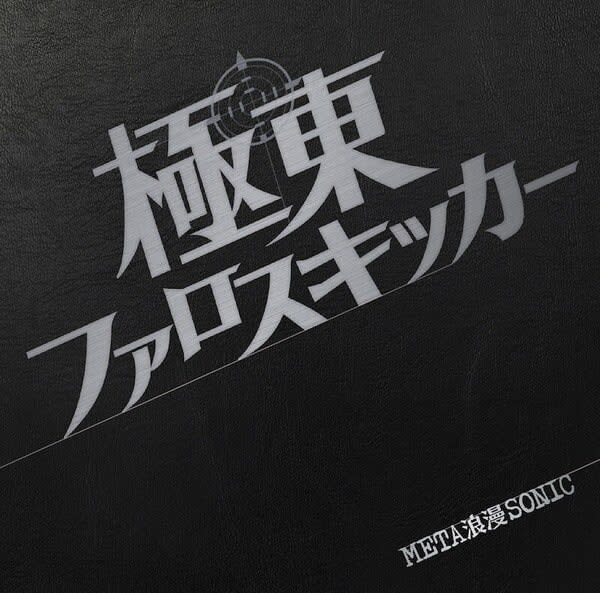
──『META浪漫SONIC』というアルバム・タイトルは、意味合いとしては“高次元の超音速浪漫”といったところでしょうか。
宙也:単純に語呂の格好良さもあるね。なんて言うのかな、最新形のロックンロールをやりながらもその先へ行きたいという欲求がバンドを始めた頃からずっとある。ただ歌が上手くなりたい、良い歌詞を書きたいだけじゃなく、自分のやっているバンドでもっともっと先へ行きたいし、まだ見ぬ景色を見続けていたい。このバンドでしか見られない先の景色を。その上で奏でられる音楽には「デウスエクスマキナ」のようなストーリー性があり、歌の要素として浪漫=ロマンとロマンスを決して忘れず、常に超音速を超えていく秀樹がいて、屋台骨を支えるERYとレイコというMETAな二人が俺と秀樹を然るべき道筋へ導いてくれる。あえて言えばそんなイメージ。
──何ものにも捉われずに全力のスピードで先の先へ行く、知覚の扉を開け続ける。まさに“ブレイク・オン・スルー・トゥ・ジ・アザー・サイド”、超音速の浪漫が宇宙を駆け巡ると言うか。
宙也:扉の向こうにあるものを見たい気持ちは常にある。こうして丹精を凝らして作り上げた作品をライブで披露して、そこでまた新しい扉が見えて開けたらそれこそがMETAだよね。これだけ長くバンドを続けてきても新たな扉はまだまだ出てくるし、だからこそいまだにバンドをやめられない。
──秀樹さんが自身で極東RECORDを立ち上げたこと然り、気づけばファロキは結成5年にしてとてもバンドらしいバンドに変貌を遂げた印象があるのですが。
ERY:最初は各々が個別にバンドをやっている中で集まってやりますという感じだったのが、今はファロキが中心になっていますしね。
レイコ:結成当初は、面白くなくなったらやめればいいやくらいの感じだったのに。
ERY:それくらい軽い始まりだったし、セッションありきの企画だったのに意外ですよね。私の中で明確な変化が訪れたのはショート・ツアーで遠征をし始めてからですね。それ以降、各自の人間性が馴染んできたと言うか、バンドに対するモチベーションが変わってきたのを感じました。
秀樹:地方で待っててくれたお客さんが意外と多くてね。各々でやっていたバンドのファンが根強く待ち望んでくれたのは嬉しかった。
レイコ:私自身はやっぱりプレイありきなんですよ。自分が楽しくのめり込んでやれるかどうかが大事だし、本当にこのボーカルの後ろで叩き続けたいか、このメンバーとずっと一緒にバンドを続けたいと思うかが大きな基準なんです。誰かに自慢できるメンバーと一緒にバンドを続けたいので。自分の中でポイントとなったのは2枚目のミニアルバムに収録した楽曲を作れたこと、当時のライブ感やそれぞれのパフォーマンスに手応えを感じるようになったことなんです。2枚目のミニアルバムを作れて以降、ライブへ行くのがより楽しくなってきたし、その頃にはもう「面白くなくなったらやめる」という選択肢は消えていましたね。ERYが言うように、ツアーに出たらさらに人間性が噛み合ってきたことも大きいです。
秀樹:ファロキは曲作りに煮詰まることもないし、やっていて純粋に楽しいんですよ。3人の楽器だけでこの先どんなアレンジができるかが課題ではあるけど、それぞれまだ使っていない引き出しがあるはずなのでいろんなことに挑戦できると思っているんです。
レイコ:とにかく宙也さんのボーカル力とキャラクターが圧倒的なので、極端な話、ベースとドラムだけのスカスカの音でも面白い曲になると思うんですよね。
宙也:実質的な3ピースでライブをやり遂げられるのは、ひとえに曲とアレンジが抜群にいいからだと思う。「最終兵器はあなたの歌声」という「デウスエクスマキナ」の歌詞の通り、自分自身の歌と3人の楽器こそがファロキにとって最大の武器だから。今回は今しか書けない歌詞を渾身の思いで書き上げて永遠に響くように唄い上げたつもりだし、その結果『META浪漫SONIC』という過去最高傑作を作れたという自負がある。だからぜひ聴いてほしい。この4人にしか生み出せない、新たな時代の純度の高いロックンロールだと思うので。

